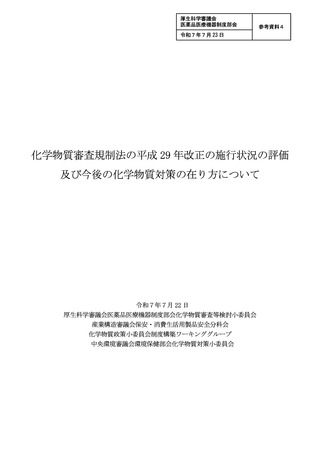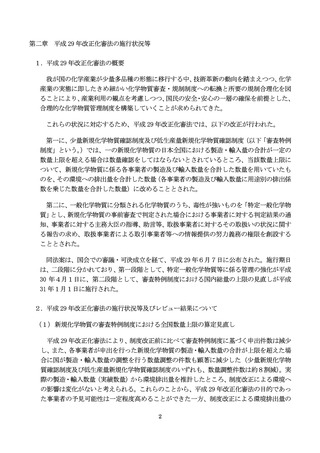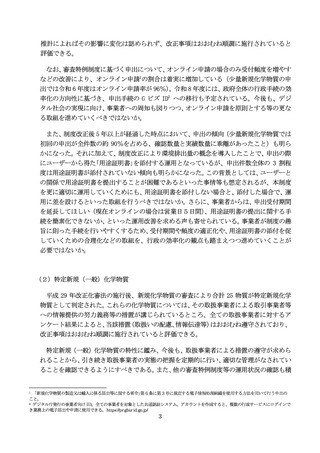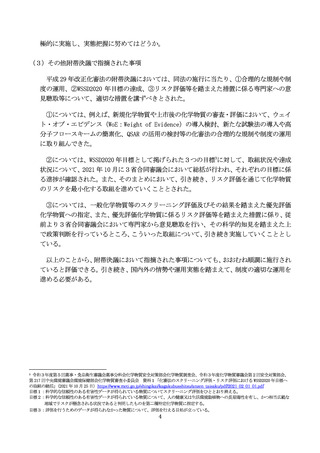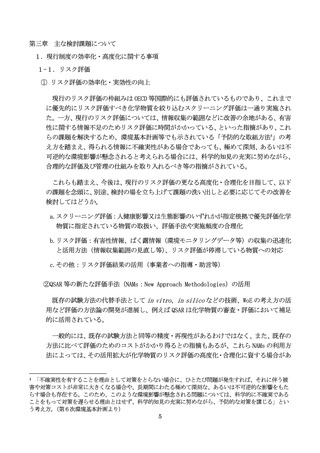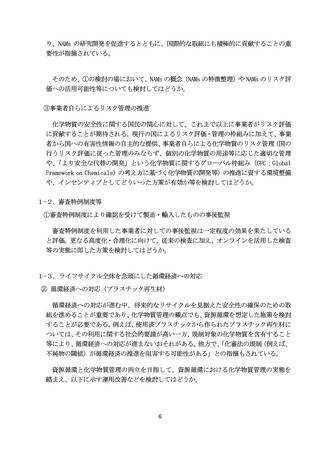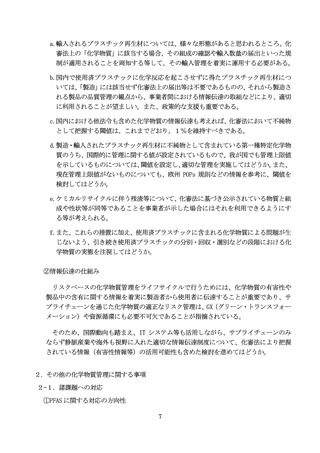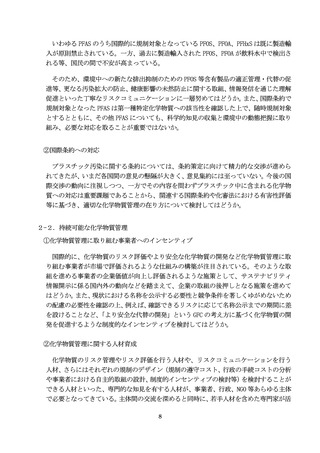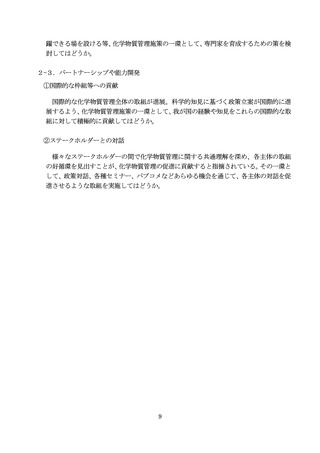よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】化学物質審査規制法の平成29 年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
推計によればその影響に変化は認められず、改正事項はおおむね順調に施行されていると
評価できる。
なお、審査特例制度に基づく申出について、オンライン申請の場合のみ受付頻度を増やす
などの改善により、オンライン申請1の割合は着実に増加している(少量新規化学物質の申
出では令和 6 年度はオンライン申請率が 96%)
。令和 8 年度には、政府全体の行政手続の効
2
率化の方向性に基づき、申出手続の G ビズ ID への移行も予定されている。今後も、デジ
タル社会の実現に向け、事業者への周知も図りつつ、オンライン申請を原則とする等の更な
る取組を進めていくべきではないか。
また、制度改正後 5 年以上が経過した時点において、申出の傾向(少量新規化学物質では
初回の申出が全件数の約 90%を占める、確認数量と実績数量に乖離があったこと)も明ら
かになった。それに加えて、制度改正により環境排出量の概念を導入したことで、申出の際
にユーザーから得た「用途証明書」を添付する運用となっているが、申出件数全体の 3 割程
度は用途証明書が添付されていない傾向も明らかになった。この背景としては、ユーザーと
の関係で用途証明書を提出することが困難であるといった事情等も想定されるが、本制度
を更に適切に運用していくためにも、用途証明書を添付しない場合と、添付した場合で、運
用に差を設けるといった取組を行うべきではないか。さらに、事業者からは、申出受付期間
を延長してほしい(現在オンラインの場合は営業日5日間)
、用途証明書の提出に関する手
続を簡素化できないか、といった運用改善を求める声も寄せられている。事業者が制度の趣
旨に則った手続を行いやすくするため、受付期間や頻度の適正化や、用途証明書の添付を促
していくための合理化などの取組を、行政の効率化の観点も踏まえつつ進めていくことが
必要ではないか。
(2)特定新規(一般)化学物質
平成 29 年改正化審法の施行後、新規化学物質の審査により合計 25 物質が特定新規化学
物質として判定された。これらの化学物質については、その取扱事業者による取引事業者等
への情報提供の努力義務等の措置が講じられているところ、全ての取扱事業者に対するア
ンケート結果によると、当該措置(取扱いの配慮、情報伝達等)はおおむね遵守されており、
改正事項はおおむね順調に施行されていると評価できる。
特定新規(一般)化学物質の特性に鑑み、今後も、取扱事業者による措置の遵守が求めら
れることから、引き続き取扱事業者の実態の把握を定期的に行い、適切な管理がなされてい
ることを確認できるようにすべきである。また、他の審査特例制度等の運用状況の確認も積
「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」第 6 条に第 3 号に規定する電子情報処理組織を使用する方法を用いて行う申出の
こと。
2 デジタル庁発行の事業者向け ID。全ての事業者を対象とした共通認証システム。アカウントを作成すると、複数の行政サービスにログインで
き業務上の電子届出や申請に使用できる。https://pr.gbiz-id.go.jp/
1
3
評価できる。
なお、審査特例制度に基づく申出について、オンライン申請の場合のみ受付頻度を増やす
などの改善により、オンライン申請1の割合は着実に増加している(少量新規化学物質の申
出では令和 6 年度はオンライン申請率が 96%)
。令和 8 年度には、政府全体の行政手続の効
2
率化の方向性に基づき、申出手続の G ビズ ID への移行も予定されている。今後も、デジ
タル社会の実現に向け、事業者への周知も図りつつ、オンライン申請を原則とする等の更な
る取組を進めていくべきではないか。
また、制度改正後 5 年以上が経過した時点において、申出の傾向(少量新規化学物質では
初回の申出が全件数の約 90%を占める、確認数量と実績数量に乖離があったこと)も明ら
かになった。それに加えて、制度改正により環境排出量の概念を導入したことで、申出の際
にユーザーから得た「用途証明書」を添付する運用となっているが、申出件数全体の 3 割程
度は用途証明書が添付されていない傾向も明らかになった。この背景としては、ユーザーと
の関係で用途証明書を提出することが困難であるといった事情等も想定されるが、本制度
を更に適切に運用していくためにも、用途証明書を添付しない場合と、添付した場合で、運
用に差を設けるといった取組を行うべきではないか。さらに、事業者からは、申出受付期間
を延長してほしい(現在オンラインの場合は営業日5日間)
、用途証明書の提出に関する手
続を簡素化できないか、といった運用改善を求める声も寄せられている。事業者が制度の趣
旨に則った手続を行いやすくするため、受付期間や頻度の適正化や、用途証明書の添付を促
していくための合理化などの取組を、行政の効率化の観点も踏まえつつ進めていくことが
必要ではないか。
(2)特定新規(一般)化学物質
平成 29 年改正化審法の施行後、新規化学物質の審査により合計 25 物質が特定新規化学
物質として判定された。これらの化学物質については、その取扱事業者による取引事業者等
への情報提供の努力義務等の措置が講じられているところ、全ての取扱事業者に対するア
ンケート結果によると、当該措置(取扱いの配慮、情報伝達等)はおおむね遵守されており、
改正事項はおおむね順調に施行されていると評価できる。
特定新規(一般)化学物質の特性に鑑み、今後も、取扱事業者による措置の遵守が求めら
れることから、引き続き取扱事業者の実態の把握を定期的に行い、適切な管理がなされてい
ることを確認できるようにすべきである。また、他の審査特例制度等の運用状況の確認も積
「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」第 6 条に第 3 号に規定する電子情報処理組織を使用する方法を用いて行う申出の
こと。
2 デジタル庁発行の事業者向け ID。全ての事業者を対象とした共通認証システム。アカウントを作成すると、複数の行政サービスにログインで
き業務上の電子届出や申請に使用できる。https://pr.gbiz-id.go.jp/
1
3