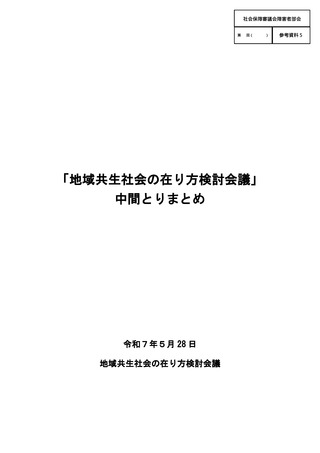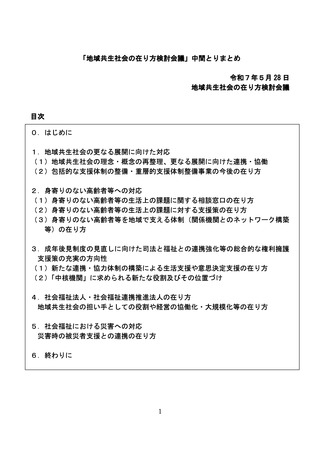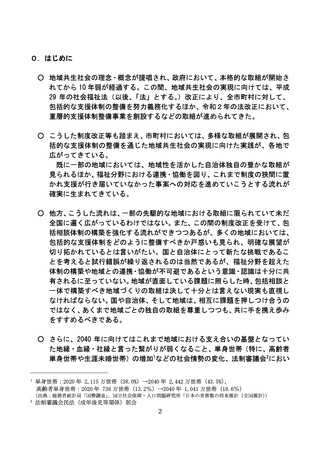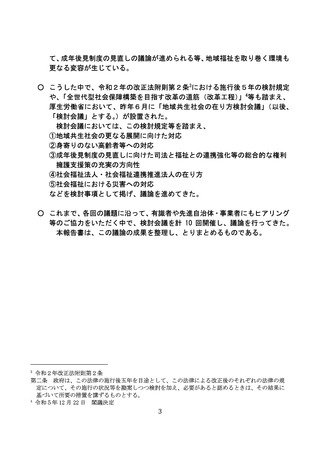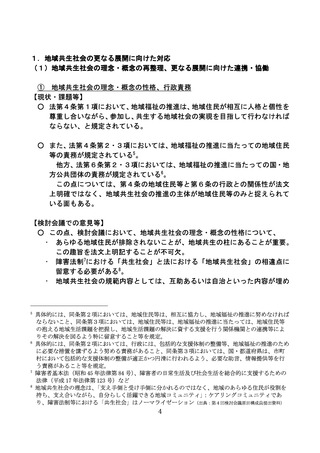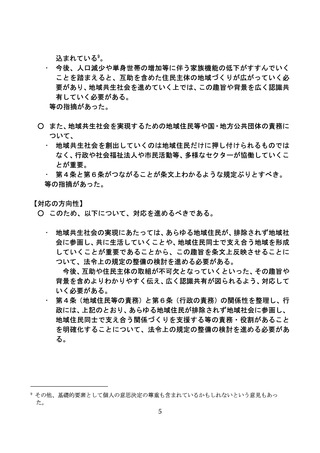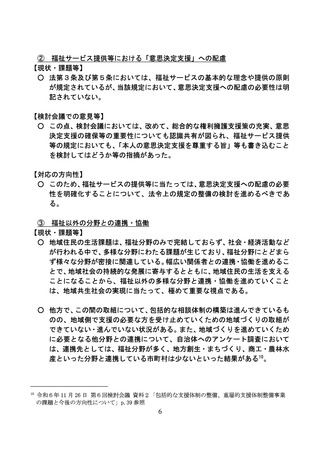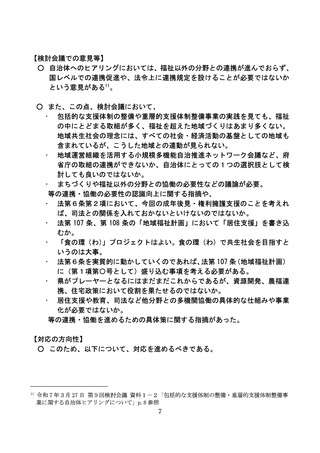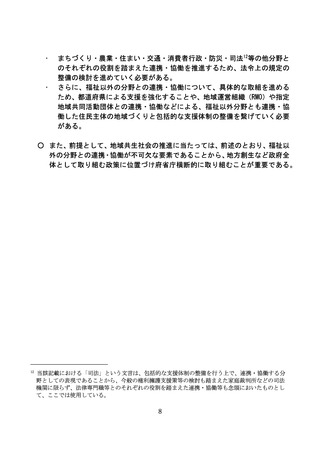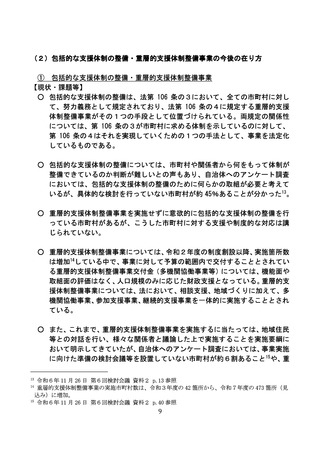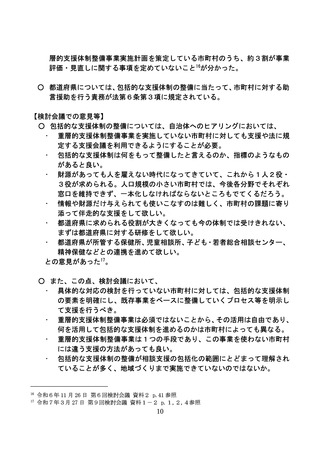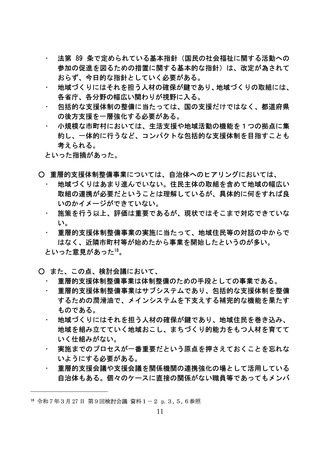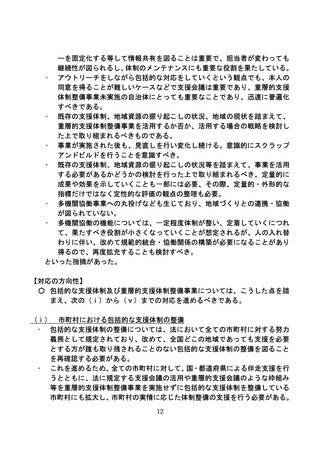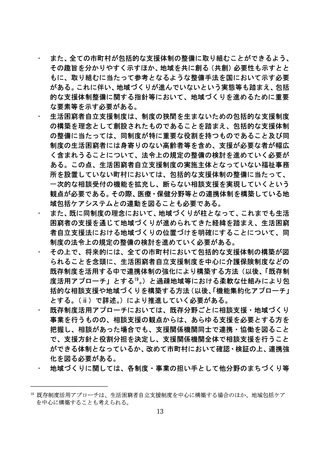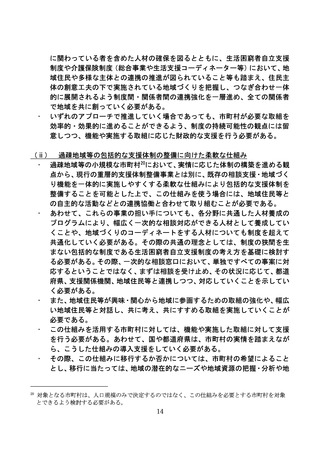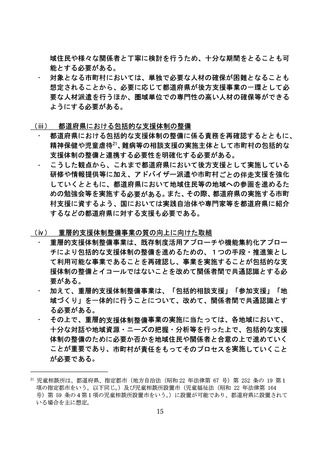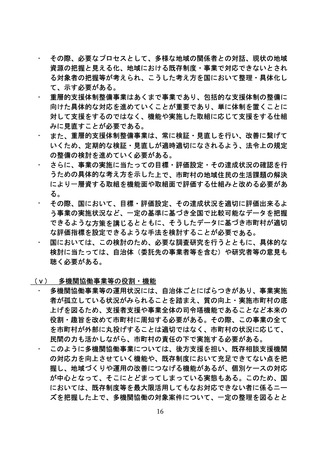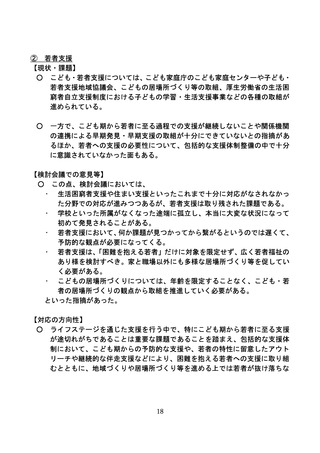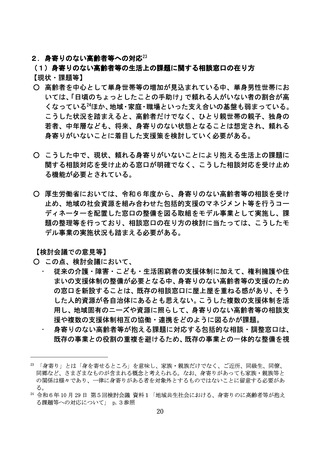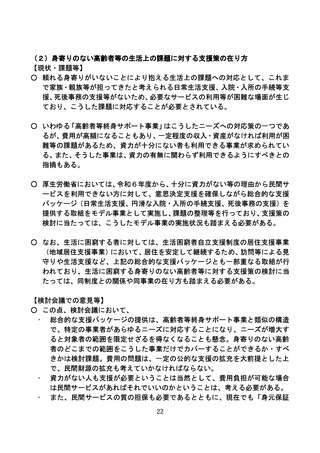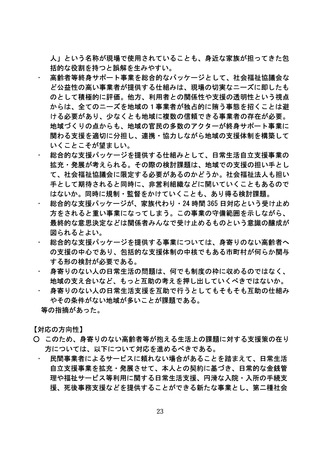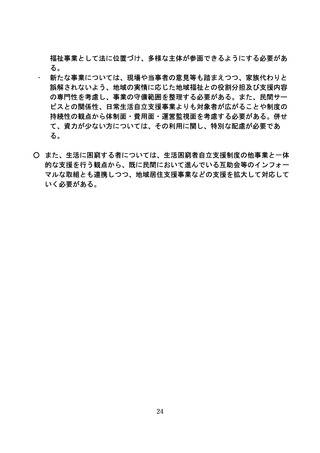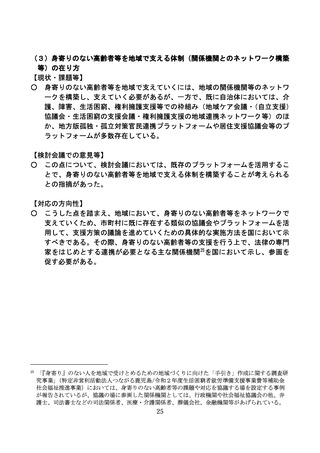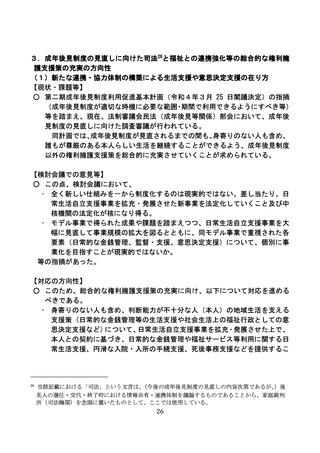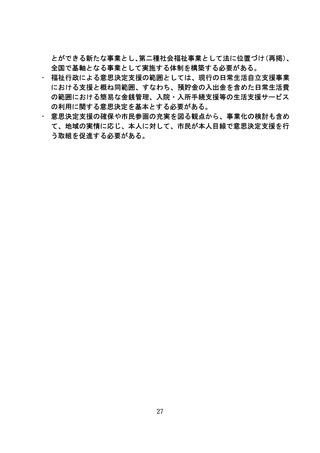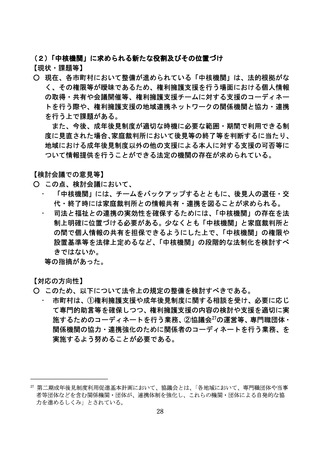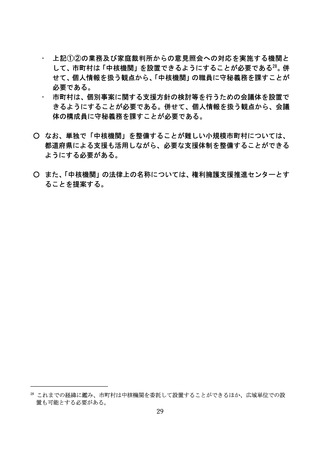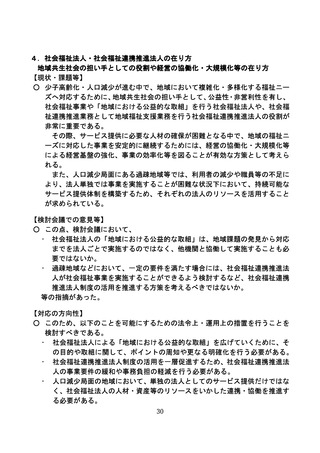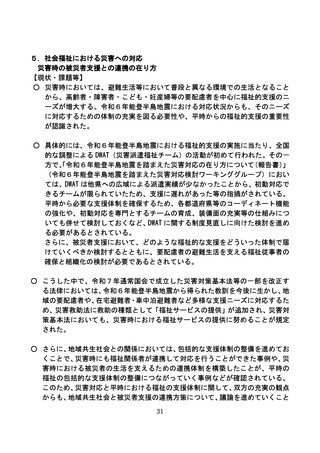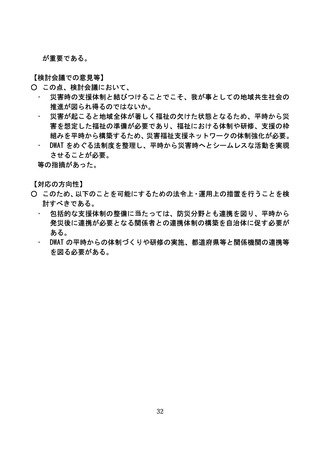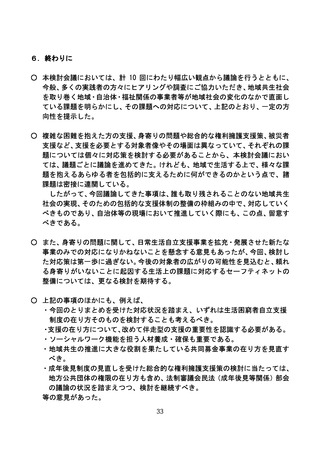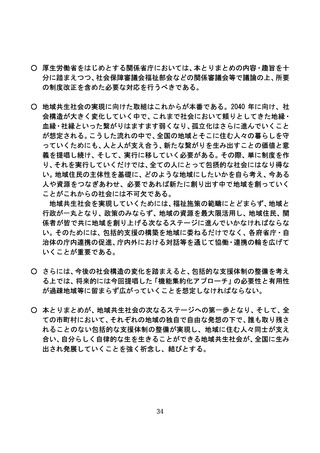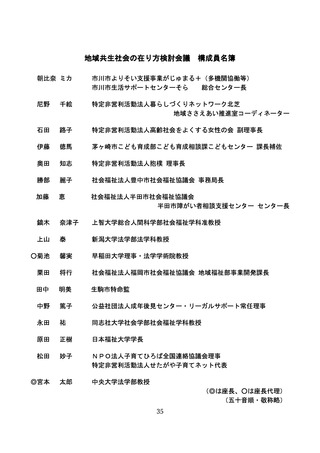よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ーを固定化する等して情報共有を図ることは重要で、担当者が変わっても
継続性が図られるし、体制のメンテナンスにも重要な役割を果たしている。
アウトリーチをしながら包括的な対応をしていくという観点でも、本人の
同意を得ることが難しいケースなどで支援会議は重要であり、重層的支援
体制整備事業未実施の自治体にとっても重要なことであり、迅速に普遍化
すべきである。
既存の支援体制、地域資源の掘り起こしの状況、地域の現状を踏まえて、
重層的支援体制整備事業を活用するか否か、活用する場合の戦略を検討し
た上で取り組まれるべきものである。
事業が実施された後も、見直しを行い変化し続ける。意識的にスクラップ
アンドビルドを行うことを意識すべき。
既存の支援体制、地域資源の掘り起こしの状況等を踏まえて、事業を活用
する必要があるかどうかの検討を行った上で取り組まれるべき、定量的に
成果や効果を示していくことも一部には必要、その際、定量的・外形的な
指標だけではなく定性的な評価の観点の整理も必要。
多機関協働事業への丸投げなども生じており、地域づくりとの連携・協働
が図られていない。
多機関協働の機能については、一定程度体制が整い、定着していくにつれ
て、果たすべき役割が小さくなっていくことが想定されるが、人の入れ替
わりに伴い、改めて規範的統合・協働関係の構築が必要になることがあり
得るので、再度拡充することも検討すべき。
といった指摘があった。
【対応の方向性】
○ 包括的な支援体制及び重層的支援体制整備事業については、こうした点を踏
まえ、次の(ⅰ)から(ⅴ)までの対応を進めるべきである。
(ⅰ) 市町村における包括的な支援体制の整備
包括的な支援体制の整備については、法において全ての市町村に対する努力
義務として規定されており、改めて、全国どこの地域であっても支援を必要
とする方が誰も取り残されることのない包括的な支援体制の整備を図ること
を再確認する必要がある。
これを進めるため、全ての市町村に対して、国・都道府県による伴走支援を行
うとともに、法に規定する支援会議の活用や重層的支援会議のような枠組み
等を重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している
市町村にも拡大し、市町村の実情に応じた体制整備の支援を行う必要がある。
12
継続性が図られるし、体制のメンテナンスにも重要な役割を果たしている。
アウトリーチをしながら包括的な対応をしていくという観点でも、本人の
同意を得ることが難しいケースなどで支援会議は重要であり、重層的支援
体制整備事業未実施の自治体にとっても重要なことであり、迅速に普遍化
すべきである。
既存の支援体制、地域資源の掘り起こしの状況、地域の現状を踏まえて、
重層的支援体制整備事業を活用するか否か、活用する場合の戦略を検討し
た上で取り組まれるべきものである。
事業が実施された後も、見直しを行い変化し続ける。意識的にスクラップ
アンドビルドを行うことを意識すべき。
既存の支援体制、地域資源の掘り起こしの状況等を踏まえて、事業を活用
する必要があるかどうかの検討を行った上で取り組まれるべき、定量的に
成果や効果を示していくことも一部には必要、その際、定量的・外形的な
指標だけではなく定性的な評価の観点の整理も必要。
多機関協働事業への丸投げなども生じており、地域づくりとの連携・協働
が図られていない。
多機関協働の機能については、一定程度体制が整い、定着していくにつれ
て、果たすべき役割が小さくなっていくことが想定されるが、人の入れ替
わりに伴い、改めて規範的統合・協働関係の構築が必要になることがあり
得るので、再度拡充することも検討すべき。
といった指摘があった。
【対応の方向性】
○ 包括的な支援体制及び重層的支援体制整備事業については、こうした点を踏
まえ、次の(ⅰ)から(ⅴ)までの対応を進めるべきである。
(ⅰ) 市町村における包括的な支援体制の整備
包括的な支援体制の整備については、法において全ての市町村に対する努力
義務として規定されており、改めて、全国どこの地域であっても支援を必要
とする方が誰も取り残されることのない包括的な支援体制の整備を図ること
を再確認する必要がある。
これを進めるため、全ての市町村に対して、国・都道府県による伴走支援を行
うとともに、法に規定する支援会議の活用や重層的支援会議のような枠組み
等を重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している
市町村にも拡大し、市町村の実情に応じた体制整備の支援を行う必要がある。
12