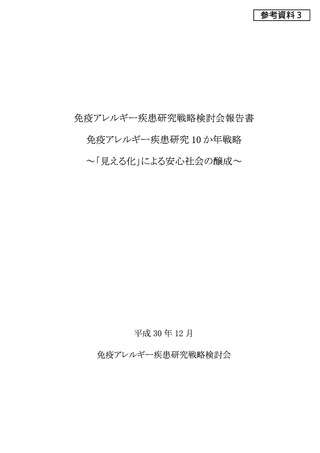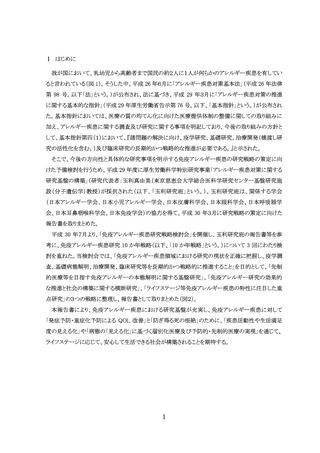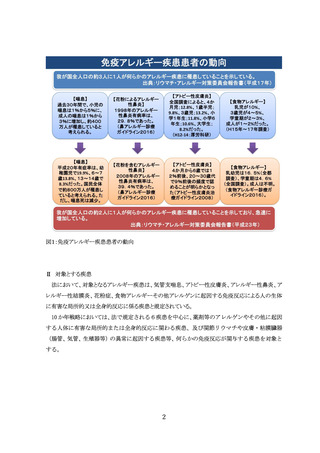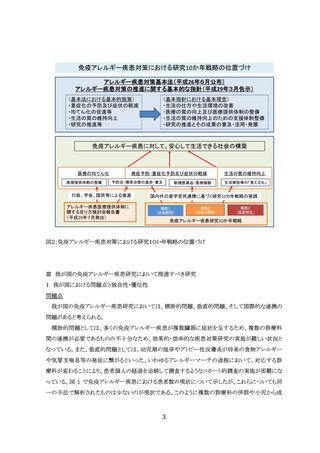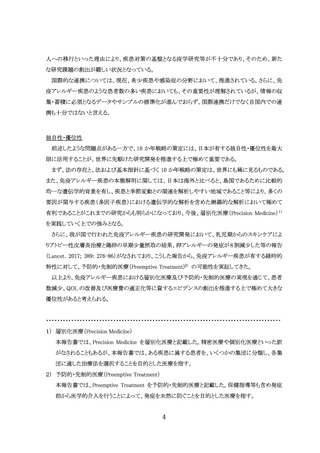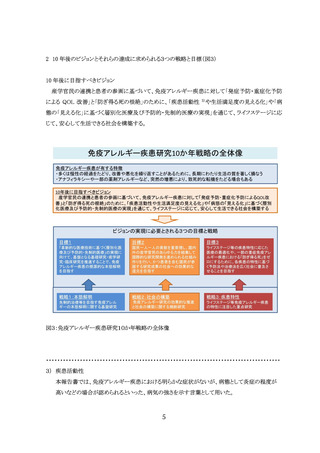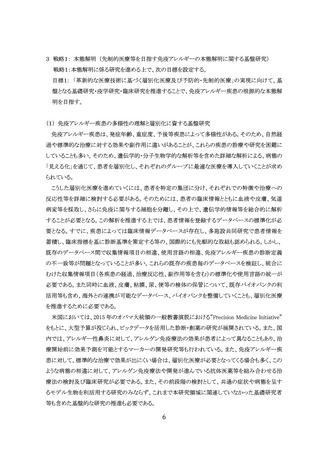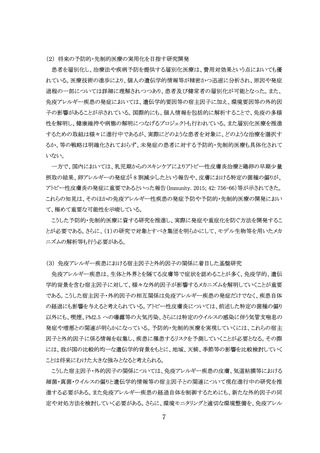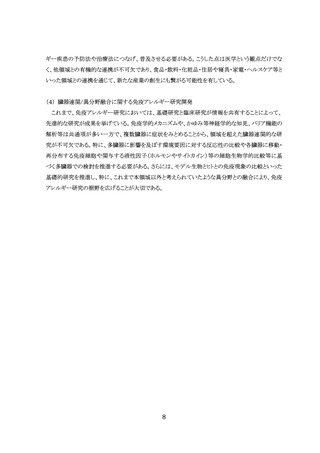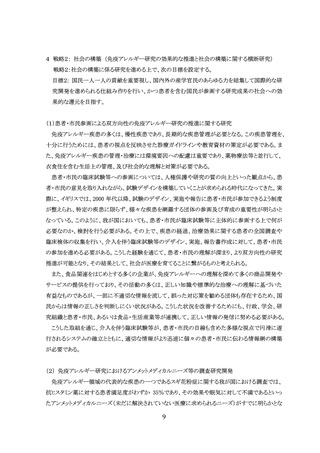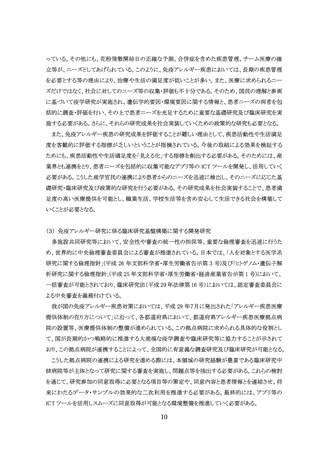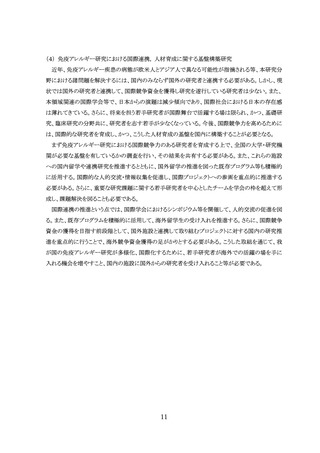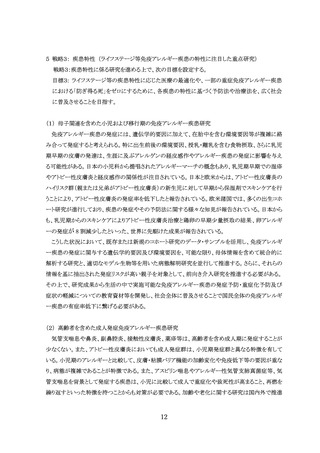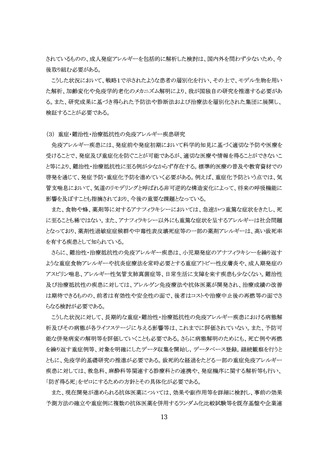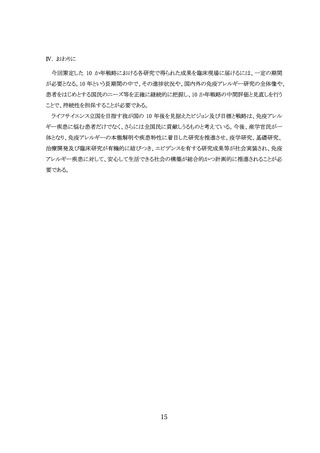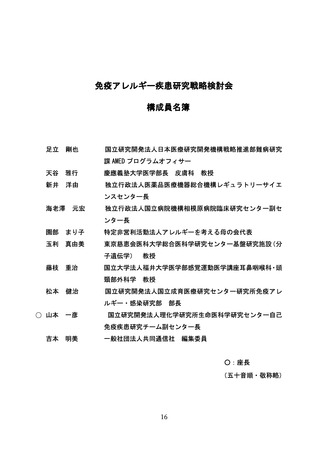よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3】免疫アレルギー疾患研究10か年戦略 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
携のもとに実施し、適切な患者に適切な薬剤が用いられるようにすることが、医療費の観点からも必要
である。
(4) 希少疾患と関連する免疫アレルギー疾患研究
希少疾患に用いる医薬品に対しては、医療上の必要性や開発の可能性を踏まえ、薬事・食品衛生
審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が希少疾病用医薬品として指定する制度があり、対象となる医
薬品の早期承認に資している。医薬品の承認審査における「希少疾病用医薬品等の指定制度」の実
施に加え、2017 年 10 月より「医薬品条件付き早期承認制度」が導入され、重篤な疾患を対象とし、医
療上の有用性が高く、何らかの試験で一定の有効性、安全性が示されている一方で、検証的な臨床
試験の実施が困難な医薬品での迅速な実用化を支援するための枠組み作りが進んでいる。 免疫ア
レルギー疾患の中にも、好酸球性副鼻腔炎のような希少疾患に該当する疾患が存在し、積極的に希
少疾患領域での開発支援制度を有効活用していくことが望まれる。
また希少疾患領域においては、診断がつかない患者に対する遺伝子診断等により希少疾患やこれ
までに知られていない新しい疾患を診断することを目的とした未診断疾患イニシアチブ(Initiative on
Rare and Undiagnosed Diseases:IRUD)という取組や、さらには国際的に患者登録を行い、モデル生
物等を活用して治療法の開発を目的とした国際コンソーシアム(IRUD Beyond)といった取組が、国立
研究開発法人日本医療開発研究機構により推進され、成果を上げている。
こうした状況において、研究者、企業、開発推進者等が連携し、希少疾患領域での検討を含め、現
在の研究開発状況を整理することが必要である。その中で、特に、単一遺伝子変異に起因する希少
疾患の中には、免疫アレルギー疾患症状を呈するものがあり、その遺伝子の機能や病態の解析をす
ることによって、免疫アレルギー疾患の治療対象となる分子が判明する可能性がある。その遺伝子変
異を持つモデル生物等を用いて、新規の創薬につなげることも期待できる。
14
である。
(4) 希少疾患と関連する免疫アレルギー疾患研究
希少疾患に用いる医薬品に対しては、医療上の必要性や開発の可能性を踏まえ、薬事・食品衛生
審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が希少疾病用医薬品として指定する制度があり、対象となる医
薬品の早期承認に資している。医薬品の承認審査における「希少疾病用医薬品等の指定制度」の実
施に加え、2017 年 10 月より「医薬品条件付き早期承認制度」が導入され、重篤な疾患を対象とし、医
療上の有用性が高く、何らかの試験で一定の有効性、安全性が示されている一方で、検証的な臨床
試験の実施が困難な医薬品での迅速な実用化を支援するための枠組み作りが進んでいる。 免疫ア
レルギー疾患の中にも、好酸球性副鼻腔炎のような希少疾患に該当する疾患が存在し、積極的に希
少疾患領域での開発支援制度を有効活用していくことが望まれる。
また希少疾患領域においては、診断がつかない患者に対する遺伝子診断等により希少疾患やこれ
までに知られていない新しい疾患を診断することを目的とした未診断疾患イニシアチブ(Initiative on
Rare and Undiagnosed Diseases:IRUD)という取組や、さらには国際的に患者登録を行い、モデル生
物等を活用して治療法の開発を目的とした国際コンソーシアム(IRUD Beyond)といった取組が、国立
研究開発法人日本医療開発研究機構により推進され、成果を上げている。
こうした状況において、研究者、企業、開発推進者等が連携し、希少疾患領域での検討を含め、現
在の研究開発状況を整理することが必要である。その中で、特に、単一遺伝子変異に起因する希少
疾患の中には、免疫アレルギー疾患症状を呈するものがあり、その遺伝子の機能や病態の解析をす
ることによって、免疫アレルギー疾患の治療対象となる分子が判明する可能性がある。その遺伝子変
異を持つモデル生物等を用いて、新規の創薬につなげることも期待できる。
14