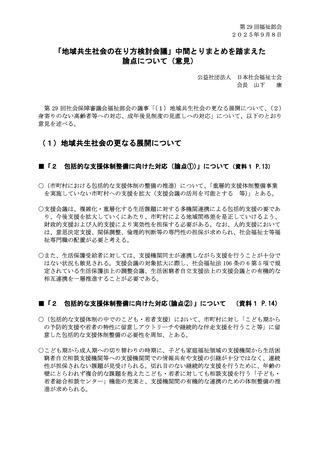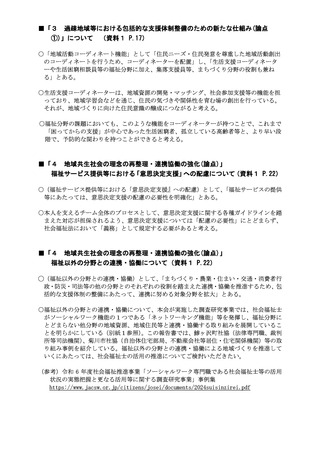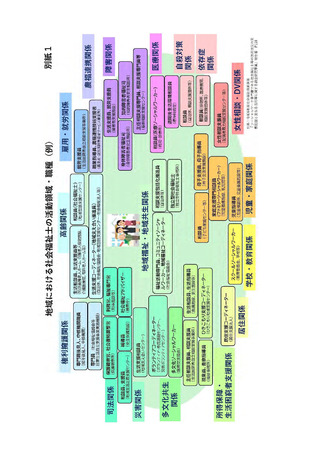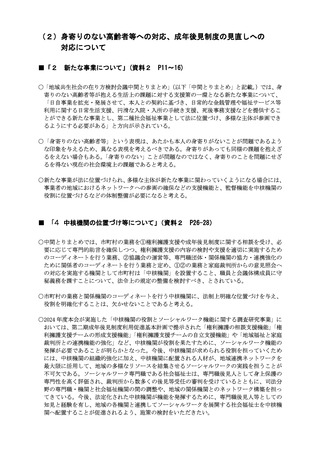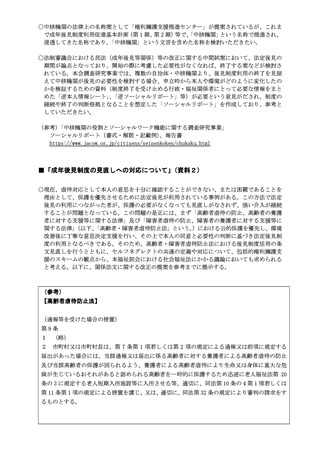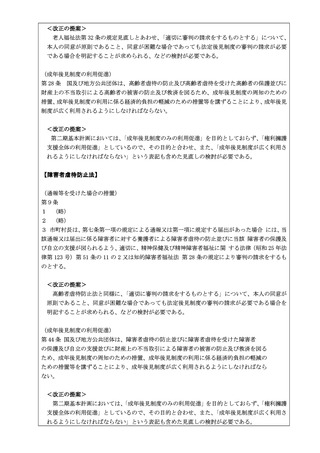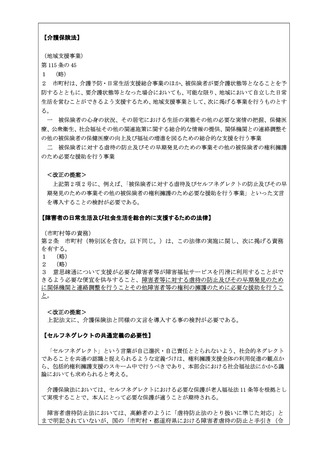よむ、つかう、まなぶ。
山下委員提出資料 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○中核機関の法律上の名称案として「権利擁護支援推進センター」が提案されているが、これま
で成年後見制度利用促進基本計画(第 1 期、第 2 期)等で、
「中核機関」という名称で推進され、
浸透してきた名称であり、
「中核機関」という文言を含めた名称を検討いただきたい。
○法制審議会における民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案において、法定後見の
期間が論点となっており、開始の際に考慮した必要性がなくなれば、終了する案などが検討さ
れている。本会調査研究事業では、複数の自治体・中核機関より、後見制度利用の終了を見据
えて中核機関が後見の必要性を検討する場合、申立時から本人や環境がどのように変化したの
かを検証するための資料(制度終了を受け止める行政・福祉関係者にとって必要な情報をまと
めた「逆本人情報シート」
、「逆ソーシャルリポート」等)が必要という意見がだされ、制度の
継続や終了の判断根拠となることを想定した「ソーシャルリポート」を作成しており、参考と
していただきたい。
(参考)
「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」
ソーシャルリポート(書式・解説・記載例)
、報告書
https://www.jacsw.or.jp/citizens/seinenkoken/chukaku.html
■「成年後見制度の見直しへの対応について」(資料2)
○現在、虐待対応として本人の意思を十分に確認することができない、または困難であることを
理由として、保護を優先させるために法定後見が利用されている事例がある。この方法で法定
後見の利用につながった者が、保護の必要がなくなっても見直しがなされず、強い介入が継続
することが問題となっている。この問題の是正には、まず「高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律」及び「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律」
(以下、
「高齢者・障害者虐待防止法」という。
)における公的保護を優先し、環境
改善後に丁寧な意思決定支援を行い、その上で本人の同意と必要性の判断に基づき法定後見制
度の利用となるべきである。そのため、高齢者・障害者虐待防止法における後見制度活用の条
文見直しを行うとともに、セルフネグレクトの共通の定義や対応について、包括的権利擁護支
援のスキームの観点から、本福祉部会における社会福祉法にかかる議論においても求められる
と考える。以下に、関係法文に関する改正の提案を参考までに提示する。
(参考)
【高齢者虐待防止法】
(通報等を受けた場合の措置)
第9条
1 (略)
2 市町村又は市町村長は、第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による通報又は前項に規定する
届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止
及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危
険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第 20
条の 3 に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第 10 条の 4 第 1 項若しくは
第 11 条第 1 項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第 32 条の規定により審判の請求をす
るものとする。
で成年後見制度利用促進基本計画(第 1 期、第 2 期)等で、
「中核機関」という名称で推進され、
浸透してきた名称であり、
「中核機関」という文言を含めた名称を検討いただきたい。
○法制審議会における民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案において、法定後見の
期間が論点となっており、開始の際に考慮した必要性がなくなれば、終了する案などが検討さ
れている。本会調査研究事業では、複数の自治体・中核機関より、後見制度利用の終了を見据
えて中核機関が後見の必要性を検討する場合、申立時から本人や環境がどのように変化したの
かを検証するための資料(制度終了を受け止める行政・福祉関係者にとって必要な情報をまと
めた「逆本人情報シート」
、「逆ソーシャルリポート」等)が必要という意見がだされ、制度の
継続や終了の判断根拠となることを想定した「ソーシャルリポート」を作成しており、参考と
していただきたい。
(参考)
「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」
ソーシャルリポート(書式・解説・記載例)
、報告書
https://www.jacsw.or.jp/citizens/seinenkoken/chukaku.html
■「成年後見制度の見直しへの対応について」(資料2)
○現在、虐待対応として本人の意思を十分に確認することができない、または困難であることを
理由として、保護を優先させるために法定後見が利用されている事例がある。この方法で法定
後見の利用につながった者が、保護の必要がなくなっても見直しがなされず、強い介入が継続
することが問題となっている。この問題の是正には、まず「高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律」及び「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律」
(以下、
「高齢者・障害者虐待防止法」という。
)における公的保護を優先し、環境
改善後に丁寧な意思決定支援を行い、その上で本人の同意と必要性の判断に基づき法定後見制
度の利用となるべきである。そのため、高齢者・障害者虐待防止法における後見制度活用の条
文見直しを行うとともに、セルフネグレクトの共通の定義や対応について、包括的権利擁護支
援のスキームの観点から、本福祉部会における社会福祉法にかかる議論においても求められる
と考える。以下に、関係法文に関する改正の提案を参考までに提示する。
(参考)
【高齢者虐待防止法】
(通報等を受けた場合の措置)
第9条
1 (略)
2 市町村又は市町村長は、第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による通報又は前項に規定する
届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止
及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危
険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第 20
条の 3 に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第 10 条の 4 第 1 項若しくは
第 11 条第 1 項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第 32 条の規定により審判の請求をす
るものとする。