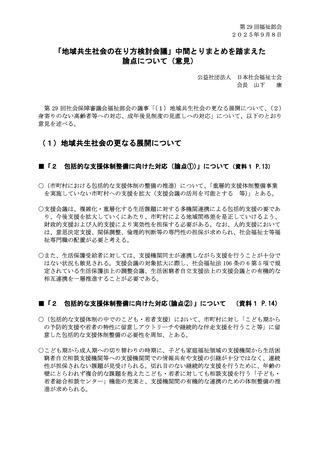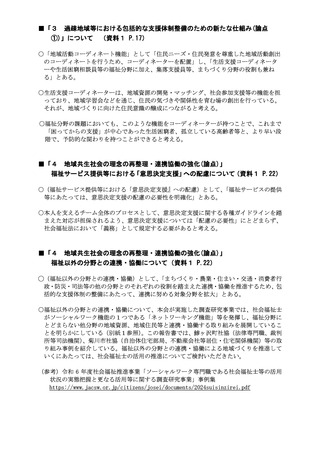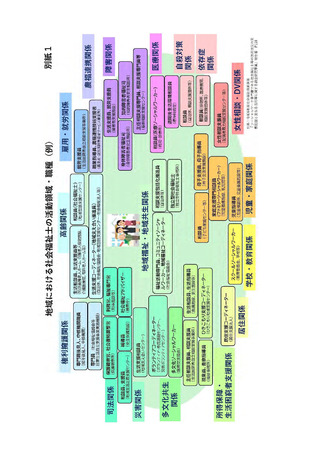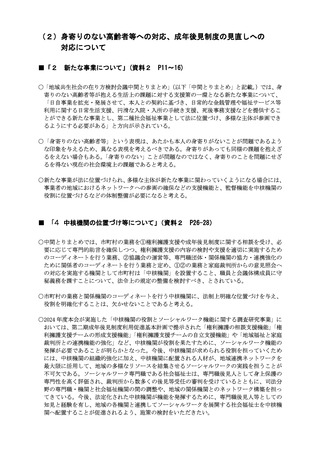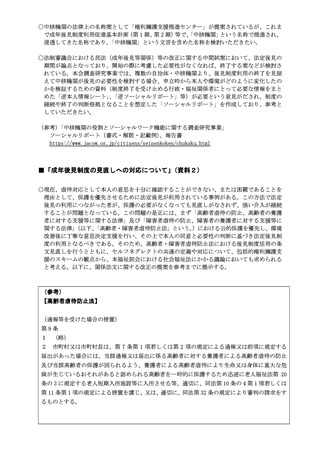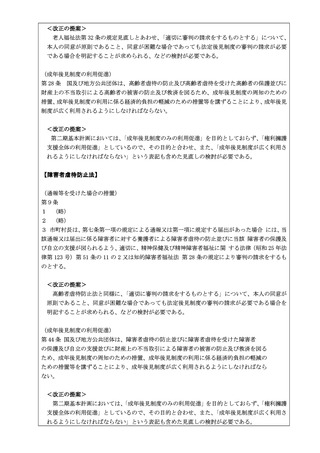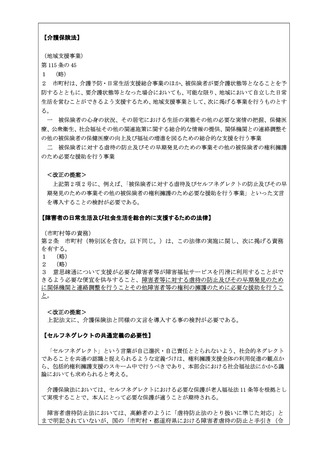よむ、つかう、まなぶ。
山下委員提出資料 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 29 回福祉部会
2025年9月8日
「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめを踏まえた
論点について(意見)
公益社団法人 日本社会福祉士会
会長 山下
康
第 29 回社会保障審議会福祉部会の議事「(1)地域共生社会の更なる展開について、
(2)
身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応」について、以下のとおり
意見を述べる。
(1)地域共生社会の更なる展開について
■「2
包括的な支援体制整備に向けた対応(論点①)」について(資料1 P.13)
○(市町村における包括的な支援体制の整備の推進)について、
「重層的支援体制整備事業
を実施していない市町村への支援を拡大(支援会議の活用を可能とする 等)
」とある。
○支援会議は、複雑化・重層化する生活課題に対する多機関連携による包括的支援の要であ
り、今後支援を拡大していくにあたり、市町村による地域間格差を是正していけるよう、
財政的支援および人的支援により実効性を担保する必要がある。なお、人的支援において
は、意思決定支援、関係調整、倫理的判断等の専門性の担保が求められ、社会福祉士等福
祉専門職の配置が必要と考える。
○また、生活保護受給者に対しては、支援機関同士が連携しながら支援を行うことが十分で
はない状況も散見される。支援会議の対象拡大に際し、社会福祉法 106 条の 6 第 5 項で規
定されている生活保護法上の調整会議、生活困窮者自立支援法上の支援会議との有機的な
相互連携を一層推進することが必要である。
■「2
包括的な支援体制整備に向けた対応(論点②)」について
(資料1 P.14)
○(包括的な支援体制の中でのこども・若者支援)において、市町村に対し「こども期から
の予防的支援や若者の特性に留意しアウトリーチや継続的な伴走支援を行うこと等」に留
意した包括的な支援体制整備の必要性を周知、とある。
○こども期から成人期への切り替わりの時期に、子ども家庭福祉領域の支援機関から生活困
窮者自立相談支援機関等への支援機関間での情報共有や支援の引継が十分ではなく、連続
性が担保されない課題が見受けられる。切れ目のない継続的な支援を行うために、年齢の
壁にとらわれず複合的な課題を抱えたこども・若者に対しても相談支援を行う「子ども・
若者総合相談センター」機能の充実と、支援機関間の有機的な連携のための体制整備の推
進が求められる。
2025年9月8日
「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめを踏まえた
論点について(意見)
公益社団法人 日本社会福祉士会
会長 山下
康
第 29 回社会保障審議会福祉部会の議事「(1)地域共生社会の更なる展開について、
(2)
身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応」について、以下のとおり
意見を述べる。
(1)地域共生社会の更なる展開について
■「2
包括的な支援体制整備に向けた対応(論点①)」について(資料1 P.13)
○(市町村における包括的な支援体制の整備の推進)について、
「重層的支援体制整備事業
を実施していない市町村への支援を拡大(支援会議の活用を可能とする 等)
」とある。
○支援会議は、複雑化・重層化する生活課題に対する多機関連携による包括的支援の要であ
り、今後支援を拡大していくにあたり、市町村による地域間格差を是正していけるよう、
財政的支援および人的支援により実効性を担保する必要がある。なお、人的支援において
は、意思決定支援、関係調整、倫理的判断等の専門性の担保が求められ、社会福祉士等福
祉専門職の配置が必要と考える。
○また、生活保護受給者に対しては、支援機関同士が連携しながら支援を行うことが十分で
はない状況も散見される。支援会議の対象拡大に際し、社会福祉法 106 条の 6 第 5 項で規
定されている生活保護法上の調整会議、生活困窮者自立支援法上の支援会議との有機的な
相互連携を一層推進することが必要である。
■「2
包括的な支援体制整備に向けた対応(論点②)」について
(資料1 P.14)
○(包括的な支援体制の中でのこども・若者支援)において、市町村に対し「こども期から
の予防的支援や若者の特性に留意しアウトリーチや継続的な伴走支援を行うこと等」に留
意した包括的な支援体制整備の必要性を周知、とある。
○こども期から成人期への切り替わりの時期に、子ども家庭福祉領域の支援機関から生活困
窮者自立相談支援機関等への支援機関間での情報共有や支援の引継が十分ではなく、連続
性が担保されない課題が見受けられる。切れ目のない継続的な支援を行うために、年齢の
壁にとらわれず複合的な課題を抱えたこども・若者に対しても相談支援を行う「子ども・
若者総合相談センター」機能の充実と、支援機関間の有機的な連携のための体制整備の推
進が求められる。