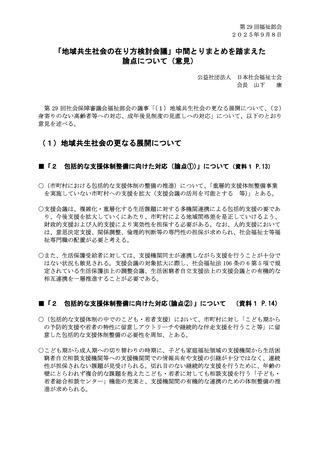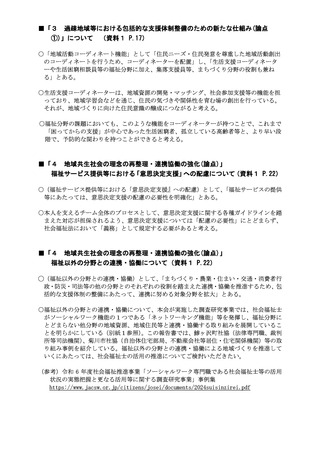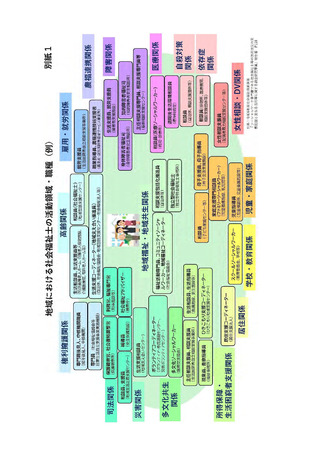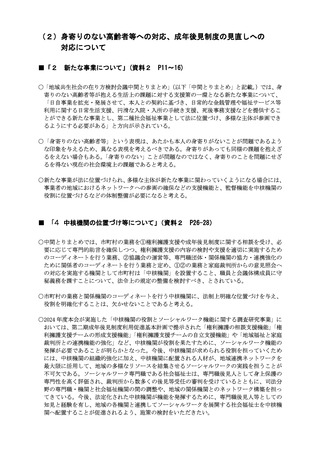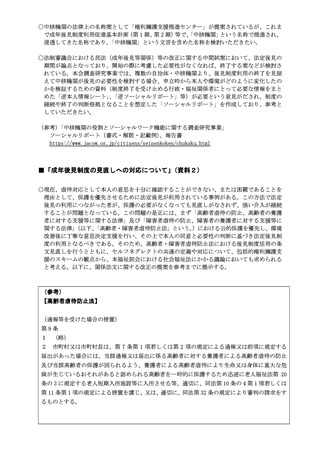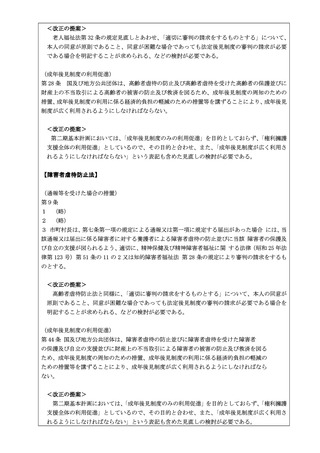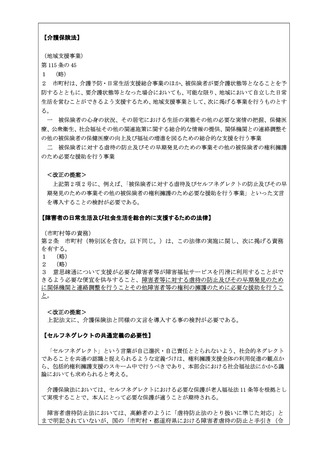よむ、つかう、まなぶ。
山下委員提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
■「3 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点
①)」について (資料1 P.17)
○「地域活動コーディネート機能」として「住民ニーズ・住民発意を尊重した地域活動創出
のコーディネートを行うため、コーディネーターを配置」し、
「生活支援コーディネータ
ーや生活困窮相談員等の福祉分野に加え、集落支援員等、まちづくり分野の役割も兼ね
る」とある。
○生活支援コーディネーターは、地域資源の開発・マッチング、社会参加支援等の機能を担
っており、地域学習会などを通じ、住民の気づきや関係性を育む場の創出を行っている。
それが、地域づくりに向けた住民意識の醸成につながると考える。
○福祉分野の課題においても、このような機能をコーディネーターが持つことで、これまで
「困ってからの支援」が中心であった生活困窮者、孤立している高齢者等と、より早い段
階で、予防的な関わりを持つことができると考える。
■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」
福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮について(資料1 P.22)
○(福祉サービス提供等における「意思決定支援』への配慮)として、
「福祉サービスの提供
等にあたっては、意思決定支援の配慮の必要性を明確化」とある。
○本人を支えるチーム全体のプロセスとして、意思決定支援に関する各種ガイドラインを踏
まえた対応が担保されるよう、意思決定支援については「配慮の必要性」にとどまらず、
社会福祉法において「義務」として規定する必要があると考える。
■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」
福祉以外の分野との連携・協働について(資料1 P.22)
◯(福祉以外の分野との連携・協働)として、
「まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行
政・防災・司法等の他の分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、包
括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大」とある。
○福祉以外の分野との連携・協働について、本会が実施した調査研究事業では、社会福祉士
がソーシャルワーク機能の1つである「ネットワーキング機能」等を発揮し、福祉分野に
とどまらない他分野の地域資源、地域住民等と連携・協働する取り組みを展開しているこ
とを明らかにしている(別紙1参照)
。この報告書では、鰺ヶ沢町社協(法律専門職、裁判
所等司法機関)、菊川市社協(自治体住宅部局、不動産会社等居住・住宅関係機関)等の取
り組み事例を紹介している。福祉以外の分野との連携・協働による地域づくりを推進して
いくにあたっては、社会福祉士の活用の推進についてご検討いただきたい。
(参考)令和 6 年度社会福祉推進事業「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士等の活用
状況の実態把握と更なる活用等に関する調査研究事業」事例集
https://www.jacsw.or.jp/citizens/josei/documents/2024suisinzirei.pdf
①)」について (資料1 P.17)
○「地域活動コーディネート機能」として「住民ニーズ・住民発意を尊重した地域活動創出
のコーディネートを行うため、コーディネーターを配置」し、
「生活支援コーディネータ
ーや生活困窮相談員等の福祉分野に加え、集落支援員等、まちづくり分野の役割も兼ね
る」とある。
○生活支援コーディネーターは、地域資源の開発・マッチング、社会参加支援等の機能を担
っており、地域学習会などを通じ、住民の気づきや関係性を育む場の創出を行っている。
それが、地域づくりに向けた住民意識の醸成につながると考える。
○福祉分野の課題においても、このような機能をコーディネーターが持つことで、これまで
「困ってからの支援」が中心であった生活困窮者、孤立している高齢者等と、より早い段
階で、予防的な関わりを持つことができると考える。
■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」
福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮について(資料1 P.22)
○(福祉サービス提供等における「意思決定支援』への配慮)として、
「福祉サービスの提供
等にあたっては、意思決定支援の配慮の必要性を明確化」とある。
○本人を支えるチーム全体のプロセスとして、意思決定支援に関する各種ガイドラインを踏
まえた対応が担保されるよう、意思決定支援については「配慮の必要性」にとどまらず、
社会福祉法において「義務」として規定する必要があると考える。
■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」
福祉以外の分野との連携・協働について(資料1 P.22)
◯(福祉以外の分野との連携・協働)として、
「まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行
政・防災・司法等の他の分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、包
括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大」とある。
○福祉以外の分野との連携・協働について、本会が実施した調査研究事業では、社会福祉士
がソーシャルワーク機能の1つである「ネットワーキング機能」等を発揮し、福祉分野に
とどまらない他分野の地域資源、地域住民等と連携・協働する取り組みを展開しているこ
とを明らかにしている(別紙1参照)
。この報告書では、鰺ヶ沢町社協(法律専門職、裁判
所等司法機関)、菊川市社協(自治体住宅部局、不動産会社等居住・住宅関係機関)等の取
り組み事例を紹介している。福祉以外の分野との連携・協働による地域づくりを推進して
いくにあたっては、社会福祉士の活用の推進についてご検討いただきたい。
(参考)令和 6 年度社会福祉推進事業「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士等の活用
状況の実態把握と更なる活用等に関する調査研究事業」事例集
https://www.jacsw.or.jp/citizens/josei/documents/2024suisinzirei.pdf