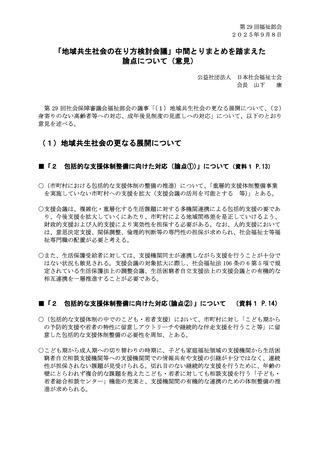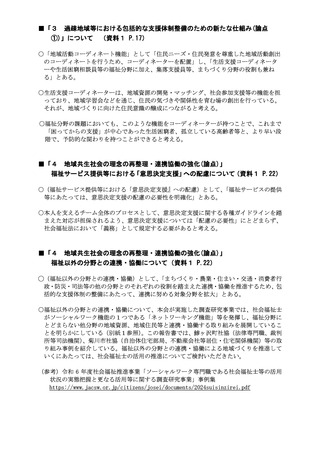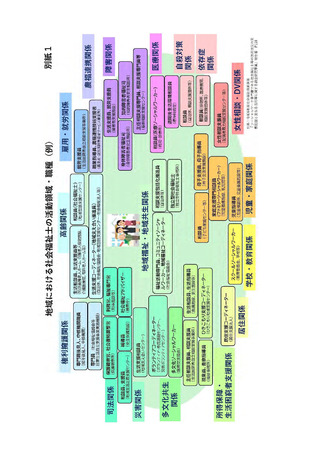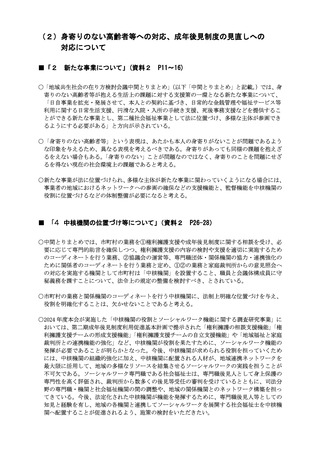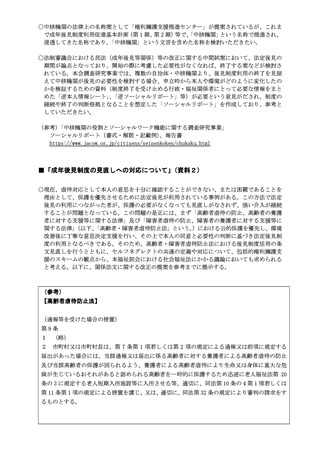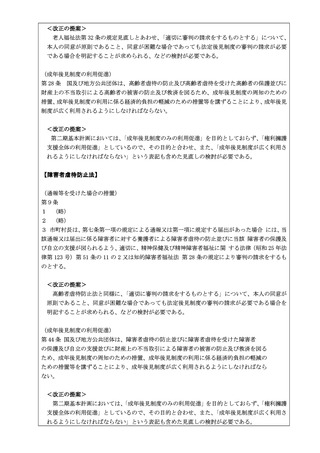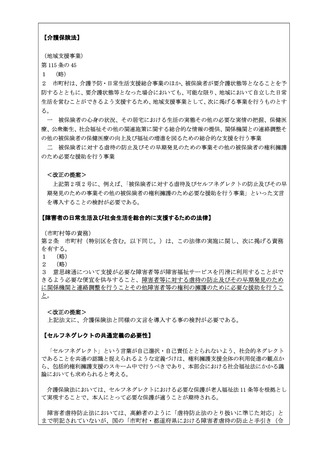よむ、つかう、まなぶ。
山下委員提出資料 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの
対応について
■「2
新たな事業について」(資料2
P11~16)
○「地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ」
(以下「中間とりまとめ」と記載。
)では、身
寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の一環となる新たな事業について、
「日自事業を拡充・発展させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等
利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続き支援、死後事務支援などを提供するこ
とができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画でき
るようにする必要がある」と方向が示されている。
○「身寄りのない高齢者等」という表現は、あたかも本人の身寄りがないことが問題であるよう
な印象を与えるため、異なる表現を考えるべきである。身寄りがあっても同様の課題を抱えざ
るをえない場合もある。
「身寄りのない」ことが問題なのではなく、身寄りのことを問題にせざ
るを得ない現在の社会環境上の課題であると考える。
○新たな事業が法に位置づけられ、多様な主体が新たな事業に関わっていくようになる場合には、
事業者の地域におけるネットワークへの参画の確保などの支援機能と、監督機能を中核機関の
役割に位置づけるなどの体制整備が必要になると考える。
■
「4 中核機関の位置づけ等について」(資料2
P26-28)
○中間とりまとめでは、市町村の業務を①権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必
要に応じて専門的助言を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するため
のコーディネートを行う業務、②協議会の運営等、専門職団体・関係機関の協力・連携強化の
ために関係者のコーディネートを行う業務と定め、①②の業務と家庭裁判所からの意見照会へ
の対応を実施する機関として市町村は「中核機関」を設置すること、職員と会議体構成員に守
秘義務を課すことについて、法令上の規定の整備を検討すべき、とされている。
○市町村の業務と関係機関のコーディネートを行う中核機関に、法制上明確な位置づけを与え、
役割を明確化することは、欠かせないことであると考える。
○2024 年度本会が実施した「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」に
おいては、第二期成年後見制度利用促進基本計画で提示された「権利擁護の相談支援機能」
「権
利擁護支援チームの形成支援機能」
「権利擁護支援チームの自立支援機能」や「地域福祉と家庭
裁判所との連携機能の強化」など、中核機関が役割を果たすために、ソーシャルワーク機能の
発揮が必要であることが明らかとなった。今後、中核機関が求められる役割を担っていくため
には、中核機関の組織的強化に加え、中核機関に配置される人材が、地域連携ネットワークを
最大限に活用して、地域の多様なリソースを結集させるソーシャルワークの実践を担うことが
不可欠である。ソーシャルワーク専門職である社会福祉士は、専門職後見人として身上保護の
専門性を高く評価され、裁判所から数多くの後見等受任の審判を受けているとともに、司法分
野の専門職・機関と社会福祉機関の間の調整や、地域の関係機関とのネットワーク構築を担っ
てきている。今後、法定化された中核機関が機能を発揮するために、専門職後見人等としての
知見と経験を有し、地域の各機関と連携してソーシャルワークを展開する社会福祉士を中核機
関へ配置することが促進されるよう、施策の検討をいただきたい。
対応について
■「2
新たな事業について」(資料2
P11~16)
○「地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ」
(以下「中間とりまとめ」と記載。
)では、身
寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の一環となる新たな事業について、
「日自事業を拡充・発展させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等
利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続き支援、死後事務支援などを提供するこ
とができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画でき
るようにする必要がある」と方向が示されている。
○「身寄りのない高齢者等」という表現は、あたかも本人の身寄りがないことが問題であるよう
な印象を与えるため、異なる表現を考えるべきである。身寄りがあっても同様の課題を抱えざ
るをえない場合もある。
「身寄りのない」ことが問題なのではなく、身寄りのことを問題にせざ
るを得ない現在の社会環境上の課題であると考える。
○新たな事業が法に位置づけられ、多様な主体が新たな事業に関わっていくようになる場合には、
事業者の地域におけるネットワークへの参画の確保などの支援機能と、監督機能を中核機関の
役割に位置づけるなどの体制整備が必要になると考える。
■
「4 中核機関の位置づけ等について」(資料2
P26-28)
○中間とりまとめでは、市町村の業務を①権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必
要に応じて専門的助言を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するため
のコーディネートを行う業務、②協議会の運営等、専門職団体・関係機関の協力・連携強化の
ために関係者のコーディネートを行う業務と定め、①②の業務と家庭裁判所からの意見照会へ
の対応を実施する機関として市町村は「中核機関」を設置すること、職員と会議体構成員に守
秘義務を課すことについて、法令上の規定の整備を検討すべき、とされている。
○市町村の業務と関係機関のコーディネートを行う中核機関に、法制上明確な位置づけを与え、
役割を明確化することは、欠かせないことであると考える。
○2024 年度本会が実施した「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」に
おいては、第二期成年後見制度利用促進基本計画で提示された「権利擁護の相談支援機能」
「権
利擁護支援チームの形成支援機能」
「権利擁護支援チームの自立支援機能」や「地域福祉と家庭
裁判所との連携機能の強化」など、中核機関が役割を果たすために、ソーシャルワーク機能の
発揮が必要であることが明らかとなった。今後、中核機関が求められる役割を担っていくため
には、中核機関の組織的強化に加え、中核機関に配置される人材が、地域連携ネットワークを
最大限に活用して、地域の多様なリソースを結集させるソーシャルワークの実践を担うことが
不可欠である。ソーシャルワーク専門職である社会福祉士は、専門職後見人として身上保護の
専門性を高く評価され、裁判所から数多くの後見等受任の審判を受けているとともに、司法分
野の専門職・機関と社会福祉機関の間の調整や、地域の関係機関とのネットワーク構築を担っ
てきている。今後、法定化された中核機関が機能を発揮するために、専門職後見人等としての
知見と経験を有し、地域の各機関と連携してソーシャルワークを展開する社会福祉士を中核機
関へ配置することが促進されるよう、施策の検討をいただきたい。