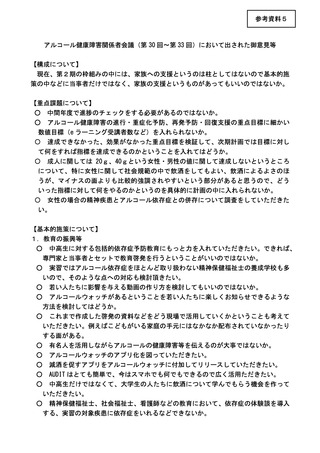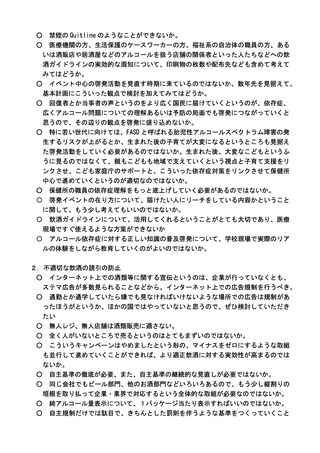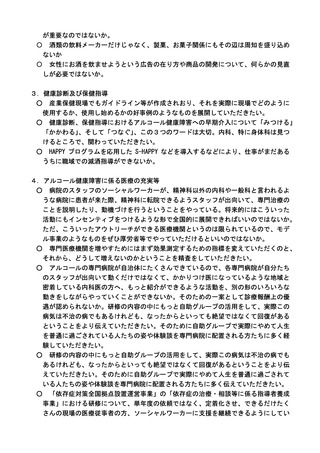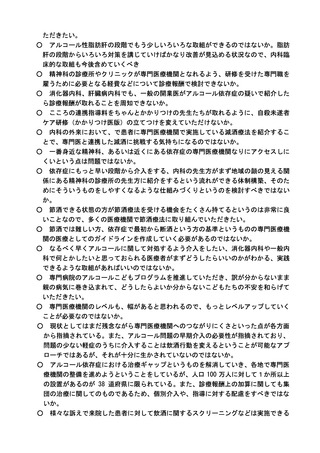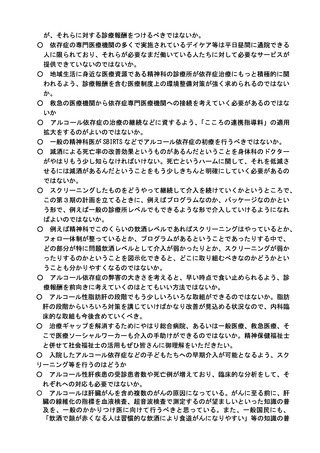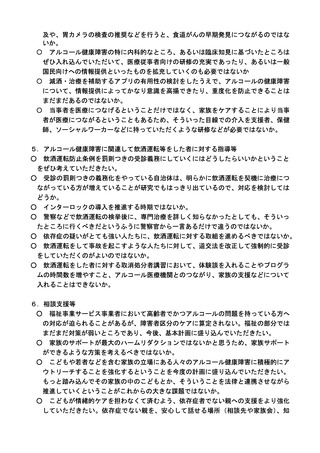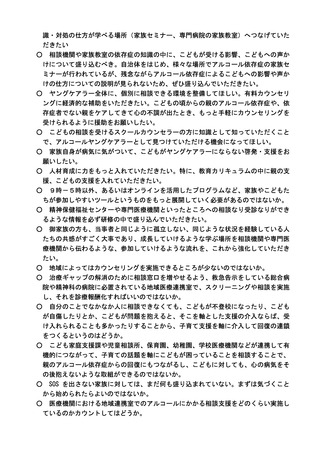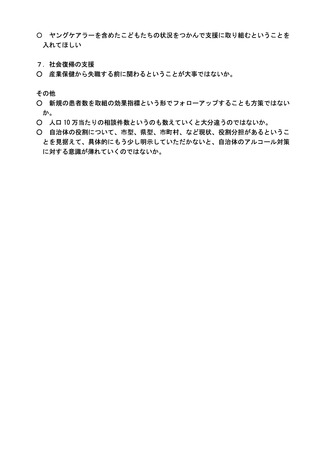よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 アルコール健康障害関係者会議(第30回~第33回)において出された御意見等 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html |
| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
識・対処の仕方が学べる場所(家族セミナー、専門病院の家族教室)へつなげていた
だきたい
○ 相談機関や家族教室の依存症の知識の中に、こどもが受ける影響、こどもへの声か
けについて盛り込むべき。自治体をはじめ、様々な場所でアルコール依存症の家族セ
ミナーが行われているが、残念ながらアルコール依存症によるこどもへの影響や声か
けの仕方についての説明が見られないため、ぜひ盛り込んでいただきたい。
○ ヤングケアラー全体に、個別に相談できる環境を整備してほしい。有料カウンセリ
ングに経済的な補助をいただきたい。こどもの頃からの親のアルコール依存症や、依
存症者でない親をケアしてきて心の不調が出たとき、もっと手軽にカウンセリングを
受けられるように援助をお願いしたい。
○ こどもの相談を受けるスクールカウンセラーの方に知識として知っていただくこと
で、アルコールヤングケアラーとして見つけていただける機会になってほしい。
○
家族自身が病気に気がついて、こどもがヤングケアラーにならない啓発・支援をお
願いしたい。
○ 人材育成に力をもっと入れていただきたい。特に、教育カリキュラムの中に親の支
援、こどもの支援を入れていただきたい。
○ 9時-5時以外、あるいはオンラインを活用したプログラムなど、家族やこどもた
ちが参加しやすいツールというものをもっと展開していく必要があるのではないか。
○ 精神保健福祉センターや専門医療機関といったところへの相談なり受診なりができ
るような情報を必ず研修の中で盛り込んでいただきたい。
○ 御家族の方も、当事者と同じように孤立しない、同じような状況を経験している人
たちの共感がすごく大事であり、成長していけるような学ぶ場所を相談機関や専門医
療機関から伝わるような、参加していけるような流れを、これから強化していただき
たい。
○ 地域によってはカウンセリングを実施できるところが少ないのではないか。
○ 治療ギャップの解消のために相談窓口を増やせるよう、救急告示をしている総合病
院や精神科の病院に必置されている地域医療連携室で、スクリーニングや相談を実施
し、それを診療報酬化すればいいのではないか。
○ 自分のことでなかなか人に相談できなくても、こどもが不登校になったり、こども
が自傷したりとか、こどもが問題を抱えると、そこを軸とした支援の介入ならば、受
け入れられることも多かったりすることから、子育て支援を軸に介入して回復の連鎖
をつくるというのはどうか。
○
こども家庭支援課や児童相談所、保育園、幼稚園、学校医療機関などが連携して有
機的につながって、子育ての話題を軸にこどもが困っていることを相談することで、
親のアルコール依存症からの回復にもつながるし、こどもに対しても、心の病気をそ
の後抱えないような取組ができるのではないか。
○ SOS を出さない家族に対しては、まだ何も盛り込まれていない。まずは気づくこと
から始められたらよいのではないか。
○ 医療機関における地域連携室でのアルコールにかかる相談支援をどのくらい実施し
ているのかカウントしてはどうか。
だきたい
○ 相談機関や家族教室の依存症の知識の中に、こどもが受ける影響、こどもへの声か
けについて盛り込むべき。自治体をはじめ、様々な場所でアルコール依存症の家族セ
ミナーが行われているが、残念ながらアルコール依存症によるこどもへの影響や声か
けの仕方についての説明が見られないため、ぜひ盛り込んでいただきたい。
○ ヤングケアラー全体に、個別に相談できる環境を整備してほしい。有料カウンセリ
ングに経済的な補助をいただきたい。こどもの頃からの親のアルコール依存症や、依
存症者でない親をケアしてきて心の不調が出たとき、もっと手軽にカウンセリングを
受けられるように援助をお願いしたい。
○ こどもの相談を受けるスクールカウンセラーの方に知識として知っていただくこと
で、アルコールヤングケアラーとして見つけていただける機会になってほしい。
○
家族自身が病気に気がついて、こどもがヤングケアラーにならない啓発・支援をお
願いしたい。
○ 人材育成に力をもっと入れていただきたい。特に、教育カリキュラムの中に親の支
援、こどもの支援を入れていただきたい。
○ 9時-5時以外、あるいはオンラインを活用したプログラムなど、家族やこどもた
ちが参加しやすいツールというものをもっと展開していく必要があるのではないか。
○ 精神保健福祉センターや専門医療機関といったところへの相談なり受診なりができ
るような情報を必ず研修の中で盛り込んでいただきたい。
○ 御家族の方も、当事者と同じように孤立しない、同じような状況を経験している人
たちの共感がすごく大事であり、成長していけるような学ぶ場所を相談機関や専門医
療機関から伝わるような、参加していけるような流れを、これから強化していただき
たい。
○ 地域によってはカウンセリングを実施できるところが少ないのではないか。
○ 治療ギャップの解消のために相談窓口を増やせるよう、救急告示をしている総合病
院や精神科の病院に必置されている地域医療連携室で、スクリーニングや相談を実施
し、それを診療報酬化すればいいのではないか。
○ 自分のことでなかなか人に相談できなくても、こどもが不登校になったり、こども
が自傷したりとか、こどもが問題を抱えると、そこを軸とした支援の介入ならば、受
け入れられることも多かったりすることから、子育て支援を軸に介入して回復の連鎖
をつくるというのはどうか。
○
こども家庭支援課や児童相談所、保育園、幼稚園、学校医療機関などが連携して有
機的につながって、子育ての話題を軸にこどもが困っていることを相談することで、
親のアルコール依存症からの回復にもつながるし、こどもに対しても、心の病気をそ
の後抱えないような取組ができるのではないか。
○ SOS を出さない家族に対しては、まだ何も盛り込まれていない。まずは気づくこと
から始められたらよいのではないか。
○ 医療機関における地域連携室でのアルコールにかかる相談支援をどのくらい実施し
ているのかカウントしてはどうか。