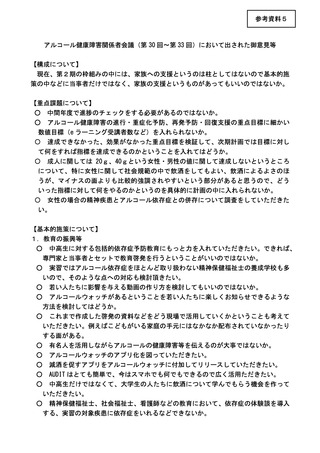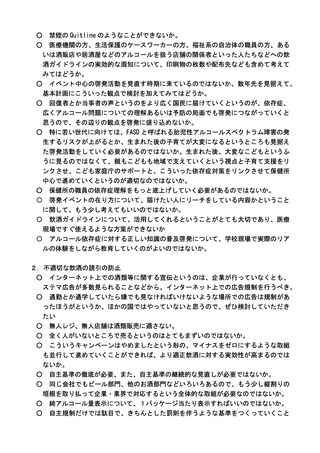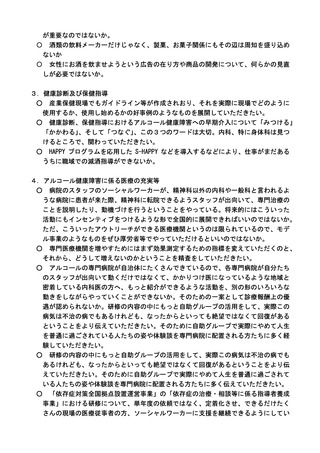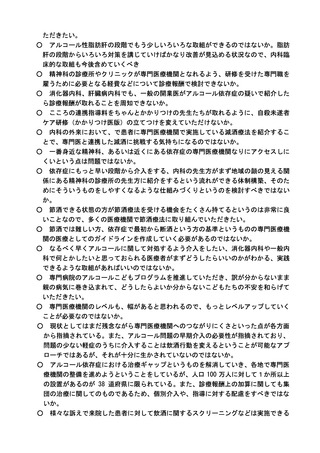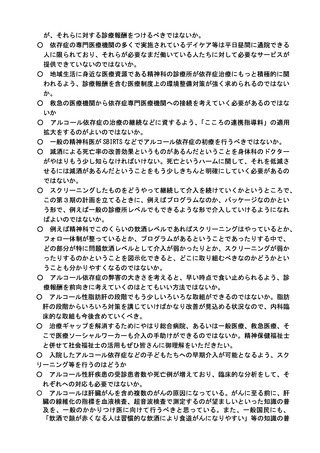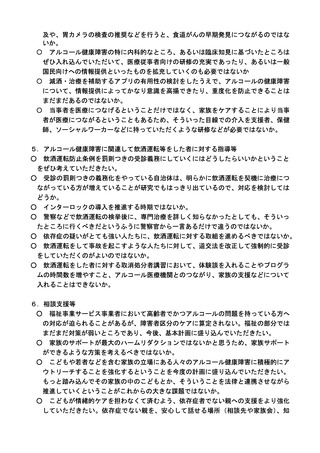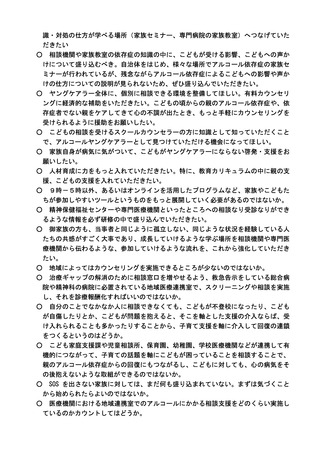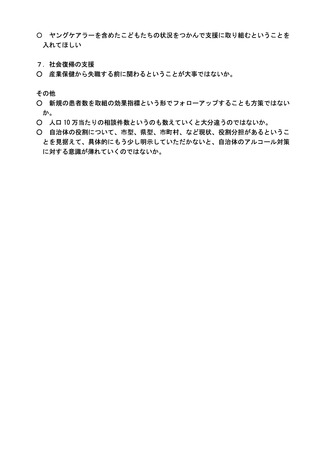よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 アルコール健康障害関係者会議(第30回~第33回)において出された御意見等 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html |
| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が、それらに対する診療報酬をつけるべきではないか。
○
依存症の専門医療機関の多くで実施されているデイケア等は平日昼間に通院できる
人に限られており、それらが必要なまだ働いている人たちに対して必要なサービスが
提供できていないのではないか。
○ 地域生活に身近な医療資源である精神科の診療所が依存症治療にもっと積極的に関
われるよう、診療報酬を含む医療制度上の環境整備対策が強く求められるのではない
か。
○ 救急の医療機関から依存症専門医療機関への接続を考えていく必要があるのではな
いか
○ アルコール依存症の治療の継続などに資するよう、「こころの連携指導料」の適用
拡大をするのがよいのではないか。
○ 一般の精神科医が SBIRTS などでアルコール依存症の初療を行うべきではないか。
○
減酒による死亡率の改善効果というものがあるんだということを身体科のドクター
がやはりもう少し知らなければいけない。死亡というハームに関して、それを低減さ
せるには減酒があるんだということをもう少しきちんと明確にしていく必要があるの
ではないか。
○ スクリーニングしたものをどうやって継続して介入を続けていくかというところで、
この第3期の計画を立てるときに、例えばプログラムなのか、パッケージなのかとい
う形で、例えば一般の診療所レベルでもできるような形で介入していけるようになれ
ばよいのではないか。
○ 例えば精神科でこのくらいの飲酒レベルであればスクリーニングはやっているとか、
フォロー体制が整っているとか、プログラムがあるということであったりする中で、
どの部分が特に問題飲酒レベルとして介入が弱かったりとか、スクリーニングが弱か
ったりするのかということを図示化できると、どこに取り組むべきなのかどうかとい
うことも分かりやすくなるのではないか。
○ アルコール依存症の弊害の大きさを考えると、早い時点で食い止められるよう、診
療報酬を前向きに考えていくのはとてもいい方法ではないか。
○ アルコール性脂肪肝の段階でもう少しいろいろな取組ができるのではないか。脂肪
肝の段階からいろいろ対策を講じていけばかなり改善が見込める状況なので、内科臨
床的な取組も今後含めていくべき。
○ 治療ギャップを解消するためにやはり総合病院、あるいは一般医療、救急医療、そ
こで医療ソーシャルワーカーも介入の手助けができるのではないか。精神保健福祉士
と併せて社会福祉士の活用もぜひ皆さんに御理解をいただきたい。
○ 入院したアルコール依存症などの子どもたちへの早期介入が可能となるよう、スク
リーニング等を行うのはどうか
○ アルコール性肝疾患の受診患者数や死亡例が増えており、臨床的な分析をして、そ
れぞれへの対応も必要ではないか。
〇 アルコールは肝臓がんを含め複数のがんの原因になっている。がんに至る前に、肝
臓の線維化の指標を血液検査、超音波検査で測定するのが望ましいといった知識の普
及を、一般のかかりつけ医に向けて行うべきと思っている。また、一般国民にも、
「飲酒で顔が赤くなる人は習慣的な飲酒により食道がんになりやすい」等の知識の普
○
依存症の専門医療機関の多くで実施されているデイケア等は平日昼間に通院できる
人に限られており、それらが必要なまだ働いている人たちに対して必要なサービスが
提供できていないのではないか。
○ 地域生活に身近な医療資源である精神科の診療所が依存症治療にもっと積極的に関
われるよう、診療報酬を含む医療制度上の環境整備対策が強く求められるのではない
か。
○ 救急の医療機関から依存症専門医療機関への接続を考えていく必要があるのではな
いか
○ アルコール依存症の治療の継続などに資するよう、「こころの連携指導料」の適用
拡大をするのがよいのではないか。
○ 一般の精神科医が SBIRTS などでアルコール依存症の初療を行うべきではないか。
○
減酒による死亡率の改善効果というものがあるんだということを身体科のドクター
がやはりもう少し知らなければいけない。死亡というハームに関して、それを低減さ
せるには減酒があるんだということをもう少しきちんと明確にしていく必要があるの
ではないか。
○ スクリーニングしたものをどうやって継続して介入を続けていくかというところで、
この第3期の計画を立てるときに、例えばプログラムなのか、パッケージなのかとい
う形で、例えば一般の診療所レベルでもできるような形で介入していけるようになれ
ばよいのではないか。
○ 例えば精神科でこのくらいの飲酒レベルであればスクリーニングはやっているとか、
フォロー体制が整っているとか、プログラムがあるということであったりする中で、
どの部分が特に問題飲酒レベルとして介入が弱かったりとか、スクリーニングが弱か
ったりするのかということを図示化できると、どこに取り組むべきなのかどうかとい
うことも分かりやすくなるのではないか。
○ アルコール依存症の弊害の大きさを考えると、早い時点で食い止められるよう、診
療報酬を前向きに考えていくのはとてもいい方法ではないか。
○ アルコール性脂肪肝の段階でもう少しいろいろな取組ができるのではないか。脂肪
肝の段階からいろいろ対策を講じていけばかなり改善が見込める状況なので、内科臨
床的な取組も今後含めていくべき。
○ 治療ギャップを解消するためにやはり総合病院、あるいは一般医療、救急医療、そ
こで医療ソーシャルワーカーも介入の手助けができるのではないか。精神保健福祉士
と併せて社会福祉士の活用もぜひ皆さんに御理解をいただきたい。
○ 入院したアルコール依存症などの子どもたちへの早期介入が可能となるよう、スク
リーニング等を行うのはどうか
○ アルコール性肝疾患の受診患者数や死亡例が増えており、臨床的な分析をして、そ
れぞれへの対応も必要ではないか。
〇 アルコールは肝臓がんを含め複数のがんの原因になっている。がんに至る前に、肝
臓の線維化の指標を血液検査、超音波検査で測定するのが望ましいといった知識の普
及を、一般のかかりつけ医に向けて行うべきと思っている。また、一般国民にも、
「飲酒で顔が赤くなる人は習慣的な飲酒により食道がんになりやすい」等の知識の普