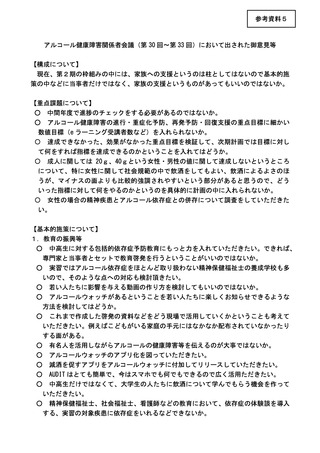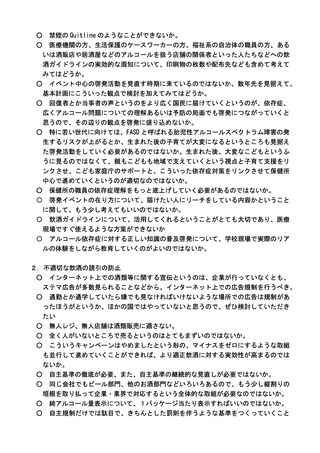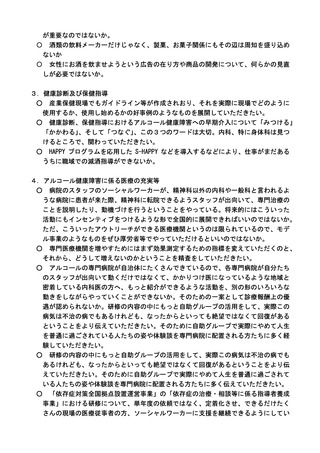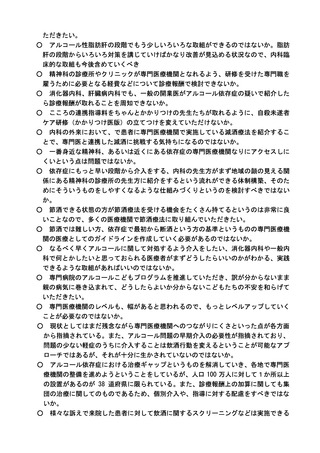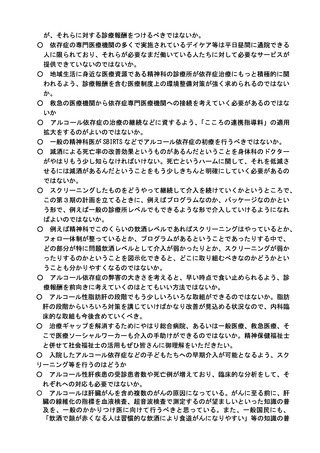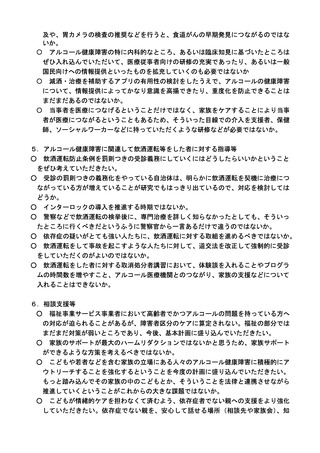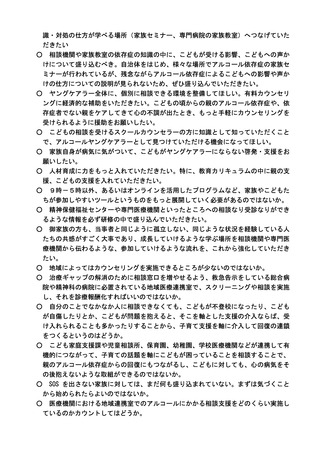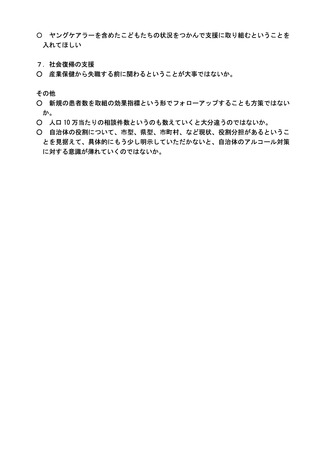よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 アルコール健康障害関係者会議(第30回~第33回)において出された御意見等 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html |
| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が重要なのではないか。
〇
酒類の飲料メーカーだけじゃなく、製菓、お菓子関係にもその辺は周知を盛り込め
ないか
〇 女性にお酒を飲ませようという広告の在り方や商品の開発について、何らかの見直
しが必要ではないか。
3.健康診断及び保健指導
○ 産業保健現場でもガイドライン等が作成されおり、それを実際に現場でどのように
使用するか、使用し始めるかの好事例のようなものを展開していただきたい。
○ 健康診断、保健指導におけるアルコール健康障害への早期介入について「みつける」
「かかわる」、そして「つなぐ」、この3つのワードは大切。内科、特に身体科は見つ
けるところで、関わっていただきたい。
○
HAPPY プログラムを応用した S-HAPPY などを導入するなどにより、仕事がまだある
うちに職域での減酒指導ができないか。
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
○ 病院のスタッフのソーシャルワーカーが、精神科以外の内科や一般科と言われるよ
うな病院に患者が来た際、精神科に転院できるようスタッフが出向いて、専門治療の
ことを説明したり、動機づけを行うということをやっている。将来的にはこういった
活動にもインセンティブをつけるような形で全国的に展開できればいいのではないか。
ただ、こういったアウトリーチができる医療機関というのは限られているので、モデ
ル事業のようなものをぜひ厚労省等でやっていただけるといいのではないか。
○
専門医療機関を増やすためにはまず効果測定するための指標を変えていただくのと、
それから、どうして増えないのかということを精査をしていただきたい。
○ アルコールの専門病院が自治体にたくさんできているので、各専門病院が自分たち
のスタッフが出向いて動くだけではなくて、かかりつけ医になっているような地域と
密着している内科医の方へ、もっと紹介ができるような活動を、別の形のいろいろな
動きをしながらやっていくことができないか。そのための一案として診療報酬上の優
遇が認められないか。研修の内容の中にもっと自助グループの活用をして、実際この
病気は不治の病でもあるけれども、なったからといっても絶望ではなくて回復がある
ということをより伝えていただきたい。そのために自助グループで実際にやめて人生
を普通に過ごされている人たちの姿や体験談を専門病院に配置される方たちに多く経
験していただきたい。
○ 研修の内容の中にもっと自助グループの活用をして、実際この病気は不治の病でも
あるけれども、なったからといっても絶望ではなくて回復があるということをより伝
えていただきたい。そのために自助グループで実際にやめて人生を普通に過ごされて
いる人たちの姿や体験談を専門病院に配置される方たちに多く伝えていただきたい。
○ 「依存症対策全国拠点設置運営事業」の「依存症の治療・相談等に係る指導者養成
事業」における研修について、単年度の依頼ではなく、定着化させ、できるだけたく
さんの現場の医療従事者の方、ソーシャルワーカーに支援を継続できるようにしてい
〇
酒類の飲料メーカーだけじゃなく、製菓、お菓子関係にもその辺は周知を盛り込め
ないか
〇 女性にお酒を飲ませようという広告の在り方や商品の開発について、何らかの見直
しが必要ではないか。
3.健康診断及び保健指導
○ 産業保健現場でもガイドライン等が作成されおり、それを実際に現場でどのように
使用するか、使用し始めるかの好事例のようなものを展開していただきたい。
○ 健康診断、保健指導におけるアルコール健康障害への早期介入について「みつける」
「かかわる」、そして「つなぐ」、この3つのワードは大切。内科、特に身体科は見つ
けるところで、関わっていただきたい。
○
HAPPY プログラムを応用した S-HAPPY などを導入するなどにより、仕事がまだある
うちに職域での減酒指導ができないか。
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
○ 病院のスタッフのソーシャルワーカーが、精神科以外の内科や一般科と言われるよ
うな病院に患者が来た際、精神科に転院できるようスタッフが出向いて、専門治療の
ことを説明したり、動機づけを行うということをやっている。将来的にはこういった
活動にもインセンティブをつけるような形で全国的に展開できればいいのではないか。
ただ、こういったアウトリーチができる医療機関というのは限られているので、モデ
ル事業のようなものをぜひ厚労省等でやっていただけるといいのではないか。
○
専門医療機関を増やすためにはまず効果測定するための指標を変えていただくのと、
それから、どうして増えないのかということを精査をしていただきたい。
○ アルコールの専門病院が自治体にたくさんできているので、各専門病院が自分たち
のスタッフが出向いて動くだけではなくて、かかりつけ医になっているような地域と
密着している内科医の方へ、もっと紹介ができるような活動を、別の形のいろいろな
動きをしながらやっていくことができないか。そのための一案として診療報酬上の優
遇が認められないか。研修の内容の中にもっと自助グループの活用をして、実際この
病気は不治の病でもあるけれども、なったからといっても絶望ではなくて回復がある
ということをより伝えていただきたい。そのために自助グループで実際にやめて人生
を普通に過ごされている人たちの姿や体験談を専門病院に配置される方たちに多く経
験していただきたい。
○ 研修の内容の中にもっと自助グループの活用をして、実際この病気は不治の病でも
あるけれども、なったからといっても絶望ではなくて回復があるということをより伝
えていただきたい。そのために自助グループで実際にやめて人生を普通に過ごされて
いる人たちの姿や体験談を専門病院に配置される方たちに多く伝えていただきたい。
○ 「依存症対策全国拠点設置運営事業」の「依存症の治療・相談等に係る指導者養成
事業」における研修について、単年度の依頼ではなく、定着化させ、できるだけたく
さんの現場の医療従事者の方、ソーシャルワーカーに支援を継続できるようにしてい