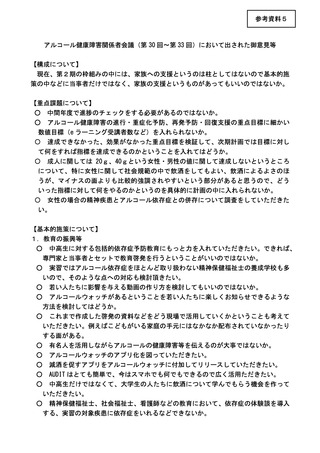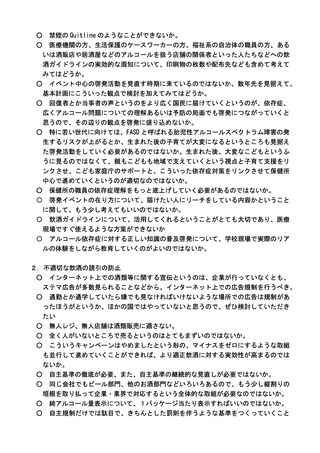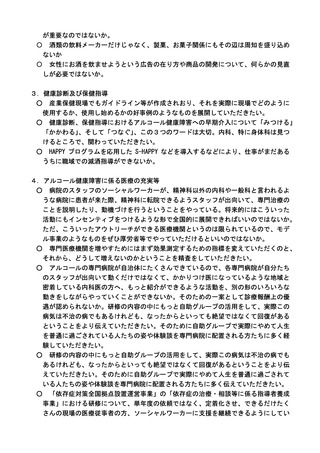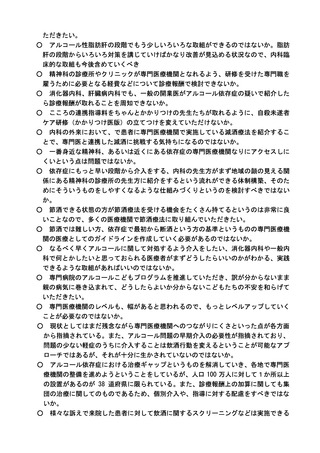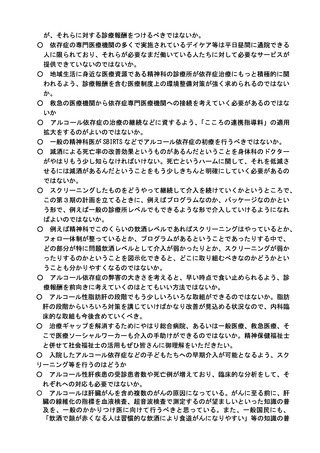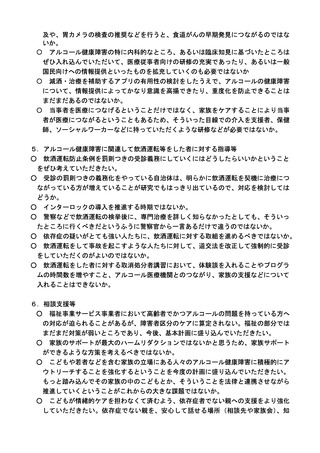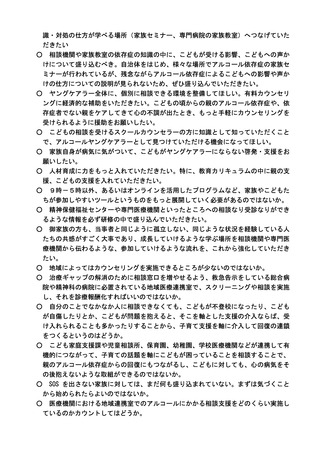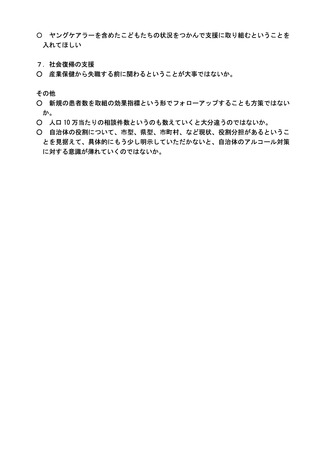よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 アルコール健康障害関係者会議(第30回~第33回)において出された御意見等 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html |
| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
禁煙の Quitline のようなことができないか。
○
医療機関の方、生活保護のケースワーカーの方、福祉系の自治体の職員の方、ある
いは酒販店や居酒屋などのアルコールを扱う店舗の関係者といった人たちなどへの飲
酒ガイドラインの実効的な周知について、印刷物の枚数や配布先なども含めて考えて
みてはどうか。
○ イベント中心の啓発活動を見直す時期に来ているのではないか。数年先を見据えて、
基本計画にこういった観点で検討を加えてみてはどうか。
○ 回復者とか当事者の声というのをより広く国民に届けていくというのが、依存症、
広くアルコール問題についての理解あるいは予防の局面でも啓発につながっていくと
思うので、その辺りの観点を啓発に盛り込めないか。
○ 特に若い世代に向けては、FASD と呼ばれる胎児性アルコールスペクトラム障害の発
生するリスクが上がるとか、生まれた後の子育てが大変になるというところも見据え
た啓発活動をしていく必要があるのではないか。生まれた後、大変なこどもというふ
うに見るのではなくて、親もこどもも地域で支えていくという視点と子育て支援をリ
ンクさせ、こども家庭庁のサポートと、こういった依存症対策をリンクさせて保健所
中心で進めていくというのが適切なのではないか。
○ 保健所の職員の依存症理解をもっと底上げしていく必要があるのではないか。
〇 啓発イベントの在り方について、届けたい人にリーチをしている内容かということ
に関して、もう少し考えてもいいのではないか。
〇 飲酒ガイドラインについて、活用してくれるということがとても大切であり、医療
現場ですぐ使えるような方策ができないか
〇 アルコール依存症に対する正しい知識の普及啓発について、学校現場で実際のリア
ルの体験をしながら教育していくのがよいのではないか。
2.不適切な飲酒の誘引の防止
○ インターネット上での酒類等に関する宣伝というのは、企業が行っていなくとも、
ステマ広告が多数見られることなどから、インターネット上での広告規制を行うべき。
○ 通勤とか通学していたら嫌でも見なければいけないような場所での広告は規制があ
ったほうがというか、ほかの国ではやっていないと思うので、ぜひ検討していただき
たい
○ 無人レジ、無人店舗は酒類販売に適さない。
○ 全く人がいないところで売るというのはとてもまずいのではないか。
○
こういうキャンペーンはやめましたという形の、マイナスをゼロにするような取組
も並行して進めていくことができれば、より適正飲酒に対する実効性が高まるのでは
ないか。
○ 自主基準の徹底が必要、また、自主基準の継続的な見直しが必要ではないか。
○ 同じ会社でもビール部門、他のお酒部門などいろいろあるので、もう少し縦割りの
垣根を取り払って企業・業界で対応するという全体的な取組が必要なのではないか。
○ 純アルコール量表示について、1パッケージ当たり表示すればいいのではないか。
○ 自主規制だけでは駄目で、きちんとした罰則を伴うような基準をつくっていくこと
禁煙の Quitline のようなことができないか。
○
医療機関の方、生活保護のケースワーカーの方、福祉系の自治体の職員の方、ある
いは酒販店や居酒屋などのアルコールを扱う店舗の関係者といった人たちなどへの飲
酒ガイドラインの実効的な周知について、印刷物の枚数や配布先なども含めて考えて
みてはどうか。
○ イベント中心の啓発活動を見直す時期に来ているのではないか。数年先を見据えて、
基本計画にこういった観点で検討を加えてみてはどうか。
○ 回復者とか当事者の声というのをより広く国民に届けていくというのが、依存症、
広くアルコール問題についての理解あるいは予防の局面でも啓発につながっていくと
思うので、その辺りの観点を啓発に盛り込めないか。
○ 特に若い世代に向けては、FASD と呼ばれる胎児性アルコールスペクトラム障害の発
生するリスクが上がるとか、生まれた後の子育てが大変になるというところも見据え
た啓発活動をしていく必要があるのではないか。生まれた後、大変なこどもというふ
うに見るのではなくて、親もこどもも地域で支えていくという視点と子育て支援をリ
ンクさせ、こども家庭庁のサポートと、こういった依存症対策をリンクさせて保健所
中心で進めていくというのが適切なのではないか。
○ 保健所の職員の依存症理解をもっと底上げしていく必要があるのではないか。
〇 啓発イベントの在り方について、届けたい人にリーチをしている内容かということ
に関して、もう少し考えてもいいのではないか。
〇 飲酒ガイドラインについて、活用してくれるということがとても大切であり、医療
現場ですぐ使えるような方策ができないか
〇 アルコール依存症に対する正しい知識の普及啓発について、学校現場で実際のリア
ルの体験をしながら教育していくのがよいのではないか。
2.不適切な飲酒の誘引の防止
○ インターネット上での酒類等に関する宣伝というのは、企業が行っていなくとも、
ステマ広告が多数見られることなどから、インターネット上での広告規制を行うべき。
○ 通勤とか通学していたら嫌でも見なければいけないような場所での広告は規制があ
ったほうがというか、ほかの国ではやっていないと思うので、ぜひ検討していただき
たい
○ 無人レジ、無人店舗は酒類販売に適さない。
○ 全く人がいないところで売るというのはとてもまずいのではないか。
○
こういうキャンペーンはやめましたという形の、マイナスをゼロにするような取組
も並行して進めていくことができれば、より適正飲酒に対する実効性が高まるのでは
ないか。
○ 自主基準の徹底が必要、また、自主基準の継続的な見直しが必要ではないか。
○ 同じ会社でもビール部門、他のお酒部門などいろいろあるので、もう少し縦割りの
垣根を取り払って企業・業界で対応するという全体的な取組が必要なのではないか。
○ 純アルコール量表示について、1パッケージ当たり表示すればいいのではないか。
○ 自主規制だけでは駄目で、きちんとした罰則を伴うような基準をつくっていくこと