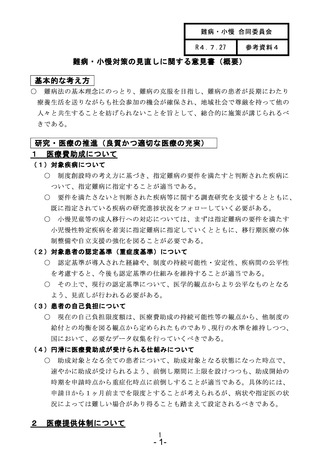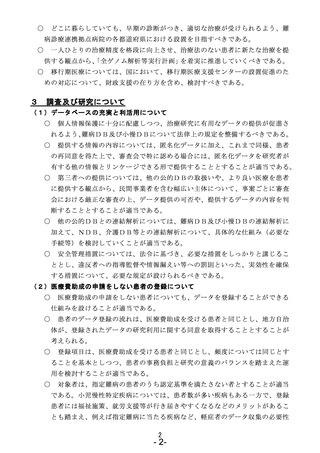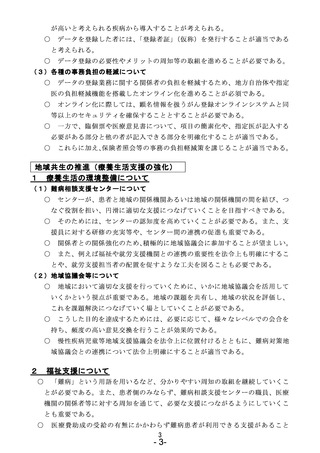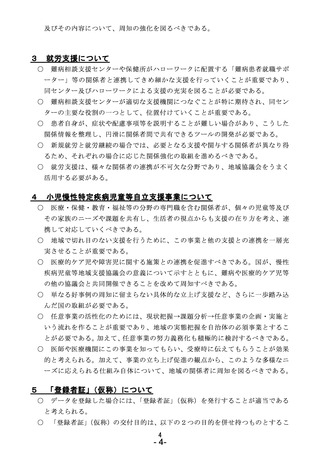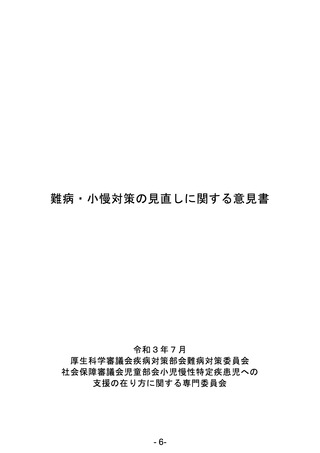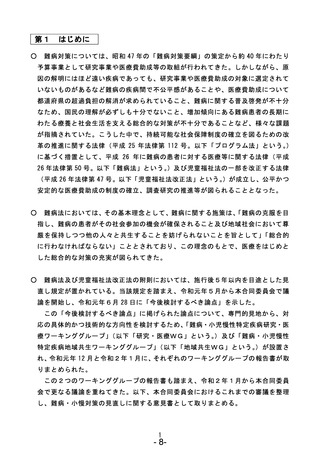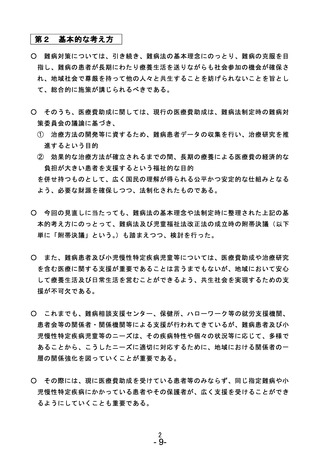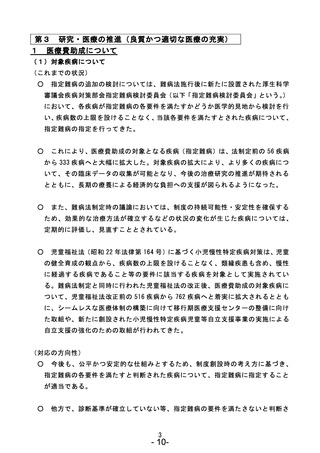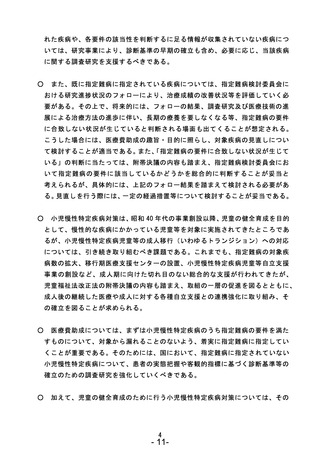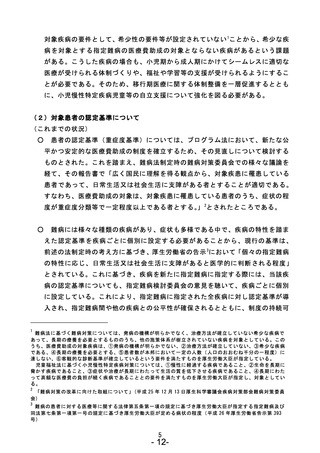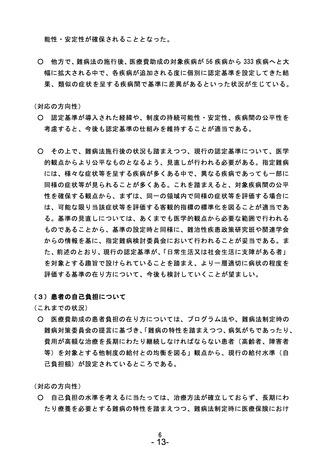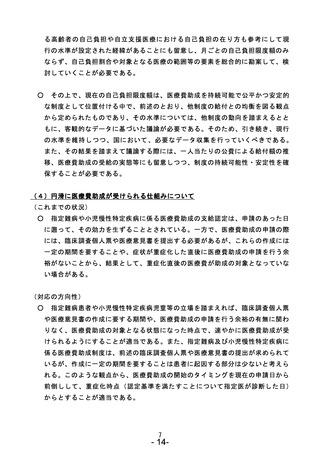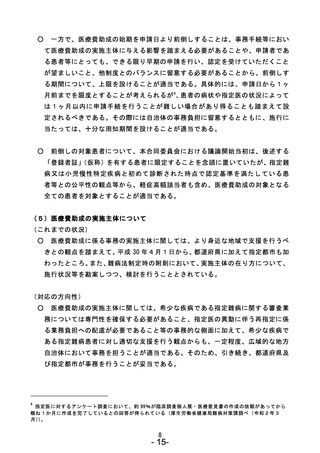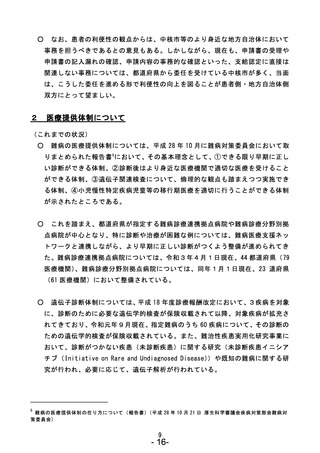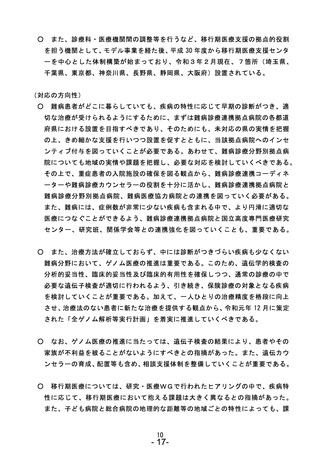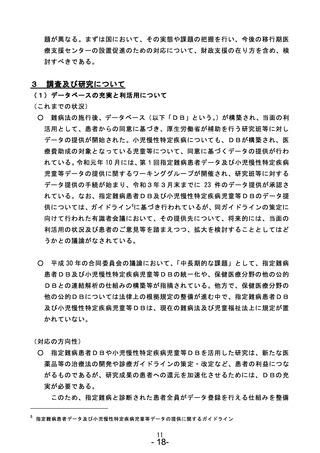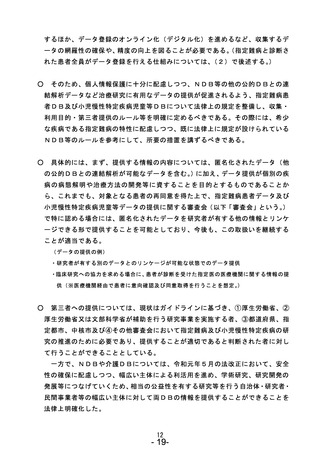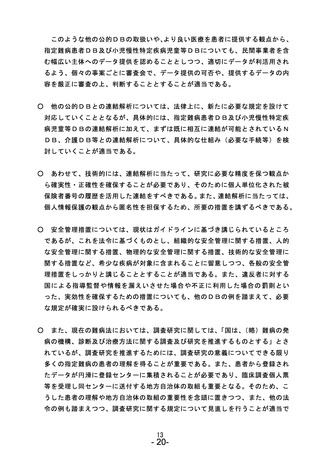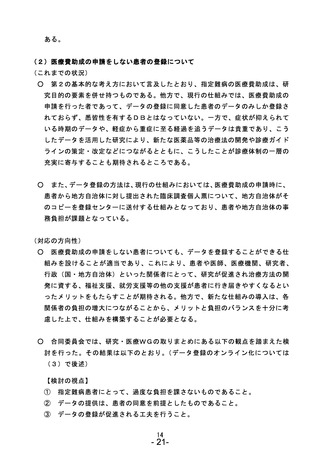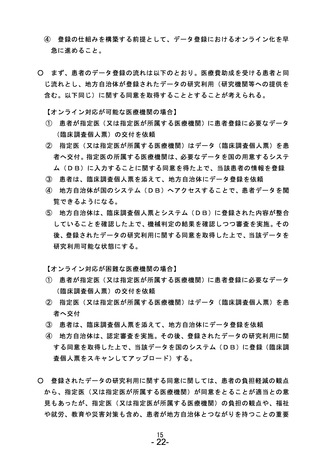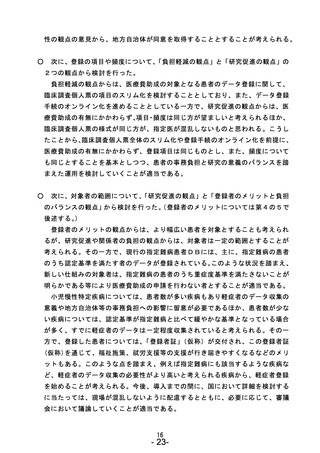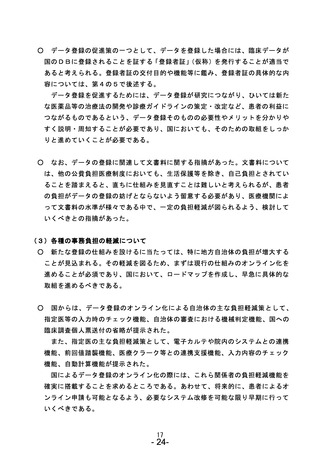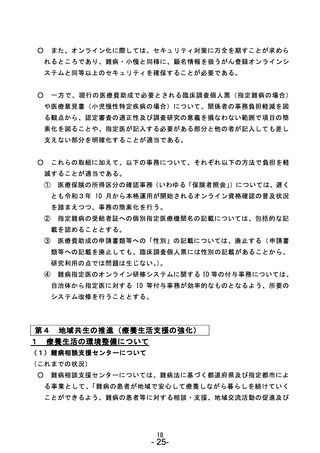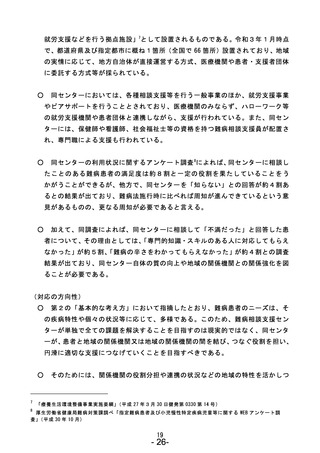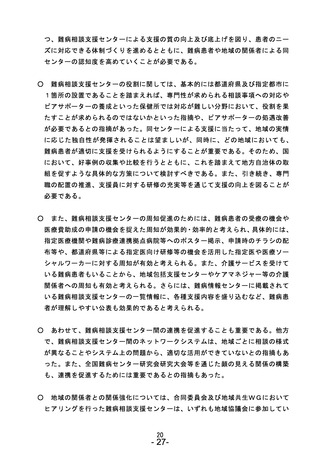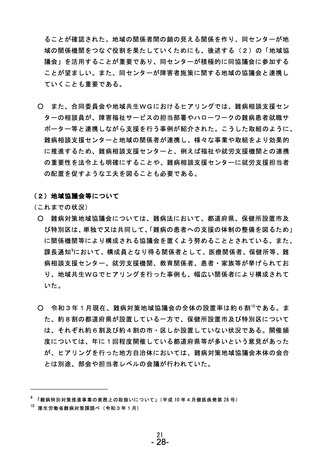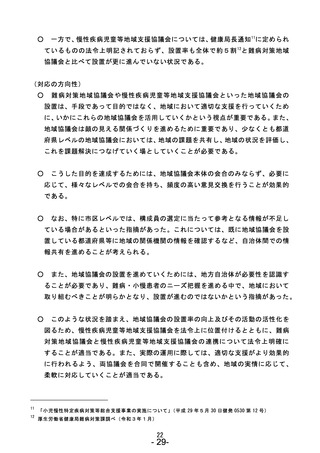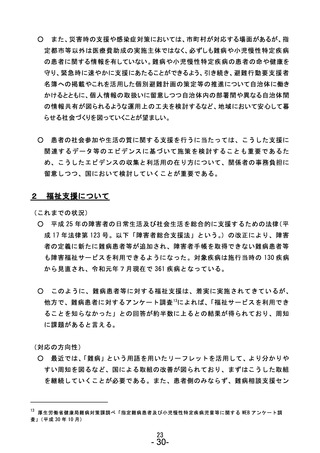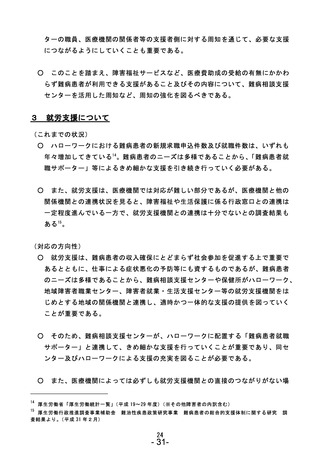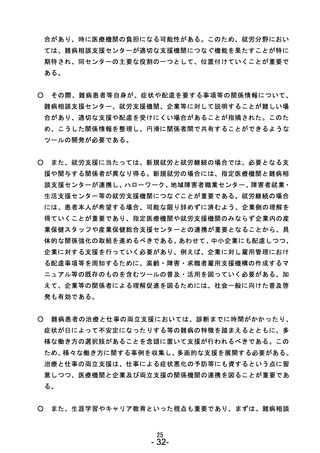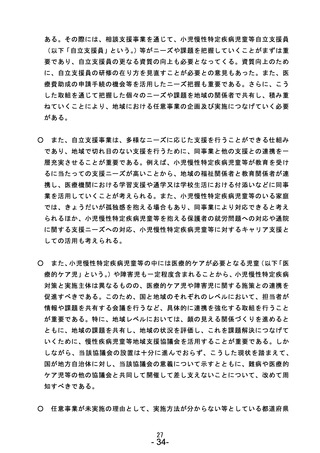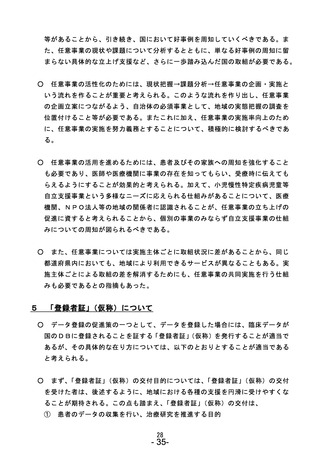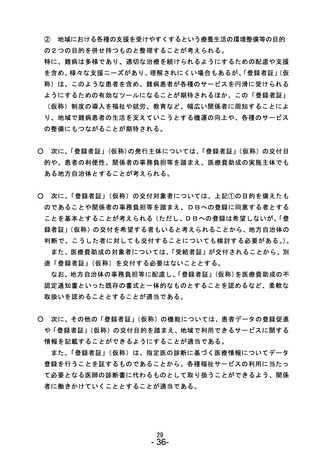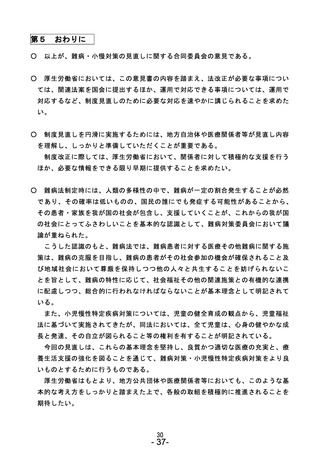よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)概要及び本文 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
支援センターの就労支援担当者への周知・啓発等の取組を進めていくことが考え
られる。
○
さらに、合同委員会及び地域共生WGにおけるヒアリングを通じて、地域協議
会に就労に関する部会を設置している地方自治体もあることが確認された。就労
支援は、様々な関係者の連携が不可欠な分野であり、地域協議会をうまく活用す
る必要がある。
○
なお、難病患者の雇用を促進する観点から、難病患者を障害者雇用における法
定雇用率の算定基礎 16 に入れるかどうかという議論を労働政策審議会において始
めるべきではないかとの意見や、当該審議会の検討状況をフォローし、必要に応
じて連携していくべきとの意見もあった。
4
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について
(これまでの状況)
○
児童福祉法改正法において小児慢性特定疾病児童等自立支援事業が法定化さ
れ、実施が開始された。同事業は、相談支援事業に加えて、就職支援、きょうだ
い支援、学習支援等を提供できる仕組みとなっており、小児慢性特定疾病児童等
及びその家族が抱える悩みを受け止める上で、意義のある事業である。
○
他方で、都道府県等における実施が義務である相談支援事業は、ほぼ全ての都
道府県等において実施されているが、任意事業の実施率は低い 17。任意事業は地域
のニーズや支援資源等の実情に応じた事業展開が可能であるという趣旨の事業
であり、必要ではないという意味合いではないことを改めて意識する必要がある。
未実施である理由としては、実施方法が分からない、ニーズを把握して いない、
予算がない等を挙げる都道府県等が見られた 18。
(対応の方向性)
○
小児慢性特定疾病児童等の自立を支援するためには、医療・保健・教育・福祉
等の分野の専門職を含む関係者が、個々の児童等及びその家族のニーズや課題を
共有し、生活者の視点からも支援の在り方を考え、連携して対応していくべきで
16
現在は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が法定雇用率の算定基礎の対象。
17
厚生労働省健康局難病対策課調べ(平成 31 年4月)
18
第1回地域共生WGにおける掛江参考人ヒアリング資料(資料 2-4)より。
26
- 33-
られる。
○
さらに、合同委員会及び地域共生WGにおけるヒアリングを通じて、地域協議
会に就労に関する部会を設置している地方自治体もあることが確認された。就労
支援は、様々な関係者の連携が不可欠な分野であり、地域協議会をうまく活用す
る必要がある。
○
なお、難病患者の雇用を促進する観点から、難病患者を障害者雇用における法
定雇用率の算定基礎 16 に入れるかどうかという議論を労働政策審議会において始
めるべきではないかとの意見や、当該審議会の検討状況をフォローし、必要に応
じて連携していくべきとの意見もあった。
4
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について
(これまでの状況)
○
児童福祉法改正法において小児慢性特定疾病児童等自立支援事業が法定化さ
れ、実施が開始された。同事業は、相談支援事業に加えて、就職支援、きょうだ
い支援、学習支援等を提供できる仕組みとなっており、小児慢性特定疾病児童等
及びその家族が抱える悩みを受け止める上で、意義のある事業である。
○
他方で、都道府県等における実施が義務である相談支援事業は、ほぼ全ての都
道府県等において実施されているが、任意事業の実施率は低い 17。任意事業は地域
のニーズや支援資源等の実情に応じた事業展開が可能であるという趣旨の事業
であり、必要ではないという意味合いではないことを改めて意識する必要がある。
未実施である理由としては、実施方法が分からない、ニーズを把握して いない、
予算がない等を挙げる都道府県等が見られた 18。
(対応の方向性)
○
小児慢性特定疾病児童等の自立を支援するためには、医療・保健・教育・福祉
等の分野の専門職を含む関係者が、個々の児童等及びその家族のニーズや課題を
共有し、生活者の視点からも支援の在り方を考え、連携して対応していくべきで
16
現在は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が法定雇用率の算定基礎の対象。
17
厚生労働省健康局難病対策課調べ(平成 31 年4月)
18
第1回地域共生WGにおける掛江参考人ヒアリング資料(資料 2-4)より。
26
- 33-