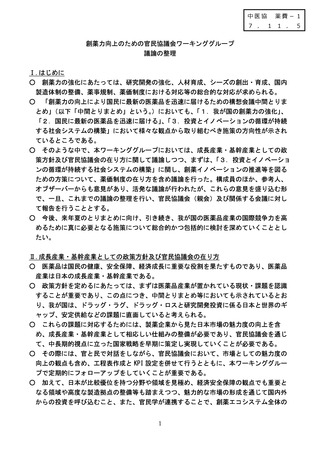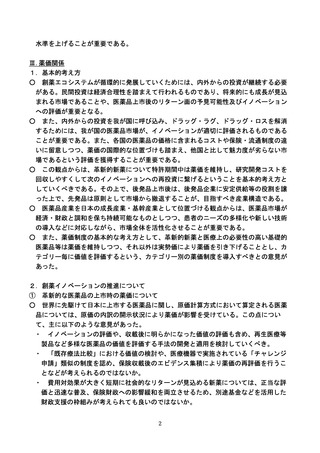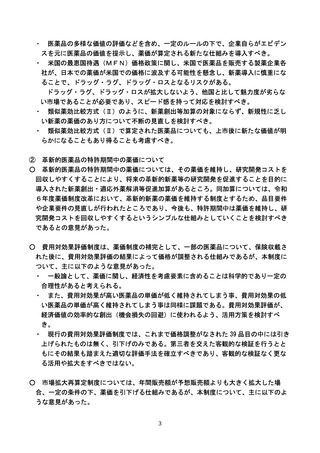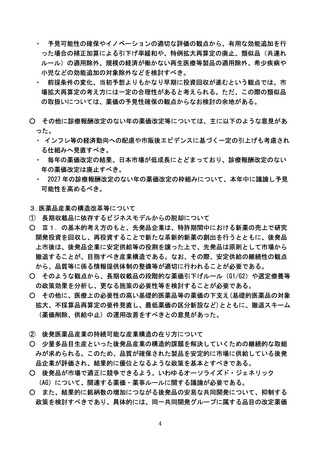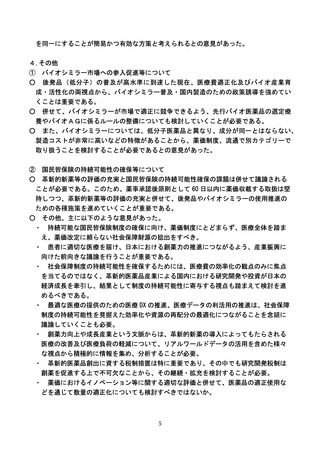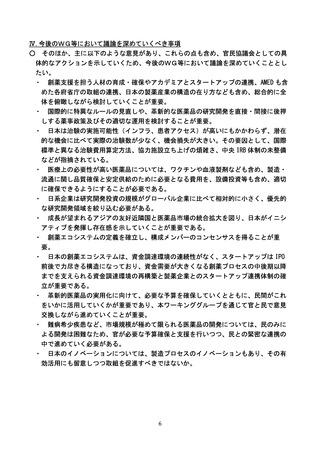よむ、つかう、まなぶ。
薬費-1創薬力向上のための官民協議会ワーキンググループ議論の整理 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65609.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会 合同部会(第8回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・
予見可能性の確保やイノベーションの適切な評価の観点から、有用な効能追加を行
った場合の補正加算による引下げ率緩和や、特例拡大再算定の廃止、類似品(共連れ
ルール)の適用除外、規模の経済が働かない再生医療等製品の適用除外、希少疾病や
小児などの効能追加の対象除外などを検討すべき。
・ 前提条件の変化、当初予想よりもかなり早期に投資回収が進むという観点では、市
場拡大再算定の考え方には一定の合理性があると考えられる。ただ、この際の類似品
の取扱いについては、薬価の予見性確保の観点からなお検討の余地がある。
○
その他に診療報酬改定のない年の薬価改定等については、主に以下のような意見があ
った。
・ インフレ等の経済動向への配慮や市販後エビデンスに基づく一定の引上げも考慮され
る仕組みへ見直すべき。
・ 毎年の薬価改定の結果、日本市場が低成長にとどまっており、診療報酬改定のない
年の薬価改定は廃止すべき。
・ 2027 年の診療報酬改定のない年の薬価改定の枠組みについて、本年中に議論し予見
可能性を高めるべき。
3.医薬品産業の構造改革等について
① 長期収載品に依存するビジネスモデルからの脱却について
○ Ⅲ1.の基本的考え方のもと、先発品企業は、特許期間中における新薬の売上で研究
開発投資を回収し、再投資することで新たな革新的新薬の創出を行うとともに、後発品
上市後は、後発品企業に安定供給等の役割を譲った上で、先発品は原則として市場から
撤退することが、目指すべき産業構造である。なお、その際、安定供給の継続性の観点
から、品質等に係る情報提供体制の整備等が適切に行われることが必要である。
○ そのような観点から、長期収載品の段階的な薬価引下げルール(G1/G2)や選定療養等
の政策効果を分析し、更なる施策の必要性等を検討することが必要である。
○ その他に、医療上の必要性の高い基礎的医薬品等の薬価の下支え(基礎的医薬品の対象
拡大、不採算品再算定の要件見直し、最低薬価の区分新設など)とともに、撤退スキーム
(薬価削除、供給中止)の運用改善をすべきとの意見があった。
②
○
後発医薬品産業の持続可能な産業構造の在り方について
少量多品目生産といった後発品産業の構造的課題を解決していくための継続的な取組
みが求められる。このため、品質が確保された製品を安定的に市場に供給している後発
品企業が評価され、結果的に優位となるような政策を基本とすべきである。
○ 後発品が市場で適正に競争できるよう、いわゆるオーソライズド・ジェネリック
(AG)について、関連する薬価・薬事ルールに関する議論が必要である。
○ また、結果的に銘柄数の増加につながる後発品の安易な共同開発について、抑制する
政策を検討すべきであり、具体的には、同一共同開発グループに属する品目の改定薬価
4
予見可能性の確保やイノベーションの適切な評価の観点から、有用な効能追加を行
った場合の補正加算による引下げ率緩和や、特例拡大再算定の廃止、類似品(共連れ
ルール)の適用除外、規模の経済が働かない再生医療等製品の適用除外、希少疾病や
小児などの効能追加の対象除外などを検討すべき。
・ 前提条件の変化、当初予想よりもかなり早期に投資回収が進むという観点では、市
場拡大再算定の考え方には一定の合理性があると考えられる。ただ、この際の類似品
の取扱いについては、薬価の予見性確保の観点からなお検討の余地がある。
○
その他に診療報酬改定のない年の薬価改定等については、主に以下のような意見があ
った。
・ インフレ等の経済動向への配慮や市販後エビデンスに基づく一定の引上げも考慮され
る仕組みへ見直すべき。
・ 毎年の薬価改定の結果、日本市場が低成長にとどまっており、診療報酬改定のない
年の薬価改定は廃止すべき。
・ 2027 年の診療報酬改定のない年の薬価改定の枠組みについて、本年中に議論し予見
可能性を高めるべき。
3.医薬品産業の構造改革等について
① 長期収載品に依存するビジネスモデルからの脱却について
○ Ⅲ1.の基本的考え方のもと、先発品企業は、特許期間中における新薬の売上で研究
開発投資を回収し、再投資することで新たな革新的新薬の創出を行うとともに、後発品
上市後は、後発品企業に安定供給等の役割を譲った上で、先発品は原則として市場から
撤退することが、目指すべき産業構造である。なお、その際、安定供給の継続性の観点
から、品質等に係る情報提供体制の整備等が適切に行われることが必要である。
○ そのような観点から、長期収載品の段階的な薬価引下げルール(G1/G2)や選定療養等
の政策効果を分析し、更なる施策の必要性等を検討することが必要である。
○ その他に、医療上の必要性の高い基礎的医薬品等の薬価の下支え(基礎的医薬品の対象
拡大、不採算品再算定の要件見直し、最低薬価の区分新設など)とともに、撤退スキーム
(薬価削除、供給中止)の運用改善をすべきとの意見があった。
②
○
後発医薬品産業の持続可能な産業構造の在り方について
少量多品目生産といった後発品産業の構造的課題を解決していくための継続的な取組
みが求められる。このため、品質が確保された製品を安定的に市場に供給している後発
品企業が評価され、結果的に優位となるような政策を基本とすべきである。
○ 後発品が市場で適正に競争できるよう、いわゆるオーソライズド・ジェネリック
(AG)について、関連する薬価・薬事ルールに関する議論が必要である。
○ また、結果的に銘柄数の増加につながる後発品の安易な共同開発について、抑制する
政策を検討すべきであり、具体的には、同一共同開発グループに属する品目の改定薬価
4