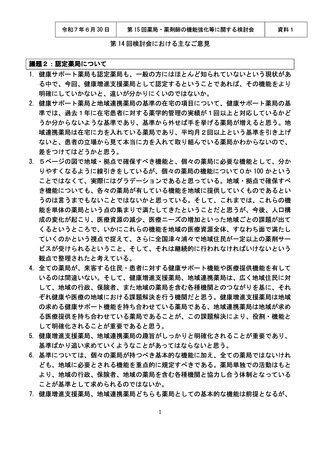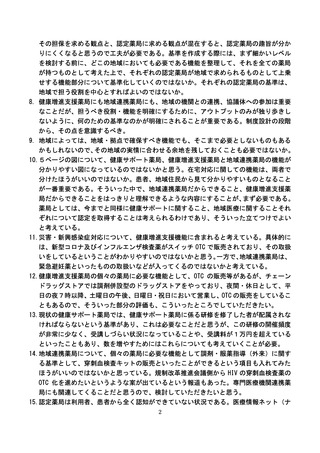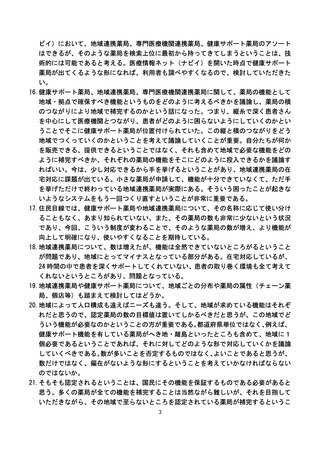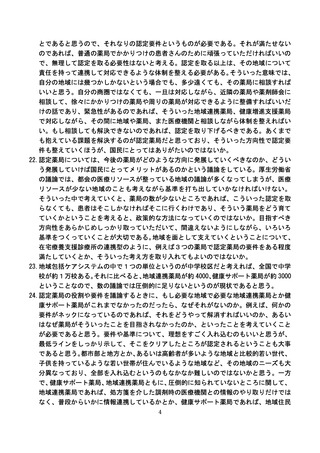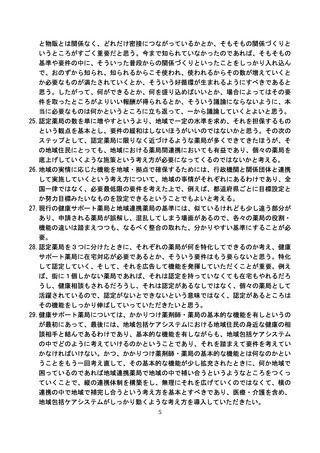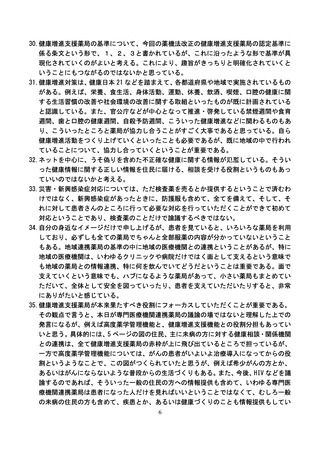よむ、つかう、まなぶ。
資料1_第14回検討会の主なご意見 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59230.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第15回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
30.健康増進支援薬局の基準について、今回の薬機法改正の健康増進支援薬局の認定基準に
係る条文という形で、1、2、3と書かれているが、これに沿ったような形で基準が具
現化されていくのがよいと考える。これにより、趣旨がきっちりと明確化されていくと
いうことにもつながるのではないかと思っている。
31.健康増進対策は、健康日本 21 などを踏まえて、各都道府県や地域で実施されているもの
がある。例えば、栄養、食生活、身体活動、運動、休養、飲酒、喫煙、口腔の健康に関
する生活習慣の改善や社会環境の改善に関する取組といったものが既に計画されている
と認識している。また、官公庁などが中心となって推進・啓発している禁煙週間や食育
週間、歯と口腔の健康週間、自殺予防週間、こういった健康増進などに関わるものもあ
り、こういったところと薬局が協力し合うことがすごく大事であると思っている。自ら
健康増進活動をつくり上げていくといったことも必要であるが、既に地域の中で行われ
ていることについて、協力し合っていくということが重要である。
32.ネットを中心に、うそ偽りを含めた不正確な健康に関する情報が氾濫している。そうい
った健康情報に関する正しい情報を住民に届ける、相談を受ける役割というものもあっ
ていいのではないかと考える。
33.災害・新興感染症対応については、ただ検査薬を売るとか提供するということで済むわ
けではなく、新興感染症があったときに、防護服も含めて、全てを備えて、そして、そ
れに対して患者さんのところに行って必要な対応を行っていただくことができて初めて
対応ということであり、検査薬のことだけで論議するべきではない。
34.自分の身近なイメージだけで申し上げるが、患者を見ていると、いろいろな薬局を利用
しており、必ずしも全ての薬局でちゃんと全部服薬の内容が分かっていないということ
もある。地域連携薬局の基準の中に地域の医療機関との連携ということがあるが、特に
地域の医療機関は、いわゆるクリニックや病院だけではく面として支えるという意味で
も地域の薬局との情報連携、特に何を飲んでいてどうだということは重要である。面で
支えていくという意味でも、ハブになるような薬局があって、小さい薬局もまとめてい
ただいて、全体として安全を図っていったり、患者を支えていただいたりすると、非常
にありがたいと感じている。
35.健康増進支援薬局が本来果たすべき役割にフォーカスしていただくことが重要である。
その観点で言うと、本日が専門医療機関連携薬局の議論の場ではないと理解した上での
発言になるが、例えば高度薬学管理機能と、健康増進支援機能との役割分担もあってい
いと思う。具体的には、5 ページの図の住民、主に未病の方に対する健康相談・関係機関
との連携は、全て健康増進支援薬局の赤枠が上に飛び出ているところで担っているが、
一方で高度薬学管理機能については、がんの患者がいよいよ治療導入になってからの役
割というようなことで、この図がつくられていたと思うが、例えば希少がんの方とか、
あるいはがんにならないような普段からの生活づくりもある。また、今後、HIV などを議
論するのであれば、そういった一般の住民の方への情報提供も含めて、いわゆる専門医
療機関連携薬局は患者になった人だけを見ればいいということではなくて、むしろ一般
の未病の住民の方も含めて、疾患とか、あるいは健康づくりのことも情報提供もしてい
6
係る条文という形で、1、2、3と書かれているが、これに沿ったような形で基準が具
現化されていくのがよいと考える。これにより、趣旨がきっちりと明確化されていくと
いうことにもつながるのではないかと思っている。
31.健康増進対策は、健康日本 21 などを踏まえて、各都道府県や地域で実施されているもの
がある。例えば、栄養、食生活、身体活動、運動、休養、飲酒、喫煙、口腔の健康に関
する生活習慣の改善や社会環境の改善に関する取組といったものが既に計画されている
と認識している。また、官公庁などが中心となって推進・啓発している禁煙週間や食育
週間、歯と口腔の健康週間、自殺予防週間、こういった健康増進などに関わるものもあ
り、こういったところと薬局が協力し合うことがすごく大事であると思っている。自ら
健康増進活動をつくり上げていくといったことも必要であるが、既に地域の中で行われ
ていることについて、協力し合っていくということが重要である。
32.ネットを中心に、うそ偽りを含めた不正確な健康に関する情報が氾濫している。そうい
った健康情報に関する正しい情報を住民に届ける、相談を受ける役割というものもあっ
ていいのではないかと考える。
33.災害・新興感染症対応については、ただ検査薬を売るとか提供するということで済むわ
けではなく、新興感染症があったときに、防護服も含めて、全てを備えて、そして、そ
れに対して患者さんのところに行って必要な対応を行っていただくことができて初めて
対応ということであり、検査薬のことだけで論議するべきではない。
34.自分の身近なイメージだけで申し上げるが、患者を見ていると、いろいろな薬局を利用
しており、必ずしも全ての薬局でちゃんと全部服薬の内容が分かっていないということ
もある。地域連携薬局の基準の中に地域の医療機関との連携ということがあるが、特に
地域の医療機関は、いわゆるクリニックや病院だけではく面として支えるという意味で
も地域の薬局との情報連携、特に何を飲んでいてどうだということは重要である。面で
支えていくという意味でも、ハブになるような薬局があって、小さい薬局もまとめてい
ただいて、全体として安全を図っていったり、患者を支えていただいたりすると、非常
にありがたいと感じている。
35.健康増進支援薬局が本来果たすべき役割にフォーカスしていただくことが重要である。
その観点で言うと、本日が専門医療機関連携薬局の議論の場ではないと理解した上での
発言になるが、例えば高度薬学管理機能と、健康増進支援機能との役割分担もあってい
いと思う。具体的には、5 ページの図の住民、主に未病の方に対する健康相談・関係機関
との連携は、全て健康増進支援薬局の赤枠が上に飛び出ているところで担っているが、
一方で高度薬学管理機能については、がんの患者がいよいよ治療導入になってからの役
割というようなことで、この図がつくられていたと思うが、例えば希少がんの方とか、
あるいはがんにならないような普段からの生活づくりもある。また、今後、HIV などを議
論するのであれば、そういった一般の住民の方への情報提供も含めて、いわゆる専門医
療機関連携薬局は患者になった人だけを見ればいいということではなくて、むしろ一般
の未病の住民の方も含めて、疾患とか、あるいは健康づくりのことも情報提供もしてい
6