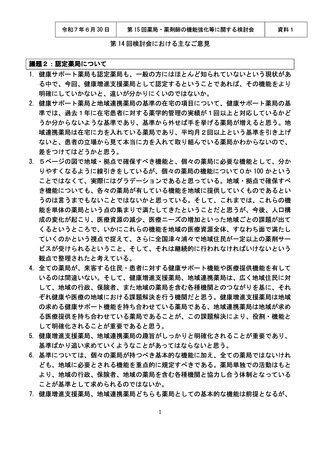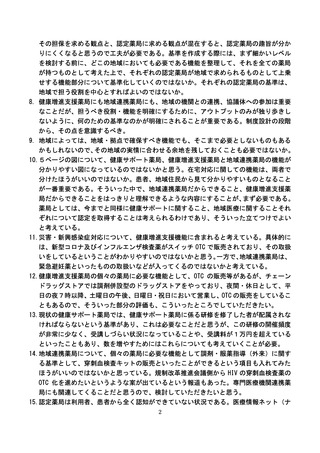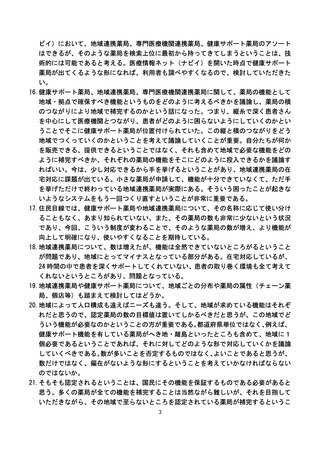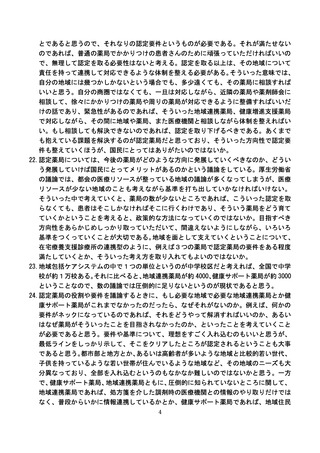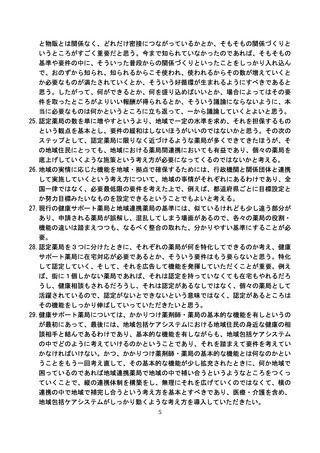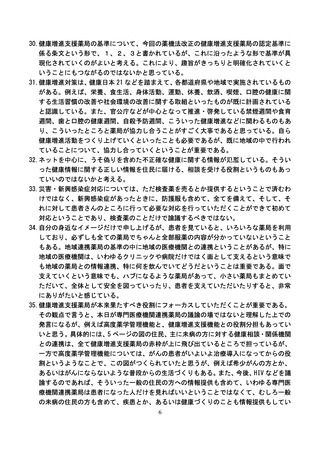よむ、つかう、まなぶ。
資料1_第14回検討会の主なご意見 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59230.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第15回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
と物販とは関係なく、どれだけ密接につながっているかとか、そもそもの関係づくりと
いうところがすごく重要だと思う。今まで知られていなかったのであれば、そもそもの
基準や要件の中に、そういった普段からの関係づくりといったことをしっかり入れ込ん
で、おのずから知られ、知られるからこそ使われ、使われるからその数が増えていくと
か必要なものが満たされていくとか、そういう好循環が生まれるようにすべきであると
思う。したがって、何ができるとか、何を盛り込めばいいとか、場合によってはその要
件を取ったところがよりいい報酬が得られるとか、そういう議論にならないように、本
当に必要なものは何かというところに立ち返って、一から議論していくとよいと思う。
25.認定薬局の数を単に増やすというより、地域で一定の水準を求め、それを担保するもの
という観点を基本とし、要件の緩和はしないほうがいいのではないかと思う。その次の
ステップとして、認定薬局に限りなく近づけるような薬局が多くできてきたほうが、そ
の地域住民にとっても、地域における薬局間連携においても有益であり、個々の薬局を
底上げしていくような施策という考え方が必要になってくるのではないかと考える。
26.地域の実情に応じた機能を地域・拠点で確保するためには、行政機関と関係団体と連携
して実施していくという考え方について、地域の事情がそれぞれにあるわけであり、全
国一律ではなく、必要最低限の要件を考えた上で、例えば、都道府県ごとに目標設定と
か努力目標みたいなものを設定できるということでもよいと考える。
27.現行の健康サポート薬局と地域連携薬局の基準には、似ているけれども少し違う部分が
あり、申請される薬局が誤解し、混乱してしまう場面があるので、各々の薬局の役割・
機能の違いは踏まえつつも、なるべく整合の取れた、分かりやすい基準にすることが必
要。
28.認定薬局を3つに分けたときに、それぞれの薬局が何を特化してできるのか考え、健康
サポート薬局に在宅対応が必要であるとか、そういう要件はもう要らないと思う。特化
して認定していく、そして、それを広告して機能を発揮していただくことが重要。例え
ば、街に1個しかない薬局であれば、それは認定を持っていなくても在宅もやれるだろ
うし、健康相談もされるだろうし、それは認定があるなしではなく、個々の薬局として
活躍されているので、認定がないとできないという意味ではなく、認定があるところは
その機能をしっかり伸ばしていっていただきたいと思う。
29.健康サポート薬局については、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有しというの
が最初にあって、最後には、地域包括ケアシステムにおける地域住民の身近な健康の相
談相手と結んであるわけであり、基本的な機能を有しながらも、地域包括ケアシステム
の中でどのように考えていけるのかということであり、それを踏まえて要件を考えてい
かなければいけない。かつ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能とは何なのかとい
うことをもう一回考え直して、その基本的な機能が少し拡充されたときに、何か地域で
困っているのであれば地域連携薬局で地域の中で補い合うというようなところをつくっ
ていくことで、縦の連携体制を構築をし、無理にそれを広げていくのではなくて、横の
連携の中で地域で補完し合うという考え方を基本とすべきであり、医療・介護を含め、
地域包括ケアシステムがしっかり動くような考え方を導入していただきたい。
5
いうところがすごく重要だと思う。今まで知られていなかったのであれば、そもそもの
基準や要件の中に、そういった普段からの関係づくりといったことをしっかり入れ込ん
で、おのずから知られ、知られるからこそ使われ、使われるからその数が増えていくと
か必要なものが満たされていくとか、そういう好循環が生まれるようにすべきであると
思う。したがって、何ができるとか、何を盛り込めばいいとか、場合によってはその要
件を取ったところがよりいい報酬が得られるとか、そういう議論にならないように、本
当に必要なものは何かというところに立ち返って、一から議論していくとよいと思う。
25.認定薬局の数を単に増やすというより、地域で一定の水準を求め、それを担保するもの
という観点を基本とし、要件の緩和はしないほうがいいのではないかと思う。その次の
ステップとして、認定薬局に限りなく近づけるような薬局が多くできてきたほうが、そ
の地域住民にとっても、地域における薬局間連携においても有益であり、個々の薬局を
底上げしていくような施策という考え方が必要になってくるのではないかと考える。
26.地域の実情に応じた機能を地域・拠点で確保するためには、行政機関と関係団体と連携
して実施していくという考え方について、地域の事情がそれぞれにあるわけであり、全
国一律ではなく、必要最低限の要件を考えた上で、例えば、都道府県ごとに目標設定と
か努力目標みたいなものを設定できるということでもよいと考える。
27.現行の健康サポート薬局と地域連携薬局の基準には、似ているけれども少し違う部分が
あり、申請される薬局が誤解し、混乱してしまう場面があるので、各々の薬局の役割・
機能の違いは踏まえつつも、なるべく整合の取れた、分かりやすい基準にすることが必
要。
28.認定薬局を3つに分けたときに、それぞれの薬局が何を特化してできるのか考え、健康
サポート薬局に在宅対応が必要であるとか、そういう要件はもう要らないと思う。特化
して認定していく、そして、それを広告して機能を発揮していただくことが重要。例え
ば、街に1個しかない薬局であれば、それは認定を持っていなくても在宅もやれるだろ
うし、健康相談もされるだろうし、それは認定があるなしではなく、個々の薬局として
活躍されているので、認定がないとできないという意味ではなく、認定があるところは
その機能をしっかり伸ばしていっていただきたいと思う。
29.健康サポート薬局については、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有しというの
が最初にあって、最後には、地域包括ケアシステムにおける地域住民の身近な健康の相
談相手と結んであるわけであり、基本的な機能を有しながらも、地域包括ケアシステム
の中でどのように考えていけるのかということであり、それを踏まえて要件を考えてい
かなければいけない。かつ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能とは何なのかとい
うことをもう一回考え直して、その基本的な機能が少し拡充されたときに、何か地域で
困っているのであれば地域連携薬局で地域の中で補い合うというようなところをつくっ
ていくことで、縦の連携体制を構築をし、無理にそれを広げていくのではなくて、横の
連携の中で地域で補完し合うという考え方を基本とすべきであり、医療・介護を含め、
地域包括ケアシステムがしっかり動くような考え方を導入していただきたい。
5