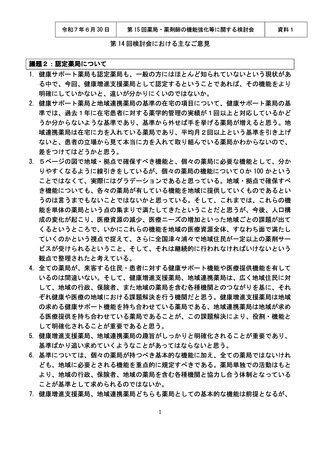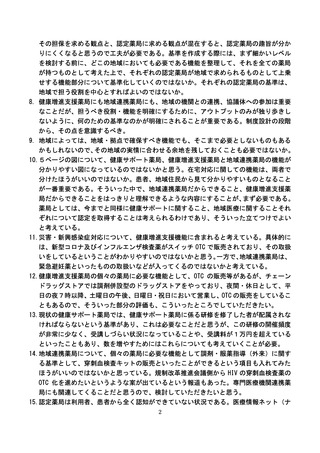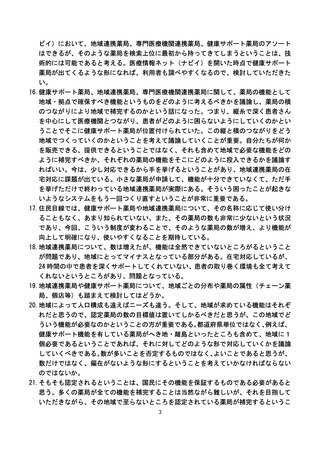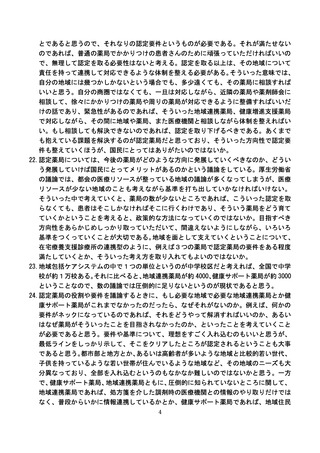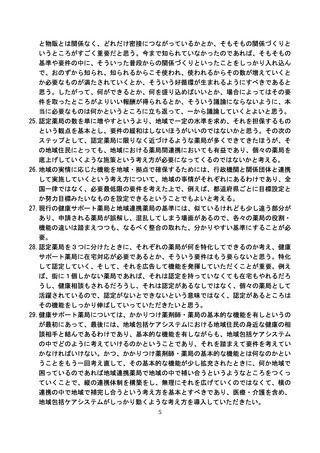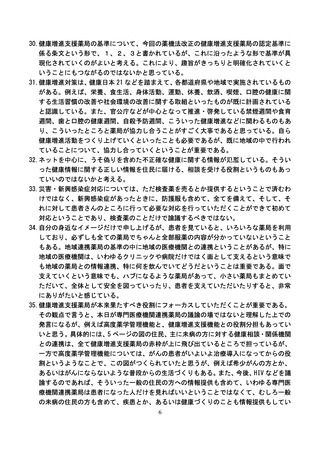よむ、つかう、まなぶ。
資料1_第14回検討会の主なご意見 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59230.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第15回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
とであると思うので、それなりの認定要件というものが必要である。それが満たせない
のであれば、普通の薬局でかかりつけの患者さんのために頑張っていただければいいの
で、無理して認定を取る必要性はないと考える。認定を取る以上は、その地域について
責任を持って連携して対応できるような体制を整える必要がある。そういった意味では、
自分の地域には幾つかしかないという場合でも、多少遠くても、その薬局に相談すれば
いいと思う。自分の商圏ではなくても、一旦は対応しながら、近隣の薬局や薬剤師会に
相談して、徐々にかかりつけの薬局や周りの薬局が対応できるように整備すればいいだ
けの話であり、緊急性があるのであれば、そういった地域連携薬局、健康増進支援薬局
で対応しながら、その間に地域や薬局、また医療機関と相談しながら体制を整えればい
い。もし相談しても解決できないのであれば、認定を取り下げるべきである。あくまで
も抱えている課題を解決するのが認定薬局だと思っており、そういった方向性で認定要
件も整えていくほうが、国民にとってはありがたいのではないか。
22.認定薬局については、今後の薬局がどのような方向に発展していくべきなのか、どうい
う発展していけば国民にとってメリットがあるのかという議論をしている。厚生労働省
の議論では、都会の医療リソースが整っている地域の議論が多くなってしまうが、医療
リソースが少ない地域のことも考えながら基準を打ち出していかなければいけない。
そういった中で考えていくと、薬局の数が少ないところであれば、こういった認定を取
らなくても、患者はそこしかなければそこに行くわけであり、そういう薬局をどう育て
ていくかということを考えると、政策的な方法になっていくのではないか。目指すべき
方向性をあらかじめしっかり取っていただいて、間違えないようにしながら、いろいろ
基準をつくっていくことが大切である。地域を面として支えていくということについて、
在宅療養支援診療所の連携型のように、例えば3つの薬局で認定薬局の要件をある程度
満たしていくとか、そういった考え方を取り入れてもよいのではないか。
23.地域包括ケアシステムの中で1つの単位というのが中学校区だと考えれば、全国で中学
校が約1万校ある。それに比べると、地域連携薬局が約 4000、健康サポート薬局が約 3000
ということなので、数の議論では圧倒的に足りないというのが現状であると思う。
24.認定薬局の役割や要件を議論するときに、もし必要な地域で必要な地域連携薬局とか健
康サポート薬局がこれまでなかったのだったら、なぜそれがないのか。例えば、何かの
要件がネックになっているのであれば、それをどうやって解消すればいいのか、あるい
はなぜ薬局がそういったことを目指されなかったのか、といったことを考えていくこと
が必要であると思う。要件や基準について、理想をすごく入れ込むのもいいと思うが、
最低ラインをしっかり示して、そこをクリアしたところが認定されるということも大事
であると思う。都市部と地方とか、あるいは高齢者が多いような地域と比較的若い世代、
子供を持っているような若い世帯が住んでいるような地域など、その地域のニーズも大
分異なっており、全部を入れ込むというのもなかなか難しいのではないかと思う。一方
で、健康サポート薬局、地域連携薬局ともに、圧倒的に知られていないところに関して、
地域連携薬局であれば、処方箋を介した調剤時の医療機関との情報のやり取りだけでは
なく、普段からいかに情報連携しているかとか、健康サポート薬局であれば、地域住民
4
のであれば、普通の薬局でかかりつけの患者さんのために頑張っていただければいいの
で、無理して認定を取る必要性はないと考える。認定を取る以上は、その地域について
責任を持って連携して対応できるような体制を整える必要がある。そういった意味では、
自分の地域には幾つかしかないという場合でも、多少遠くても、その薬局に相談すれば
いいと思う。自分の商圏ではなくても、一旦は対応しながら、近隣の薬局や薬剤師会に
相談して、徐々にかかりつけの薬局や周りの薬局が対応できるように整備すればいいだ
けの話であり、緊急性があるのであれば、そういった地域連携薬局、健康増進支援薬局
で対応しながら、その間に地域や薬局、また医療機関と相談しながら体制を整えればい
い。もし相談しても解決できないのであれば、認定を取り下げるべきである。あくまで
も抱えている課題を解決するのが認定薬局だと思っており、そういった方向性で認定要
件も整えていくほうが、国民にとってはありがたいのではないか。
22.認定薬局については、今後の薬局がどのような方向に発展していくべきなのか、どうい
う発展していけば国民にとってメリットがあるのかという議論をしている。厚生労働省
の議論では、都会の医療リソースが整っている地域の議論が多くなってしまうが、医療
リソースが少ない地域のことも考えながら基準を打ち出していかなければいけない。
そういった中で考えていくと、薬局の数が少ないところであれば、こういった認定を取
らなくても、患者はそこしかなければそこに行くわけであり、そういう薬局をどう育て
ていくかということを考えると、政策的な方法になっていくのではないか。目指すべき
方向性をあらかじめしっかり取っていただいて、間違えないようにしながら、いろいろ
基準をつくっていくことが大切である。地域を面として支えていくということについて、
在宅療養支援診療所の連携型のように、例えば3つの薬局で認定薬局の要件をある程度
満たしていくとか、そういった考え方を取り入れてもよいのではないか。
23.地域包括ケアシステムの中で1つの単位というのが中学校区だと考えれば、全国で中学
校が約1万校ある。それに比べると、地域連携薬局が約 4000、健康サポート薬局が約 3000
ということなので、数の議論では圧倒的に足りないというのが現状であると思う。
24.認定薬局の役割や要件を議論するときに、もし必要な地域で必要な地域連携薬局とか健
康サポート薬局がこれまでなかったのだったら、なぜそれがないのか。例えば、何かの
要件がネックになっているのであれば、それをどうやって解消すればいいのか、あるい
はなぜ薬局がそういったことを目指されなかったのか、といったことを考えていくこと
が必要であると思う。要件や基準について、理想をすごく入れ込むのもいいと思うが、
最低ラインをしっかり示して、そこをクリアしたところが認定されるということも大事
であると思う。都市部と地方とか、あるいは高齢者が多いような地域と比較的若い世代、
子供を持っているような若い世帯が住んでいるような地域など、その地域のニーズも大
分異なっており、全部を入れ込むというのもなかなか難しいのではないかと思う。一方
で、健康サポート薬局、地域連携薬局ともに、圧倒的に知られていないところに関して、
地域連携薬局であれば、処方箋を介した調剤時の医療機関との情報のやり取りだけでは
なく、普段からいかに情報連携しているかとか、健康サポート薬局であれば、地域住民
4