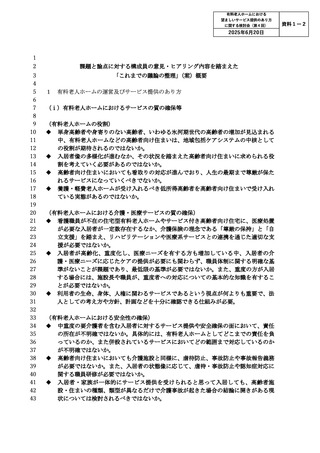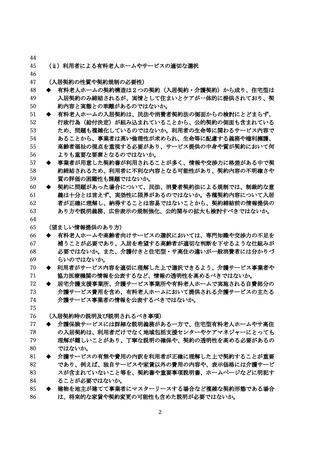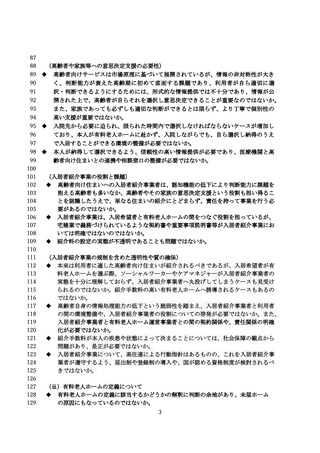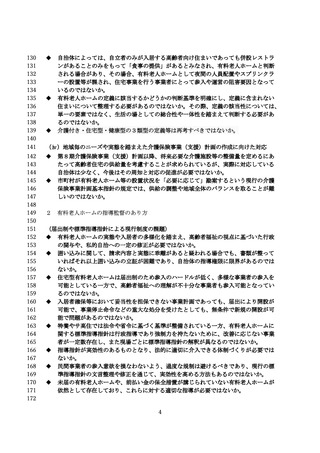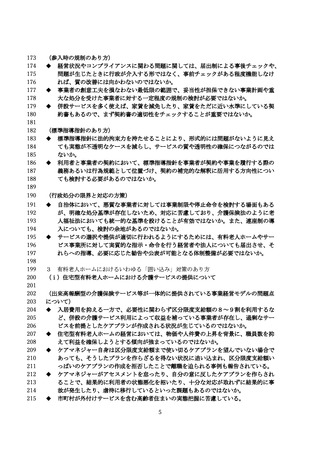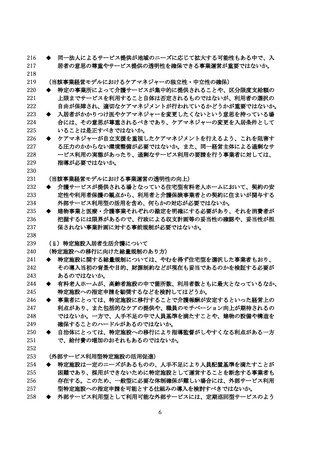よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえたこれまでの議論の整理(案)【概要】 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
◆
同一法人によるサービス提供が地域のニーズに応じて拡大する可能性もある中で、入
居者の意思の尊重やサービス提供の透明性を確保できる事業運営が重要ではないか。
(当該事業経営モデルにおけるケアマネジャーの独立性・中立性の確保)
◆ 特定の事業所によって介護サービスが集中的に提供されることや、区分限度支給額の
上限までサービスを利用すること自体は否定されるものではないが、利用者の選択の
自由が保障され、適切なケアマネジメントが行われているかどうかが重要ではないか。
◆ 入居者がかかりつけ医やケアマネジャーを変更したくないという意思を持っている場
合には、その意思が尊重されるべきであり、ケアマネジャーの変更を入居条件として
いることは是正すべきではないか。
◆ ケアマネジャーが自立支援を重視したケアマネジメントを行えるよう、これを阻害す
る圧力のかからない環境整備が必要ではないか。また、同一経営主体による過剰なサ
ービス利用の実態があったり、過剰なサービス利用の要請を行う事業者に対しては、
指導が必要ではないか。
(当該事業経営モデルにおける事業運営の透明性の向上)
◆ 介護サービスが提供される場となっている住宅型有料老人ホームにおいて、契約の安
定性や利用者保護の観点から、利用者と介護保険事業者との契約に住まいが関与する
外部サービス利用型の活用を含め、何らかの対応が必要ではないか。
◆ 建物事業と医療・介護事業それぞれの勘定を明確にする必要があり、それを消費者が
把握するには限界があるので、行政による収支計画等の妥当性の確認や、妥当性が担
保されない事業計画に対する事前規制が必要ではないか。
(ⅱ)特定施設入居者生活介護について
(特定施設への移行に向けた総量規制のあり方)
◆ 特定施設に関する総量規制については、やむを得ず住宅型を選択した事業者もおり、
その導入当初の背景や目的、財源制約などが現在も妥当であるのかを検証する必要が
あるのではないか。
◆ 有料老人ホームが、高齢者施設の中で箇所数、利用者数ともに最大となっているなか、
特定施設への指定申請を勧奨するなどを検討してはどうか。
◆ 事業者にとっては、特定施設に移行することで介護報酬が安定するといった経営上の
利点があり、また包括的なケアの提供や、職員のモチベーション向上が期待されるの
ではないか。一方で、人手不足の中で人員基準を満たすことや、建物の設備や構造を
確保することのハードルがあるのではないか。
◆ 自治体にとっては、特定施設への移行により指導監督がしやすくなる利点がある一方
で、給付費の増加のおそれもあるのではないか。
(外部サービス利用型特定施設の活用促進)
◆ 特定施設は一定のニーズがあるものの、人手不足により人員配置基準を満たすことが
困難であり、採用ができないために特定施設として運営することを断念する事業者も
存在する。このため、一般型に必要な体制確保が難しい場合には、外部サービス利用
型特定施設への指定申請を可能とする仕組みの導入を検討すべきではないか。
◆ 外部サービス利用型として利用可能な外部サービスには、定期巡回型サービスのよう
6
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
◆
同一法人によるサービス提供が地域のニーズに応じて拡大する可能性もある中で、入
居者の意思の尊重やサービス提供の透明性を確保できる事業運営が重要ではないか。
(当該事業経営モデルにおけるケアマネジャーの独立性・中立性の確保)
◆ 特定の事業所によって介護サービスが集中的に提供されることや、区分限度支給額の
上限までサービスを利用すること自体は否定されるものではないが、利用者の選択の
自由が保障され、適切なケアマネジメントが行われているかどうかが重要ではないか。
◆ 入居者がかかりつけ医やケアマネジャーを変更したくないという意思を持っている場
合には、その意思が尊重されるべきであり、ケアマネジャーの変更を入居条件として
いることは是正すべきではないか。
◆ ケアマネジャーが自立支援を重視したケアマネジメントを行えるよう、これを阻害す
る圧力のかからない環境整備が必要ではないか。また、同一経営主体による過剰なサ
ービス利用の実態があったり、過剰なサービス利用の要請を行う事業者に対しては、
指導が必要ではないか。
(当該事業経営モデルにおける事業運営の透明性の向上)
◆ 介護サービスが提供される場となっている住宅型有料老人ホームにおいて、契約の安
定性や利用者保護の観点から、利用者と介護保険事業者との契約に住まいが関与する
外部サービス利用型の活用を含め、何らかの対応が必要ではないか。
◆ 建物事業と医療・介護事業それぞれの勘定を明確にする必要があり、それを消費者が
把握するには限界があるので、行政による収支計画等の妥当性の確認や、妥当性が担
保されない事業計画に対する事前規制が必要ではないか。
(ⅱ)特定施設入居者生活介護について
(特定施設への移行に向けた総量規制のあり方)
◆ 特定施設に関する総量規制については、やむを得ず住宅型を選択した事業者もおり、
その導入当初の背景や目的、財源制約などが現在も妥当であるのかを検証する必要が
あるのではないか。
◆ 有料老人ホームが、高齢者施設の中で箇所数、利用者数ともに最大となっているなか、
特定施設への指定申請を勧奨するなどを検討してはどうか。
◆ 事業者にとっては、特定施設に移行することで介護報酬が安定するといった経営上の
利点があり、また包括的なケアの提供や、職員のモチベーション向上が期待されるの
ではないか。一方で、人手不足の中で人員基準を満たすことや、建物の設備や構造を
確保することのハードルがあるのではないか。
◆ 自治体にとっては、特定施設への移行により指導監督がしやすくなる利点がある一方
で、給付費の増加のおそれもあるのではないか。
(外部サービス利用型特定施設の活用促進)
◆ 特定施設は一定のニーズがあるものの、人手不足により人員配置基準を満たすことが
困難であり、採用ができないために特定施設として運営することを断念する事業者も
存在する。このため、一般型に必要な体制確保が難しい場合には、外部サービス利用
型特定施設への指定申請を可能とする仕組みの導入を検討すべきではないか。
◆ 外部サービス利用型として利用可能な外部サービスには、定期巡回型サービスのよう
6