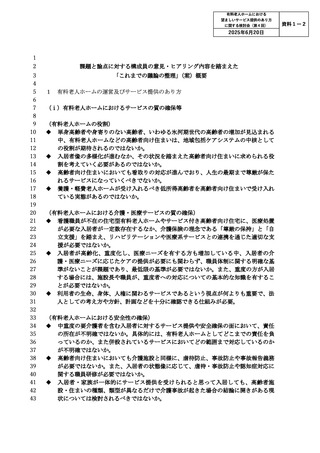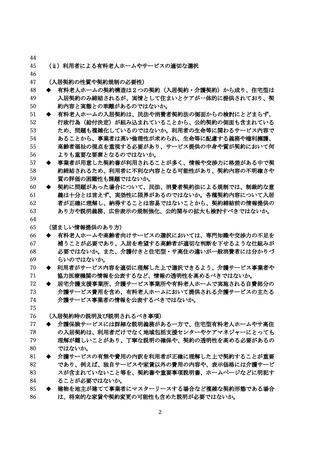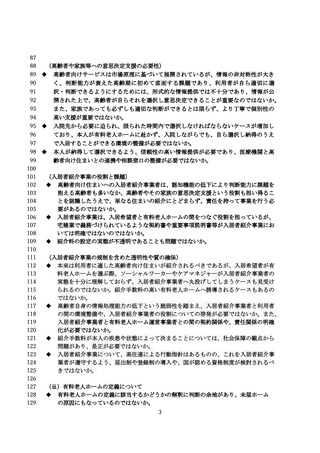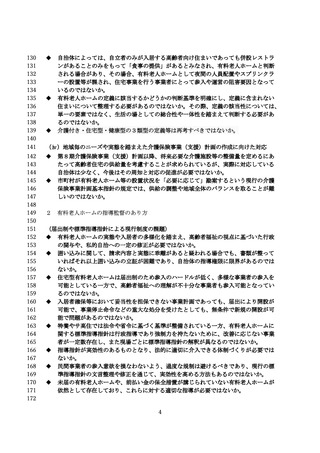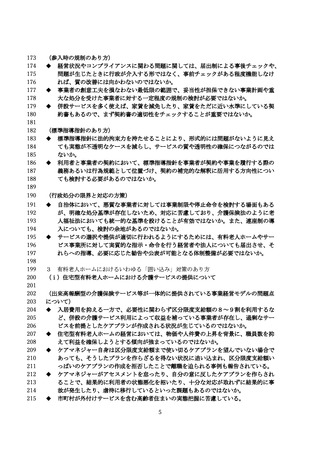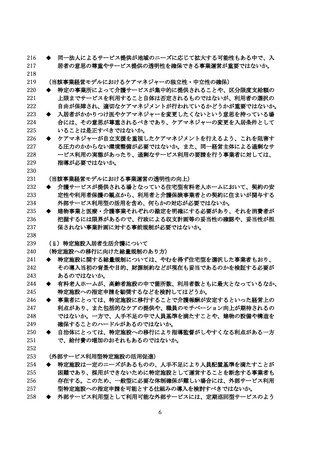よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえたこれまでの議論の整理(案)【概要】 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
◆
141
(ⅳ)地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
◆
◆
◆
◆
自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいであっても併設レストラ
ンがあることのみをもって「食事の提供」があるとみなされ、有料老人ホームと判断
される場合があり、その場合、有料老人ホームとして夜間の人員配置やスプリンクラ
ーの設置等が課され、住宅事業を行う事業者にとって参入や運営の阻害要因となって
いるのではないか。
有料老人ホームの定義に該当するかどうかの判断基準を明確にし、定義に含まれない
住まいについて整理する必要があるのではないか。その際、定義の該当性については、
単一の要素ではなく、生活の場としての総合性や一体性を踏まえて判断する必要があ
るのではないか。
介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義等は再考すべきではないか。
第8期介護保険事業(支援)計画以降、将来必要な介護施設等の整備量を定めるにあ
たって高齢者住宅の供給量を考慮することが求められているが、実際に対応している
自治体は少なく、今後はその周知と対応の促進が必要ではないか。
市町村が有料老人ホーム等の設置状況を「必要に応じて」勘案するという現行の介護
保険事業計画基本指針の規定では、供給の調整や地域全体のバランスを取ることが難
しいのではないか。
2 有料老人ホームの指導監督のあり方
(届出制や標準指導指針による現行制度の課題)
◆ 有料老人ホームの実態や入居者の多様化を踏まえ、高齢者福祉の視点に基づいた行政
の関与や、私的自治への一定の修正が必要ではないか。
◆ 囲い込みに関して、請求内容と実態に乖離があると疑われる場合でも、書類が整って
いればそれ以上囲い込みの立証が困難であり、自治体の指導権限に限界があるのでは
ないか。
◆ 住宅型有料老人ホームは届出制のため参入のハードルが低く、多様な事業者の参入を
可能としている一方で、高齢者福祉への理解が不十分な事業者も参入可能となってい
るのではないか。
◆ 入居者確保等において妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設が
可能で、事業停止命令などの重大な処分を受けたとしても、無条件で新規の開設が可
能で問題があるのではないか。
◆ 特養やサ高住では法令や省令に基づく基準が整備されている一方、有料老人ホームに
関する標準指導指針は行政指導であり強制力を持たないために、改善に応じない事業
者が一定数存在し、また現場ごとに標準指導指針の解釈が異なるのではないか。
◆ 指導指針が実効性のあるものとなり、法的に適切に介入できる体制づくりが必要では
ないか。
◆ 民間事業者の参入意欲を損なわないよう、過度な規制は避けるべきであり、現行の標
準指導指針の文言整理や修正を通じて、実効性を高める方法もあるのではないか。
◆ 未届の有料老人ホームや、前払い金の保全措置が講じられていない有料老人ホームが
依然として存在しており、これらに対する適切な指導が必要ではないか。
4
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
◆
141
(ⅳ)地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
◆
◆
◆
◆
自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいであっても併設レストラ
ンがあることのみをもって「食事の提供」があるとみなされ、有料老人ホームと判断
される場合があり、その場合、有料老人ホームとして夜間の人員配置やスプリンクラ
ーの設置等が課され、住宅事業を行う事業者にとって参入や運営の阻害要因となって
いるのではないか。
有料老人ホームの定義に該当するかどうかの判断基準を明確にし、定義に含まれない
住まいについて整理する必要があるのではないか。その際、定義の該当性については、
単一の要素ではなく、生活の場としての総合性や一体性を踏まえて判断する必要があ
るのではないか。
介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義等は再考すべきではないか。
第8期介護保険事業(支援)計画以降、将来必要な介護施設等の整備量を定めるにあ
たって高齢者住宅の供給量を考慮することが求められているが、実際に対応している
自治体は少なく、今後はその周知と対応の促進が必要ではないか。
市町村が有料老人ホーム等の設置状況を「必要に応じて」勘案するという現行の介護
保険事業計画基本指針の規定では、供給の調整や地域全体のバランスを取ることが難
しいのではないか。
2 有料老人ホームの指導監督のあり方
(届出制や標準指導指針による現行制度の課題)
◆ 有料老人ホームの実態や入居者の多様化を踏まえ、高齢者福祉の視点に基づいた行政
の関与や、私的自治への一定の修正が必要ではないか。
◆ 囲い込みに関して、請求内容と実態に乖離があると疑われる場合でも、書類が整って
いればそれ以上囲い込みの立証が困難であり、自治体の指導権限に限界があるのでは
ないか。
◆ 住宅型有料老人ホームは届出制のため参入のハードルが低く、多様な事業者の参入を
可能としている一方で、高齢者福祉への理解が不十分な事業者も参入可能となってい
るのではないか。
◆ 入居者確保等において妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設が
可能で、事業停止命令などの重大な処分を受けたとしても、無条件で新規の開設が可
能で問題があるのではないか。
◆ 特養やサ高住では法令や省令に基づく基準が整備されている一方、有料老人ホームに
関する標準指導指針は行政指導であり強制力を持たないために、改善に応じない事業
者が一定数存在し、また現場ごとに標準指導指針の解釈が異なるのではないか。
◆ 指導指針が実効性のあるものとなり、法的に適切に介入できる体制づくりが必要では
ないか。
◆ 民間事業者の参入意欲を損なわないよう、過度な規制は避けるべきであり、現行の標
準指導指針の文言整理や修正を通じて、実効性を高める方法もあるのではないか。
◆ 未届の有料老人ホームや、前払い金の保全措置が講じられていない有料老人ホームが
依然として存在しており、これらに対する適切な指導が必要ではないか。
4