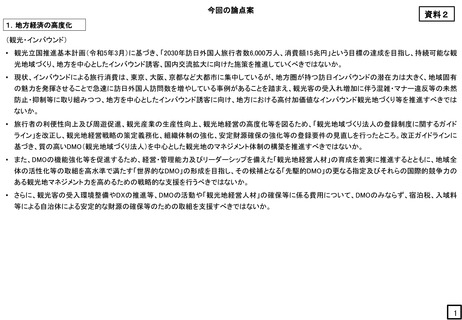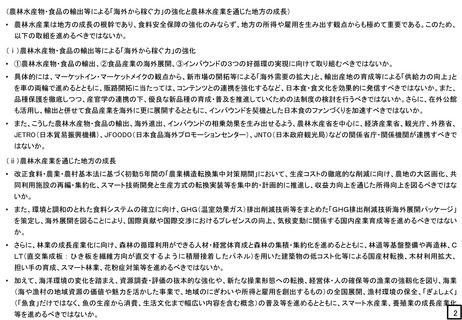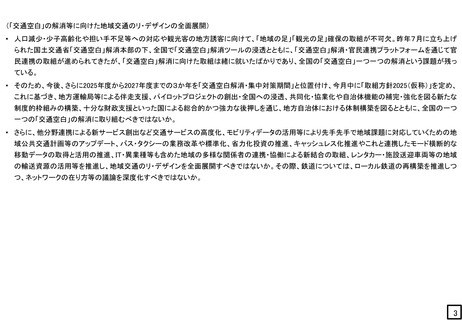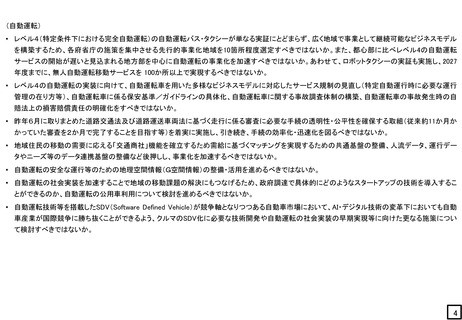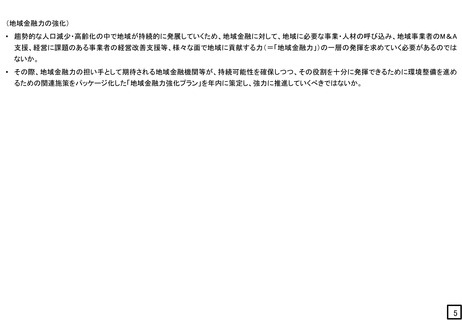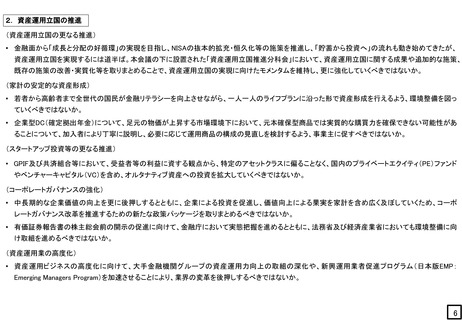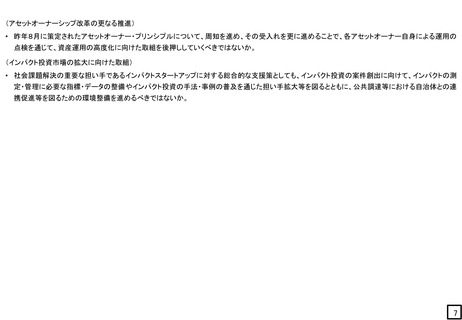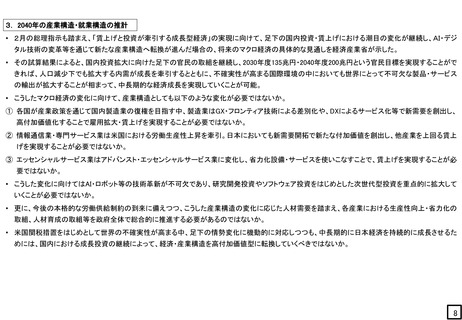よむ、つかう、まなぶ。
資料2論点案 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
| 出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(農林水産物・食品の輸出等による「海外から稼ぐ力」の強化と農林水産業を通じた地方の成長)
• 農林水産業は地方の成長の根幹であり、食料安全保障の強化のみならず、地方の所得や雇用を生み出す観点からも極めて重要である。このため、
以下の取組を進めるべきではないか。
(ⅰ)農林水産物・食品の輸出等による「海外から稼ぐ力」の強化
• ①農林水産物・食品の輸出、②食品産業の海外展開、③インバウンドの3つの好循環の実現に向けて取り組むべきではないか。
• 具体的には、マーケットイン・マーケットメイクの観点から、新市場の開拓等による「海外需要の拡大」と、輸出産地の育成等による「供給力の向上」と
を車の両輪で進めるとともに、販路開拓に当たっては、コンテンツとの連携を強化するなど、日本食・食文化を効果的に発信すべきではないか。また、
品種保護を徹底しつつ、産官学の連携の下、優良な新品種の育成・普及を推進していくための法制度の検討を行うべきではないか。さらに、在外公館
も活用し、輸出と併せて食品産業を海外に更に展開するとともに、インバウンドを契機とした日本食のファンづくりを加速すべきではないか。
• また、こうした農林水産物・食品の輸出、海外進出、インバウンドの相乗効果を生み出せるよう、農林水産省を中心に、経済産業省、観光庁、外務省、
JETRO(日本貿易振興機構)、JFOODO(日本食品海外プロモーションセンター)、JNTO(日本政府観光局)などの関係省庁・関係機関が連携すべきで
はないか。
(ⅱ)農林水産業を通じた地方の成長
• 改正食料・農業・農村基本法に基づく初動5年間の「農業構造転換集中対策期間」において、生産コストの徹底的な削減に向け、農地の大区画化、共
同利用施設の再編・集約化、スマート技術開発と生産方式の転換実装等を集中的・計画的に推進し、収益力向上を通じた所得向上を図るべきではな
いか。
• また、環境と調和のとれた食料システムの確立に向け、GHG(温室効果ガス)排出削減技術等をまとめた「GHG排出削減技術海外展開パッケージ」
を策定し、海外展開を図ることにより、国際貢献や国際交渉におけるプレゼンスの向上、気候変動に関係する国内産業育成等を進めるべきではない
か。
• さらに、林業の成長産業化に向け、森林の循環利用ができる人材・経営体育成と森林の集積・集約化を進めるとともに、林道等基盤整備や再造林、C
LT(直交集成板:ひき板を繊維方向が直交するように積層接着したパネル)を用いた建築物の低コスト化等による国産材転換、木材利用拡大、
担い手の育成、スマート林業、花粉症対策等を進めるべきではないか。
• 加えて、海洋環境の変化を踏まえ、資源調査・評価の抜本的な強化や、新たな操業形態への転換、経営体・人の確保等の漁業の強靱化を図り、海業
(海や漁村の地域資源の価値や魅力を活かした事業で、地域のにぎわいや所得と雇用を創出するもの)の全国展開、漁村環境の保全、「ぎょしょく」
(「魚食」だけではなく、魚の生産から消費、生活文化まで幅広い内容を含む概念)の普及等を進めるとともに、スマート水産業、養殖業の成長産業化
等を進めるべきではないか。
2
• 農林水産業は地方の成長の根幹であり、食料安全保障の強化のみならず、地方の所得や雇用を生み出す観点からも極めて重要である。このため、
以下の取組を進めるべきではないか。
(ⅰ)農林水産物・食品の輸出等による「海外から稼ぐ力」の強化
• ①農林水産物・食品の輸出、②食品産業の海外展開、③インバウンドの3つの好循環の実現に向けて取り組むべきではないか。
• 具体的には、マーケットイン・マーケットメイクの観点から、新市場の開拓等による「海外需要の拡大」と、輸出産地の育成等による「供給力の向上」と
を車の両輪で進めるとともに、販路開拓に当たっては、コンテンツとの連携を強化するなど、日本食・食文化を効果的に発信すべきではないか。また、
品種保護を徹底しつつ、産官学の連携の下、優良な新品種の育成・普及を推進していくための法制度の検討を行うべきではないか。さらに、在外公館
も活用し、輸出と併せて食品産業を海外に更に展開するとともに、インバウンドを契機とした日本食のファンづくりを加速すべきではないか。
• また、こうした農林水産物・食品の輸出、海外進出、インバウンドの相乗効果を生み出せるよう、農林水産省を中心に、経済産業省、観光庁、外務省、
JETRO(日本貿易振興機構)、JFOODO(日本食品海外プロモーションセンター)、JNTO(日本政府観光局)などの関係省庁・関係機関が連携すべきで
はないか。
(ⅱ)農林水産業を通じた地方の成長
• 改正食料・農業・農村基本法に基づく初動5年間の「農業構造転換集中対策期間」において、生産コストの徹底的な削減に向け、農地の大区画化、共
同利用施設の再編・集約化、スマート技術開発と生産方式の転換実装等を集中的・計画的に推進し、収益力向上を通じた所得向上を図るべきではな
いか。
• また、環境と調和のとれた食料システムの確立に向け、GHG(温室効果ガス)排出削減技術等をまとめた「GHG排出削減技術海外展開パッケージ」
を策定し、海外展開を図ることにより、国際貢献や国際交渉におけるプレゼンスの向上、気候変動に関係する国内産業育成等を進めるべきではない
か。
• さらに、林業の成長産業化に向け、森林の循環利用ができる人材・経営体育成と森林の集積・集約化を進めるとともに、林道等基盤整備や再造林、C
LT(直交集成板:ひき板を繊維方向が直交するように積層接着したパネル)を用いた建築物の低コスト化等による国産材転換、木材利用拡大、
担い手の育成、スマート林業、花粉症対策等を進めるべきではないか。
• 加えて、海洋環境の変化を踏まえ、資源調査・評価の抜本的な強化や、新たな操業形態への転換、経営体・人の確保等の漁業の強靱化を図り、海業
(海や漁村の地域資源の価値や魅力を活かした事業で、地域のにぎわいや所得と雇用を創出するもの)の全国展開、漁村環境の保全、「ぎょしょく」
(「魚食」だけではなく、魚の生産から消費、生活文化まで幅広い内容を含む概念)の普及等を進めるとともに、スマート水産業、養殖業の成長産業化
等を進めるべきではないか。
2