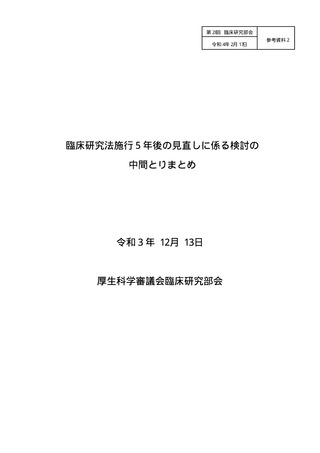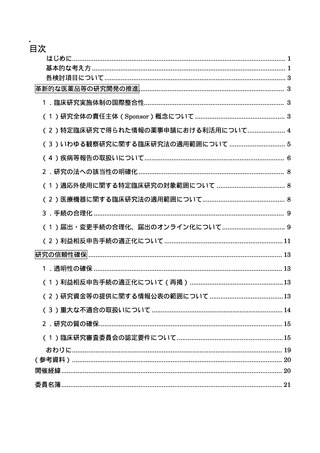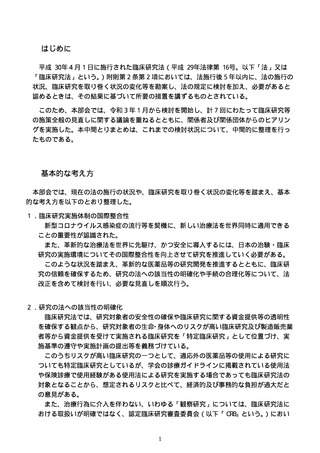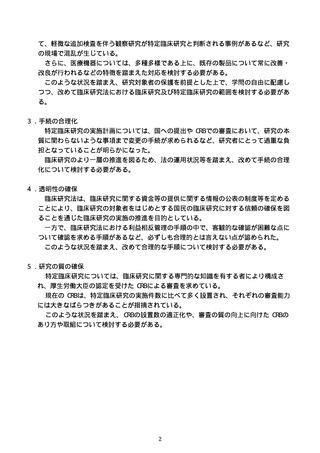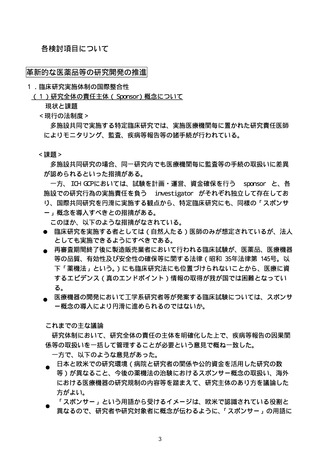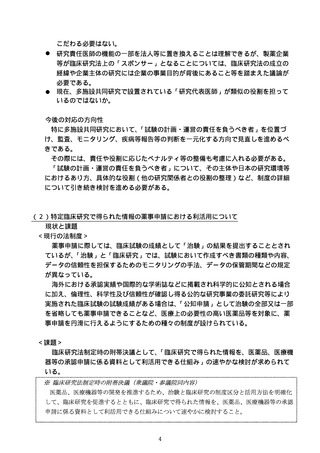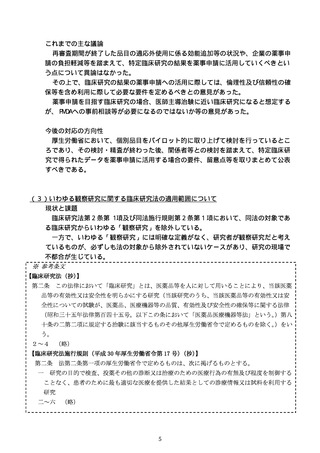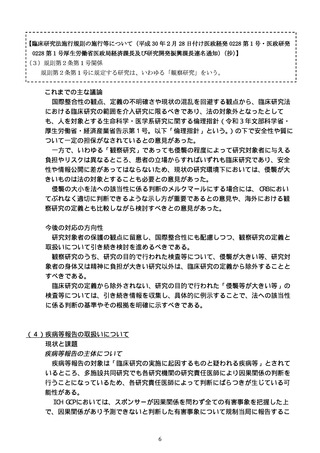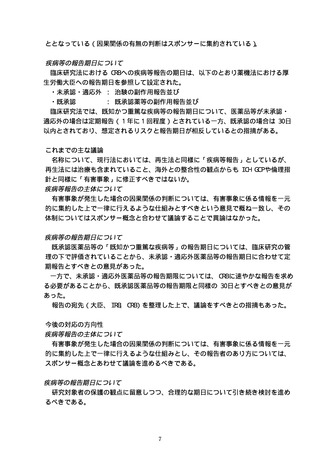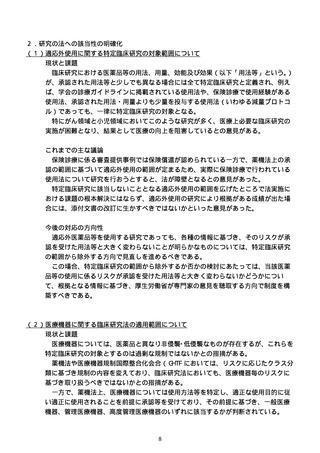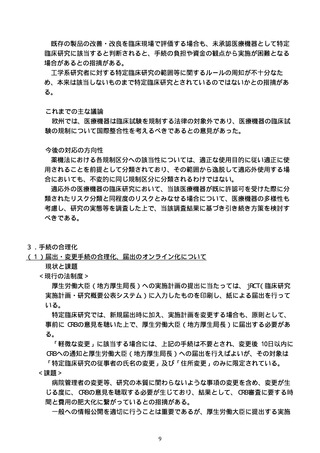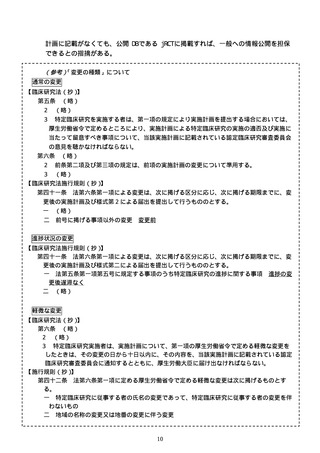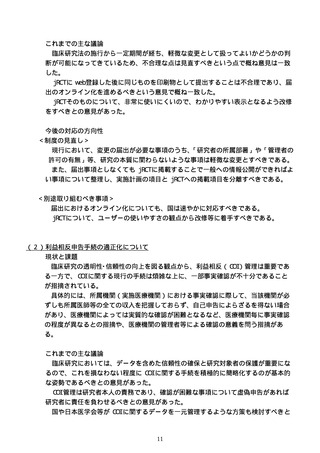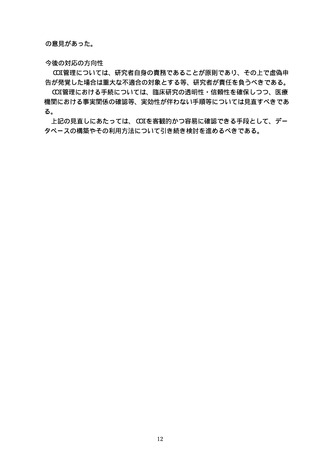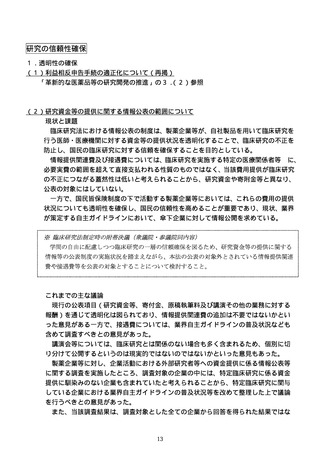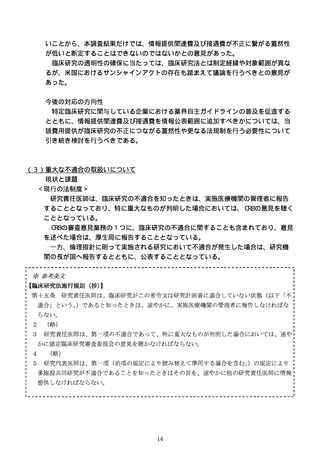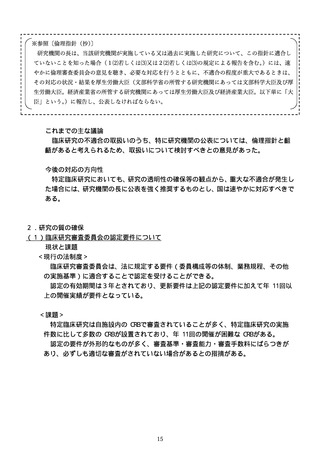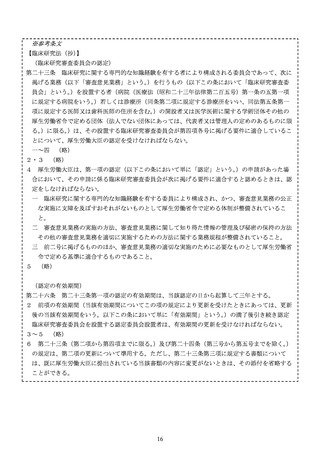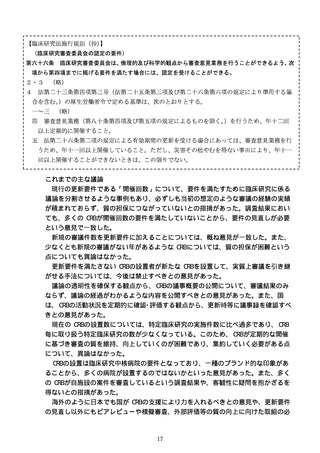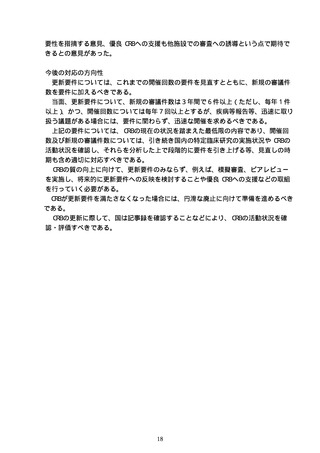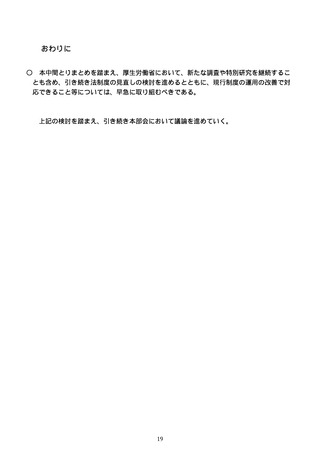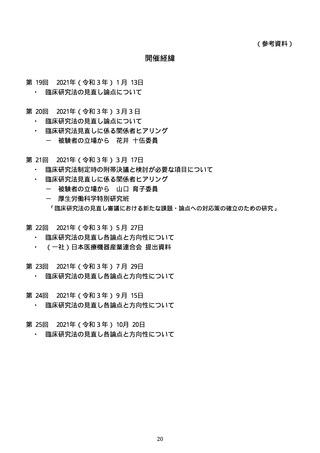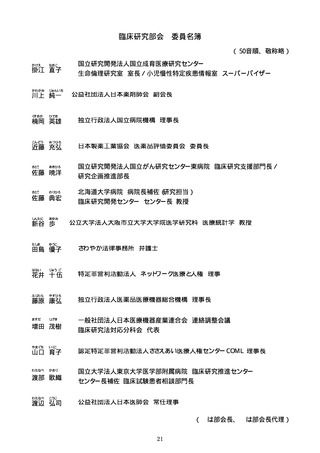よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2: 臨床研究法施行5年後の見直しに係る検討の中間取りまとめ(令和3年12月13日付け) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ
○
はじめに
平成 30 年4月1日に施行された臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号。以下「法」又は
「臨床研究法」という。)附則第2条第2項においては、法施行後5年以内に、法の施行の
状況、臨床研究を取り巻く状況の変化等を勘案し、法の規定に検討を加え、必要があると
認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。
○
このため、本部会では、令和3年1月から検討を開始し、計7回にわたって臨床研究等
の施策全般の見直しに関する議論を重ねるとともに、関係者及び関係団体からのヒアリン
グを実施した。本中間とりまとめは、これまでの検討状況について、中間的に整理を行っ
たものである。
Ⅱ
基本的な考え方
本部会では、現在の法の施行の状況や、臨床研究を取り巻く状況の変化等を踏まえ、基本
的な考え方を以下のとおり整理した。
1.臨床研究実施体制の国際整合性
○
新型コロナウイルス感染症の流行等を契機に、新しい治療法を世界同時に適用できる
ことの重要性が認識された。
○
また、革新的な治療法を世界に先駆け、かつ安全に導入するには、日本の治験・臨床
研究の実施環境についてその国際整合性を向上させて研究を推進していく必要がある。
○ このような状況を踏まえ、革新的な医薬品等の研究開発を推進するとともに、臨床研
究の信頼を確保するため、研究の法への該当性の明確化や手続の合理化等について、法
改正を含めて検討を行い、必要な見直しを順次行う。
2.研究の法への該当性の明確化
○
臨床研究法では、研究対象者の安全性の確保や臨床研究に関する資金提供等の透明性
を確保する観点から、研究対象者の生命・身体へのリスクが高い臨床研究及び製造販売業
者等から資金提供を受けて実施される臨床研究を「特定臨床研究」として位置づけ、実
施基準の遵守や実施計画の提出等を義務づけている。
○ このうちリスクが高い臨床研究の一つとして、適応外の医薬品等の使用による研究に
ついても特定臨床研究としているが、学会の診療ガイドラインに掲載されている使用法
や保険診療で使用経験がある使用法による研究を実施する場合であっても臨床研究法の
対象となることから、想定されるリスクと比べて、経済的及び事務的な負担が過大だと
の意見がある。
○ また、治療行為に介入を伴わない、いわゆる「観察研究」については、臨床研究法に
おける取扱いが明確ではなく、認定臨床研究審査委員会(以下「CRB」という。)におい
1
○
はじめに
平成 30 年4月1日に施行された臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号。以下「法」又は
「臨床研究法」という。)附則第2条第2項においては、法施行後5年以内に、法の施行の
状況、臨床研究を取り巻く状況の変化等を勘案し、法の規定に検討を加え、必要があると
認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。
○
このため、本部会では、令和3年1月から検討を開始し、計7回にわたって臨床研究等
の施策全般の見直しに関する議論を重ねるとともに、関係者及び関係団体からのヒアリン
グを実施した。本中間とりまとめは、これまでの検討状況について、中間的に整理を行っ
たものである。
Ⅱ
基本的な考え方
本部会では、現在の法の施行の状況や、臨床研究を取り巻く状況の変化等を踏まえ、基本
的な考え方を以下のとおり整理した。
1.臨床研究実施体制の国際整合性
○
新型コロナウイルス感染症の流行等を契機に、新しい治療法を世界同時に適用できる
ことの重要性が認識された。
○
また、革新的な治療法を世界に先駆け、かつ安全に導入するには、日本の治験・臨床
研究の実施環境についてその国際整合性を向上させて研究を推進していく必要がある。
○ このような状況を踏まえ、革新的な医薬品等の研究開発を推進するとともに、臨床研
究の信頼を確保するため、研究の法への該当性の明確化や手続の合理化等について、法
改正を含めて検討を行い、必要な見直しを順次行う。
2.研究の法への該当性の明確化
○
臨床研究法では、研究対象者の安全性の確保や臨床研究に関する資金提供等の透明性
を確保する観点から、研究対象者の生命・身体へのリスクが高い臨床研究及び製造販売業
者等から資金提供を受けて実施される臨床研究を「特定臨床研究」として位置づけ、実
施基準の遵守や実施計画の提出等を義務づけている。
○ このうちリスクが高い臨床研究の一つとして、適応外の医薬品等の使用による研究に
ついても特定臨床研究としているが、学会の診療ガイドラインに掲載されている使用法
や保険診療で使用経験がある使用法による研究を実施する場合であっても臨床研究法の
対象となることから、想定されるリスクと比べて、経済的及び事務的な負担が過大だと
の意見がある。
○ また、治療行為に介入を伴わない、いわゆる「観察研究」については、臨床研究法に
おける取扱いが明確ではなく、認定臨床研究審査委員会(以下「CRB」という。)におい
1