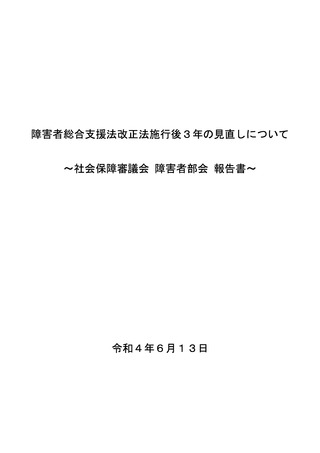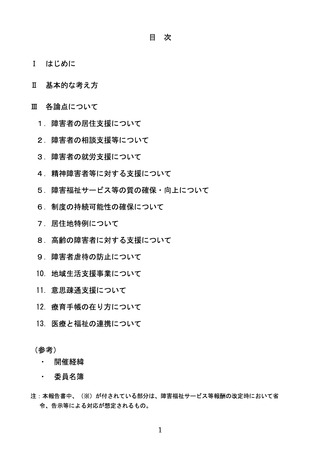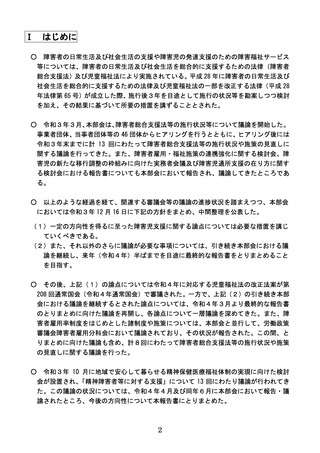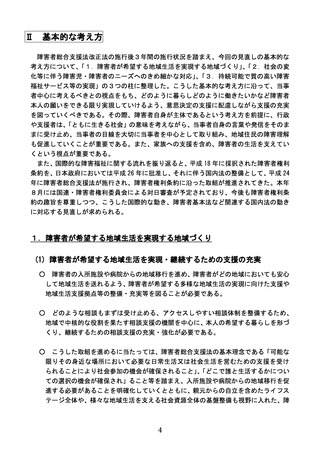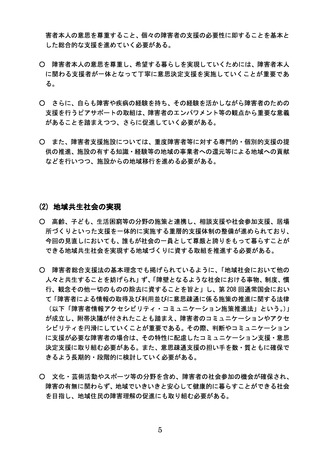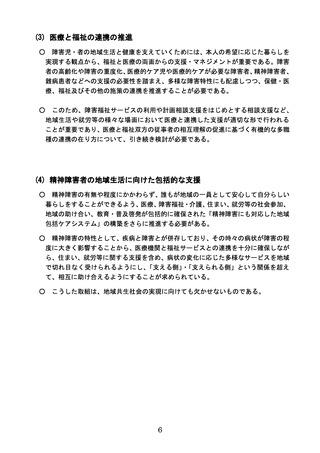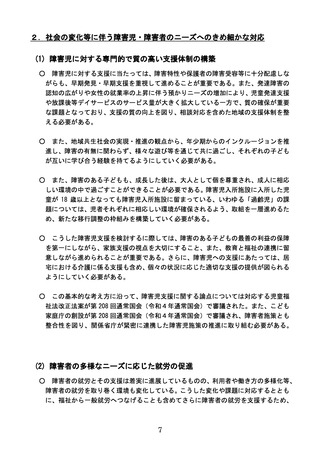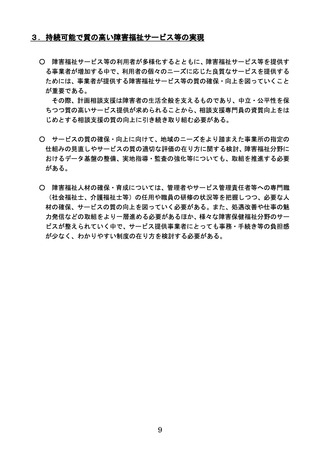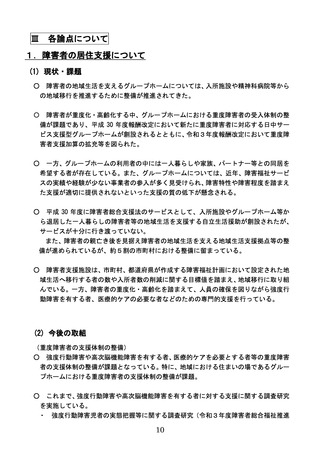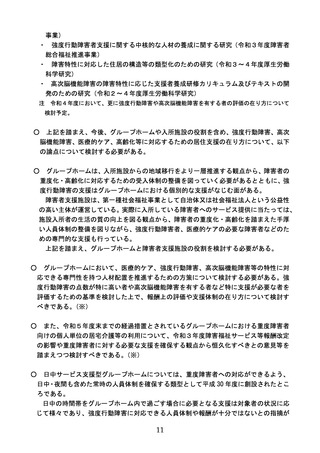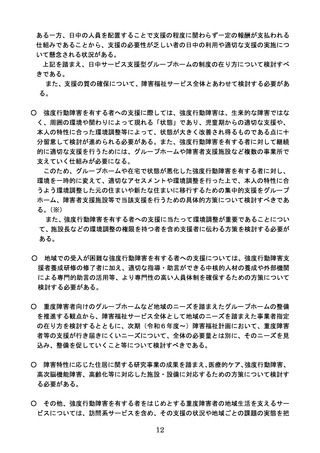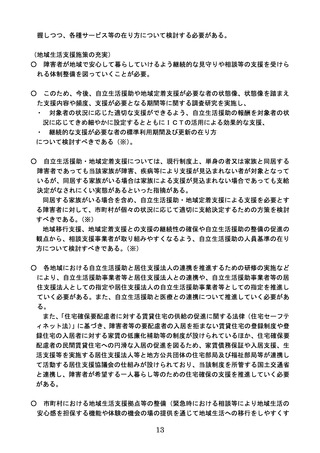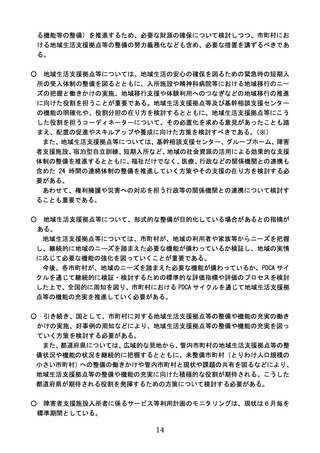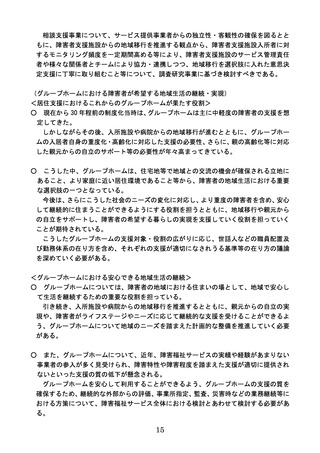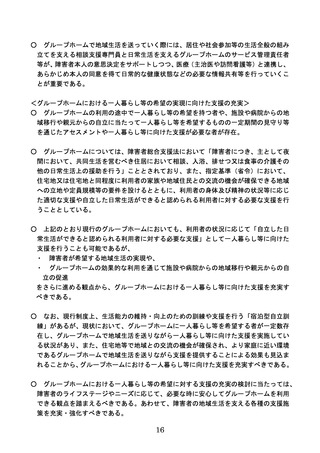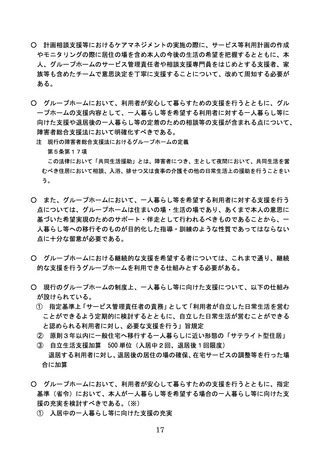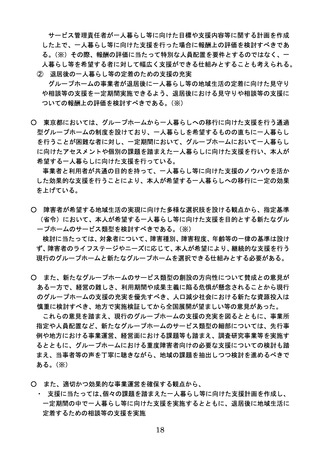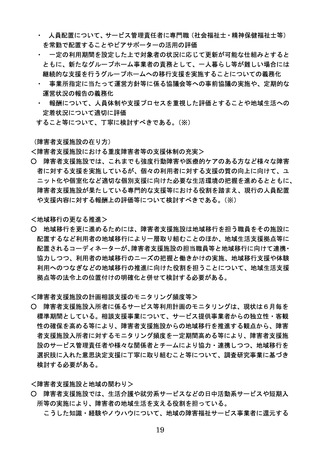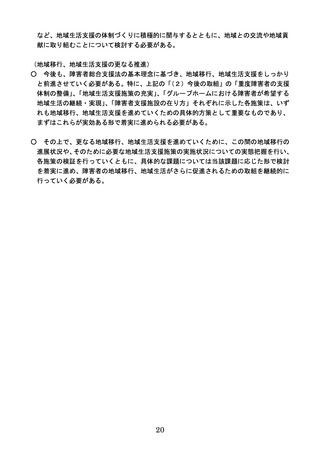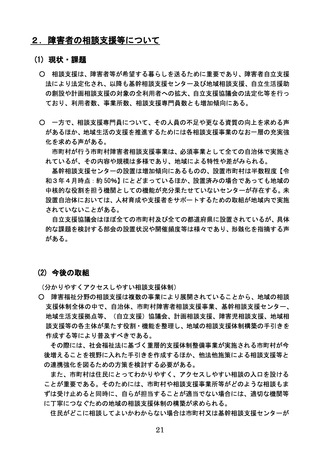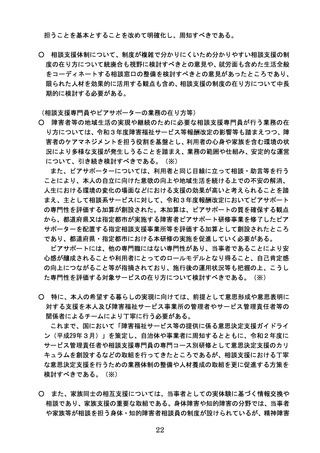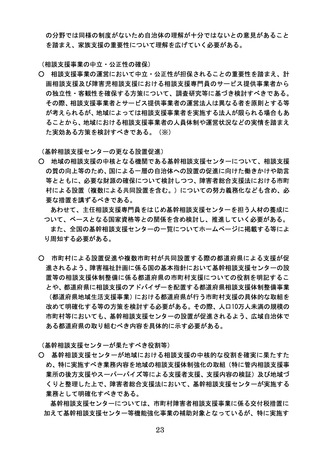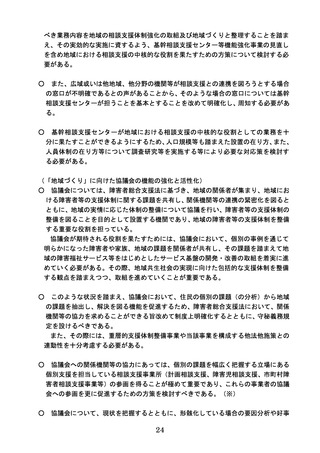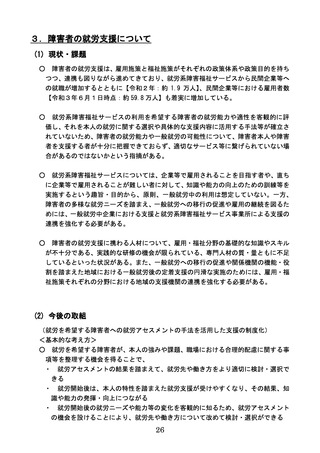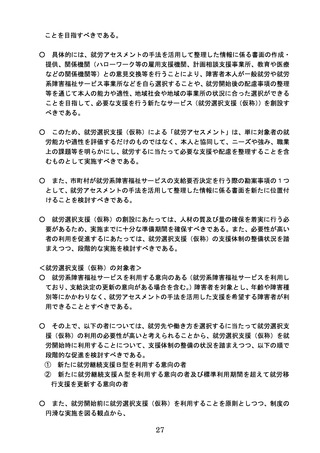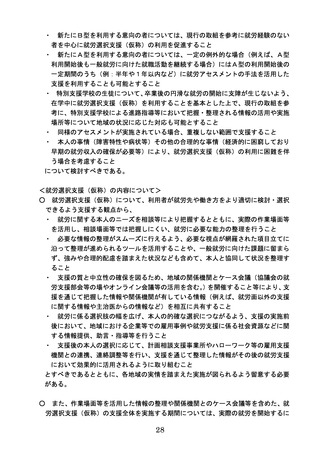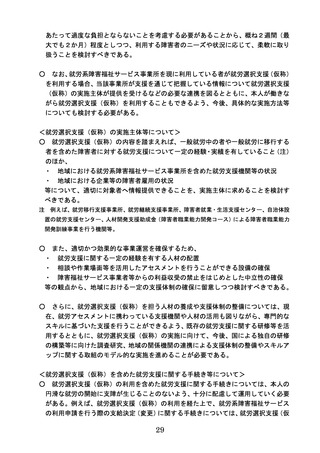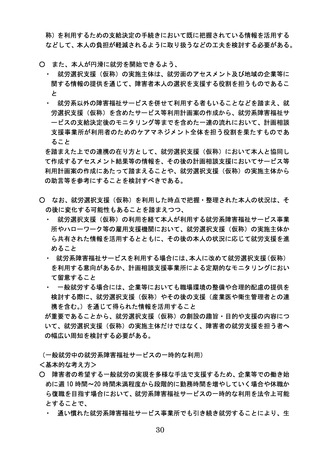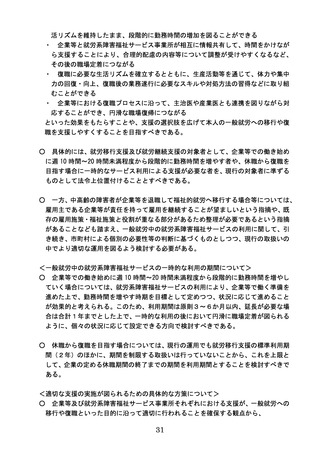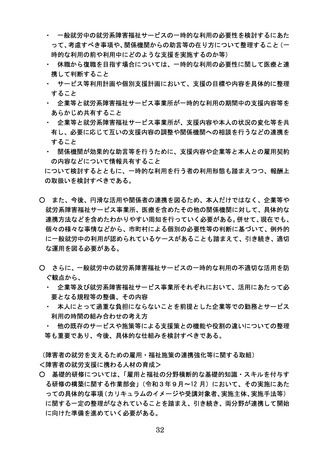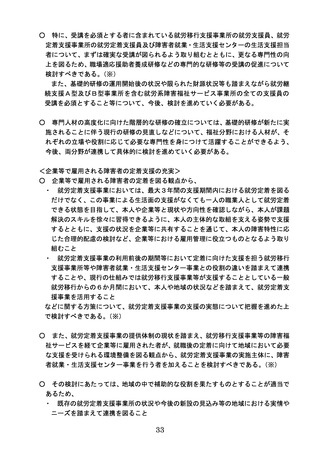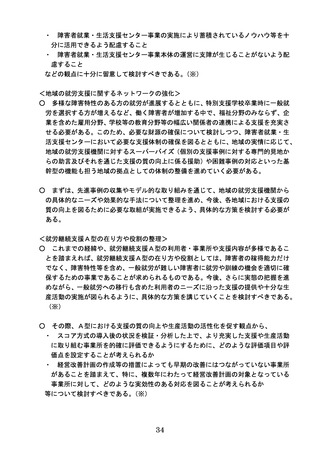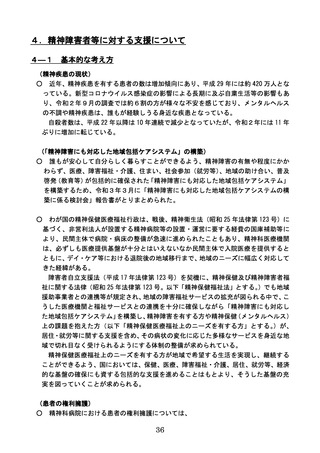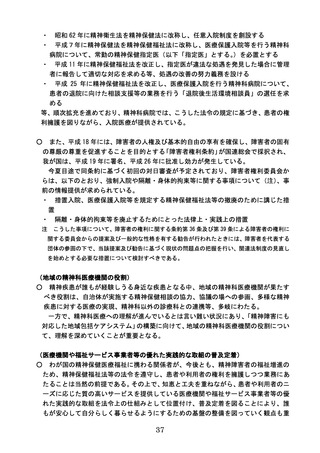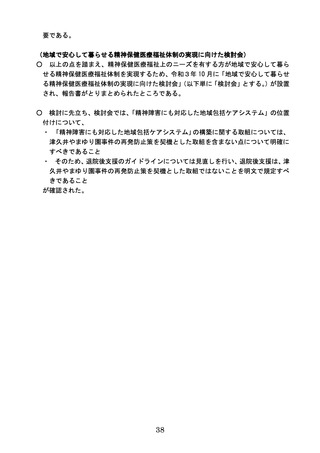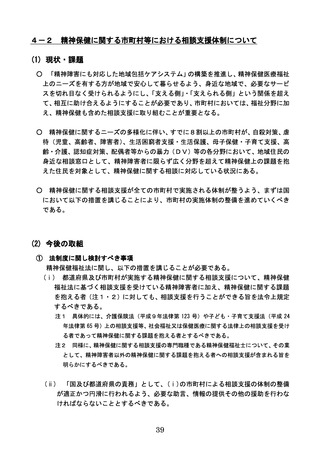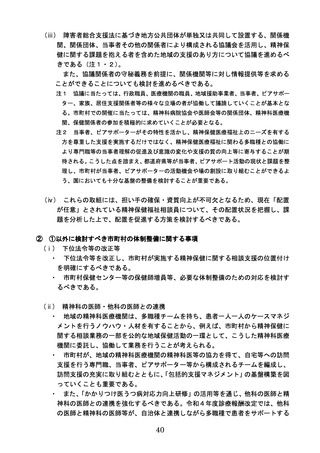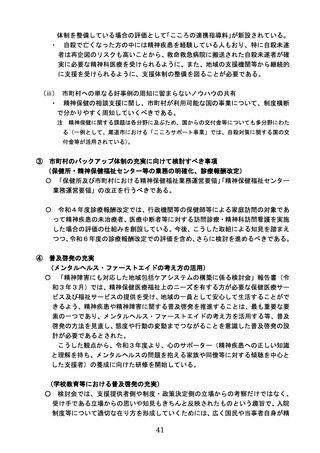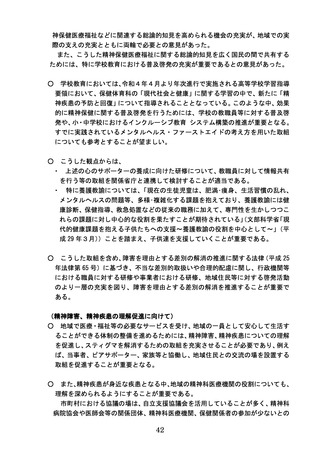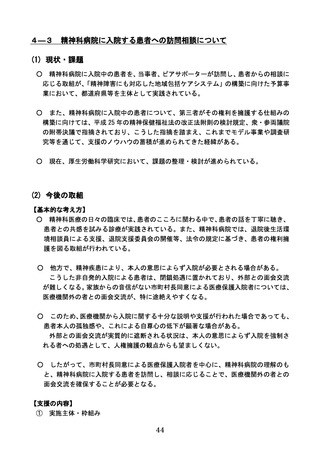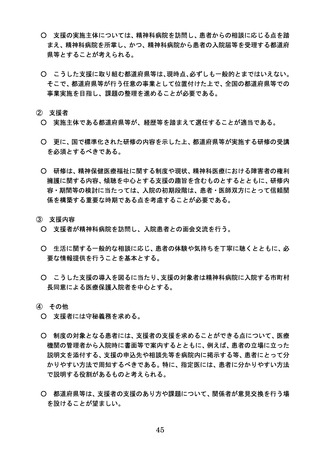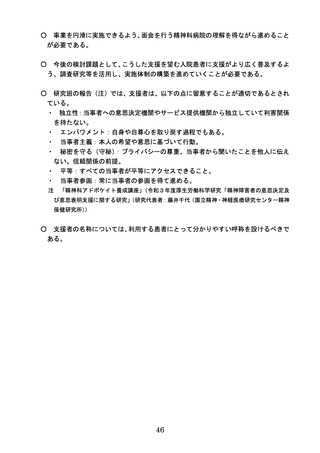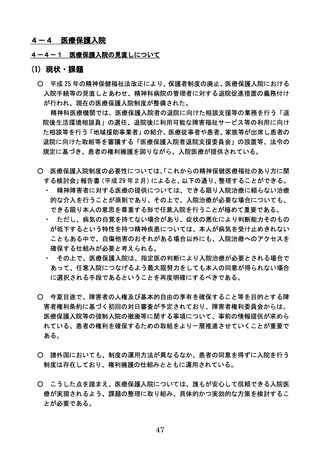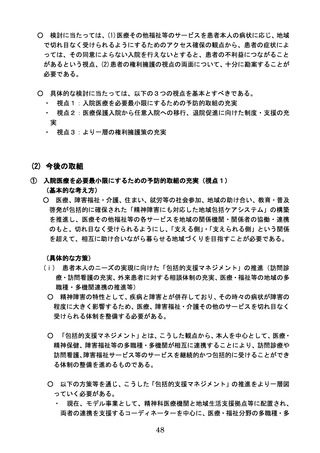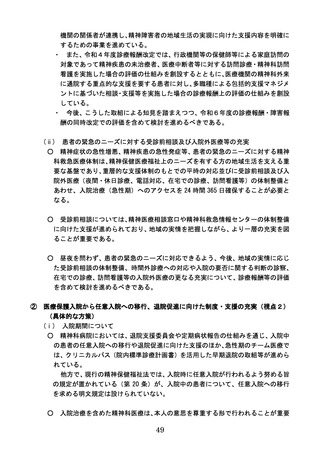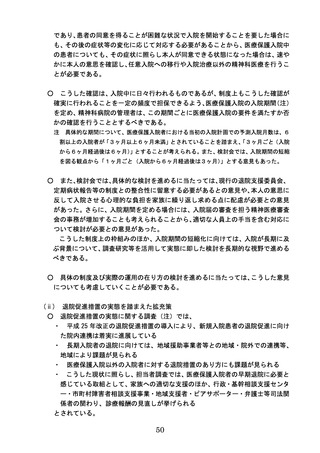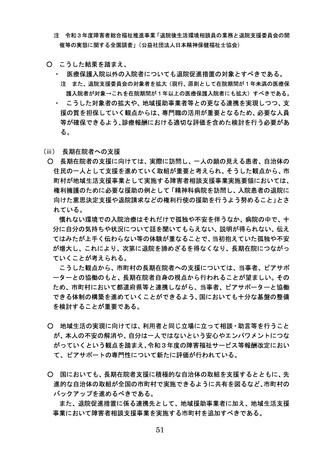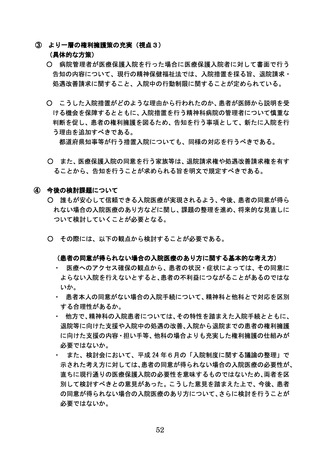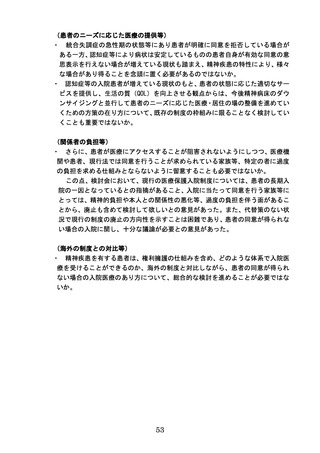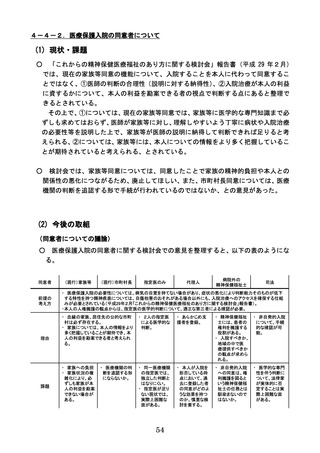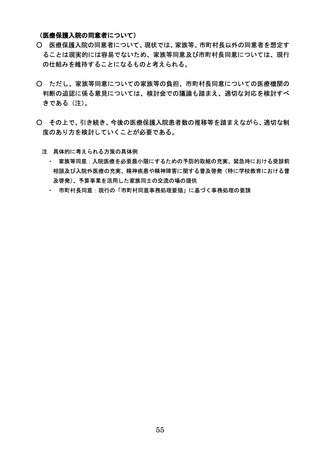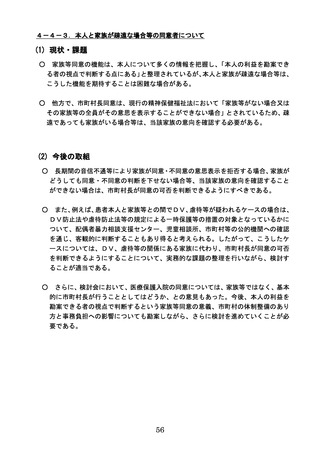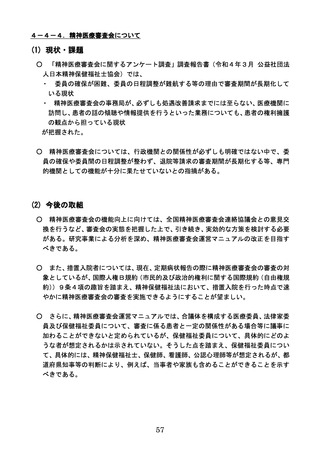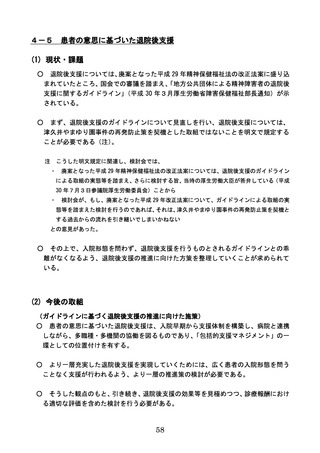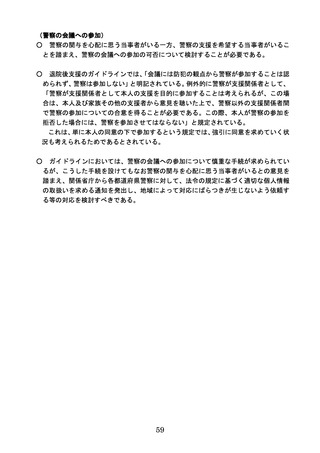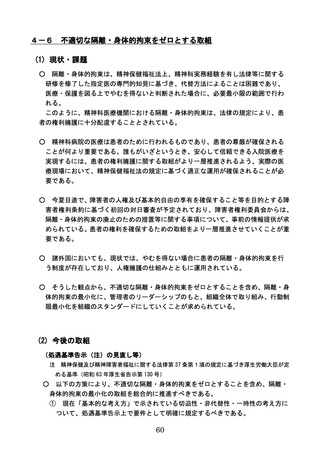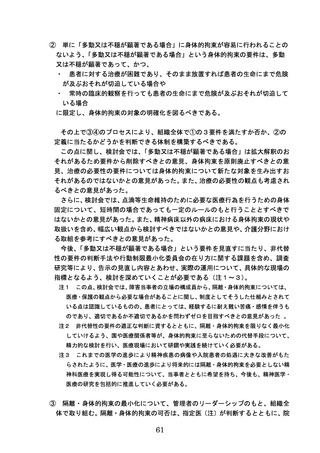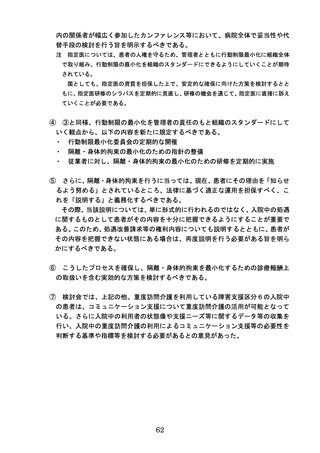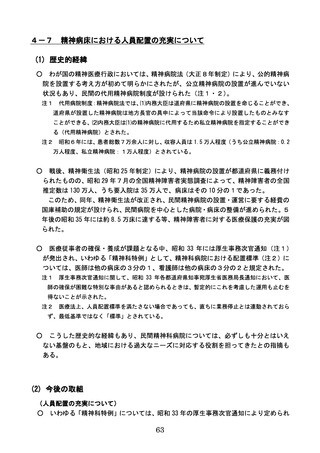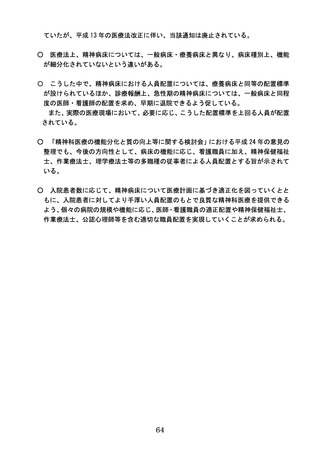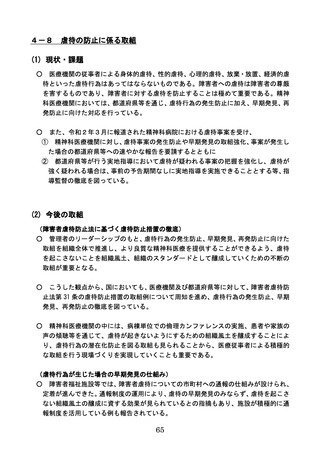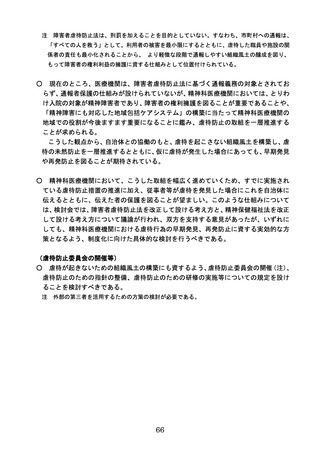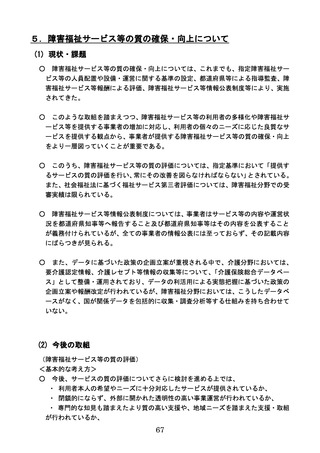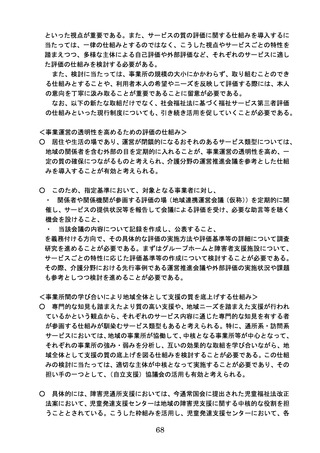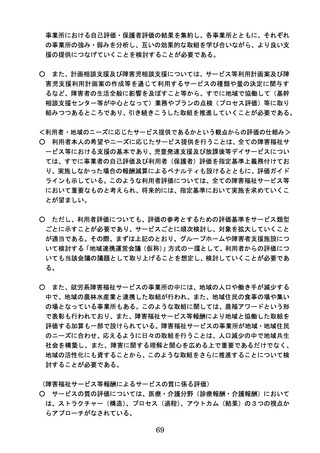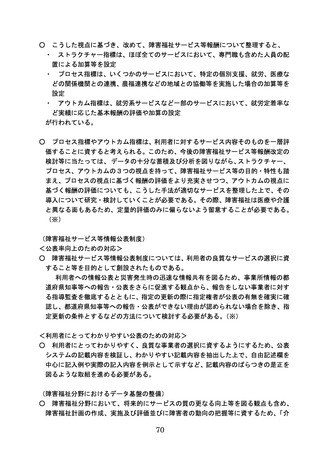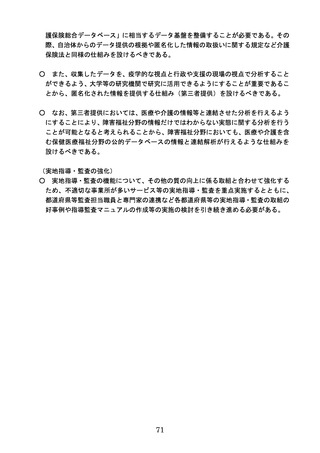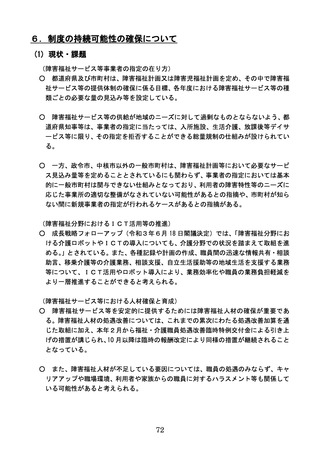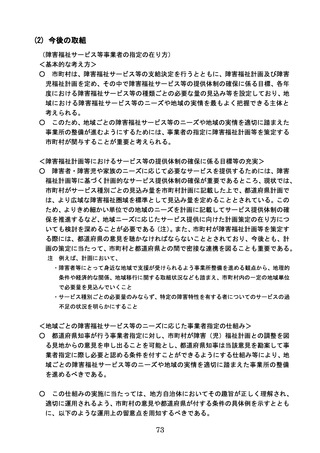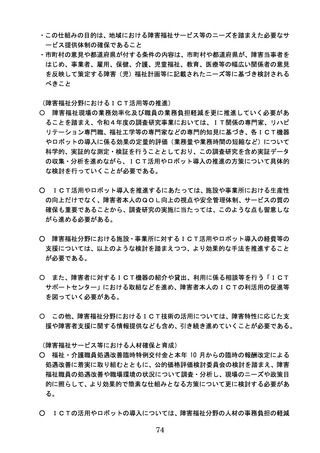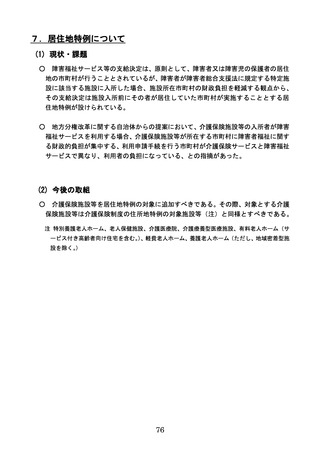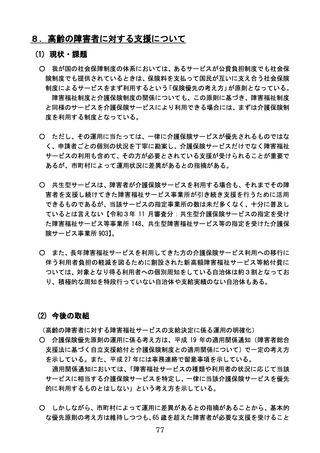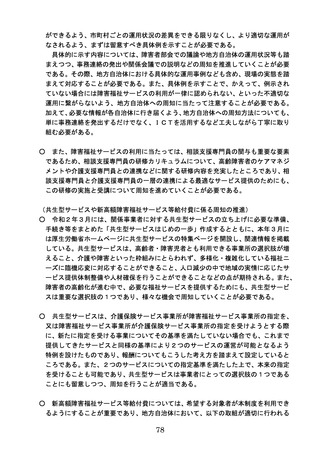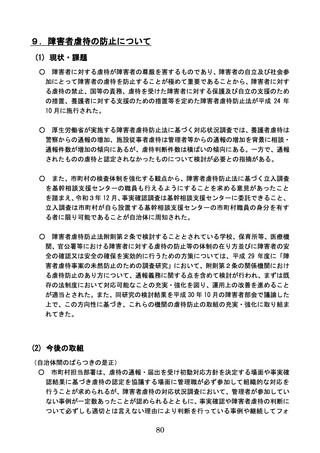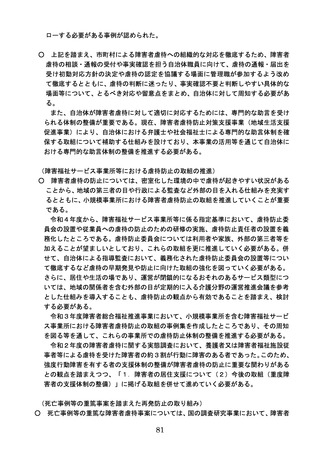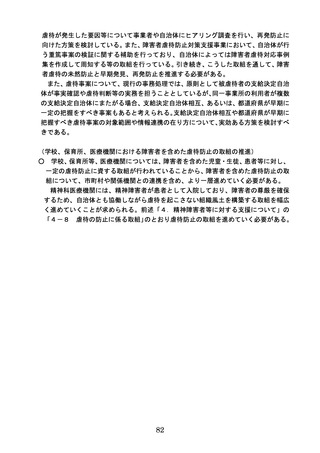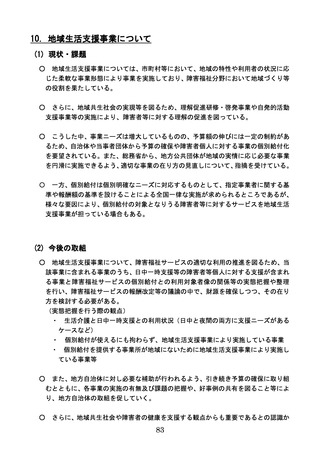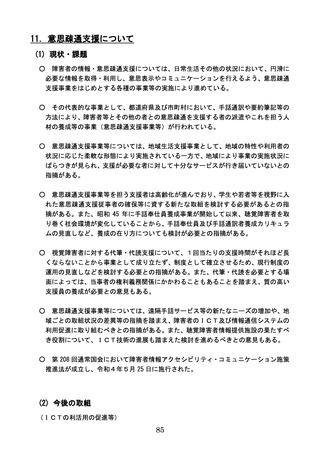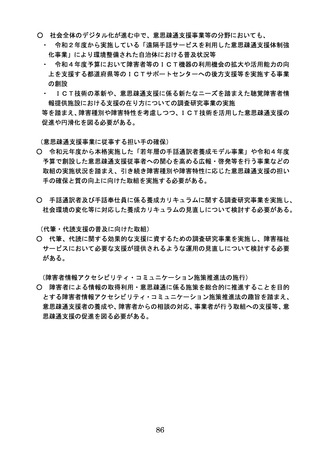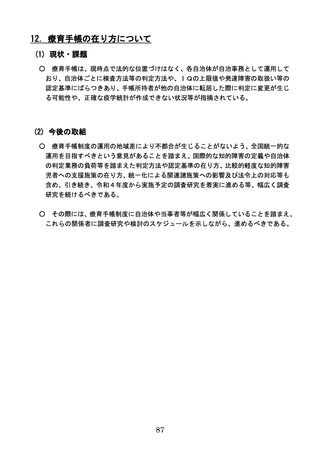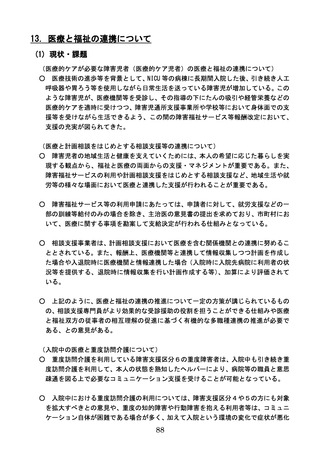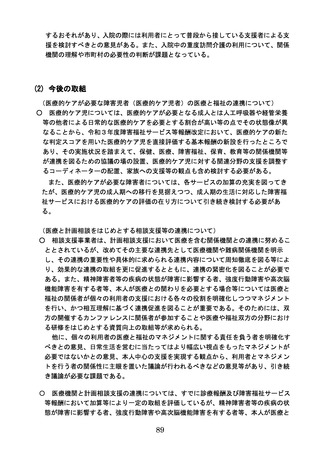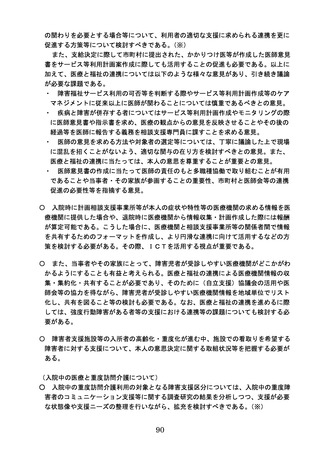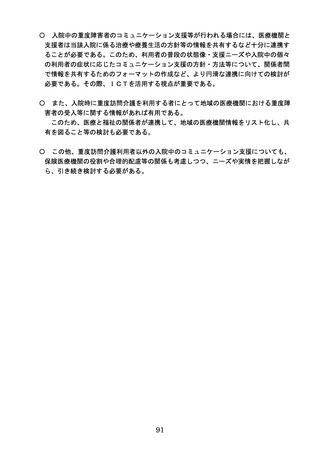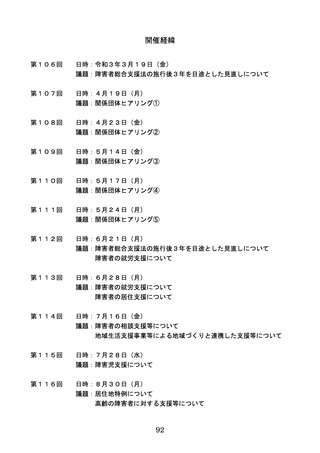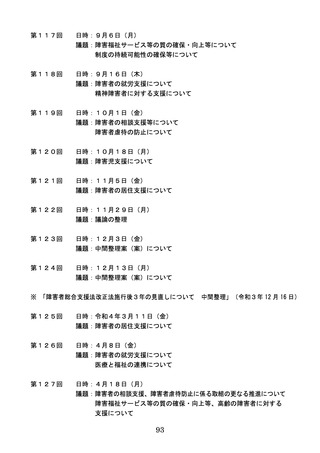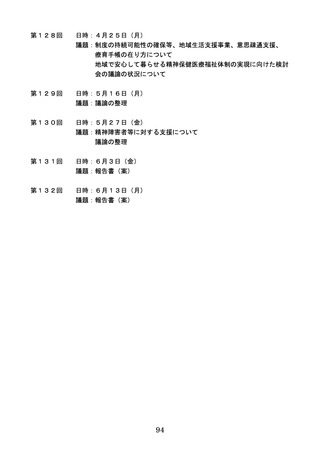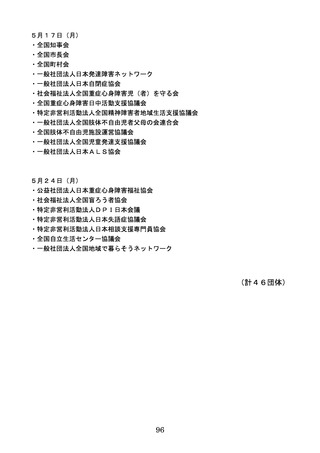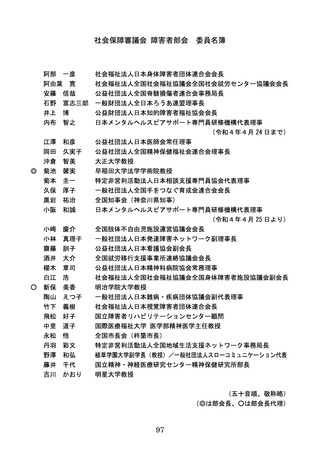よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
| 出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
あたって過度な負担とならないことを考慮する必要があることから、概ね2週間(最
大でも2か月)程度としつつ、利用する障害者のニーズや状況に応じて、柔軟に取り
扱うことを検討すべきである。
○
なお、就労系障害福祉サービス事業所を現に利用している者が就労選択支援(仮称)
を利用する場合、当該事業所が支援を通じて把握している情報について就労選択支援
(仮称)の実施主体が提供を受けるなどの必要な連携を図るとともに、本人が働きな
がら就労選択支援(仮称)を利用することもできるよう、今後、具体的な実施方法等
についても検討する必要がある。
<就労選択支援(仮称)の実施主体等について>
○ 就労選択支援(仮称)の内容を踏まえれば、一般就労中の者や一般就労に移行する
者を含めた障害者に対する就労支援について一定の経験・実績を有していること(注)
のほか、
・ 地域における就労系障害福祉サービス事業所を含めた就労支援機関等の状況
・ 地域における企業等の障害者雇用の状況
等について、適切に対象者へ情報提供できることを、実施主体に求めることを検討す
べきである。
注
例えば、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター、自治体設
置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力
開発訓練事業を行う機関等。
○ また、適切かつ効果的な事業運営を確保するため、
・ 就労支援に関する一定の経験を有する人材の配置
・ 相談や作業場面等を活用したアセスメントを行うことができる設備の確保
・ 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止をはじめとした中立性の確保
等の観点から、地域における一定の支援体制の確保に留意しつつ検討すべきである。
○
さらに、就労選択支援(仮称)を担う人材の養成や支援体制の整備については、現
在、就労アセスメントに携わっている支援機関や人材の活用も図りながら、専門的な
スキルに基づいた支援を行うことができるよう、既存の就労支援に関する研修等を活
用するとともに、就労選択支援(仮称)の実施に向けて、今後、国による独自の研修
の構築等に向けた調査研究、地域の関係機関の連携による支援体制の整備やスキルア
ップに関する取組のモデル的な実施を進めることが必要である。
<就労選択支援(仮称)を含めた就労支援に関する手続き等について>
○ 就労選択支援(仮称)の利用を含めた就労支援に関する手続きについては、本人の
円滑な就労の開始に支障が生じることのないよう、十分に配慮して運用していく必要
がある。例えば、就労選択支援(仮称)の利用を経た上で、就労系障害福祉サービス
の利用申請を行う際の支給決定(変更)に関する手続きについては、就労選択支援(仮
29
大でも2か月)程度としつつ、利用する障害者のニーズや状況に応じて、柔軟に取り
扱うことを検討すべきである。
○
なお、就労系障害福祉サービス事業所を現に利用している者が就労選択支援(仮称)
を利用する場合、当該事業所が支援を通じて把握している情報について就労選択支援
(仮称)の実施主体が提供を受けるなどの必要な連携を図るとともに、本人が働きな
がら就労選択支援(仮称)を利用することもできるよう、今後、具体的な実施方法等
についても検討する必要がある。
<就労選択支援(仮称)の実施主体等について>
○ 就労選択支援(仮称)の内容を踏まえれば、一般就労中の者や一般就労に移行する
者を含めた障害者に対する就労支援について一定の経験・実績を有していること(注)
のほか、
・ 地域における就労系障害福祉サービス事業所を含めた就労支援機関等の状況
・ 地域における企業等の障害者雇用の状況
等について、適切に対象者へ情報提供できることを、実施主体に求めることを検討す
べきである。
注
例えば、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター、自治体設
置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力
開発訓練事業を行う機関等。
○ また、適切かつ効果的な事業運営を確保するため、
・ 就労支援に関する一定の経験を有する人材の配置
・ 相談や作業場面等を活用したアセスメントを行うことができる設備の確保
・ 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止をはじめとした中立性の確保
等の観点から、地域における一定の支援体制の確保に留意しつつ検討すべきである。
○
さらに、就労選択支援(仮称)を担う人材の養成や支援体制の整備については、現
在、就労アセスメントに携わっている支援機関や人材の活用も図りながら、専門的な
スキルに基づいた支援を行うことができるよう、既存の就労支援に関する研修等を活
用するとともに、就労選択支援(仮称)の実施に向けて、今後、国による独自の研修
の構築等に向けた調査研究、地域の関係機関の連携による支援体制の整備やスキルア
ップに関する取組のモデル的な実施を進めることが必要である。
<就労選択支援(仮称)を含めた就労支援に関する手続き等について>
○ 就労選択支援(仮称)の利用を含めた就労支援に関する手続きについては、本人の
円滑な就労の開始に支障が生じることのないよう、十分に配慮して運用していく必要
がある。例えば、就労選択支援(仮称)の利用を経た上で、就労系障害福祉サービス
の利用申請を行う際の支給決定(変更)に関する手続きについては、就労選択支援(仮
29