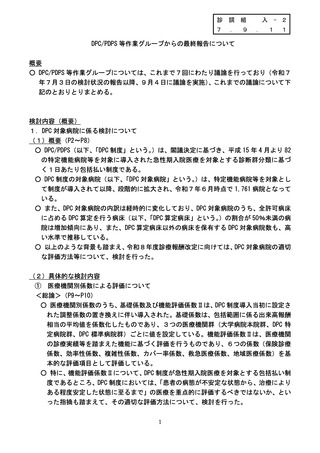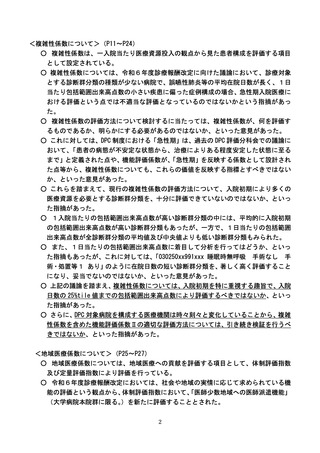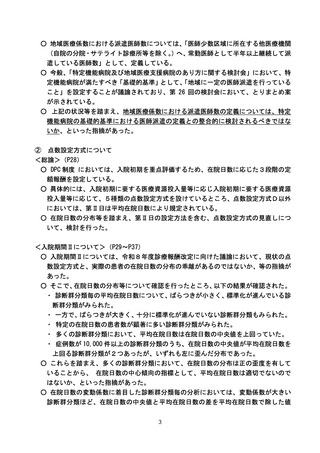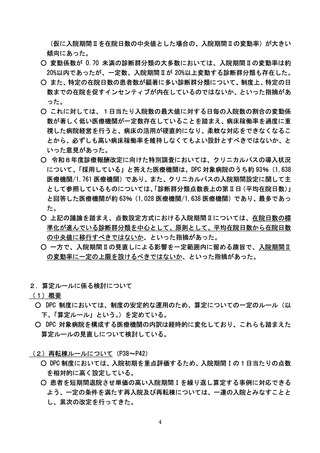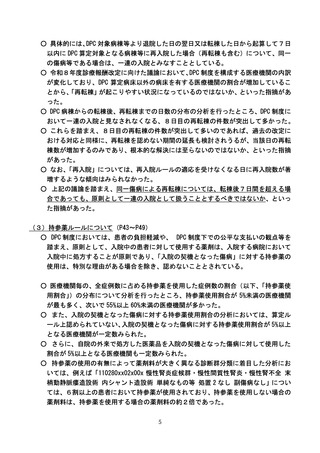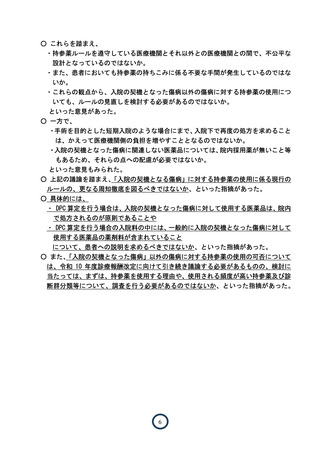よむ、つかう、まなぶ。
入ー2 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
<複雑性係数について>(P11~P24)
○ 複雑性係数は、一入院当たり医療資源投入の観点から見た患者構成を評価する項目
として設定されている。
○ 複雑性係数については、令和6年度診療報酬改定に向けた議論において、診療対象
とする診断群分類の種類が少ない病院で、誤嚥性肺炎等の平均在院日数が長く、1日
当たり包括範囲出来高点数の小さい疾患に偏った症例構成の場合、急性期入院医療に
おける評価という点では不適当な評価となっているのではないかという指摘があっ
た。
○ 複雑性係数の評価方法について検討するに当たっては、複雑性係数が、何を評価す
るものであるか、明らかにする必要があるのではないか、といった意見があった。
○ これに対しては、DPC 制度における「急性期」は、過去の DPC 評価分科会での議論に
おいて、「患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至る
まで」と定義された点や、機能評価係数が、
「急性期」を反映する係数として設計され
た点等から、複雑性係数についても、これらの価値を反映する指標とすべきではない
か、といった意見があった。
○ これらを踏まえて、現行の複雑性係数の評価方法について、入院初期により多くの
医療資源を必要とする診断群分類を、十分に評価できていないのではないか、といっ
た指摘があった。
○ 1入院当たりの包括範囲出来高点数が高い診断群分類の中には、平均的に入院初期
の包括範囲出来高点数が高い診断群分類もあったが、一方で、1日当たりの包括範囲
出来高点数が全診断群分類の平均値及び中央値よりも低い診断群分類もみられた。
○ また、1日当たりの包括範囲出来高点数に着目して分析を行ってはどうか、といっ
た指摘もあったが、これに対しては、
「030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手
術・処置等1 あり」のように在院日数の短い診断群分類を、著しく高く評価すること
になり、妥当でないのではないか、といった意見があった。
○ 上記の議論を踏まえ、複雑性係数については、入院初期を特に重視する趣旨で、入院
日数の 25%tile 値までの包括範囲出来高点数により評価するべきではないか、といっ
た指摘があった。
○ さらに、DPC 対象病院を構成する医療機関は時々刻々と変化していることから、複雑
性係数を含めた機能評価係数Ⅱの適切な評価方法については、引き続き検証を行うべ
きではないか、といった指摘があった。
<地域医療係数について>(P25~P27)
○ 地域医療係数については、地域医療への貢献を評価する項目として、体制評価指数
及び定量評価指数により評価を行っている。
○ 令和6年度診療報酬改定においては、社会や地域の実情に応じて求められている機
能の評価という観点から、体制評価指数において、
「医師少数地域への医師派遣機能」
(大学病院本院群に限る。)を新たに評価することとされた。
2
○ 複雑性係数は、一入院当たり医療資源投入の観点から見た患者構成を評価する項目
として設定されている。
○ 複雑性係数については、令和6年度診療報酬改定に向けた議論において、診療対象
とする診断群分類の種類が少ない病院で、誤嚥性肺炎等の平均在院日数が長く、1日
当たり包括範囲出来高点数の小さい疾患に偏った症例構成の場合、急性期入院医療に
おける評価という点では不適当な評価となっているのではないかという指摘があっ
た。
○ 複雑性係数の評価方法について検討するに当たっては、複雑性係数が、何を評価す
るものであるか、明らかにする必要があるのではないか、といった意見があった。
○ これに対しては、DPC 制度における「急性期」は、過去の DPC 評価分科会での議論に
おいて、「患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至る
まで」と定義された点や、機能評価係数が、
「急性期」を反映する係数として設計され
た点等から、複雑性係数についても、これらの価値を反映する指標とすべきではない
か、といった意見があった。
○ これらを踏まえて、現行の複雑性係数の評価方法について、入院初期により多くの
医療資源を必要とする診断群分類を、十分に評価できていないのではないか、といっ
た指摘があった。
○ 1入院当たりの包括範囲出来高点数が高い診断群分類の中には、平均的に入院初期
の包括範囲出来高点数が高い診断群分類もあったが、一方で、1日当たりの包括範囲
出来高点数が全診断群分類の平均値及び中央値よりも低い診断群分類もみられた。
○ また、1日当たりの包括範囲出来高点数に着目して分析を行ってはどうか、といっ
た指摘もあったが、これに対しては、
「030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手
術・処置等1 あり」のように在院日数の短い診断群分類を、著しく高く評価すること
になり、妥当でないのではないか、といった意見があった。
○ 上記の議論を踏まえ、複雑性係数については、入院初期を特に重視する趣旨で、入院
日数の 25%tile 値までの包括範囲出来高点数により評価するべきではないか、といっ
た指摘があった。
○ さらに、DPC 対象病院を構成する医療機関は時々刻々と変化していることから、複雑
性係数を含めた機能評価係数Ⅱの適切な評価方法については、引き続き検証を行うべ
きではないか、といった指摘があった。
<地域医療係数について>(P25~P27)
○ 地域医療係数については、地域医療への貢献を評価する項目として、体制評価指数
及び定量評価指数により評価を行っている。
○ 令和6年度診療報酬改定においては、社会や地域の実情に応じて求められている機
能の評価という観点から、体制評価指数において、
「医師少数地域への医師派遣機能」
(大学病院本院群に限る。)を新たに評価することとされた。
2