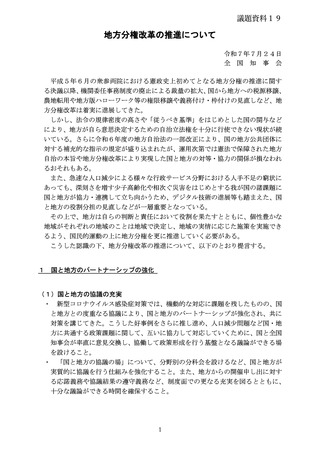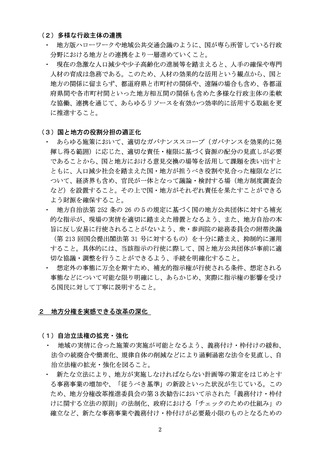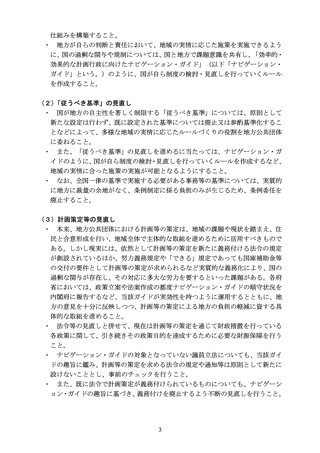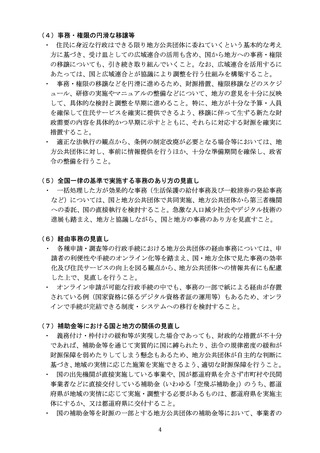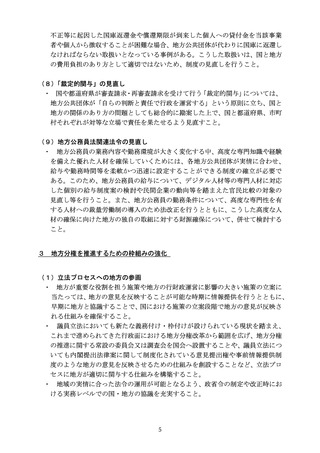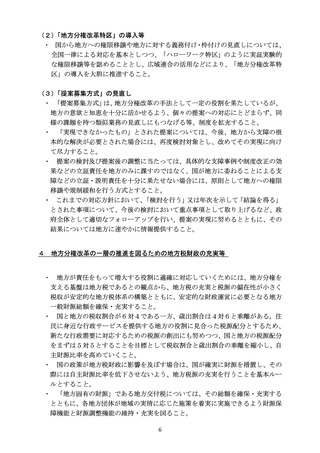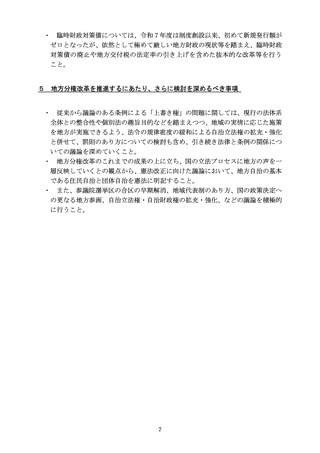よむ、つかう、まなぶ。
【議題(19)資料19】地方分権改革の推進について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)多様な行政主体の連携
・ 地方版ハローワークや地域公共交通会議のように、国が専ら所管している行政
分野における地方との連携をより一層進めていくこと。
・ 現在の急激な人口減少や少子高齢化の進展等を踏まえると、人手の確保や専門
人材の育成は急務である。このため、人材の効果的な活用という観点から、国と
地方の関係に留まらず、都道府県と市町村の関係や、遠隔の場合も含め、各都道
府県間や各市町村間といった地方相互間の関係も含めた多様な行政主体の柔軟
な協働、連携を通じて、あらゆるリソースを有効かつ効率的に活用する取組を更
に推進すること。
(3)国と地方の役割分担の適正化
・ あらゆる施策において、適切なガバナンススコープ(ガバナンスを効果的に発
揮し得る範囲)に応じた、適切な責任・権限に基づく資源の配分の見直しが必要
であることから、国と地方における意見交換の場等を活用して課題を洗い出すと
ともに、人口減少社会を踏まえた国・地方が担うべき役割や見合った権限などに
ついて、経済界も含め、官民が一体となって議論・検討する場(地方制度調査会
など)を設置すること。その上で国・地方がそれぞれ責任を果たすことができる
よう財源を確保すること。
・ 地方自治法第 252 条の 26 の5の規定に基づく国の地方公共団体に対する補充
的な指示が、現場の実情を適切に踏まえた措置となるよう、また、地方自治の本
旨に反し安易に行使されることがないよう、衆・参両院の総務委員会の附帯決議
(第 213 回国会提出閣法第 31 号に対するもの)を十分に踏まえ、抑制的に運用
すること。具体的には、当該指示の行使に際して、国と地方公共団体が事前に適
切な協議・調整を行うことができるよう、手続を明確化すること。
・ 想定外の事態に万全を期すため、補充的指示権が行使される条件、想定される
事態などについて可能な限り明確にし、あらかじめ、実際に指示権の影響を受け
る国民に対して丁寧に説明すること。
2
地方分権を実感できる改革の深化
(1)自治立法権の拡充・強化
・ 地域の実情に合った施策の実施が可能となるよう、義務付け・枠付けの緩和、
法令の統廃合や簡素化、規律自体の削減などにより過剰過密な法令を見直し、自
治立法権の拡充・強化を図ること。
・ 新たな立法により、地方が実施しなければならない計画等の策定をはじめとす
る事務事業の増加や、「従うべき基準」の新設といった状況が生じている。この
ため、地方分権改革推進委員会の第3次勧告において示された「義務付け・枠付
けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェックのための仕組み」の
確立など、新たな事務事業や義務付け・枠付けが必要最小限のものとなるための
2
・ 地方版ハローワークや地域公共交通会議のように、国が専ら所管している行政
分野における地方との連携をより一層進めていくこと。
・ 現在の急激な人口減少や少子高齢化の進展等を踏まえると、人手の確保や専門
人材の育成は急務である。このため、人材の効果的な活用という観点から、国と
地方の関係に留まらず、都道府県と市町村の関係や、遠隔の場合も含め、各都道
府県間や各市町村間といった地方相互間の関係も含めた多様な行政主体の柔軟
な協働、連携を通じて、あらゆるリソースを有効かつ効率的に活用する取組を更
に推進すること。
(3)国と地方の役割分担の適正化
・ あらゆる施策において、適切なガバナンススコープ(ガバナンスを効果的に発
揮し得る範囲)に応じた、適切な責任・権限に基づく資源の配分の見直しが必要
であることから、国と地方における意見交換の場等を活用して課題を洗い出すと
ともに、人口減少社会を踏まえた国・地方が担うべき役割や見合った権限などに
ついて、経済界も含め、官民が一体となって議論・検討する場(地方制度調査会
など)を設置すること。その上で国・地方がそれぞれ責任を果たすことができる
よう財源を確保すること。
・ 地方自治法第 252 条の 26 の5の規定に基づく国の地方公共団体に対する補充
的な指示が、現場の実情を適切に踏まえた措置となるよう、また、地方自治の本
旨に反し安易に行使されることがないよう、衆・参両院の総務委員会の附帯決議
(第 213 回国会提出閣法第 31 号に対するもの)を十分に踏まえ、抑制的に運用
すること。具体的には、当該指示の行使に際して、国と地方公共団体が事前に適
切な協議・調整を行うことができるよう、手続を明確化すること。
・ 想定外の事態に万全を期すため、補充的指示権が行使される条件、想定される
事態などについて可能な限り明確にし、あらかじめ、実際に指示権の影響を受け
る国民に対して丁寧に説明すること。
2
地方分権を実感できる改革の深化
(1)自治立法権の拡充・強化
・ 地域の実情に合った施策の実施が可能となるよう、義務付け・枠付けの緩和、
法令の統廃合や簡素化、規律自体の削減などにより過剰過密な法令を見直し、自
治立法権の拡充・強化を図ること。
・ 新たな立法により、地方が実施しなければならない計画等の策定をはじめとす
る事務事業の増加や、「従うべき基準」の新設といった状況が生じている。この
ため、地方分権改革推進委員会の第3次勧告において示された「義務付け・枠付
けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェックのための仕組み」の
確立など、新たな事務事業や義務付け・枠付けが必要最小限のものとなるための
2