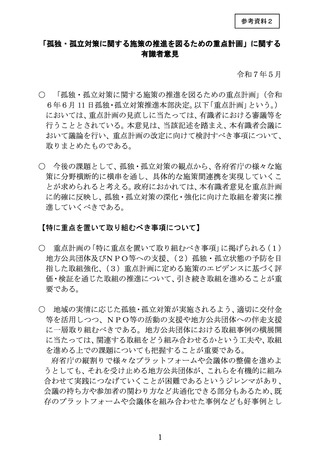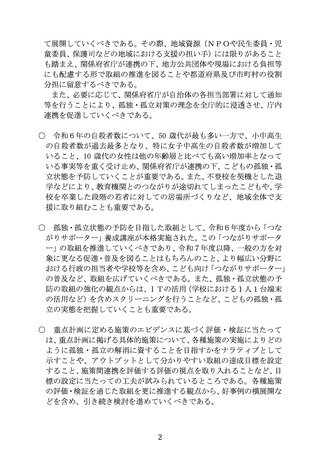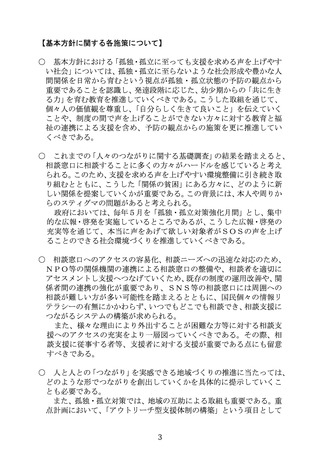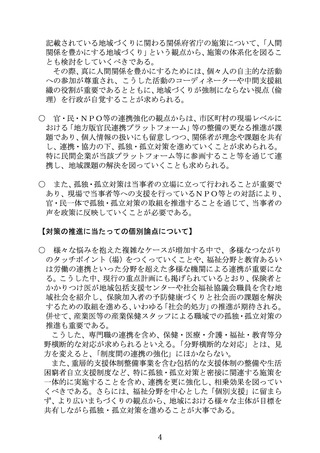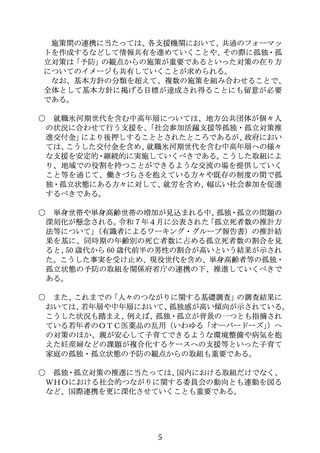よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2:孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議における意見 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
| 出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
記載されている地域づくりに関わる関係府省庁の施策について、
「人間
関係を豊かにする地域づくり」という観点から、施策の体系化を図るこ
とも検討をしていくべきである。
その際、真に人間関係を豊かにするためには、個々人の自主的な活動
への参加が尊重され、こうした活動のコーディネーターや中間支援組
織の役割が重要であるとともに、地域づくりが強制にならない視点(倫
理)を行政が自覚することが求められる。
○
官・民・NPO等の連携強化の観点からは、市区町村の現場レベルに
おける「地方版官民連携プラットフォーム」等の整備の更なる推進が課
題であり、個人情報の扱いにも留意しつつ、関係者が理念や課題を共有
し、連携・協力の下、孤独・孤立対策を進めていくことが求められる。
特に民間企業が当該プラットフォーム等に参画すること等を通じて連
携し、地域課題の解決を図っていくことも求められる。
〇
また、孤独・孤立対策は当事者の立場に立って行われることが重要で
あり、現場で当事者等への支援を行っているNPO等との対話により、
官・民一体で孤独・孤立対策の取組を推進することを通じて、当事者の
声を政策に反映していくことが必要である。
【対策の推進に当たっての個別論点について】
○
様々な悩みを抱えた複雑なケースが増加する中で、多様なつながり
のタッチポイント(場)をつくっていくことや、福祉分野と教育あるい
は労働の連携といった分野を超えた多様な機関による連携が重要にな
る。こうした中、現行の重点計画にも掲げられているとおり、保険者と
かかりつけ医が地域包括支援センターや社会福祉協議会職員を含む地
域社会を紹介し、保険加入者の予防健康づくりと社会面の課題を解決
するための取組を進める、いわゆる「社会的処方」の推進が期待される。
併せて、産業医等の産業保健スタッフによる職域での孤独・孤立対策の
推進も重要である。
こうした、専門職の連携を含め、保健・医療・介護・福祉・教育等分
野横断的な対応が求められるといえる。
「分野横断的な対応」とは、見
方を変えると、「制度間の連携の強化」にほかならない。
また、重層的支援体制整備事業を含む包括的な支援体制の整備や生活
困窮者自立支援制度など、特に孤独・孤立対策と密接に関連する施策を
一体的に実施することを含め、連携を更に強化し、相乗効果を図ってい
くべきである。さらには、福祉分野を中心とした「個別支援」に留まら
ず、より広いまちづくりの観点から、地域における様々な主体が目標を
共有しながら孤独・孤立対策を進めることが大事である。
4
「人間
関係を豊かにする地域づくり」という観点から、施策の体系化を図るこ
とも検討をしていくべきである。
その際、真に人間関係を豊かにするためには、個々人の自主的な活動
への参加が尊重され、こうした活動のコーディネーターや中間支援組
織の役割が重要であるとともに、地域づくりが強制にならない視点(倫
理)を行政が自覚することが求められる。
○
官・民・NPO等の連携強化の観点からは、市区町村の現場レベルに
おける「地方版官民連携プラットフォーム」等の整備の更なる推進が課
題であり、個人情報の扱いにも留意しつつ、関係者が理念や課題を共有
し、連携・協力の下、孤独・孤立対策を進めていくことが求められる。
特に民間企業が当該プラットフォーム等に参画すること等を通じて連
携し、地域課題の解決を図っていくことも求められる。
〇
また、孤独・孤立対策は当事者の立場に立って行われることが重要で
あり、現場で当事者等への支援を行っているNPO等との対話により、
官・民一体で孤独・孤立対策の取組を推進することを通じて、当事者の
声を政策に反映していくことが必要である。
【対策の推進に当たっての個別論点について】
○
様々な悩みを抱えた複雑なケースが増加する中で、多様なつながり
のタッチポイント(場)をつくっていくことや、福祉分野と教育あるい
は労働の連携といった分野を超えた多様な機関による連携が重要にな
る。こうした中、現行の重点計画にも掲げられているとおり、保険者と
かかりつけ医が地域包括支援センターや社会福祉協議会職員を含む地
域社会を紹介し、保険加入者の予防健康づくりと社会面の課題を解決
するための取組を進める、いわゆる「社会的処方」の推進が期待される。
併せて、産業医等の産業保健スタッフによる職域での孤独・孤立対策の
推進も重要である。
こうした、専門職の連携を含め、保健・医療・介護・福祉・教育等分
野横断的な対応が求められるといえる。
「分野横断的な対応」とは、見
方を変えると、「制度間の連携の強化」にほかならない。
また、重層的支援体制整備事業を含む包括的な支援体制の整備や生活
困窮者自立支援制度など、特に孤独・孤立対策と密接に関連する施策を
一体的に実施することを含め、連携を更に強化し、相乗効果を図ってい
くべきである。さらには、福祉分野を中心とした「個別支援」に留まら
ず、より広いまちづくりの観点から、地域における様々な主体が目標を
共有しながら孤独・孤立対策を進めることが大事である。
4