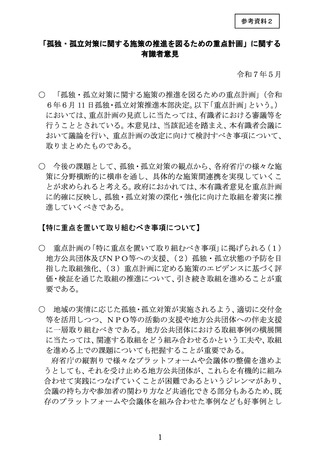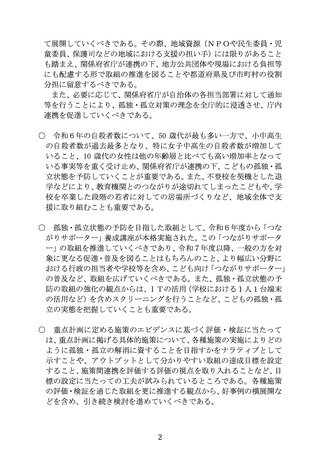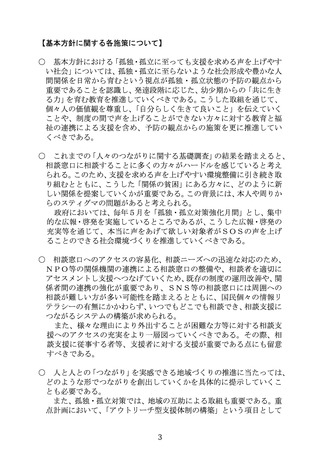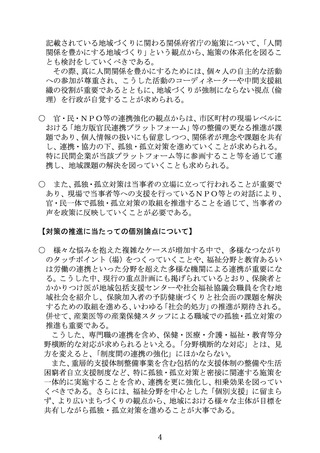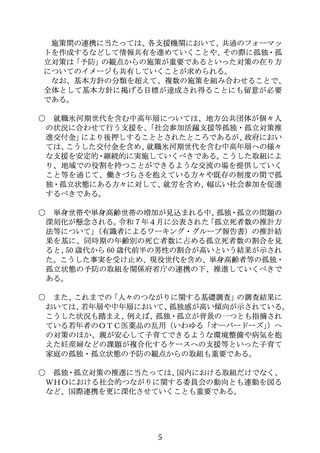よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2:孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議における意見 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
| 出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て展開していくべきである。その際、地域資源(NPOや民生委員・児
童委員、保護司などの地域における支援の担い手)には限りがあること
も踏まえ、関係府省庁が連携の下、地方公共団体や現場における負担等
にも配慮する形で取組の推進を図ることや都道府県及び市町村の役割
分担に留意するべきである。
また、必要に応じて、関係府省庁が自治体の各担当部署に対して通知
等を行うことにより、孤独・孤立対策の理念を全庁的に浸透させ、庁内
連携を促進していくべきである。
○ 令和6年の自殺者数について、50 歳代が最も多い一方で、小中高生
の自殺者数が過去最多となり、特に女子中高生の自殺者数が増加して
いること、10 歳代の女性は他の年齢層と比べても高い増加率となって
いる事実等を重く受け止め、関係府省庁が連携の下、こどもの孤独・孤
立状態を予防していくことが重要である。また、不登校を契機とした退
学などにより、教育機関とのつながりが途切れてしまったこどもや、学
校を卒業した段階の若者に対しての居場所づくりなど、地域全体で支
援に取り組むことも重要である。
○ 孤独・孤立状態の予防を目指した取組として、令和6年度から「つな
がりサポーター」養成講座が本格実施された。この「つながりサポータ
ー」の取組を推進していくべきであり、令和7年度以降、一般の方を対
象に更なる促進・普及を図ることはもちろんのこと、より幅広い分野に
おける行政の担当者や学校等を含め、こども向け「つながりサポーター」
の普及など、取組を広げていくべきである。また、孤独・孤立状態の予
防の取組の強化の観点からは、ITの活用(学校における1人1台端末
の活用など)を含めスクリーニングを行うことなど、こどもの孤独・孤
立の実態を把握していくことも重要である。
○
重点計画に定める施策のエビデンスに基づく評価・検証に当たって
は、重点計画に掲げる具体的施策について、各種施策の実施によりどの
ように孤独・孤立の解消に資することを目指すかをナラティブとして
示すことや、アウトプットとして分かりやすい取組の達成目標を設定
すること、施策間連携を評価する評価の視点を取り入れることなど、目
標の設定に当たっての工夫が試みられているところである。各種施策
の評価・検証を通じた取組を更に推進する観点から、好事例の横展開な
どを含め、引き続き検討を進めていくべきである。
2
童委員、保護司などの地域における支援の担い手)には限りがあること
も踏まえ、関係府省庁が連携の下、地方公共団体や現場における負担等
にも配慮する形で取組の推進を図ることや都道府県及び市町村の役割
分担に留意するべきである。
また、必要に応じて、関係府省庁が自治体の各担当部署に対して通知
等を行うことにより、孤独・孤立対策の理念を全庁的に浸透させ、庁内
連携を促進していくべきである。
○ 令和6年の自殺者数について、50 歳代が最も多い一方で、小中高生
の自殺者数が過去最多となり、特に女子中高生の自殺者数が増加して
いること、10 歳代の女性は他の年齢層と比べても高い増加率となって
いる事実等を重く受け止め、関係府省庁が連携の下、こどもの孤独・孤
立状態を予防していくことが重要である。また、不登校を契機とした退
学などにより、教育機関とのつながりが途切れてしまったこどもや、学
校を卒業した段階の若者に対しての居場所づくりなど、地域全体で支
援に取り組むことも重要である。
○ 孤独・孤立状態の予防を目指した取組として、令和6年度から「つな
がりサポーター」養成講座が本格実施された。この「つながりサポータ
ー」の取組を推進していくべきであり、令和7年度以降、一般の方を対
象に更なる促進・普及を図ることはもちろんのこと、より幅広い分野に
おける行政の担当者や学校等を含め、こども向け「つながりサポーター」
の普及など、取組を広げていくべきである。また、孤独・孤立状態の予
防の取組の強化の観点からは、ITの活用(学校における1人1台端末
の活用など)を含めスクリーニングを行うことなど、こどもの孤独・孤
立の実態を把握していくことも重要である。
○
重点計画に定める施策のエビデンスに基づく評価・検証に当たって
は、重点計画に掲げる具体的施策について、各種施策の実施によりどの
ように孤独・孤立の解消に資することを目指すかをナラティブとして
示すことや、アウトプットとして分かりやすい取組の達成目標を設定
すること、施策間連携を評価する評価の視点を取り入れることなど、目
標の設定に当たっての工夫が試みられているところである。各種施策
の評価・検証を通じた取組を更に推進する観点から、好事例の横展開な
どを含め、引き続き検討を進めていくべきである。
2