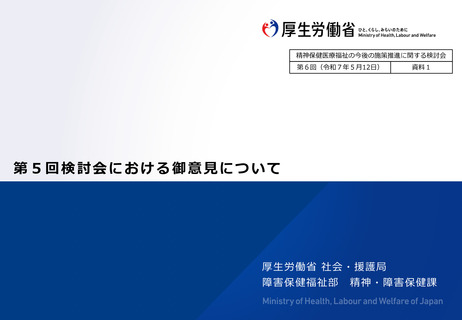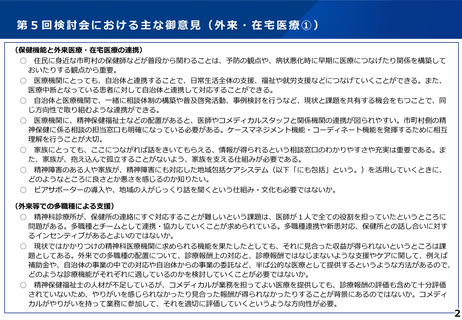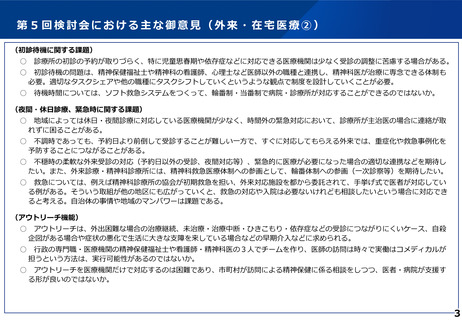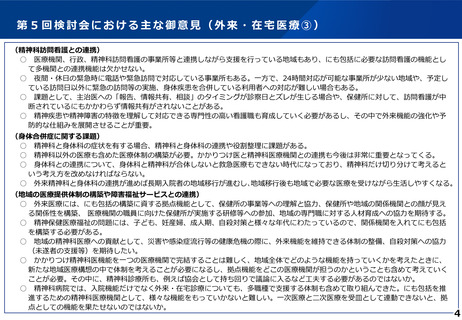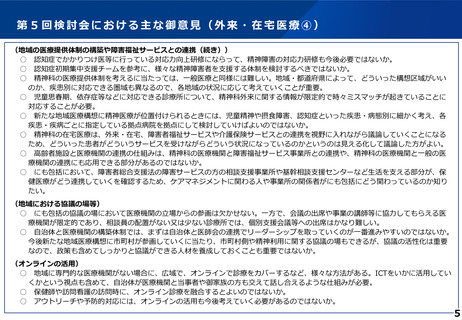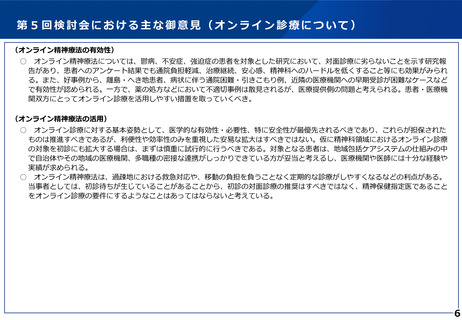よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】第5回検討会における主な御意見について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57735.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第6回 5/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第5回検討会における主な御意見(外来・在宅医療①)
(保健機能と外来医療・在宅医療の連携)
○ 住民に身近な市町村の保健師などが普段から関わることは、予防の観点や、病状悪化時に早期に医療につなげたり関係を構築して
おいたりする観点から重要。
○ 医療機関にとっても、自治体と連携することで、日常生活全体の支援、福祉や就労支援などにつなげていくことができる。また、
医療中断となっている患者に対して自治体と連携して対応することができる。
○ 自治体と医療機関で、一緒に相談体制の構築や普及啓発活動、事例検討を行うなど、現状と課題を共有する機会をもつことで、同
じ方向性で取り組むような連携ができる。
○ 医療機関に、精神保健福祉士などの配置があると、医師やコメディカルスタッフと関係機関の連携が図られやすい。市町村側の精
神保健に係る相談の担当窓口も明確になっている必要がある。ケースマネジメント機能・コーディネート機能を発揮するために相互
理解を行うことが大切。
○ 家族にとっても、ここにつながれば話をきいてもらえる、情報が得られるという相談窓口のわかりやすさや充実は重要である。ま
た、家族が、抱え込んで孤立することがないよう、家族を支える仕組みが必要である。
○ 精神障害のある人や家族が、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(以下「にも包括」という。)を活用していくときに、
どのようなところに良さとか悪さを感じるのか知りたい。
○ ピアサポーターの導入や、地域の人がじっくり話を聞くという仕組み・文化も必要ではないか。
(外来等での多職種による支援)
○ 精神科診療所が、保健所の連絡にすぐ対応することが難しいという課題は、医師が1人で全ての役割を担っていたというところに
問題がある。多職種とチームとして連携・協力していくことが求められている。多職種連携や新患対応、保健所との話し合いに対す
るインセンティブがあるとよいのではないか。
○ 現状ではかかりつけの精神科医療機関に求められる機能を果たしたとしても、それに見合った収益が得られないというところは課
題としてある。外来での多職種の配置について、診療報酬上の対応と、診療報酬ではなじまないような支援やケアに関して、例えば
補助金や、自治体の事業の中での対応や自治体からの事業の委託など、半ば公的な医療として提供するというような方法があるので、
どのような診療機能がそれぞれに適しているのかを検討していくことが必要ではないか。
○ 精神保健福祉士の人材が不足しているが、コメディカルが業務を担ってよい医療を提供しても、診療報酬の評価も含めて十分評価
されていないため、やりがいを感じられなかったり見合った報酬が得られなかったりすることが背景にあるのではないか。コメディ
カルがやりがいを持って業務に参加して、それを適切に評価していくというような方向性が必要。
2
(保健機能と外来医療・在宅医療の連携)
○ 住民に身近な市町村の保健師などが普段から関わることは、予防の観点や、病状悪化時に早期に医療につなげたり関係を構築して
おいたりする観点から重要。
○ 医療機関にとっても、自治体と連携することで、日常生活全体の支援、福祉や就労支援などにつなげていくことができる。また、
医療中断となっている患者に対して自治体と連携して対応することができる。
○ 自治体と医療機関で、一緒に相談体制の構築や普及啓発活動、事例検討を行うなど、現状と課題を共有する機会をもつことで、同
じ方向性で取り組むような連携ができる。
○ 医療機関に、精神保健福祉士などの配置があると、医師やコメディカルスタッフと関係機関の連携が図られやすい。市町村側の精
神保健に係る相談の担当窓口も明確になっている必要がある。ケースマネジメント機能・コーディネート機能を発揮するために相互
理解を行うことが大切。
○ 家族にとっても、ここにつながれば話をきいてもらえる、情報が得られるという相談窓口のわかりやすさや充実は重要である。ま
た、家族が、抱え込んで孤立することがないよう、家族を支える仕組みが必要である。
○ 精神障害のある人や家族が、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(以下「にも包括」という。)を活用していくときに、
どのようなところに良さとか悪さを感じるのか知りたい。
○ ピアサポーターの導入や、地域の人がじっくり話を聞くという仕組み・文化も必要ではないか。
(外来等での多職種による支援)
○ 精神科診療所が、保健所の連絡にすぐ対応することが難しいという課題は、医師が1人で全ての役割を担っていたというところに
問題がある。多職種とチームとして連携・協力していくことが求められている。多職種連携や新患対応、保健所との話し合いに対す
るインセンティブがあるとよいのではないか。
○ 現状ではかかりつけの精神科医療機関に求められる機能を果たしたとしても、それに見合った収益が得られないというところは課
題としてある。外来での多職種の配置について、診療報酬上の対応と、診療報酬ではなじまないような支援やケアに関して、例えば
補助金や、自治体の事業の中での対応や自治体からの事業の委託など、半ば公的な医療として提供するというような方法があるので、
どのような診療機能がそれぞれに適しているのかを検討していくことが必要ではないか。
○ 精神保健福祉士の人材が不足しているが、コメディカルが業務を担ってよい医療を提供しても、診療報酬の評価も含めて十分評価
されていないため、やりがいを感じられなかったり見合った報酬が得られなかったりすることが背景にあるのではないか。コメディ
カルがやりがいを持って業務に参加して、それを適切に評価していくというような方向性が必要。
2