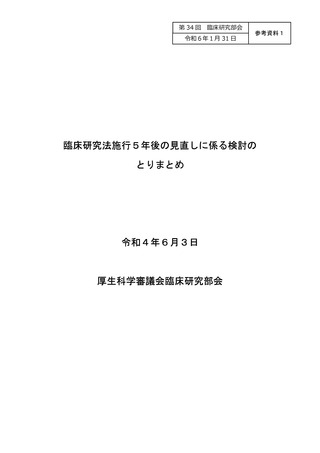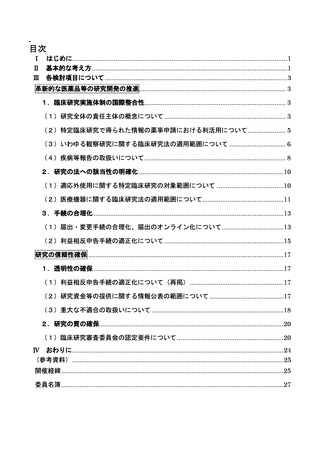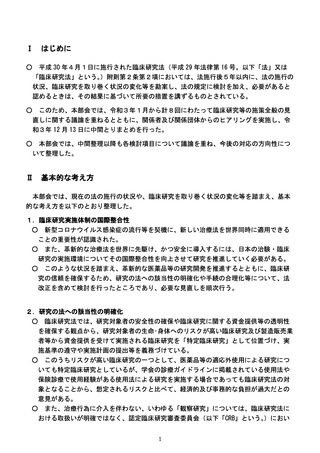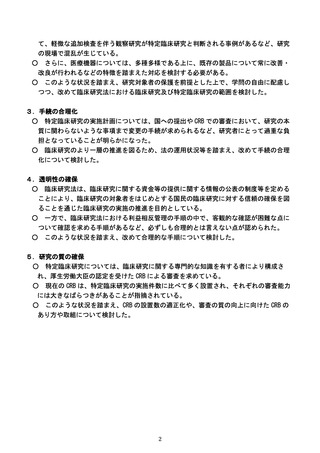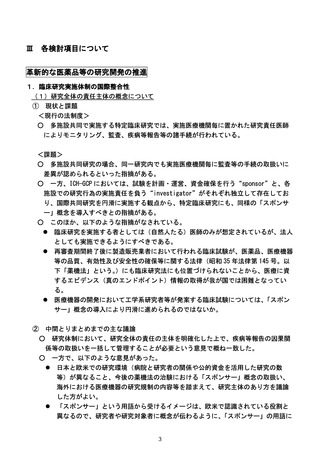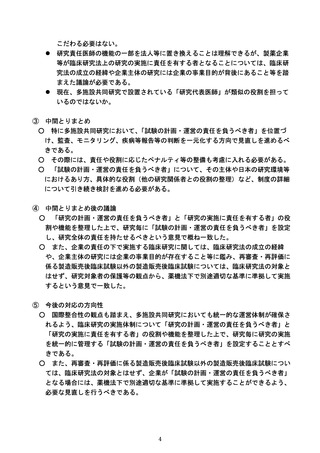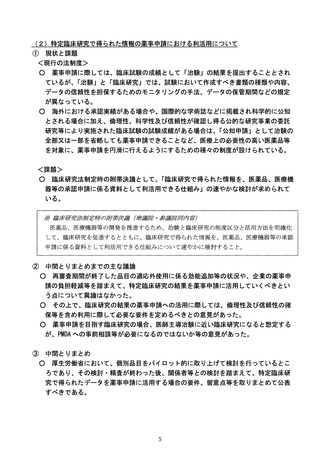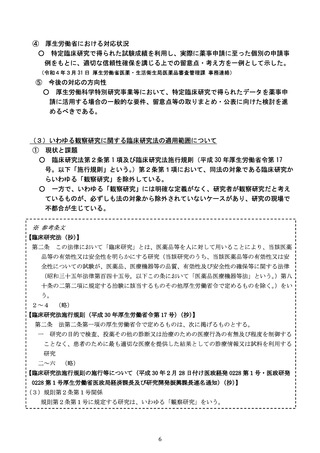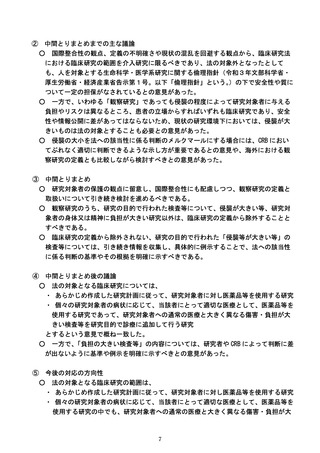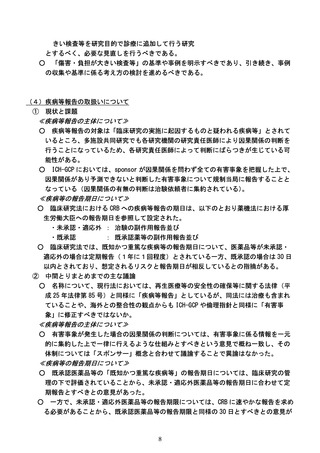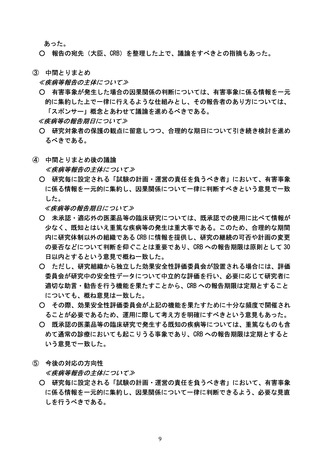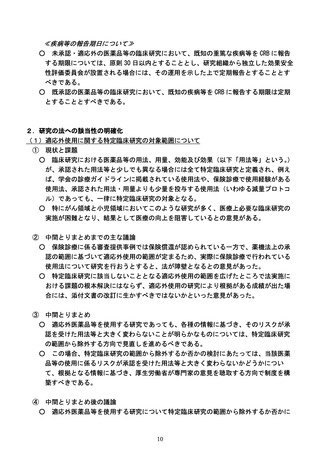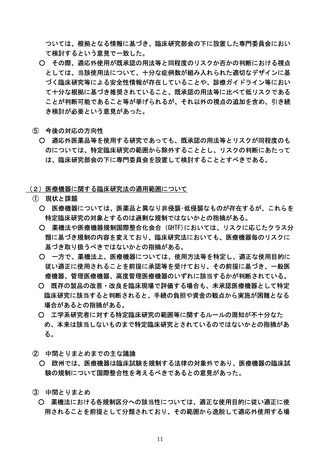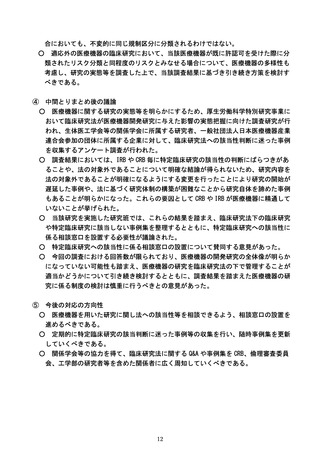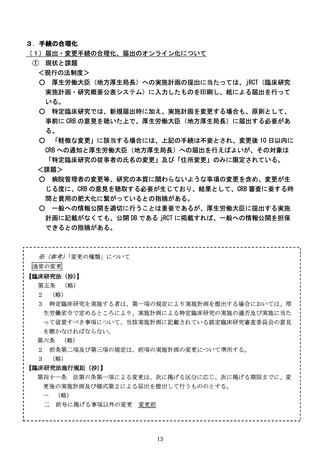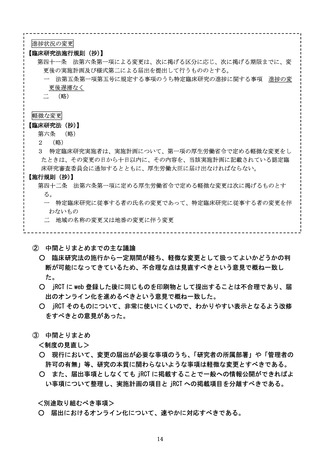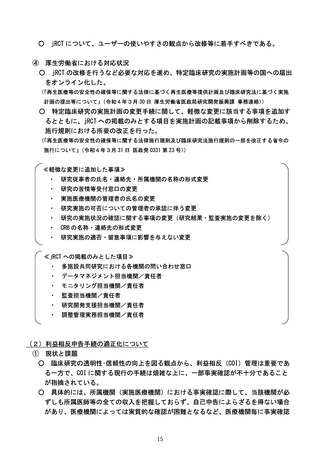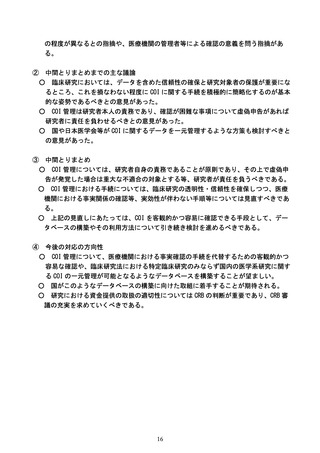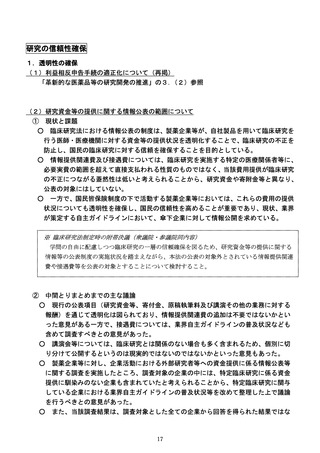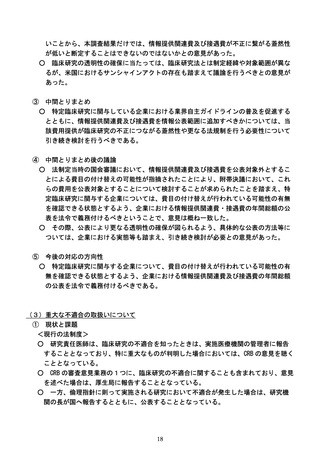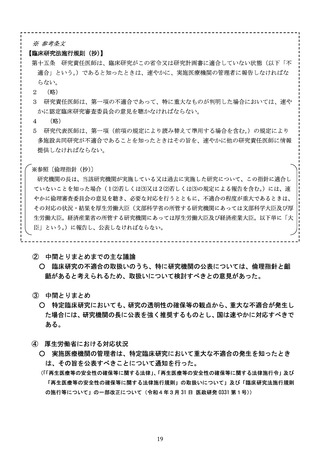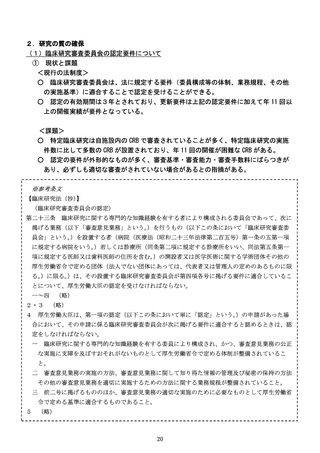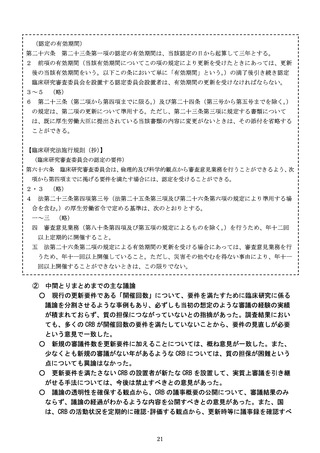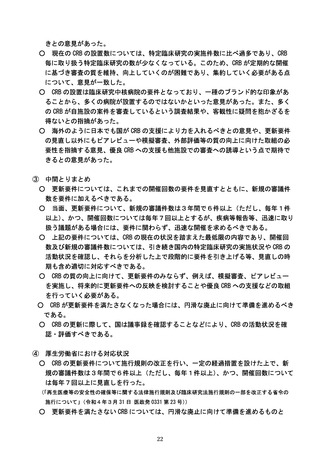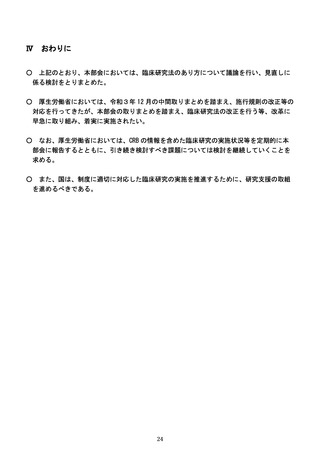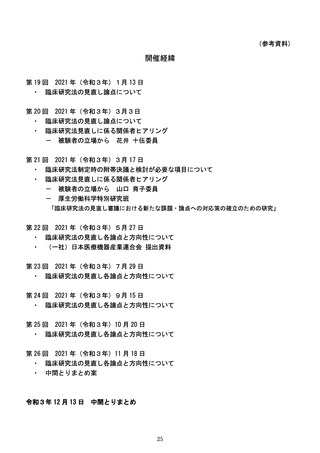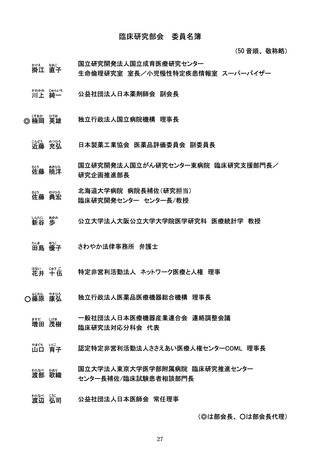よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1:臨床研究法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
合においても、不変的に同じ規制区分に分類されるわけではない。
○
適応外の医療機器の臨床研究において、当該医療機器が既に許認可を受けた際に分
類されたリスク分類と同程度のリスクとみなせる場合について、医療機器の多様性も
考慮し、研究の実態等を調査した上で、当該調査結果に基づき引き続き方策を検討す
べきである。
④
中間とりまとめ後の議論
○ 医療機器に関する研究の実態等を明らかにするため、厚生労働科学特別研究事業に
おいて臨床研究法が医療機器開発研究に与えた影響の実態把握に向けた調査研究が行
われ、生体医工学会等の関係学会に所属する研究者、一般社団法人日本医療機器産業
連合会参加の団体に所属する企業に対して、臨床研究法への該当性判断に迷った事例
を収集するアンケート調査が行われた。
○ 調査結果においては、IRB や CRB 毎に特定臨床研究の該当性の判断にばらつきがあ
ることや、法の対象外であることについて明確な結論が得られないため、研究内容を
法の対象外であることが明確になるようにする変更を行ったことにより研究の開始が
遅延した事例や、法に基づく研究体制の構築が困難なことから研究自体を諦めた事例
もあることが明らかになった。これらの要因として CRB や IRB が医療機器に精通して
いないことが挙げられた。
○ 当該研究を実施した研究班では、これらの結果を踏まえ、臨床研究法下の臨床研究
や特定臨床研究に該当しない事例集を整理するとともに、特定臨床研究への該当性に
係る相談窓口を設置する必要性が議論された。
○
○
特定臨床研究への該当性に係る相談窓口の設置について賛同する意見があった。
今回の調査における回答数が限られており、医療機器の開発研究の全体像が明らか
になっていない可能性も踏まえ、医療機器の研究を臨床研究法の下で管理することが
適当かどうかについて引き続き検討するとともに、調査結果を踏まえた医療機器の研
究に係る制度の検討は慎重に行うべきとの意見があった。
⑤
今後の対応の方向性
○ 医療機器を用いた研究に関し法への該当性等を相談できるよう、相談窓口の設置を
進めるべきである。
○ 定期的に特定臨床研究の該当判断に迷った事例等の収集を行い、随時事例集を更新
していくべきである。
○
関係学会等の協力を得て、臨床研究法に関する Q&A や事例集を CRB、倫理審査委員
会、工学部の研究者等を含めた関係者に広く周知していくべきである。
12
○
適応外の医療機器の臨床研究において、当該医療機器が既に許認可を受けた際に分
類されたリスク分類と同程度のリスクとみなせる場合について、医療機器の多様性も
考慮し、研究の実態等を調査した上で、当該調査結果に基づき引き続き方策を検討す
べきである。
④
中間とりまとめ後の議論
○ 医療機器に関する研究の実態等を明らかにするため、厚生労働科学特別研究事業に
おいて臨床研究法が医療機器開発研究に与えた影響の実態把握に向けた調査研究が行
われ、生体医工学会等の関係学会に所属する研究者、一般社団法人日本医療機器産業
連合会参加の団体に所属する企業に対して、臨床研究法への該当性判断に迷った事例
を収集するアンケート調査が行われた。
○ 調査結果においては、IRB や CRB 毎に特定臨床研究の該当性の判断にばらつきがあ
ることや、法の対象外であることについて明確な結論が得られないため、研究内容を
法の対象外であることが明確になるようにする変更を行ったことにより研究の開始が
遅延した事例や、法に基づく研究体制の構築が困難なことから研究自体を諦めた事例
もあることが明らかになった。これらの要因として CRB や IRB が医療機器に精通して
いないことが挙げられた。
○ 当該研究を実施した研究班では、これらの結果を踏まえ、臨床研究法下の臨床研究
や特定臨床研究に該当しない事例集を整理するとともに、特定臨床研究への該当性に
係る相談窓口を設置する必要性が議論された。
○
○
特定臨床研究への該当性に係る相談窓口の設置について賛同する意見があった。
今回の調査における回答数が限られており、医療機器の開発研究の全体像が明らか
になっていない可能性も踏まえ、医療機器の研究を臨床研究法の下で管理することが
適当かどうかについて引き続き検討するとともに、調査結果を踏まえた医療機器の研
究に係る制度の検討は慎重に行うべきとの意見があった。
⑤
今後の対応の方向性
○ 医療機器を用いた研究に関し法への該当性等を相談できるよう、相談窓口の設置を
進めるべきである。
○ 定期的に特定臨床研究の該当判断に迷った事例等の収集を行い、随時事例集を更新
していくべきである。
○
関係学会等の協力を得て、臨床研究法に関する Q&A や事例集を CRB、倫理審査委員
会、工学部の研究者等を含めた関係者に広く周知していくべきである。
12