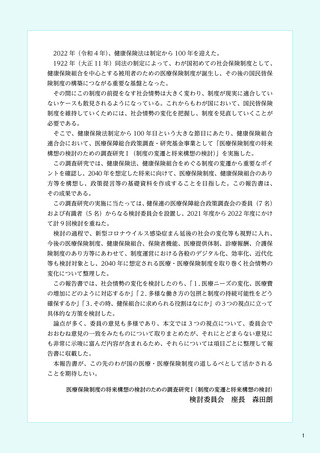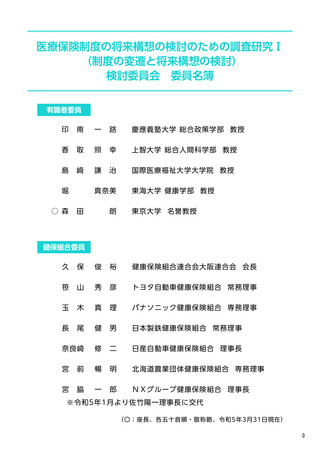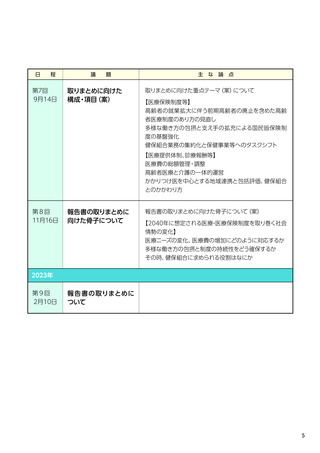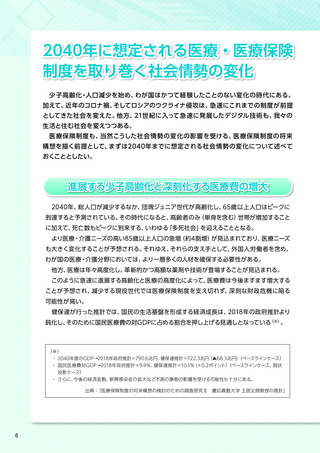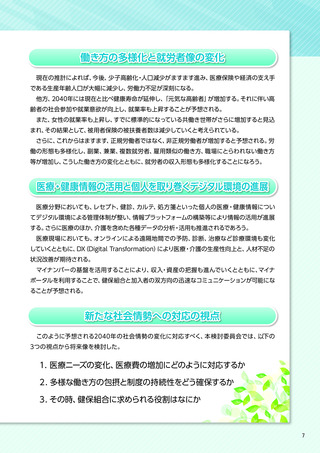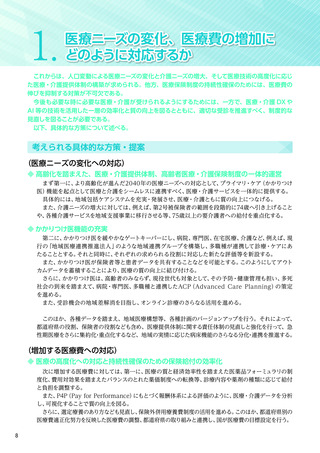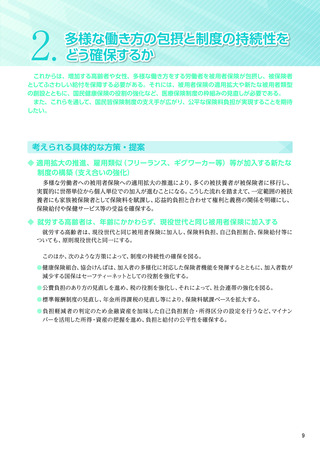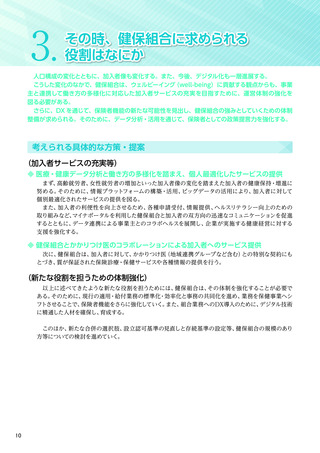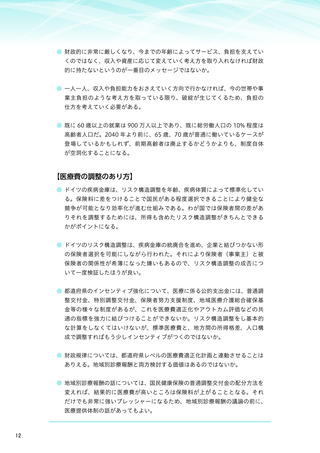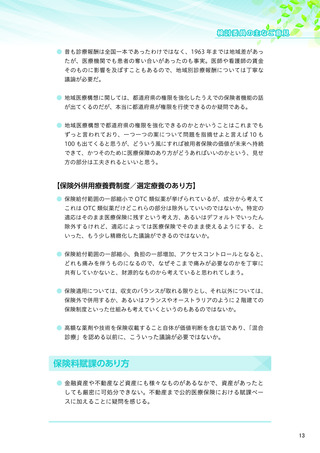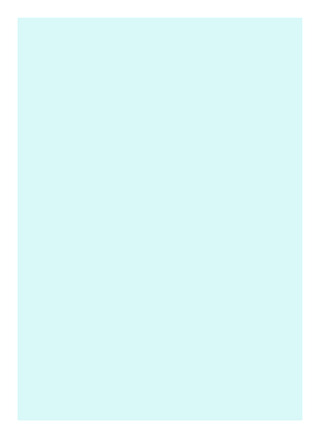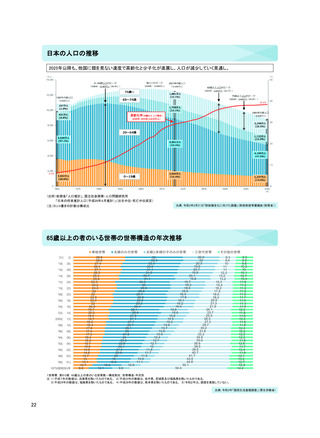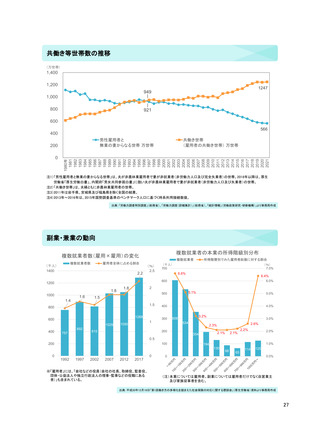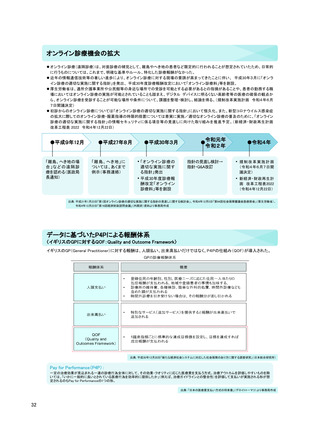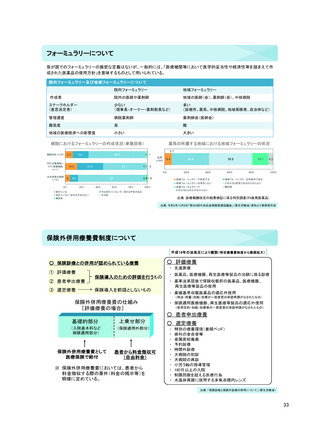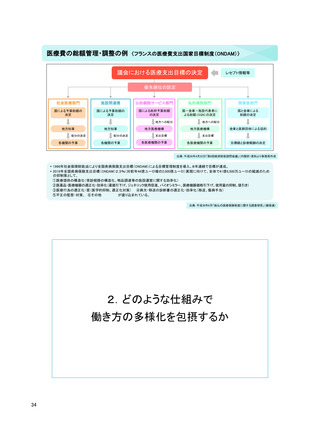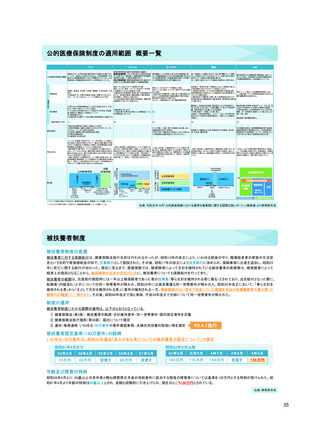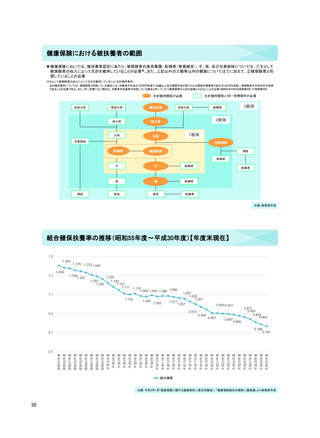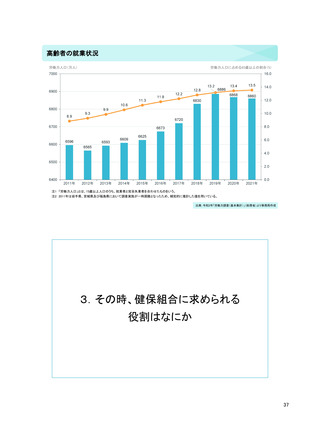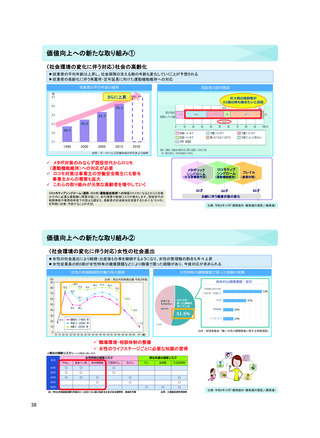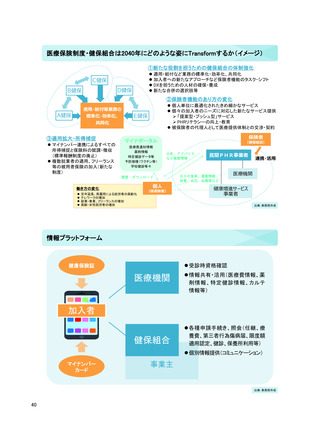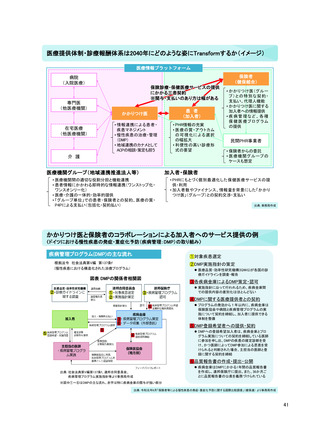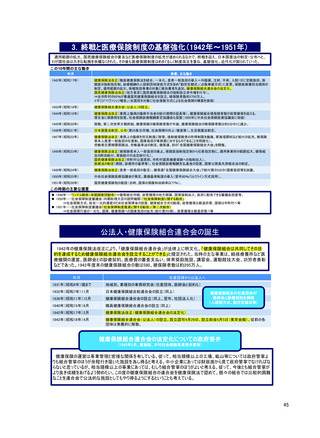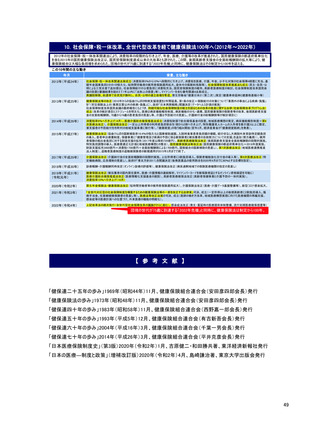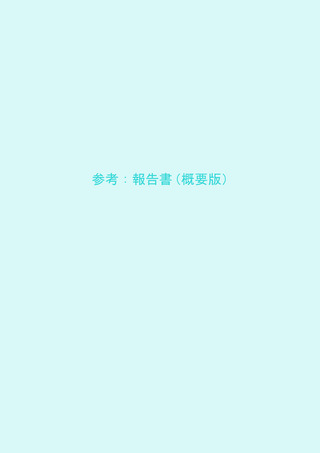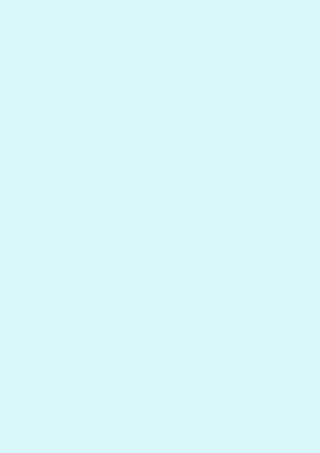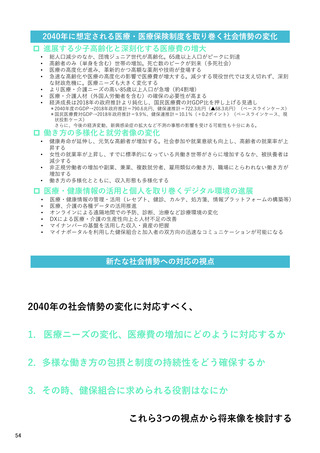よむ、つかう、まなぶ。
「医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(制度の変遷と将来構想の検討)検討委員会報告書」 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.kenporen.com/press/ |
| 出典情報 | 医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(5/17)《健康保険組合連合会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
8 .介護 保 険 制 度の 創 設と 医 療 保 険 者の 新 た な 役 割 ( 1 9 9 2 年 ~ 2 0 0 1 年 )
人口の高齢化の進展に対応するため、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、1997年に介護保険法が制定され、2000年に施行。わが国では5番目
の社会保険制度となった。健康保険組合をはじめとする医療保険者は、介護保険料の徴収等の新たな役割を担うことになった。一方、健保連は2000年度の医療
保険制度の抜本改革実現を求め、新たな提言をまとめるとともに、老人保健拠出金の延納実施に踏み切った。
この10年
年間の主な動き
年月
背景、主な動き
1992年(平成4年)
健康保険法改正(政府管掌健康保険に中期財政運営方式を導入。積立金約1兆4000億円を事業運営安定資金化。国庫補助16.4%を
13%に引き下げ=老人保健拠出金分は16.4%)。国民健康保険の財政安定化支援事業の創設(地方財政措置)。
第二次医療法改正(医療提供の理念の明文化。療養型病床群、特定機能病院、老人保健施設の法定化等)。
1993年(平成5年)
健康保険法改正(政府管掌健康保険国庫補助の減額1300憶円)。国民健康保険法改正(財政安定化支援事業の恒久制度化等)
1994年(平成6年)
健康保険法改正(付き添い看護・介護の解消と療養の給付へ位置づけ。入院時食事療養費制度。訪問看護制度。分娩費を出産育児一時
金に変更。健康診査等の保健事業の努力義務化。育児休業中の保険料免除)。厚生省「高齢者介護自立支援システム研究会」報告。
1995年(平成7年)
老人保健法改正(老人保健拠出金の上下限の引き上げ)。社会保障制度審議会勧告「社会保障体制の再構築―安心して暮らせる21世紀
の社会をめざして」(公的介護保険システムの創設、社会的入院の是正等を提言)。厚生省が一般病院の療養型病床群への転換推進を決定。
1996年(平成8年)
消費税率3%から5%に引き上げ。厚生省「介護保険制度案大綱」を審議会に提出。介護保険法案を国会に提出。
1997年(平成9年)
健康保険法改正(被保険者本人定率負担1割から2割へ引上げ。外来薬剤一部負担制度導入。政府管掌健康保険の保険料率引下げ等)。
老人保健法改正(患者定額一部負担の引き上げ、外来薬剤一部負担制度導入)。
第三次医療法改正(地域医療支援病院制度化=かかりつけ医支援、施設設備の共同利用。患者への説明と合意の努力義務化等)。
介護保険法制定(保険者は市町村。65歳以上を第1号被保険者。40歳から64歳までの医療保険加入者を第2号被保険者等)
財政構造改革法の制定(財政赤字縮小目標。主要経費の増加に上限設定)⇒翌年凍結。
1998年(平成10年)
国民健康保険法改正(退職被保険者等にかかる老人保健拠出金の2分の1を被用者保険が負担)。入院の診断群別定額払い試行開始。
1999年(平成11年)
健保連「医療保険制度構造改革への提言」(組合方式による管理運営。新たな高齢者医療制度=突き抜け方式。入院診療報酬の定額払
い方式。かかりつけ医機能の明確化。薬価制度に日本型参照価格制の導入)。抜本改革の促進を求め老人保健拠出金の延納断行。
2000年(平成12年)
健康保険法改正(外来薬剤一部負担の廃止。継続療養制度の廃止。高額療養費制度の自己負担限度額に一定額+医療費の1%を導入。
指定健康保険組合制度)。老人の月額上限付き定額1割負担。目標とされた2000年度の抜本改革実施は先送り。
第四次医療法改正(一般病床と療養病床の病床区分。医療計画の見直し、広告規制の見直し等)。
介護保険法施行(介護保険料徴収凍結、介護納付金納付猶予等)。厚生省「健康日本21」策定(生活習慣病予防と健康づくり推進)。
2001年(平成13年)
省庁再編。厚生労働省に社会保障審議会、内閣府に経済財政諮問会議を設置(政治主導の政策実現を図る)。アメリカ同時多発テロ。
介護保険法の概要(1997年
年制定当時)
保険者=市町村。被保険者=第1号被保険者(65歳以上)。第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)。
介護保険料の徴収=第1号被保険者は市町村が徴収。第2号被保険者は健康保険組合をはじめとする医療保険者が健康保険料と一体的に徴収。
利用者負担=1割負担。公費負担=利用者負担を除く介護給付費等に対して公費50%+介護保険料50%(第1号被保険者と第2号被保険者の人数比で按分)。
介護サービスの受給=第1号被保険者は要介護・要支援状態になったときに受給。第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に受給。
要介護認定制度(要介護1~5、要支援)、施設・居宅・介護予防等の各種サービス、ケアマネジメントなどの仕組みを導入。
9 .抜本 改 革 議 論を 経 て 新 た な 高 齢 者 医 療 制 度 へ ( 2 0 0 2 年 ~ 2 0 1 1 年 )
健康保険組合の財政は2002年の改正法によって小康を得たが、2008年に施行された新たな高齢者医療制度により急激な財政悪化に転じた。2009年の政権
交代後、改革議論が行われるも実現には至らず、社会保障費抑制のため、国庫負担の削減(肩代わり)を図ろうとする制度改正が行われた。
この10年
年間の主な動き
年月
背 景 、 主 な 動き
2002年(平成14年)
健康保険法改正(制定以来のカタカナ文語体からひらがな口語体へ。患者負担割合=3歳から69歳まで3割、70歳以上1割(現役並み所得者2割)、0歳から2
歳まで2割。保険料賦課に総報酬制導入。将来にわたり7割給付維持等)。健康増進法制定(医療保険者を健康増進事業実施者に)。老人保健法改正
(対象年齢を70歳から75歳へ、公費負担割合を3割から5割へ段階的に引き上げ。現役並み所得者は公費負担対象外。老人加入率上限撤廃。患者一部負
担に定率1割(現役並み所得者は2割)。外来薬剤一部負担廃止。退職被保険者にかかる老人保健拠出金の被用者保険負担部分を2分の1から全額へ)。
経済財政諮問会議「骨太の方針」(2006年度までの5年間で社会保障費を1.1兆円削減=毎年2200億円削減)。診療報酬改定は初めての本体マイナス。
2003年(平成15年)
「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」閣議決定(後期高齢者医療制度と前期高齢者財政調整、都道府県単位の保険者統合再編、
急性期入院包括評価の構想等)。特定機能病院を対象に急性期入院1日当たり定額払い制度(DPC)導入。WHO「たばこ規制枠組み条約」。SARS発生。
2004年(平成16年)
厚生年金保険法、国民年金法の改正(将来の保険料水準を固定。基礎年金の国庫負担2分の1。マクロ経済スライド)。診療報酬改定をめぐる贈収賄事件。
2005年(平成17年)
介護保険法改正(新予防給付・地域支援事業の創設、施設入所者の食費・居住費負担、地域密着型サービス・地域包括支援センター等)。健保連「新た
な高齢者医療制度の創設を含む医療制度改革に向けての提言」=65歳以上別建ての高齢者医療制度に公費負担5割、患者負担割合は原則2割(高所得
者は3割)、世代間扶養のための保険料(被用者保険は総報酬割)。健保組合再編・事業共同化。医療機能分化・連携。診療報酬包括払い拡大等。
2006年(平成18年)
健康保険法改正(70歳から74歳まで2割負担。未就学児2割負担。高額医療介護合算制度。保険外併用療養費制度。地域型健康保険組合制度。政管
健保を全国健康保険協会「協会けんぽ」へ)。高齢者の医療を確保する法律制定(後期高齢者医療制度と前期高齢者財政調整。医療費適正化計画。特
定健診・特定保健指導の導入・義務化等)。第五次医療法改正(都道府県の医療情報提供制度。医療計画に4疾病5事業の連携体制)。
2008年(平成20年)
政管健保国庫負担肩代わり法案国会提出(廃案へ)。健保連「財政調整・一元化阻止最終報告」。「健保組合IT基本構想」による「特定健診・特定保健指
導共同情報処理システム」を導入(2年後「データ分析事業」)。後期高齢者医療制度等施行(70歳から74歳患者一部負担と75歳以上の保険料の軽減等)。
2009年(平成21年)
民主党マニフェスト(医療保険制度の統合、一元的運営。後期高齢者医療制度の廃止。被用者保険適用拡大等)。衆議院総選挙で民主党が勝利、民主
党・社民党・国民新党による連立政権の発足。前年秋に発生したリーマンショックの影響が深刻化。
2010年(平成22年)
健康保険法・高齢者医療確保法の改正(協会けんぽに3年間の特例支援措置=国庫補助率を13%から16.4%へ引き上げ。後期高齢者支援金3分の1総報
酬割導入等)。健保連「肩代わり」法案に反対し街頭活動。厚生労働省「高齢者医療制度改革会議」改革案(後期高齢者医療制度の廃止。後期高齢者
支援金総報酬割の段階的導入。75歳以上の給付費に公費5割。現役並み所得者の給付費にも公費5割。国保の都道府県単位化)⇒法案提出に至らず。
2011年(平成23年)
介護保険法改正(介護療養病床廃止期限延長、定期巡回・随時対応サービス導入等)。東日本大震災。政府の検討本部「社会保障・税一体改革成案」。
後期高齢者医療制度(2006年
年高齢者医療確保法制定当時)
75歳以上の後期高齢者(65歳以上の一定の障害状態を含む)を対象に医療給付を
行う独立型の制度。都道府県の後期高齢者医療広域連合が運営主体。
患者負担割合は原則1割(現役並み所得者は3割)。給付費の5割を公費負担(現役
並み所得者の給付費は対象外)、1割を後期高齢者の保険料、残りの4割強を現役世
代が負担する後期高齢者支援金で賄う。
現役世代が負担する後期高齢者支援金は被用者保険、国保の各保険者が加入者
数に応じて負担(加入者割)。
医療費適正化計画の導入。40歳以上を対象とする特定健診、特定保健指導を各保
険者に義務付け。
48
前期高齢者財政調整(2006年
年高齢者医療確保法制定当時)
65歳から74歳までの前期高齢者が国保に偏在することによる負担の不均衡の是正を目
的に、被用者保険と国保の各保険者の前期高齢者加入率に応じて費用負担を調整。
各保険者の前期高齢者にかかる給付費と後期高齢者支援金について、前期高齢者
加入率が全国平均並みであるとみなして算定した額を負担する。主に被用者保険が前
期高齢者納付金を負担。国保には前期高齢者交付金を交付。
患者負担割合は、65歳から69歳までは3割負担、70歳以上74歳までは2割負担(予算
措置により当面1割負担に軽減)(現役並み所得者は3割負担)。
協会けんぽの前期高齢者納付金には定率の国庫補助。国保は前期高齢者交付金を
充当した後に公費5割。
人口の高齢化の進展に対応するため、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、1997年に介護保険法が制定され、2000年に施行。わが国では5番目
の社会保険制度となった。健康保険組合をはじめとする医療保険者は、介護保険料の徴収等の新たな役割を担うことになった。一方、健保連は2000年度の医療
保険制度の抜本改革実現を求め、新たな提言をまとめるとともに、老人保健拠出金の延納実施に踏み切った。
この10年
年間の主な動き
年月
背景、主な動き
1992年(平成4年)
健康保険法改正(政府管掌健康保険に中期財政運営方式を導入。積立金約1兆4000億円を事業運営安定資金化。国庫補助16.4%を
13%に引き下げ=老人保健拠出金分は16.4%)。国民健康保険の財政安定化支援事業の創設(地方財政措置)。
第二次医療法改正(医療提供の理念の明文化。療養型病床群、特定機能病院、老人保健施設の法定化等)。
1993年(平成5年)
健康保険法改正(政府管掌健康保険国庫補助の減額1300憶円)。国民健康保険法改正(財政安定化支援事業の恒久制度化等)
1994年(平成6年)
健康保険法改正(付き添い看護・介護の解消と療養の給付へ位置づけ。入院時食事療養費制度。訪問看護制度。分娩費を出産育児一時
金に変更。健康診査等の保健事業の努力義務化。育児休業中の保険料免除)。厚生省「高齢者介護自立支援システム研究会」報告。
1995年(平成7年)
老人保健法改正(老人保健拠出金の上下限の引き上げ)。社会保障制度審議会勧告「社会保障体制の再構築―安心して暮らせる21世紀
の社会をめざして」(公的介護保険システムの創設、社会的入院の是正等を提言)。厚生省が一般病院の療養型病床群への転換推進を決定。
1996年(平成8年)
消費税率3%から5%に引き上げ。厚生省「介護保険制度案大綱」を審議会に提出。介護保険法案を国会に提出。
1997年(平成9年)
健康保険法改正(被保険者本人定率負担1割から2割へ引上げ。外来薬剤一部負担制度導入。政府管掌健康保険の保険料率引下げ等)。
老人保健法改正(患者定額一部負担の引き上げ、外来薬剤一部負担制度導入)。
第三次医療法改正(地域医療支援病院制度化=かかりつけ医支援、施設設備の共同利用。患者への説明と合意の努力義務化等)。
介護保険法制定(保険者は市町村。65歳以上を第1号被保険者。40歳から64歳までの医療保険加入者を第2号被保険者等)
財政構造改革法の制定(財政赤字縮小目標。主要経費の増加に上限設定)⇒翌年凍結。
1998年(平成10年)
国民健康保険法改正(退職被保険者等にかかる老人保健拠出金の2分の1を被用者保険が負担)。入院の診断群別定額払い試行開始。
1999年(平成11年)
健保連「医療保険制度構造改革への提言」(組合方式による管理運営。新たな高齢者医療制度=突き抜け方式。入院診療報酬の定額払
い方式。かかりつけ医機能の明確化。薬価制度に日本型参照価格制の導入)。抜本改革の促進を求め老人保健拠出金の延納断行。
2000年(平成12年)
健康保険法改正(外来薬剤一部負担の廃止。継続療養制度の廃止。高額療養費制度の自己負担限度額に一定額+医療費の1%を導入。
指定健康保険組合制度)。老人の月額上限付き定額1割負担。目標とされた2000年度の抜本改革実施は先送り。
第四次医療法改正(一般病床と療養病床の病床区分。医療計画の見直し、広告規制の見直し等)。
介護保険法施行(介護保険料徴収凍結、介護納付金納付猶予等)。厚生省「健康日本21」策定(生活習慣病予防と健康づくり推進)。
2001年(平成13年)
省庁再編。厚生労働省に社会保障審議会、内閣府に経済財政諮問会議を設置(政治主導の政策実現を図る)。アメリカ同時多発テロ。
介護保険法の概要(1997年
年制定当時)
保険者=市町村。被保険者=第1号被保険者(65歳以上)。第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)。
介護保険料の徴収=第1号被保険者は市町村が徴収。第2号被保険者は健康保険組合をはじめとする医療保険者が健康保険料と一体的に徴収。
利用者負担=1割負担。公費負担=利用者負担を除く介護給付費等に対して公費50%+介護保険料50%(第1号被保険者と第2号被保険者の人数比で按分)。
介護サービスの受給=第1号被保険者は要介護・要支援状態になったときに受給。第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に受給。
要介護認定制度(要介護1~5、要支援)、施設・居宅・介護予防等の各種サービス、ケアマネジメントなどの仕組みを導入。
9 .抜本 改 革 議 論を 経 て 新 た な 高 齢 者 医 療 制 度 へ ( 2 0 0 2 年 ~ 2 0 1 1 年 )
健康保険組合の財政は2002年の改正法によって小康を得たが、2008年に施行された新たな高齢者医療制度により急激な財政悪化に転じた。2009年の政権
交代後、改革議論が行われるも実現には至らず、社会保障費抑制のため、国庫負担の削減(肩代わり)を図ろうとする制度改正が行われた。
この10年
年間の主な動き
年月
背 景 、 主 な 動き
2002年(平成14年)
健康保険法改正(制定以来のカタカナ文語体からひらがな口語体へ。患者負担割合=3歳から69歳まで3割、70歳以上1割(現役並み所得者2割)、0歳から2
歳まで2割。保険料賦課に総報酬制導入。将来にわたり7割給付維持等)。健康増進法制定(医療保険者を健康増進事業実施者に)。老人保健法改正
(対象年齢を70歳から75歳へ、公費負担割合を3割から5割へ段階的に引き上げ。現役並み所得者は公費負担対象外。老人加入率上限撤廃。患者一部負
担に定率1割(現役並み所得者は2割)。外来薬剤一部負担廃止。退職被保険者にかかる老人保健拠出金の被用者保険負担部分を2分の1から全額へ)。
経済財政諮問会議「骨太の方針」(2006年度までの5年間で社会保障費を1.1兆円削減=毎年2200億円削減)。診療報酬改定は初めての本体マイナス。
2003年(平成15年)
「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」閣議決定(後期高齢者医療制度と前期高齢者財政調整、都道府県単位の保険者統合再編、
急性期入院包括評価の構想等)。特定機能病院を対象に急性期入院1日当たり定額払い制度(DPC)導入。WHO「たばこ規制枠組み条約」。SARS発生。
2004年(平成16年)
厚生年金保険法、国民年金法の改正(将来の保険料水準を固定。基礎年金の国庫負担2分の1。マクロ経済スライド)。診療報酬改定をめぐる贈収賄事件。
2005年(平成17年)
介護保険法改正(新予防給付・地域支援事業の創設、施設入所者の食費・居住費負担、地域密着型サービス・地域包括支援センター等)。健保連「新た
な高齢者医療制度の創設を含む医療制度改革に向けての提言」=65歳以上別建ての高齢者医療制度に公費負担5割、患者負担割合は原則2割(高所得
者は3割)、世代間扶養のための保険料(被用者保険は総報酬割)。健保組合再編・事業共同化。医療機能分化・連携。診療報酬包括払い拡大等。
2006年(平成18年)
健康保険法改正(70歳から74歳まで2割負担。未就学児2割負担。高額医療介護合算制度。保険外併用療養費制度。地域型健康保険組合制度。政管
健保を全国健康保険協会「協会けんぽ」へ)。高齢者の医療を確保する法律制定(後期高齢者医療制度と前期高齢者財政調整。医療費適正化計画。特
定健診・特定保健指導の導入・義務化等)。第五次医療法改正(都道府県の医療情報提供制度。医療計画に4疾病5事業の連携体制)。
2008年(平成20年)
政管健保国庫負担肩代わり法案国会提出(廃案へ)。健保連「財政調整・一元化阻止最終報告」。「健保組合IT基本構想」による「特定健診・特定保健指
導共同情報処理システム」を導入(2年後「データ分析事業」)。後期高齢者医療制度等施行(70歳から74歳患者一部負担と75歳以上の保険料の軽減等)。
2009年(平成21年)
民主党マニフェスト(医療保険制度の統合、一元的運営。後期高齢者医療制度の廃止。被用者保険適用拡大等)。衆議院総選挙で民主党が勝利、民主
党・社民党・国民新党による連立政権の発足。前年秋に発生したリーマンショックの影響が深刻化。
2010年(平成22年)
健康保険法・高齢者医療確保法の改正(協会けんぽに3年間の特例支援措置=国庫補助率を13%から16.4%へ引き上げ。後期高齢者支援金3分の1総報
酬割導入等)。健保連「肩代わり」法案に反対し街頭活動。厚生労働省「高齢者医療制度改革会議」改革案(後期高齢者医療制度の廃止。後期高齢者
支援金総報酬割の段階的導入。75歳以上の給付費に公費5割。現役並み所得者の給付費にも公費5割。国保の都道府県単位化)⇒法案提出に至らず。
2011年(平成23年)
介護保険法改正(介護療養病床廃止期限延長、定期巡回・随時対応サービス導入等)。東日本大震災。政府の検討本部「社会保障・税一体改革成案」。
後期高齢者医療制度(2006年
年高齢者医療確保法制定当時)
75歳以上の後期高齢者(65歳以上の一定の障害状態を含む)を対象に医療給付を
行う独立型の制度。都道府県の後期高齢者医療広域連合が運営主体。
患者負担割合は原則1割(現役並み所得者は3割)。給付費の5割を公費負担(現役
並み所得者の給付費は対象外)、1割を後期高齢者の保険料、残りの4割強を現役世
代が負担する後期高齢者支援金で賄う。
現役世代が負担する後期高齢者支援金は被用者保険、国保の各保険者が加入者
数に応じて負担(加入者割)。
医療費適正化計画の導入。40歳以上を対象とする特定健診、特定保健指導を各保
険者に義務付け。
48
前期高齢者財政調整(2006年
年高齢者医療確保法制定当時)
65歳から74歳までの前期高齢者が国保に偏在することによる負担の不均衡の是正を目
的に、被用者保険と国保の各保険者の前期高齢者加入率に応じて費用負担を調整。
各保険者の前期高齢者にかかる給付費と後期高齢者支援金について、前期高齢者
加入率が全国平均並みであるとみなして算定した額を負担する。主に被用者保険が前
期高齢者納付金を負担。国保には前期高齢者交付金を交付。
患者負担割合は、65歳から69歳までは3割負担、70歳以上74歳までは2割負担(予算
措置により当面1割負担に軽減)(現役並み所得者は3割負担)。
協会けんぽの前期高齢者納付金には定率の国庫補助。国保は前期高齢者交付金を
充当した後に公費5割。