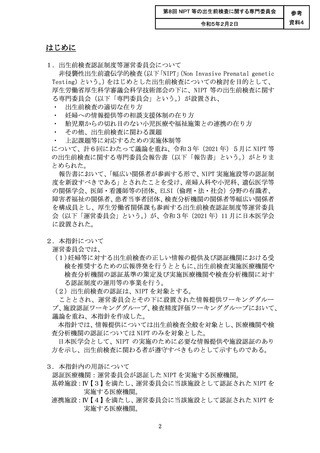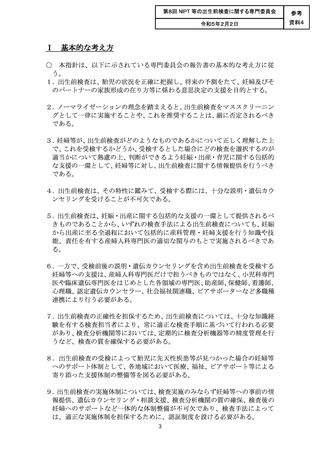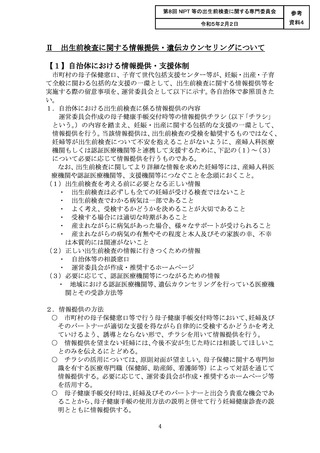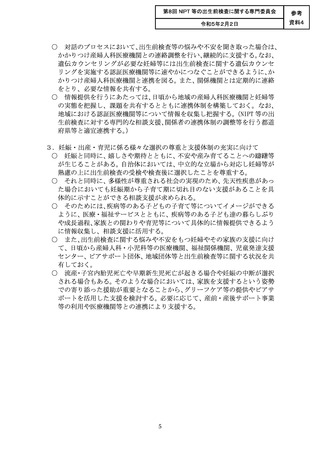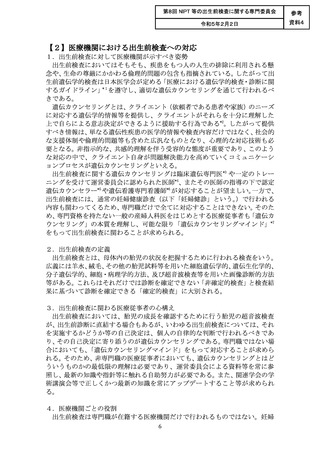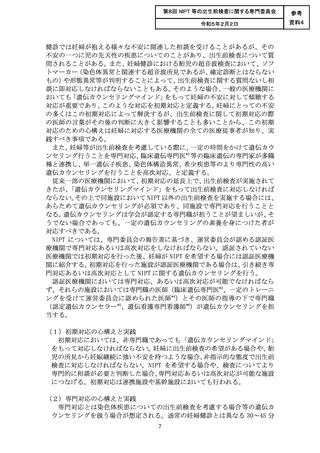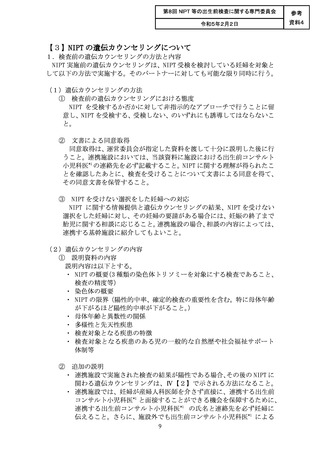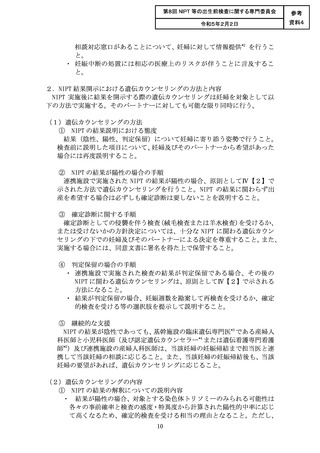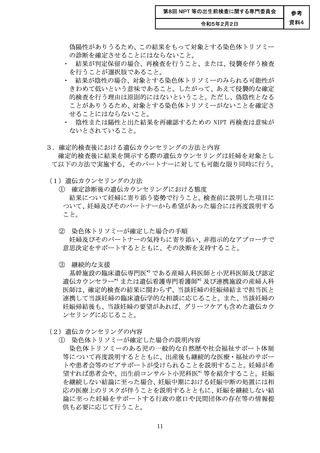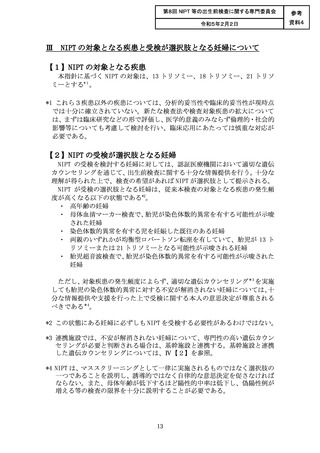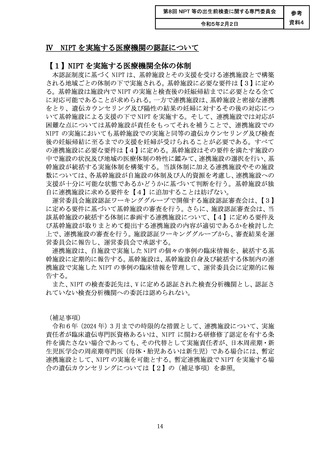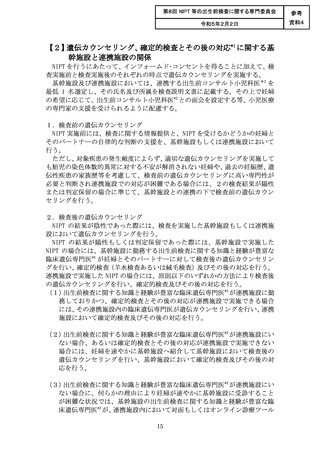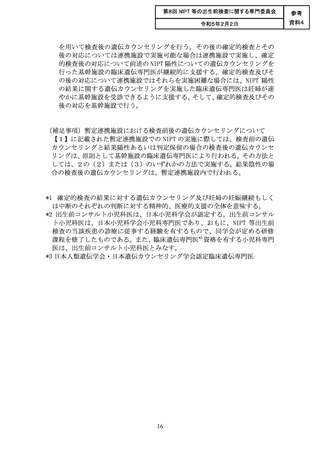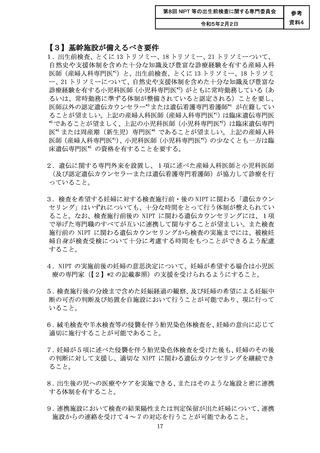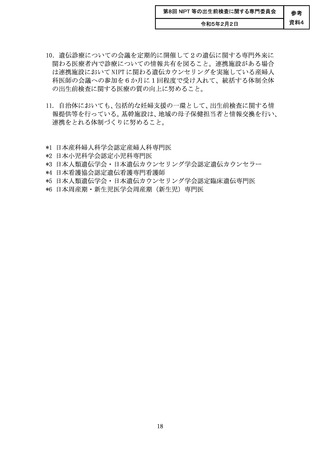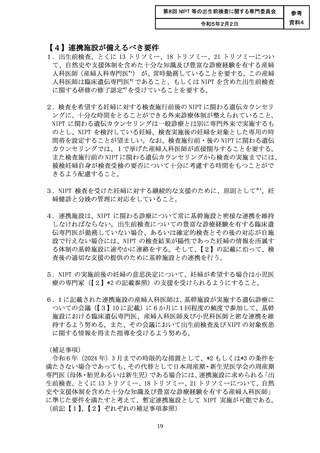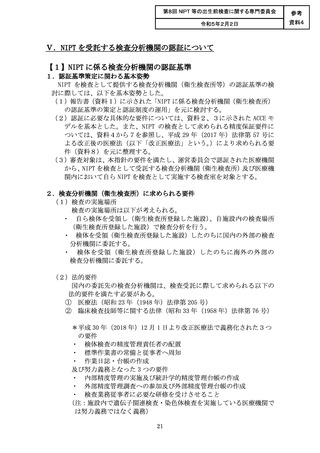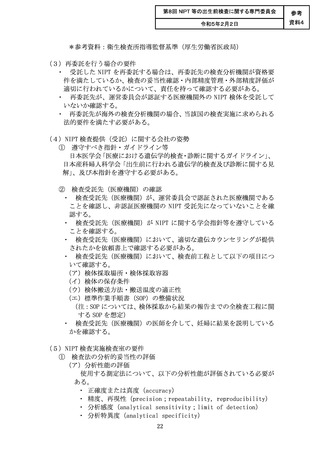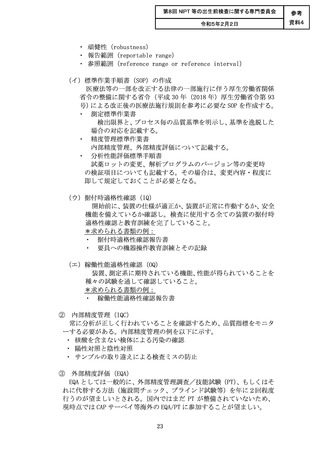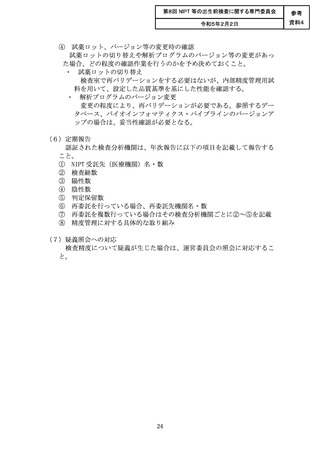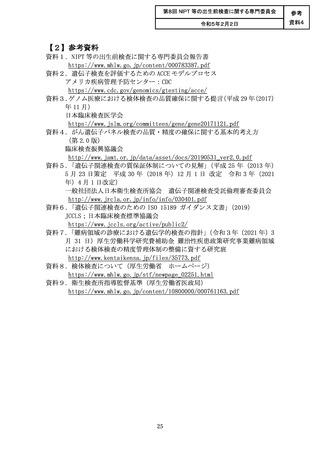よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 NIPT等の出生前検査に関する情報提供及び施設(医療機関・検査分析機関)認証の指針 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会
参考
令和5年2月2日
資料4
資料1
【4】連携施設が備えるべき要件
1.出生前検査、とくに 13 トリソミー、18 トリソミー、21 トリソミーについ
て、自然史や支援体制を含めた十分な知識及び豊富な診療経験を有する産婦
人科医師(産婦人科専門医*1) が、常時勤務していることを要する。この産婦
人科医師は臨床遺伝専門医*2 であること、もしくは NIPT を含めた出生前検査
に関する研修の修了認定*3 を受けていることを要する。
2.検査を希望する妊婦に対する検査施行前後の NIPT に関わる遺伝カウンセリ
ングに、十分な時間をとることができる外来診療体制が整えられていること。
NIPT に関わる遺伝カウンセリングは一般診療とは別に専門外来で実施するも
のとし、NIPT を検討している妊婦、検査実施後の妊婦を対象とした専用の時
間帯を設定することが望ましい。なお、検査施行前・後の NIPT に関わる遺伝
カウンセリングでは、1で挙げた産婦人科医師が直接関与することを要する。
また検査施行前の NIPT に関わる遺伝カウンセリングから検査の実施までには、
被検妊婦自身が検査受検の要否について十分に考慮する時間をもつことがで
きるよう配慮すること。
3.NIPT 検査を受けた妊婦に対する継続的な支援のために、原則として*4、妊
婦健診と分娩の管理に対応をしていること。
4.連携施設は、NIPT に関わる診療について常に基幹施設と密接な連携を維持
しなければならない。出生前検査についての豊富な診療経験を有する臨床遺
伝専門医が勤務していない場合、あるいは確定的検査とその後の対応が自施
設で行えない場合には、NIPT の検査結果が陽性であった妊婦の情報を所属す
る体制の基幹施設に速やかに連絡をする。そして、
【2】の記載に沿って、検
査後の適切な支援の提供のために基幹施設との連携を行う。
5.NIPT の実施前後の妊婦の意思決定について、妊婦が希望する場合は小児医
療の専門家(
【2】*2 の記載参照)の支援を受けられるようにすること。
6.1に記載された連携施設の産婦人科医師は、基幹施設が実施する遺伝診療に
ついての会議(【3】10 に記載)に6か月に1回程度の頻度で参加して、基幹
施設における臨床遺伝専門医、産婦人科医師及び小児科医師と密な連携を維
持するよう努める。また、その会議において出生前検査及び NIPT の対象疾患
に関する情報を得また指導を受けるよう努める。
(補足事項)
令和6年(2024 年)3 月までの時限的な措置として、*2 もしくは*3 の条件を
満たさない場合であっても、その代替として日本周産期・新生児医学会の周産期
専門医(母体・胎児あるいは新生児)である場合には、連携施設に求められる「出
生前検査、とくに 13 トリソミー、18 トリソミー、21 トリソミーについて、自然
史や支援体制を含めた十分な知識及び豊富な診療経験を有する産婦人科医師」
に準じた要件を満たすと考えて、暫定連携施設として NIPT 実施が可能である。
(前記【1】、【2】ぞれぞれの補足事項参照)
19
参考
令和5年2月2日
資料4
資料1
【4】連携施設が備えるべき要件
1.出生前検査、とくに 13 トリソミー、18 トリソミー、21 トリソミーについ
て、自然史や支援体制を含めた十分な知識及び豊富な診療経験を有する産婦
人科医師(産婦人科専門医*1) が、常時勤務していることを要する。この産婦
人科医師は臨床遺伝専門医*2 であること、もしくは NIPT を含めた出生前検査
に関する研修の修了認定*3 を受けていることを要する。
2.検査を希望する妊婦に対する検査施行前後の NIPT に関わる遺伝カウンセリ
ングに、十分な時間をとることができる外来診療体制が整えられていること。
NIPT に関わる遺伝カウンセリングは一般診療とは別に専門外来で実施するも
のとし、NIPT を検討している妊婦、検査実施後の妊婦を対象とした専用の時
間帯を設定することが望ましい。なお、検査施行前・後の NIPT に関わる遺伝
カウンセリングでは、1で挙げた産婦人科医師が直接関与することを要する。
また検査施行前の NIPT に関わる遺伝カウンセリングから検査の実施までには、
被検妊婦自身が検査受検の要否について十分に考慮する時間をもつことがで
きるよう配慮すること。
3.NIPT 検査を受けた妊婦に対する継続的な支援のために、原則として*4、妊
婦健診と分娩の管理に対応をしていること。
4.連携施設は、NIPT に関わる診療について常に基幹施設と密接な連携を維持
しなければならない。出生前検査についての豊富な診療経験を有する臨床遺
伝専門医が勤務していない場合、あるいは確定的検査とその後の対応が自施
設で行えない場合には、NIPT の検査結果が陽性であった妊婦の情報を所属す
る体制の基幹施設に速やかに連絡をする。そして、
【2】の記載に沿って、検
査後の適切な支援の提供のために基幹施設との連携を行う。
5.NIPT の実施前後の妊婦の意思決定について、妊婦が希望する場合は小児医
療の専門家(
【2】*2 の記載参照)の支援を受けられるようにすること。
6.1に記載された連携施設の産婦人科医師は、基幹施設が実施する遺伝診療に
ついての会議(【3】10 に記載)に6か月に1回程度の頻度で参加して、基幹
施設における臨床遺伝専門医、産婦人科医師及び小児科医師と密な連携を維
持するよう努める。また、その会議において出生前検査及び NIPT の対象疾患
に関する情報を得また指導を受けるよう努める。
(補足事項)
令和6年(2024 年)3 月までの時限的な措置として、*2 もしくは*3 の条件を
満たさない場合であっても、その代替として日本周産期・新生児医学会の周産期
専門医(母体・胎児あるいは新生児)である場合には、連携施設に求められる「出
生前検査、とくに 13 トリソミー、18 トリソミー、21 トリソミーについて、自然
史や支援体制を含めた十分な知識及び豊富な診療経験を有する産婦人科医師」
に準じた要件を満たすと考えて、暫定連携施設として NIPT 実施が可能である。
(前記【1】、【2】ぞれぞれの補足事項参照)
19