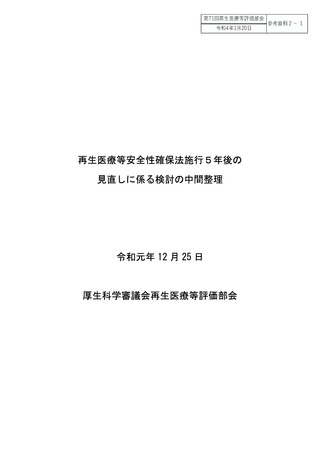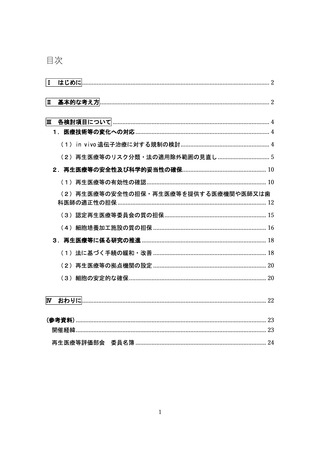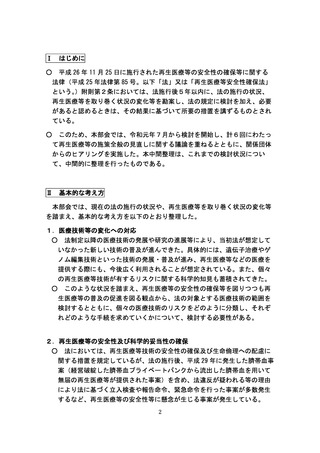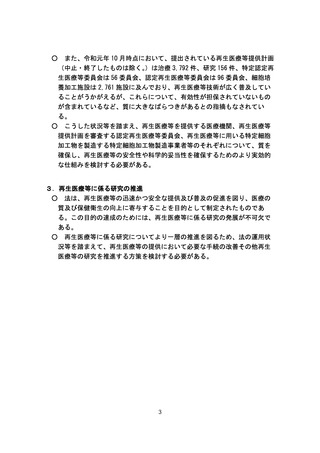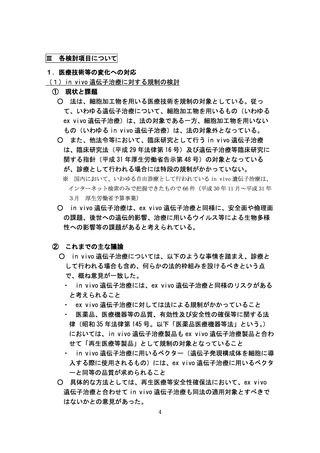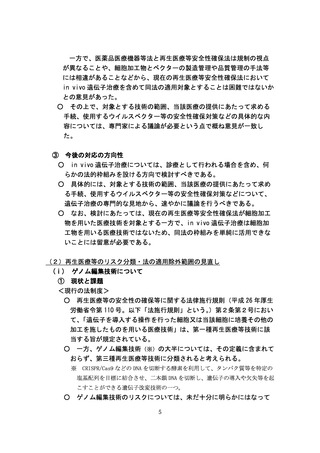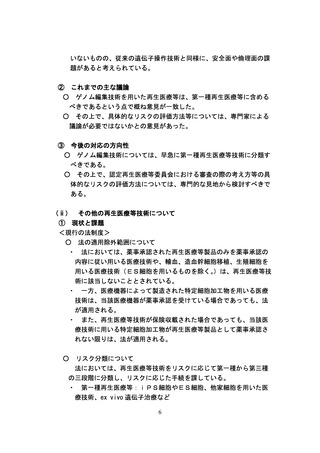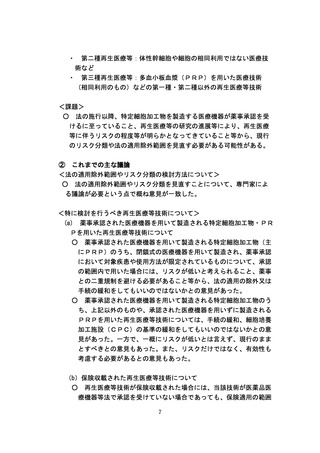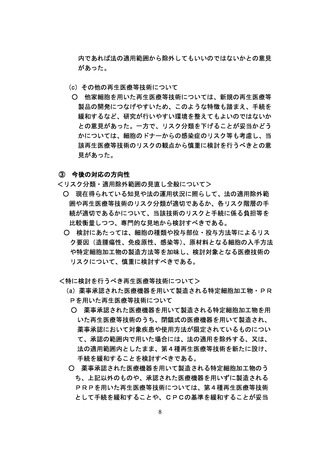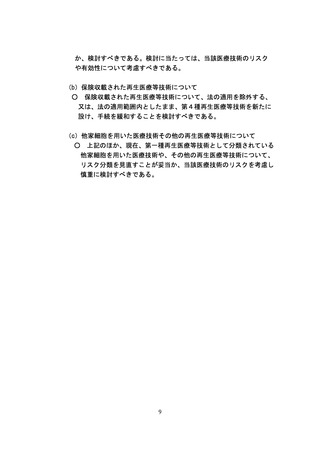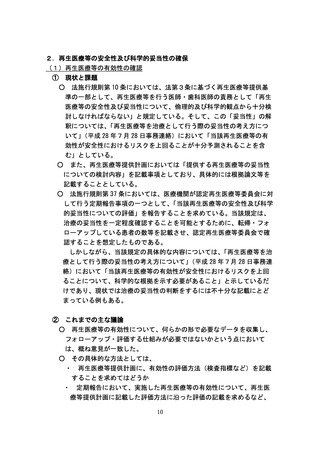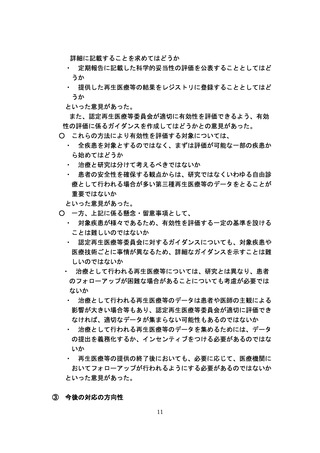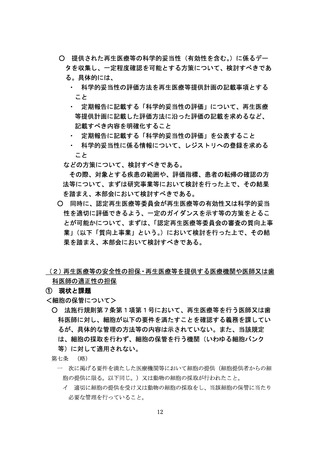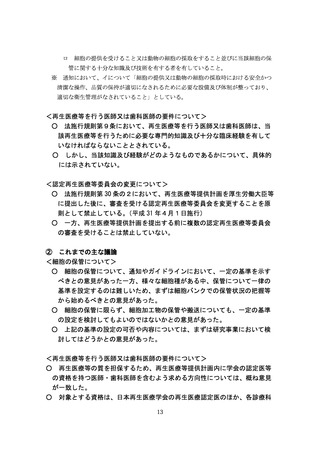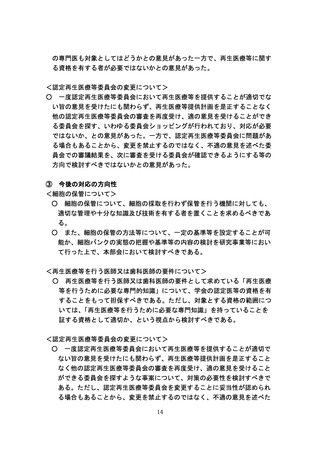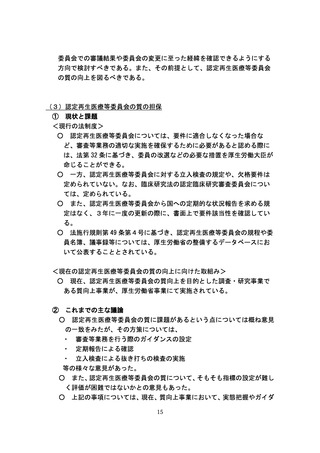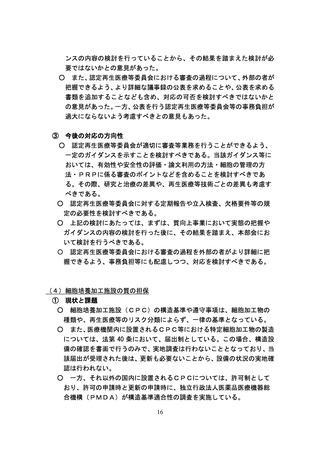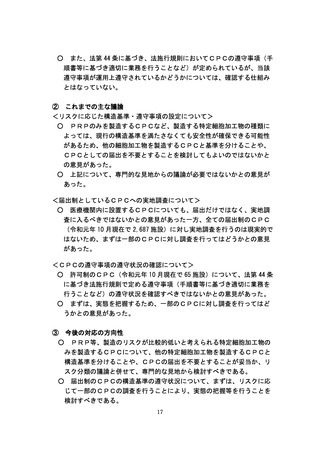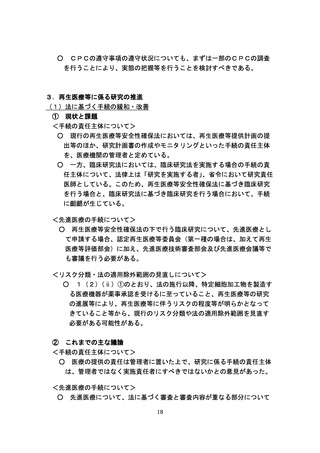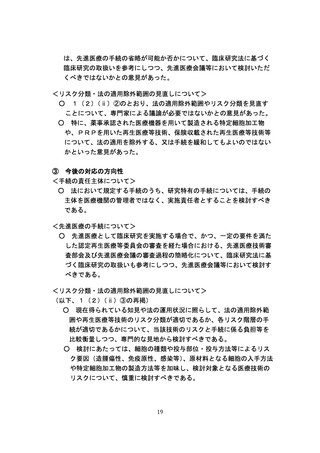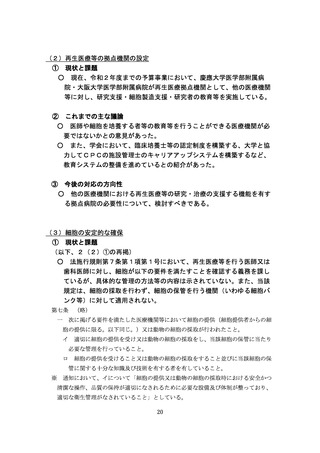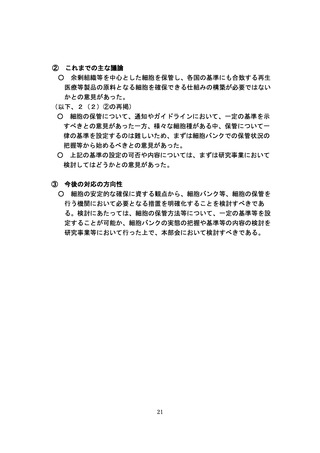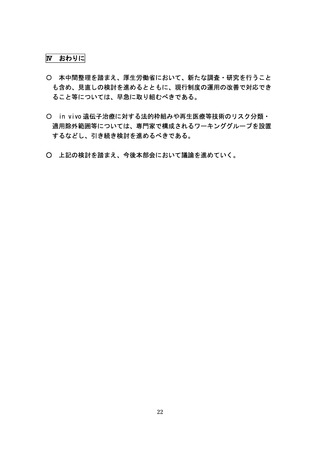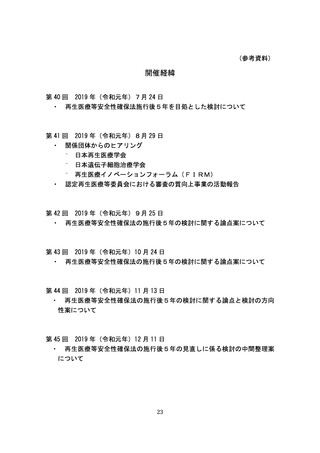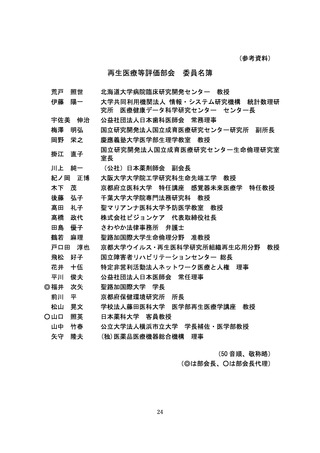よむ、つかう、まなぶ。
再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
は、先進医療の手続の省略が可能か否かについて、臨床研究法に基づく
臨床研究の取扱いを参考にしつつ、先進医療会議等において検討いただ
くべきではないかとの意見があった。
<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>
○ 1(2)(ⅱ)②のとおり、法の適用除外範囲やリスク分類を見直す
ことについて、専門家による議論が必要ではないかとの意見があった。
○ 特に、薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物
や、PRPを用いた再生医療等技術、保険収載された再生医療等技術等
について、法の適用を除外する、又は手続を緩和してもよいのではない
かといった意見があった。
③ 今後の対応の方向性
<手続の責任主体について>
○ 法において規定する手続のうち、研究特有の手続については、手続の
主体を医療機関の管理者ではなく、実施責任者とすることを検討すべき
である。
<先進医療の手続について>
○ 先進医療として臨床研究を実施する場合で、かつ、一定の要件を満た
した認定再生医療等委員会の審査を経た場合における、先進医療技術審
査部会及び先進医療会議の審査過程の簡略化について、臨床研究法に基
づく臨床研究の取扱いも参考にしつつ、先進医療会議等において検討す
べきである。
<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>
(以下、1(2)(ⅱ)③の再掲)
○ 現在得られている知見や法の運用状況に照らして、法の適用除外範
囲や再生医療等技術のリスク分類が適切であるか、各リスク階層の手
続が適切であるかについて、当該技術のリスクと手続に係る負担等を
比較衡量しつつ、専門的な見地から検討すべきである。
○ 検討にあたっては、細胞の種類や投与部位・投与方法等によるリス
ク要因(造腫瘍性、免疫原性、感染等)、原材料となる細胞の入手方法
や特定細胞加工物の製造方法等を加味し、検討対象となる医療技術の
リスクについて、慎重に検討すべきである。
19
臨床研究の取扱いを参考にしつつ、先進医療会議等において検討いただ
くべきではないかとの意見があった。
<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>
○ 1(2)(ⅱ)②のとおり、法の適用除外範囲やリスク分類を見直す
ことについて、専門家による議論が必要ではないかとの意見があった。
○ 特に、薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物
や、PRPを用いた再生医療等技術、保険収載された再生医療等技術等
について、法の適用を除外する、又は手続を緩和してもよいのではない
かといった意見があった。
③ 今後の対応の方向性
<手続の責任主体について>
○ 法において規定する手続のうち、研究特有の手続については、手続の
主体を医療機関の管理者ではなく、実施責任者とすることを検討すべき
である。
<先進医療の手続について>
○ 先進医療として臨床研究を実施する場合で、かつ、一定の要件を満た
した認定再生医療等委員会の審査を経た場合における、先進医療技術審
査部会及び先進医療会議の審査過程の簡略化について、臨床研究法に基
づく臨床研究の取扱いも参考にしつつ、先進医療会議等において検討す
べきである。
<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>
(以下、1(2)(ⅱ)③の再掲)
○ 現在得られている知見や法の運用状況に照らして、法の適用除外範
囲や再生医療等技術のリスク分類が適切であるか、各リスク階層の手
続が適切であるかについて、当該技術のリスクと手続に係る負担等を
比較衡量しつつ、専門的な見地から検討すべきである。
○ 検討にあたっては、細胞の種類や投与部位・投与方法等によるリス
ク要因(造腫瘍性、免疫原性、感染等)、原材料となる細胞の入手方法
や特定細胞加工物の製造方法等を加味し、検討対象となる医療技術の
リスクについて、慎重に検討すべきである。
19