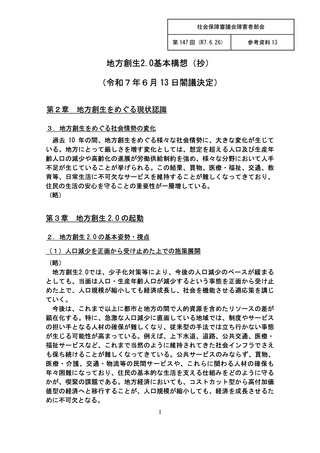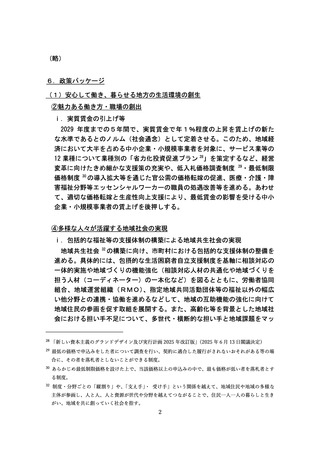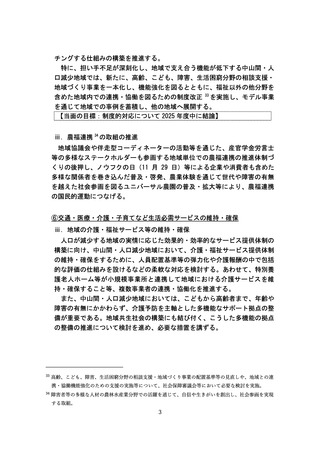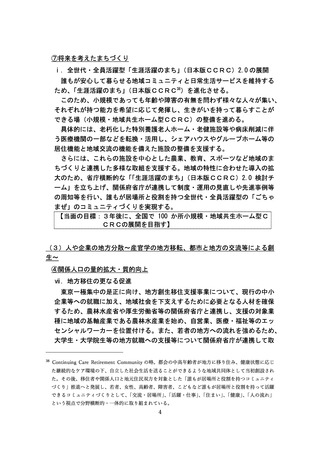よむ、つかう、まなぶ。
参考資料13 地方創生2.0基本構想(抄) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
社会保障審議会障害者部会
第 147 回(R7.6.26)
参考資料 13
地方創生2.0基本構想(抄)
(令和7年6月 13 日閣議決定)
第2章 地方創生をめぐる現状認識
3.地方創生をめぐる社会情勢の変化
過去 10 年の間、地方創生をめぐる様々な社会情勢に、大きな変化が生じて
いる。地方にとって厳しさを増す変化としては、想定を超える人口及び生産年
齢人口の減少や高齢化の進展が労働供給制約を強め、様々な分野において人手
不足が生じていることが挙げられる。この結果、買物、医療・福祉、交通、教
育等、日常生活に不可欠なサービスを維持することが難しくなってきており、
住民の生活の安心を守ることの重要性が一層増している。
(略)
第3章 地方創生 2.0 の起動
2.地方創生 2.0 の基本姿勢・視点
(1)人口減少を正面から受け止めた上での施策展開
(略)
地方創生2.0では、少子化対策等により、今後の人口減少のペースが緩まる
としても、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止
めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じ
ていく。
今後は、これまで以上に都市と地方の間で人的資源を含めたリソースの差が
顕在化する。特に、急激な人口減少に直面している地域では、制度やサービス
の担い手となる人材の確保が難しくなり、従来型の手法では立ち行かない事態
が生じる可能性が高まっている。例えば、上下水道、道路、公共交通、医療・
福祉サービスなど、これまで当然のように維持されてきた社会インフラでさえ
も保ち続けることが難しくなってきている。公共サービスのみならず、買物、
医療・介護、交通・物流等の民間サービスや、これらに関わる人材の確保も
年々困難になっており、住民の基本的な生活を支える仕組みをどのように守る
かが、喫緊の課題である。地方経済においても、コストカット型から高付加価
値型の経済へと移行することが、人口規模が縮小しても、経済を成長させるた
めに不可欠となる。
1
第 147 回(R7.6.26)
参考資料 13
地方創生2.0基本構想(抄)
(令和7年6月 13 日閣議決定)
第2章 地方創生をめぐる現状認識
3.地方創生をめぐる社会情勢の変化
過去 10 年の間、地方創生をめぐる様々な社会情勢に、大きな変化が生じて
いる。地方にとって厳しさを増す変化としては、想定を超える人口及び生産年
齢人口の減少や高齢化の進展が労働供給制約を強め、様々な分野において人手
不足が生じていることが挙げられる。この結果、買物、医療・福祉、交通、教
育等、日常生活に不可欠なサービスを維持することが難しくなってきており、
住民の生活の安心を守ることの重要性が一層増している。
(略)
第3章 地方創生 2.0 の起動
2.地方創生 2.0 の基本姿勢・視点
(1)人口減少を正面から受け止めた上での施策展開
(略)
地方創生2.0では、少子化対策等により、今後の人口減少のペースが緩まる
としても、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止
めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じ
ていく。
今後は、これまで以上に都市と地方の間で人的資源を含めたリソースの差が
顕在化する。特に、急激な人口減少に直面している地域では、制度やサービス
の担い手となる人材の確保が難しくなり、従来型の手法では立ち行かない事態
が生じる可能性が高まっている。例えば、上下水道、道路、公共交通、医療・
福祉サービスなど、これまで当然のように維持されてきた社会インフラでさえ
も保ち続けることが難しくなってきている。公共サービスのみならず、買物、
医療・介護、交通・物流等の民間サービスや、これらに関わる人材の確保も
年々困難になっており、住民の基本的な生活を支える仕組みをどのように守る
かが、喫緊の課題である。地方経済においても、コストカット型から高付加価
値型の経済へと移行することが、人口規模が縮小しても、経済を成長させるた
めに不可欠となる。
1