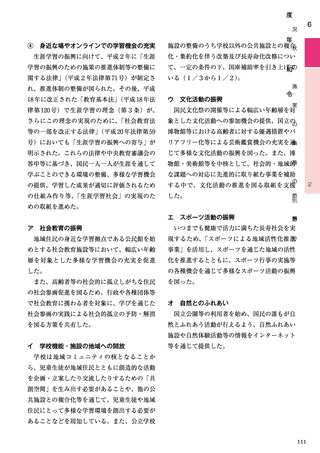よむ、つかう、まなぶ。
3 学習・社会参加 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
| 出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
このため、関係府省庁や地方公共団体・関連
拡大している。こうしたマイナンバー制度の取
団体、ボランティア団体等と連携し、デジタル
組状況について、地方公共団体等とも連携し、
機器・サービスの利用方法、各地で実装されて
国民への周知・広報を行った。
いるデジタルサービス及びマイナンバーカー
また、国全体として金融経済教育を推進する
ド・マイナポータルの利用方法をサポートする
ため、金融経済教育推進機構(J-FLEC)が令
など、国民運動としての「デジタル推進委員」
和6年4月に設立され、同年8月に本格稼働し
の取組を令和4年度にスタートさせ、令和6年
た。J-FLEC における社会保障制度を含む幅広
12 月末時点で 5 万 7,000 人超を任命した。また、
い分野の金融経済教育の取組を支援するなど、
民間企業や地方公共団体等と連携し、スマート
社会保障分野も含めた金融経済教育の充実に取
フォンを利用したオンライン行政手続等に対す
り組んだ。
る助言・相談等を行うデジタル活用支援の講習
会を令和3年度から全国の携帯電話ショップ
等において実施している。令和6年度は、全国
6,000 か所以上で実施した。
③
消費者教育の推進
消費者の自立を支援するために行われる消費
生活に関する教育(消費者教育)は、幼児期か
ら高齢期までの各段階に応じて体系的に行われ
②
社会保障教育及び金融経済教育の推進
中学校学習指導要領の社会科や技術・家庭科、
の特性に配慮した適切な方法で行わなければな
高等学校学習指導要領の公民科や家庭科におい
らない。こうした消費者教育を総合的かつ一体
て、少子高齢社会における社会保障の充実・安
的に推進するため、平成 24 年 12 月に「消費者
定化や介護に関する内容等が明記されているこ
教育の推進に関する法律」(平成 24 年法律第 61
とを踏まえ、その趣旨の徹底を図るとともに、
号)が施行され、令和5年3月 28 日には、同
令和3年度に新たに作成した教材等について内
法に基づく「消費者教育の推進に関する基本的
容の充実や効果的な周知を図る等、若い世代が
な方針」の2回目の変更の閣議決定を行った。
高齢社会を理解する力を養うために、教育現場
同方針に基づき、消費者教育コーディネーター
において社会保障教育が正しく教えられる環境
の配置・育成の支援や、地域、家庭等の様々な
づくりに取り組んだ。
場を活用した消費者教育の推進を図っている。
より公平・公正な社会保障制度の基盤となる
令和6年度は、体験型教材「鍛えよう、消費者
マイナンバー制度については、平成 29 年 11 月
力 気づく・断る・相談する」を活用したモデ
から情報連携の本格運用が開始され、各種年金
ル事業の実施や、
「高齢消費者・障がい消費者
関係手続のほか、介護保険を始め高齢者福祉に
見守りネットワーク連絡協議会」等において周
関する手続において従来必要とされていた住民
知・広報を行った。また、高齢者向け消費者教
票の写しや課税証明書、年金証書等の書類が不
育教材とその活用事例集については、
「消費者
要となっている。令和6年8月からは戸籍関
教育ポータルサイト」に取組事例を掲載するな
係情報の情報連携の本格運用も開始され、本格
ど、地方公共団体での啓発講座等での活用を促
運用の対象事務手続数は、平成 29 年 11 月の約
進した。
900 件から令和6年 11 月には約 3,300 件と順次
110
るとともに、年齢、障害の有無その他の消費者
拡大している。こうしたマイナンバー制度の取
団体、ボランティア団体等と連携し、デジタル
組状況について、地方公共団体等とも連携し、
機器・サービスの利用方法、各地で実装されて
国民への周知・広報を行った。
いるデジタルサービス及びマイナンバーカー
また、国全体として金融経済教育を推進する
ド・マイナポータルの利用方法をサポートする
ため、金融経済教育推進機構(J-FLEC)が令
など、国民運動としての「デジタル推進委員」
和6年4月に設立され、同年8月に本格稼働し
の取組を令和4年度にスタートさせ、令和6年
た。J-FLEC における社会保障制度を含む幅広
12 月末時点で 5 万 7,000 人超を任命した。また、
い分野の金融経済教育の取組を支援するなど、
民間企業や地方公共団体等と連携し、スマート
社会保障分野も含めた金融経済教育の充実に取
フォンを利用したオンライン行政手続等に対す
り組んだ。
る助言・相談等を行うデジタル活用支援の講習
会を令和3年度から全国の携帯電話ショップ
等において実施している。令和6年度は、全国
6,000 か所以上で実施した。
③
消費者教育の推進
消費者の自立を支援するために行われる消費
生活に関する教育(消費者教育)は、幼児期か
ら高齢期までの各段階に応じて体系的に行われ
②
社会保障教育及び金融経済教育の推進
中学校学習指導要領の社会科や技術・家庭科、
の特性に配慮した適切な方法で行わなければな
高等学校学習指導要領の公民科や家庭科におい
らない。こうした消費者教育を総合的かつ一体
て、少子高齢社会における社会保障の充実・安
的に推進するため、平成 24 年 12 月に「消費者
定化や介護に関する内容等が明記されているこ
教育の推進に関する法律」(平成 24 年法律第 61
とを踏まえ、その趣旨の徹底を図るとともに、
号)が施行され、令和5年3月 28 日には、同
令和3年度に新たに作成した教材等について内
法に基づく「消費者教育の推進に関する基本的
容の充実や効果的な周知を図る等、若い世代が
な方針」の2回目の変更の閣議決定を行った。
高齢社会を理解する力を養うために、教育現場
同方針に基づき、消費者教育コーディネーター
において社会保障教育が正しく教えられる環境
の配置・育成の支援や、地域、家庭等の様々な
づくりに取り組んだ。
場を活用した消費者教育の推進を図っている。
より公平・公正な社会保障制度の基盤となる
令和6年度は、体験型教材「鍛えよう、消費者
マイナンバー制度については、平成 29 年 11 月
力 気づく・断る・相談する」を活用したモデ
から情報連携の本格運用が開始され、各種年金
ル事業の実施や、
「高齢消費者・障がい消費者
関係手続のほか、介護保険を始め高齢者福祉に
見守りネットワーク連絡協議会」等において周
関する手続において従来必要とされていた住民
知・広報を行った。また、高齢者向け消費者教
票の写しや課税証明書、年金証書等の書類が不
育教材とその活用事例集については、
「消費者
要となっている。令和6年8月からは戸籍関
教育ポータルサイト」に取組事例を掲載するな
係情報の情報連携の本格運用も開始され、本格
ど、地方公共団体での啓発講座等での活用を促
運用の対象事務手続数は、平成 29 年 11 月の約
進した。
900 件から令和6年 11 月には約 3,300 件と順次
110
るとともに、年齢、障害の有無その他の消費者