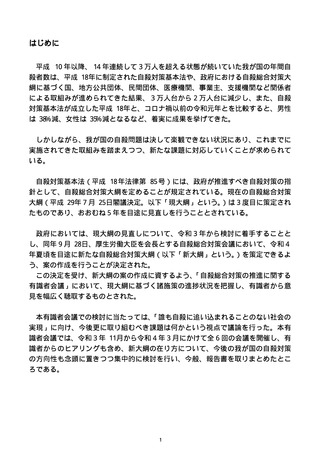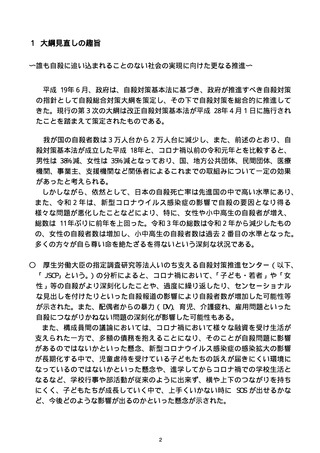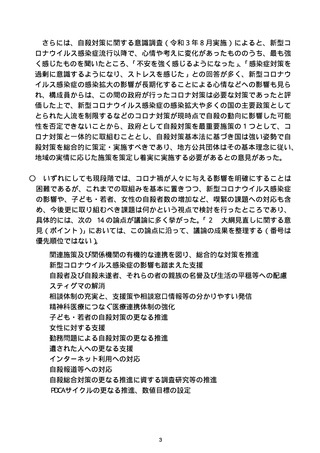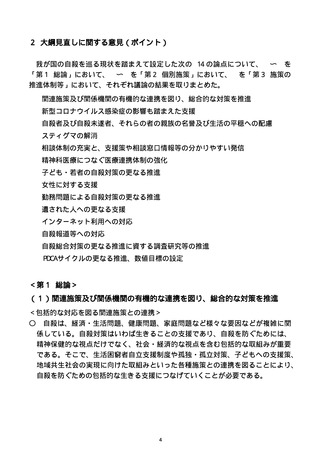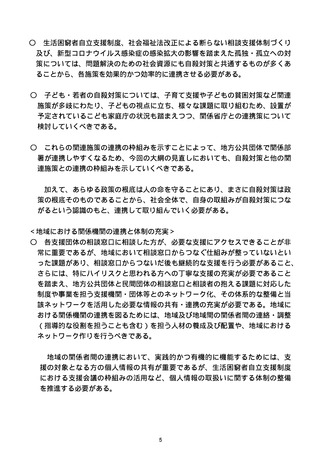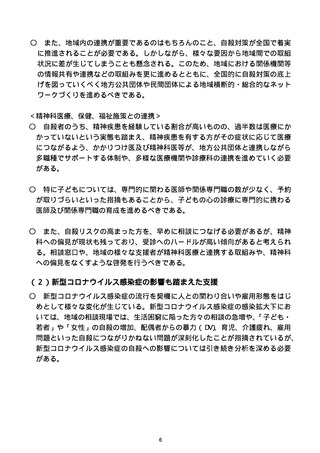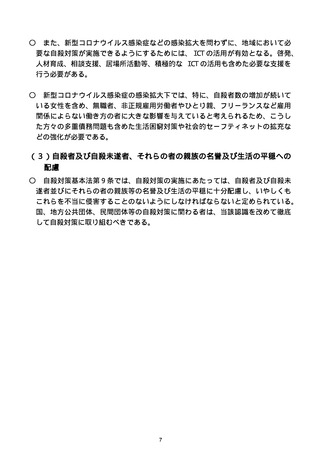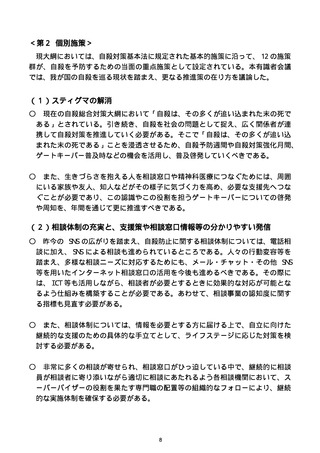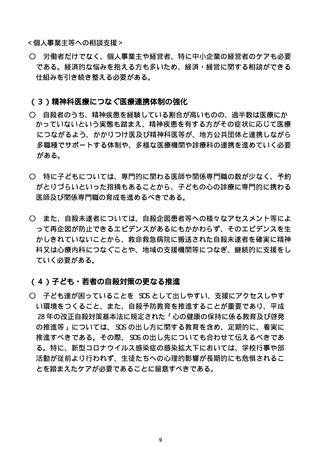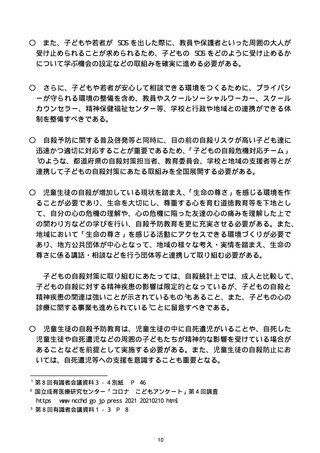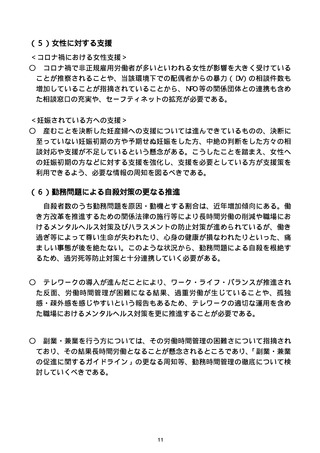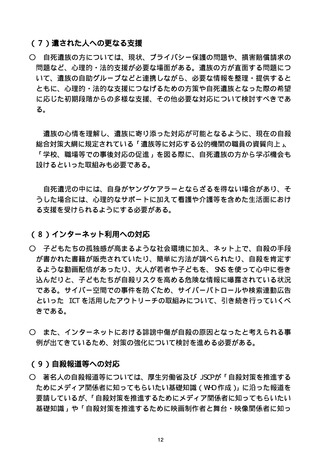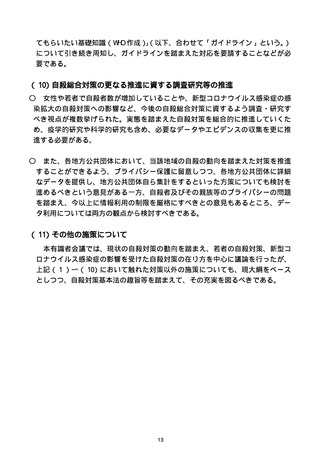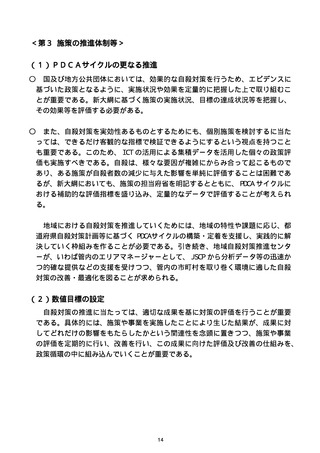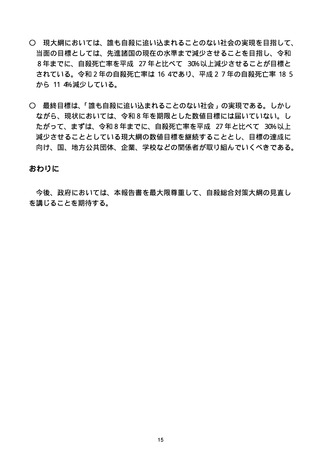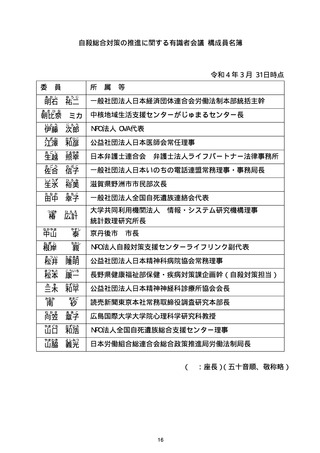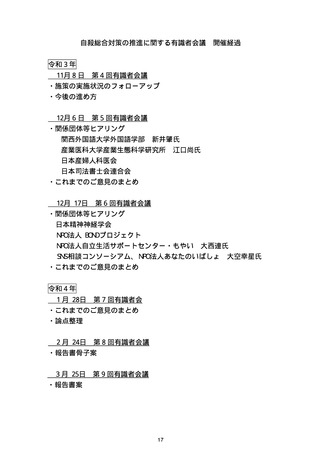よむ、つかう、まなぶ。
「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」の報告書 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/jisatsusougoutaisaku_houkokusyo220415.html |
| 出典情報 | 「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」の報告書について(4/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
<第2 個別施策>
現大綱においては、自殺対策基本法に規定された基本的施策に沿って、12 の施策
群が、自殺を予防するための当面の重点施策として設定されている。本有識者会議
では、我が国の自殺を巡る現状を踏まえ、更なる推進策の在り方を議論した。
(1)スティグマの解消
〇
現在の自殺総合対策大綱において「自殺は、その多くが追い込まれた末の死で
ある」とされている。引き続き、自殺を社会の問題として捉え、広く関係者が連
携して自殺対策を推進していく必要がある。そこで「自殺は、その多くが追い込
まれた末の死である」ことを浸透させるため、自殺予防週間や自殺対策強化月間、
ゲートキーパー普及時などの機会を活用し、普及啓発していくべきである。
〇
また、生きづらさを抱える人を相談窓口や精神科医療につなぐためには、周囲
にいる家族や友人、知人などがその様子に気づく力を高め、必要な支援先へつな
ぐことが必要であり、この認識やこの役割を担うゲートキーパーについての啓発
や周知を、年間を通じて更に推進すべきである。
(2)相談体制の充実と、支援策や相談窓口情報等の分かりやすい発信
〇 昨今の SNS の広がりを踏まえ、自殺防止に関する相談体制については、電話相
談に加え、SNS による相談も進められているところである。人々の行動変容等を
踏まえ、多様な相談ニーズに対応するためにも、メール・チャット・その他 SNS
等を用いたインターネット相談窓口の活用を今後も進めるべきである。その際に
は、ICT 等も活用しながら、相談者が必要とするときに効果的な対応が可能とな
るよう仕組みを構築することが必要である。あわせて、相談事業の認知度に関す
る指標も見直す必要がある。
〇
また、相談体制については、情報を必要とする方に届ける上で、自立に向けた
継続的な支援のための具体的な手立てとして、ライフステージに応じた対策を検
討する必要がある。
〇
非常に多くの相談が寄せられ、相談窓口がひっ迫している中で、継続的に相談
員が相談者に寄り添いながら適切に相談にあたれるよう各相談機関において、ス
ーパーバイザーの役割を果たす専門職の配置等の組織的なフォローにより、継続
的な実施体制を確保する必要がある。
8
現大綱においては、自殺対策基本法に規定された基本的施策に沿って、12 の施策
群が、自殺を予防するための当面の重点施策として設定されている。本有識者会議
では、我が国の自殺を巡る現状を踏まえ、更なる推進策の在り方を議論した。
(1)スティグマの解消
〇
現在の自殺総合対策大綱において「自殺は、その多くが追い込まれた末の死で
ある」とされている。引き続き、自殺を社会の問題として捉え、広く関係者が連
携して自殺対策を推進していく必要がある。そこで「自殺は、その多くが追い込
まれた末の死である」ことを浸透させるため、自殺予防週間や自殺対策強化月間、
ゲートキーパー普及時などの機会を活用し、普及啓発していくべきである。
〇
また、生きづらさを抱える人を相談窓口や精神科医療につなぐためには、周囲
にいる家族や友人、知人などがその様子に気づく力を高め、必要な支援先へつな
ぐことが必要であり、この認識やこの役割を担うゲートキーパーについての啓発
や周知を、年間を通じて更に推進すべきである。
(2)相談体制の充実と、支援策や相談窓口情報等の分かりやすい発信
〇 昨今の SNS の広がりを踏まえ、自殺防止に関する相談体制については、電話相
談に加え、SNS による相談も進められているところである。人々の行動変容等を
踏まえ、多様な相談ニーズに対応するためにも、メール・チャット・その他 SNS
等を用いたインターネット相談窓口の活用を今後も進めるべきである。その際に
は、ICT 等も活用しながら、相談者が必要とするときに効果的な対応が可能とな
るよう仕組みを構築することが必要である。あわせて、相談事業の認知度に関す
る指標も見直す必要がある。
〇
また、相談体制については、情報を必要とする方に届ける上で、自立に向けた
継続的な支援のための具体的な手立てとして、ライフステージに応じた対策を検
討する必要がある。
〇
非常に多くの相談が寄せられ、相談窓口がひっ迫している中で、継続的に相談
員が相談者に寄り添いながら適切に相談にあたれるよう各相談機関において、ス
ーパーバイザーの役割を果たす専門職の配置等の組織的なフォローにより、継続
的な実施体制を確保する必要がある。
8