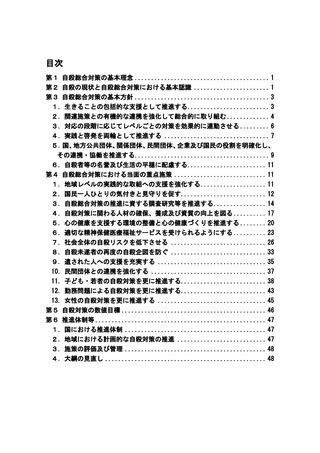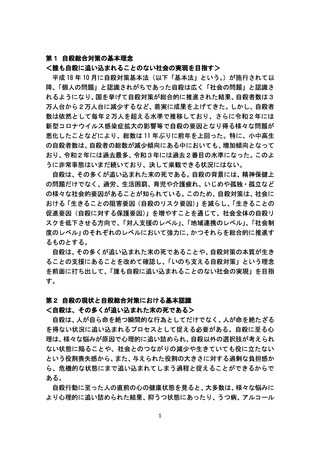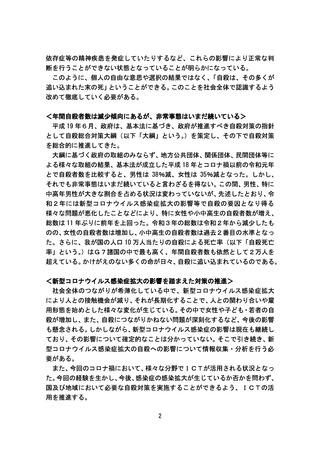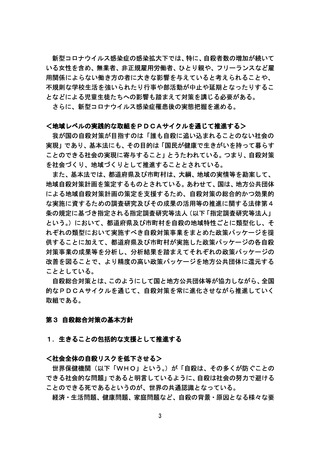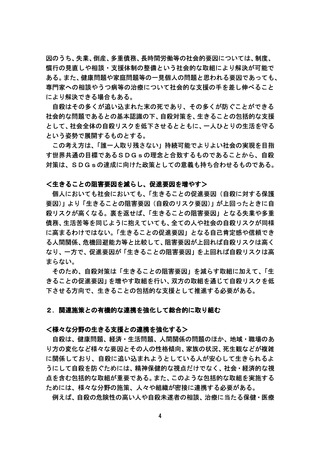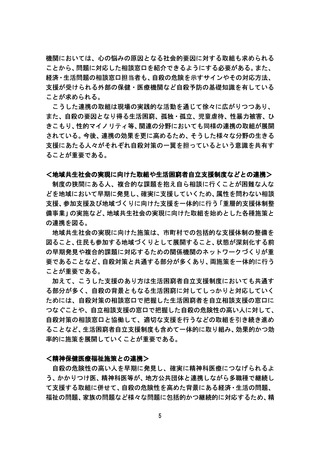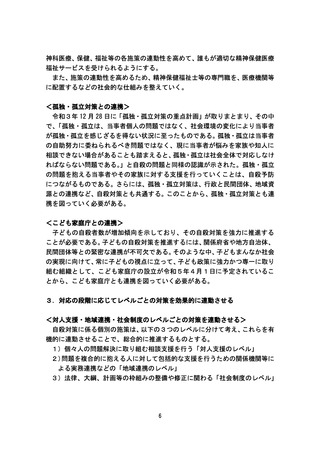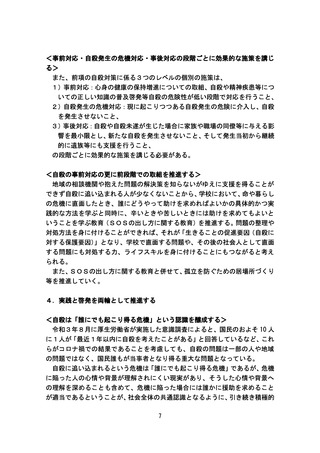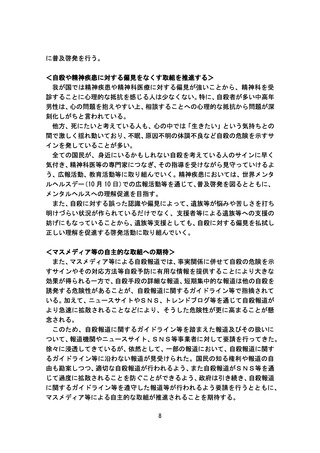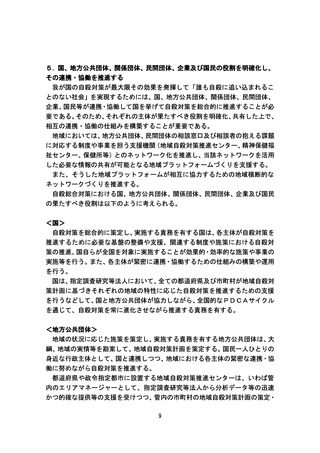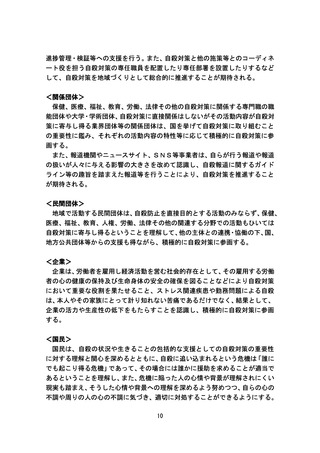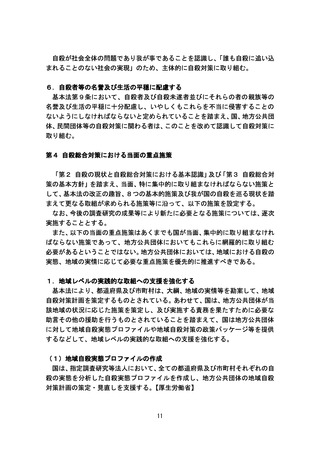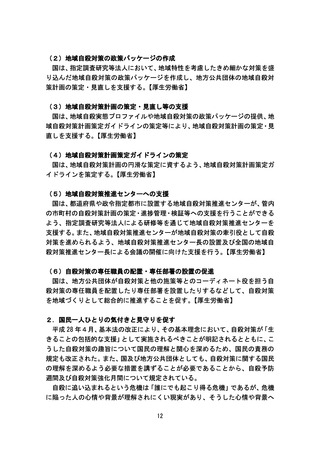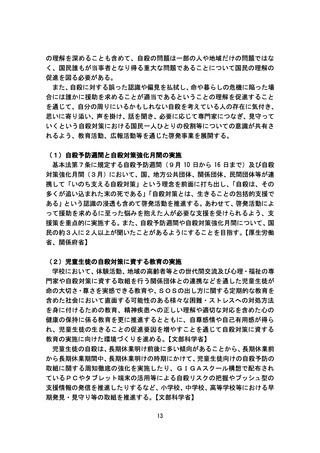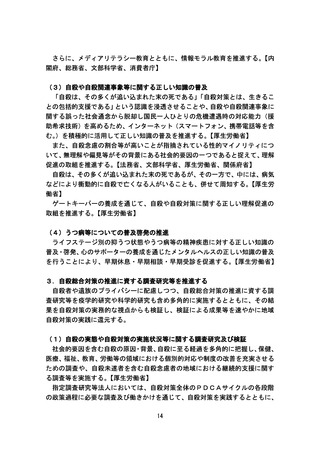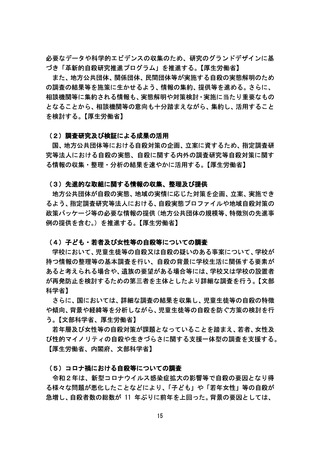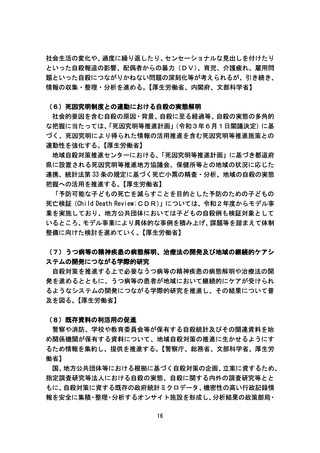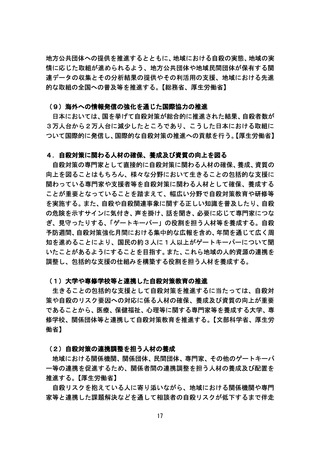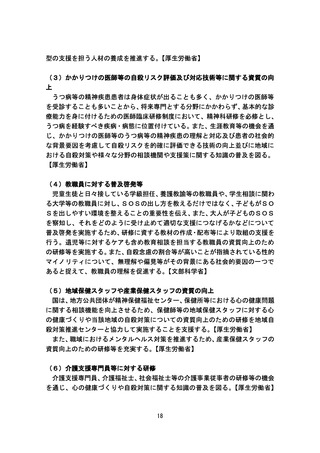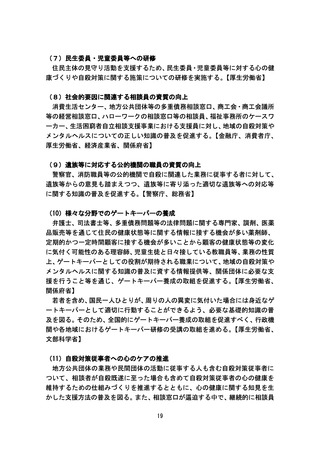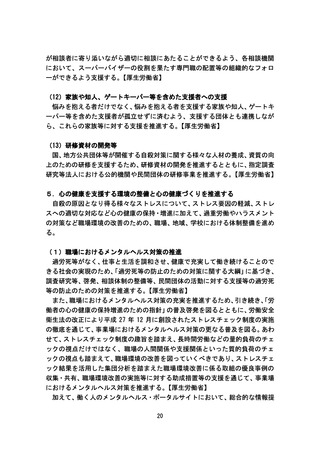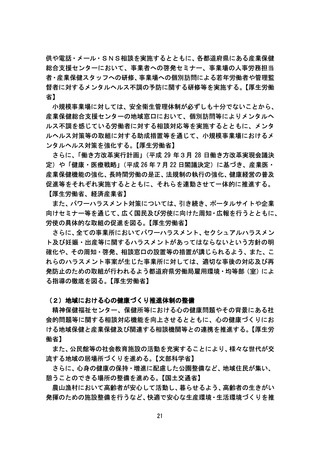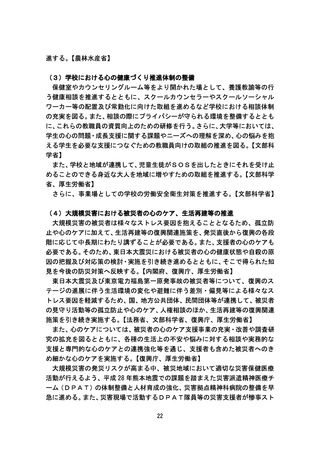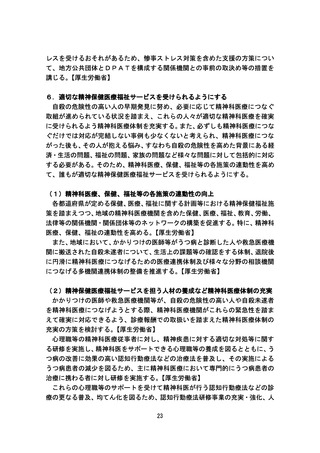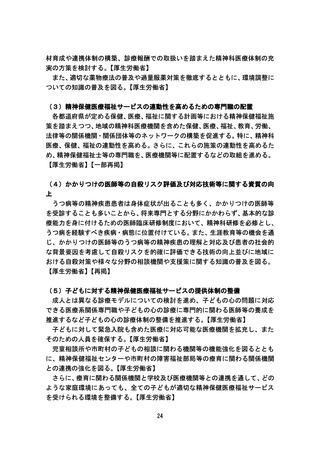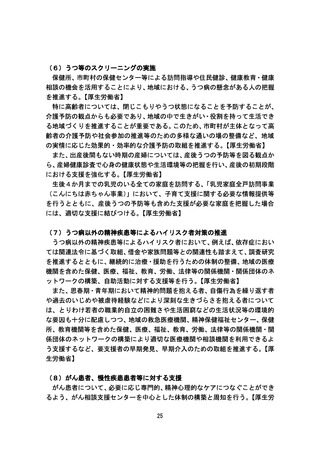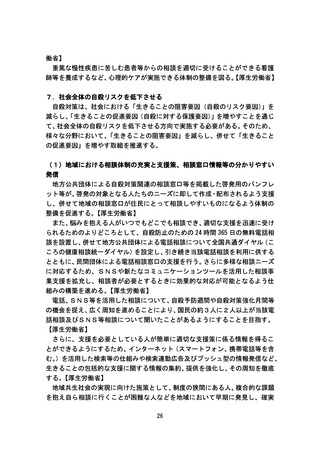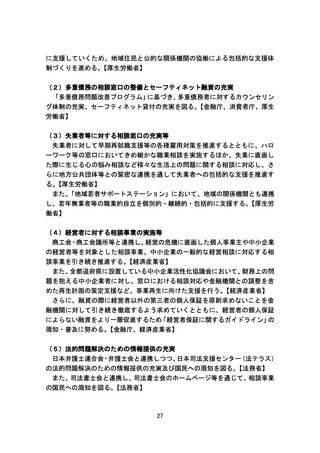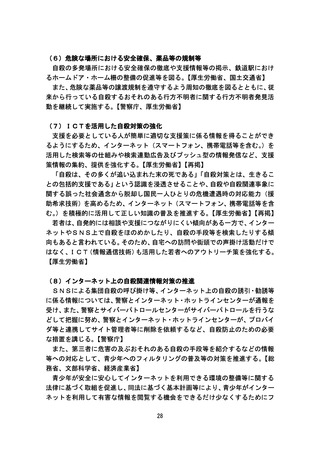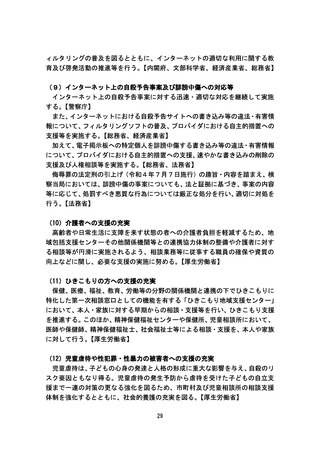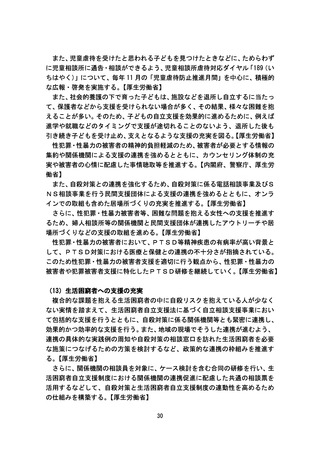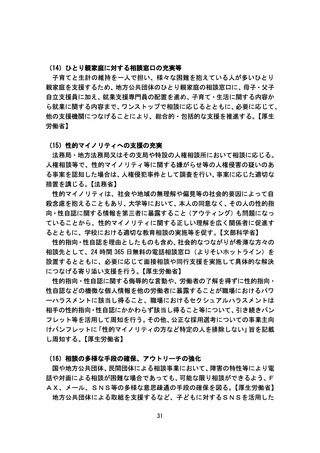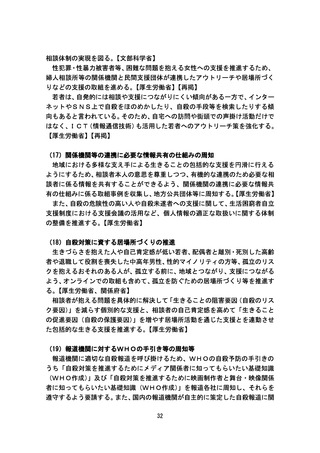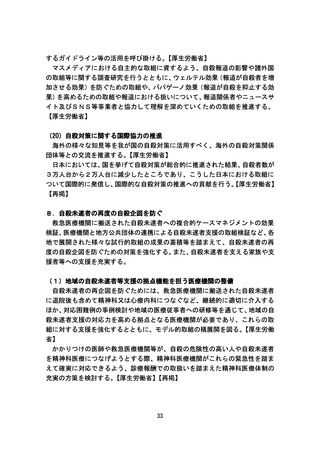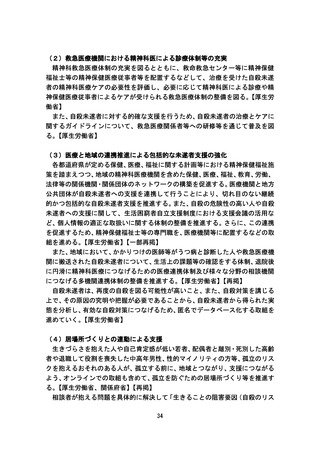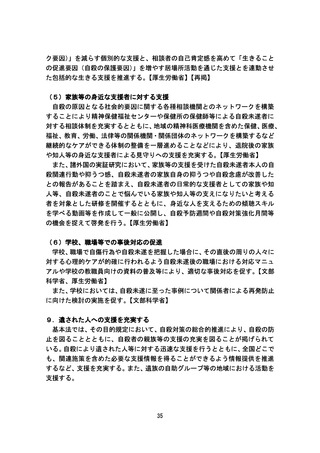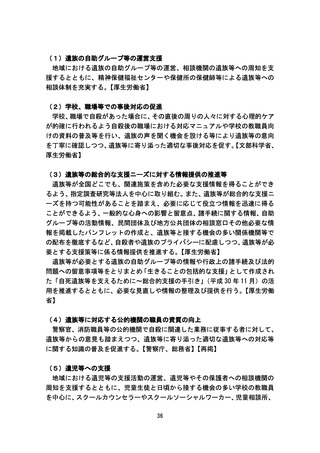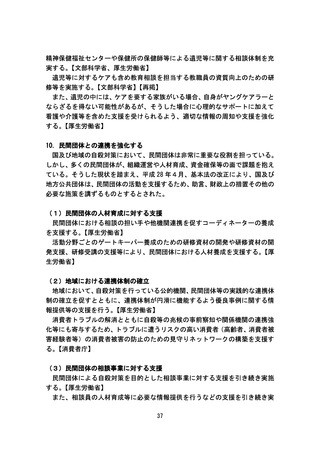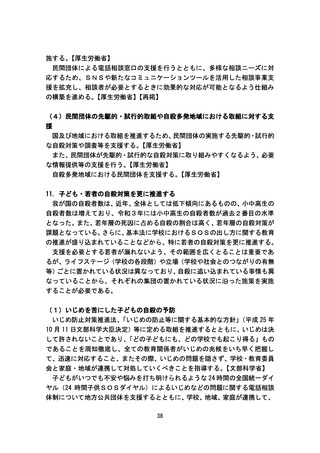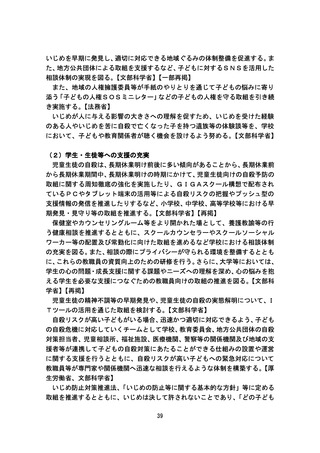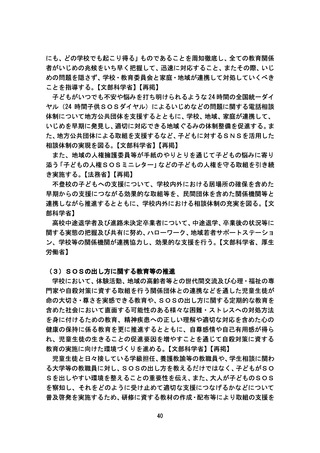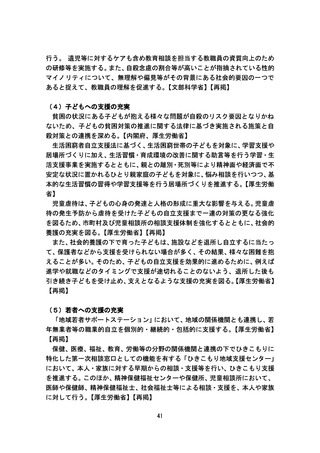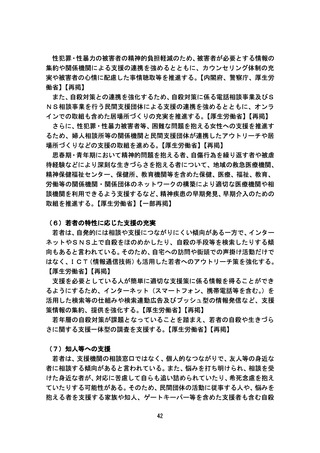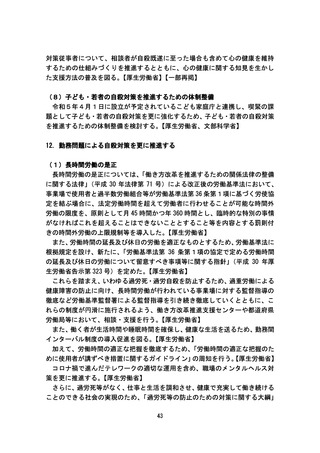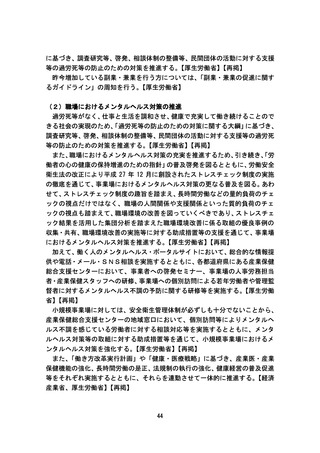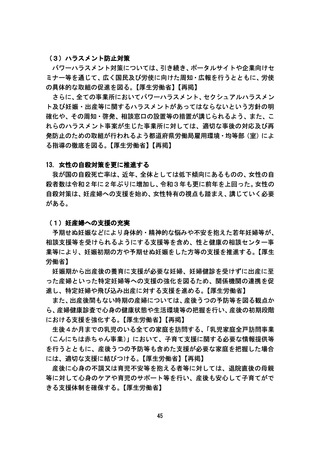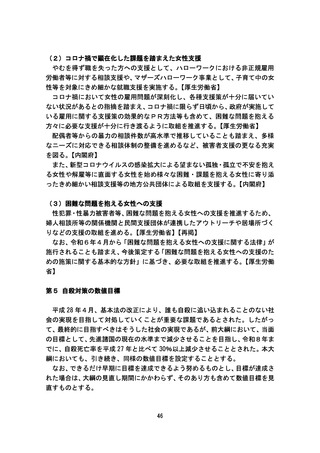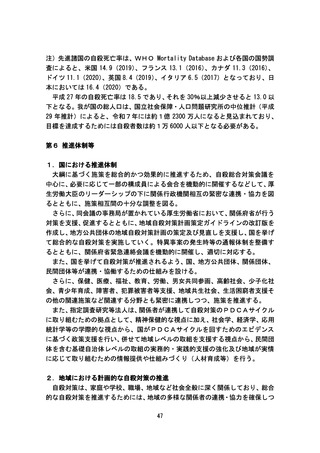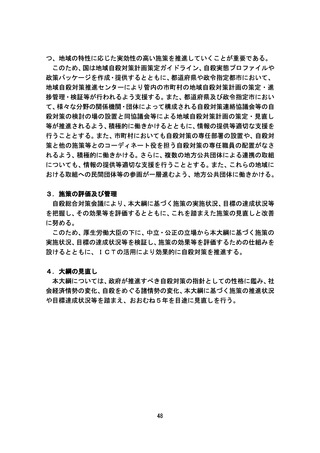よむ、つかう、まなぶ。
参考3 自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html |
| 出典情報 | 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
因のうち、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度、
慣行の見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組により解決が可能で
ある。また、健康問題や家庭問題等の一見個人の問題と思われる要因であっても、
専門家への相談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸べること
により解決できる場合もある。
自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる
社会的な問題であるとの基本認識の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援
として、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守る
という姿勢で展開するものとする。
この考え方は、
「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指
す世界共通の目標であるSDGsの理念と合致するものであることから、自殺
対策は、SDGsの達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるものである。
<生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす>
個人においても社会においても、
「生きることの促進要因(自殺に対する保護
要因)」より「生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)」が上回ったときに自
殺リスクが高くなる。裏を返せば、
「生きることの阻害要因」となる失業や多重
債務、生活苦等を同じように抱えていても、全ての人や社会の自殺リスクが同様
に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上回れば自殺リスクは高く
なり、一方で、促進要因が「生きることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高
まらない。
そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、
「生
きることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低
下させる方向で、生きることの包括的な支援として推進する必要がある。
2.関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
<様々な分野の生きる支援との連携を強化する>
自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあ
り方の変化など様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑
に関係しており、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるよ
うにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視
点を含む包括的な取組が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要がある。
例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、治療に当たる保健・医療
4
慣行の見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組により解決が可能で
ある。また、健康問題や家庭問題等の一見個人の問題と思われる要因であっても、
専門家への相談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸べること
により解決できる場合もある。
自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる
社会的な問題であるとの基本認識の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援
として、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守る
という姿勢で展開するものとする。
この考え方は、
「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指
す世界共通の目標であるSDGsの理念と合致するものであることから、自殺
対策は、SDGsの達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるものである。
<生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす>
個人においても社会においても、
「生きることの促進要因(自殺に対する保護
要因)」より「生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)」が上回ったときに自
殺リスクが高くなる。裏を返せば、
「生きることの阻害要因」となる失業や多重
債務、生活苦等を同じように抱えていても、全ての人や社会の自殺リスクが同様
に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上回れば自殺リスクは高く
なり、一方で、促進要因が「生きることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高
まらない。
そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、
「生
きることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低
下させる方向で、生きることの包括的な支援として推進する必要がある。
2.関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
<様々な分野の生きる支援との連携を強化する>
自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあ
り方の変化など様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑
に関係しており、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるよ
うにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視
点を含む包括的な取組が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要がある。
例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、治療に当たる保健・医療
4