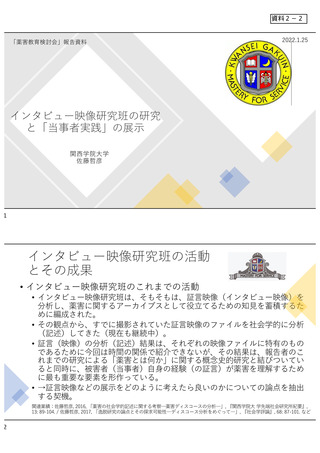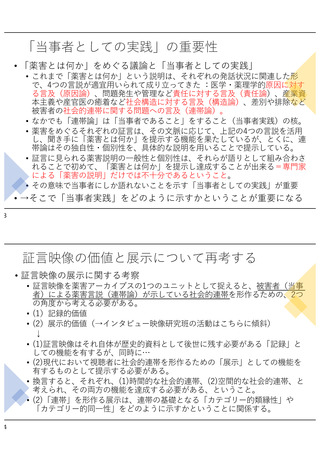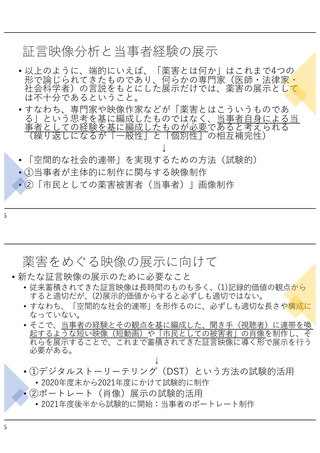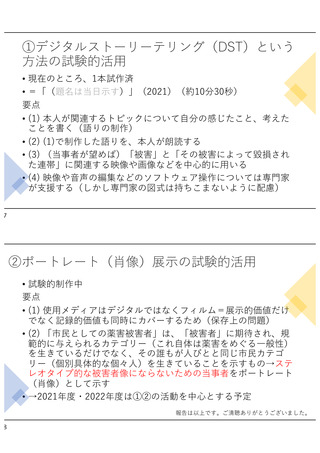よむ、つかう、まなぶ。
資料2-2 インタビュー映像研究班の研究と「当事者実践」の展示 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00005.html |
| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第21回 1/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「当事者としての実践」の重要性
• 「薬害とは何か」をめぐる議論と「当事者としての実践」
• これまで「薬害とは何か」という説明は、それぞれの発話状況に関連した形
で、4つの⾔説が適宜⽤いられて成り⽴ってきた :医学・薬理学的原因に対す
る⾔及(原因論)、問題発⽣や管理など責任に対する⾔及(責任論)、産業資
本主義や産官医の癒着など社会構造に対する⾔及(構造論)、差別や排除など
被害者の社会的連帯に関する問題への⾔及(連帯論)。
• なかでも「連帯論」は「当事者であること」をすること(当事者実践)の核。
• 薬害をめぐるそれぞれの証⾔は、その⽂脈に応じて、上記の4つの⾔説を活⽤
し、聞き⼿に「薬害とは何か」を提⽰する機能を果たしているが、とくに、連
帯論はその独⾃性・個別性を、具体的な説明を⽤いることで提⽰している。
• 証⾔に⾒られる薬害説明の⼀般性と個別性は、それらが語りとして組み合わさ
れることで初めて、「薬害とは何か」を提⽰し達成することが出来る=専⾨家
による「薬害の説明」だけでは不⼗分であるということ。
• その意味で当事者にしか語れないことを⽰す「当事者としての実践」が重要
• →そこで「当事者実践」をどのように⽰すかということが重要になる
3
証⾔映像の価値と展⽰について再考する
• 証⾔映像の展⽰に関する考察
• 証⾔映像を薬害アーカイブスの1つのユニットとして捉えると、被害者(当事
者)による薬害⾔説(連帯論)が⽰している社会的連帯を形作るための、2つ
の⾓度から考える必要がある。
• (1)記録的価値
• (2)展⽰的価値(→インタビュー映像研究班の活動はこちらに傾斜)
↓
• (1)証⾔映像はそれ⾃体が歴史的資料として後世に残す必要がある「記録」と
しての機能を有するが、同時に…
• (2)現代において視聴者に社会的連帯を形作るための「展⽰」としての機能を
有するものとして提⽰する必要がある。
• 換⾔すると、それぞれ、(1)時間的な社会的連帯、(2)空間的な社会的連帯、と
考えられ、その両⽅の機能を達成する必要がある、ということ。
• (2)「連帯」を形作る展⽰は、連帯の基礎となる「カテゴリー的類縁性」や
「カテゴリー的同⼀性」をどのように⽰すかということに関係する。
4
• 「薬害とは何か」をめぐる議論と「当事者としての実践」
• これまで「薬害とは何か」という説明は、それぞれの発話状況に関連した形
で、4つの⾔説が適宜⽤いられて成り⽴ってきた :医学・薬理学的原因に対す
る⾔及(原因論)、問題発⽣や管理など責任に対する⾔及(責任論)、産業資
本主義や産官医の癒着など社会構造に対する⾔及(構造論)、差別や排除など
被害者の社会的連帯に関する問題への⾔及(連帯論)。
• なかでも「連帯論」は「当事者であること」をすること(当事者実践)の核。
• 薬害をめぐるそれぞれの証⾔は、その⽂脈に応じて、上記の4つの⾔説を活⽤
し、聞き⼿に「薬害とは何か」を提⽰する機能を果たしているが、とくに、連
帯論はその独⾃性・個別性を、具体的な説明を⽤いることで提⽰している。
• 証⾔に⾒られる薬害説明の⼀般性と個別性は、それらが語りとして組み合わさ
れることで初めて、「薬害とは何か」を提⽰し達成することが出来る=専⾨家
による「薬害の説明」だけでは不⼗分であるということ。
• その意味で当事者にしか語れないことを⽰す「当事者としての実践」が重要
• →そこで「当事者実践」をどのように⽰すかということが重要になる
3
証⾔映像の価値と展⽰について再考する
• 証⾔映像の展⽰に関する考察
• 証⾔映像を薬害アーカイブスの1つのユニットとして捉えると、被害者(当事
者)による薬害⾔説(連帯論)が⽰している社会的連帯を形作るための、2つ
の⾓度から考える必要がある。
• (1)記録的価値
• (2)展⽰的価値(→インタビュー映像研究班の活動はこちらに傾斜)
↓
• (1)証⾔映像はそれ⾃体が歴史的資料として後世に残す必要がある「記録」と
しての機能を有するが、同時に…
• (2)現代において視聴者に社会的連帯を形作るための「展⽰」としての機能を
有するものとして提⽰する必要がある。
• 換⾔すると、それぞれ、(1)時間的な社会的連帯、(2)空間的な社会的連帯、と
考えられ、その両⽅の機能を達成する必要がある、ということ。
• (2)「連帯」を形作る展⽰は、連帯の基礎となる「カテゴリー的類縁性」や
「カテゴリー的同⼀性」をどのように⽰すかということに関係する。
4