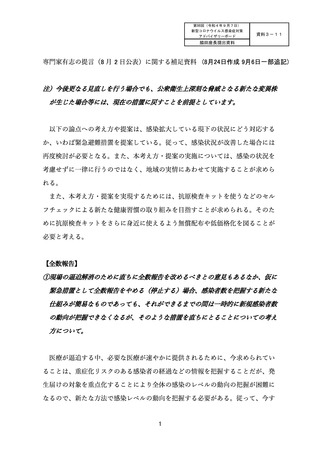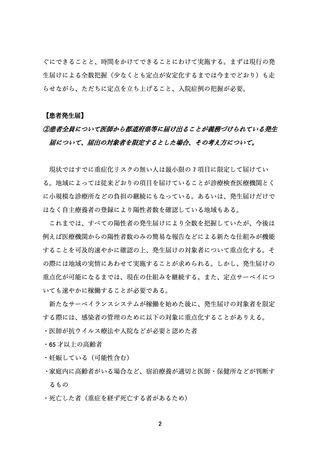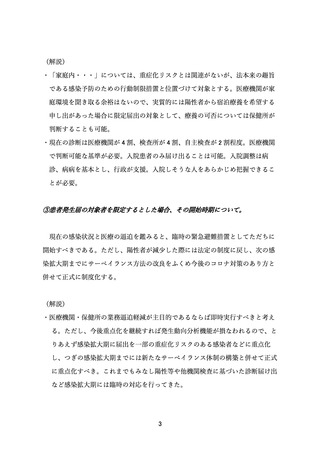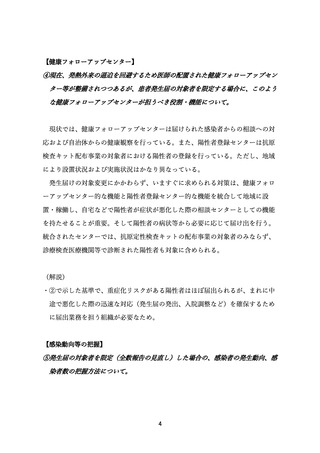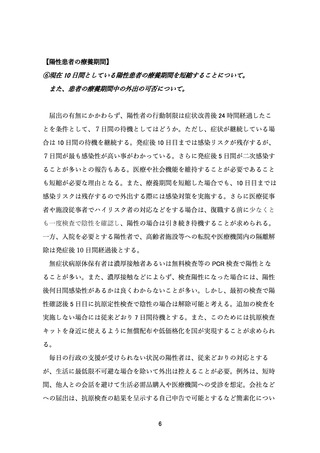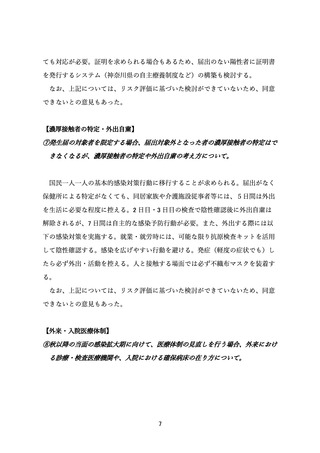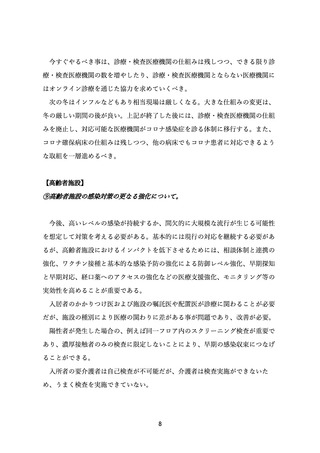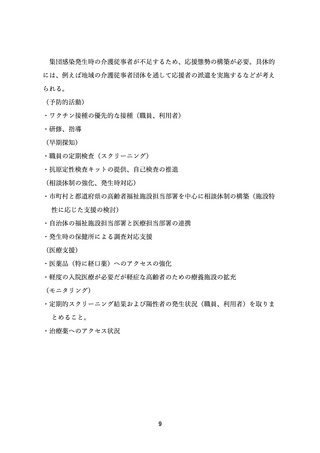よむ、つかう、まなぶ。
資料3-11 脇田座長提出資料 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |
| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
発生届けの対象を、重症化リスクのある感染者などの情報の把握に重点化した
場合には、全体の感染のレベルの動向を発生届けから把握することが困難になる
ため、新たな方法で感染レベルの動向を把握する必要がある。従って、今すぐに
できることと、時間をかけてできることにわけて実施する。
まずは上記②で述べたように全数把握を継続しつつ、並行して定点把握を出来
るだけ速やかに開始するべきである[1]。継続性の観点から、現行のインフルエン
ザ定点医療機関を受診した全症例を週単位で届出(現行のインフルエンザ定点サ
ーベイランスと同様、NESID の活用)とし、新規入院例については全例を HERSYS で届出(ただし届け出項目については現行からの見直しが考えられる)とす
ることが考えられる。「全数か定点か」という考えではなく、諸外国では全数把
握と定点把握を並行して実施しているところが多く、これを踏襲するのがよい。
複合的サーベイランスの観点から、特定の医療機関のネットワークを活用(強
化定点)することが望ましく、これについては現在準備が進められている。主要
民間検査会社の PCR 検査結果を週単位で集計し公開できる体制を出来るだけ速
やかに準備するべきである。また G-MIS のサーベイランス目的での活用を進める
必要がある。こうした複合的サーベイランスについては英国のシステムが参考に
なる[2]。
一方で、以上の複数のデータソースを用いて全患者数の推計方法を準備する必
要があるが、これについては研究班で検討中である。
1. Scott JN McNabb, et al. Transforming Public Health Surveillance: Proactive
Measures for Prevention, Detection, and Response. Elsevier; 第 1 版 (2016/5/2)
2. https://www.gov.uk/government/publications/national-covid-19-surveillancereports/sources-of-covid-19-systems
5
場合には、全体の感染のレベルの動向を発生届けから把握することが困難になる
ため、新たな方法で感染レベルの動向を把握する必要がある。従って、今すぐに
できることと、時間をかけてできることにわけて実施する。
まずは上記②で述べたように全数把握を継続しつつ、並行して定点把握を出来
るだけ速やかに開始するべきである[1]。継続性の観点から、現行のインフルエン
ザ定点医療機関を受診した全症例を週単位で届出(現行のインフルエンザ定点サ
ーベイランスと同様、NESID の活用)とし、新規入院例については全例を HERSYS で届出(ただし届け出項目については現行からの見直しが考えられる)とす
ることが考えられる。「全数か定点か」という考えではなく、諸外国では全数把
握と定点把握を並行して実施しているところが多く、これを踏襲するのがよい。
複合的サーベイランスの観点から、特定の医療機関のネットワークを活用(強
化定点)することが望ましく、これについては現在準備が進められている。主要
民間検査会社の PCR 検査結果を週単位で集計し公開できる体制を出来るだけ速
やかに準備するべきである。また G-MIS のサーベイランス目的での活用を進める
必要がある。こうした複合的サーベイランスについては英国のシステムが参考に
なる[2]。
一方で、以上の複数のデータソースを用いて全患者数の推計方法を準備する必
要があるが、これについては研究班で検討中である。
1. Scott JN McNabb, et al. Transforming Public Health Surveillance: Proactive
Measures for Prevention, Detection, and Response. Elsevier; 第 1 版 (2016/5/2)
2. https://www.gov.uk/government/publications/national-covid-19-surveillancereports/sources-of-covid-19-systems
5