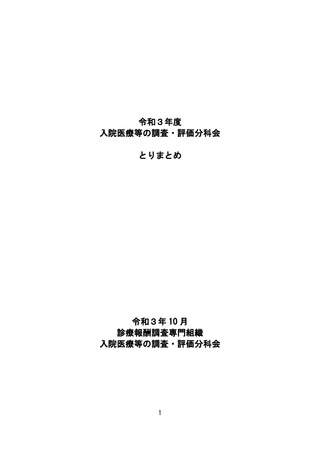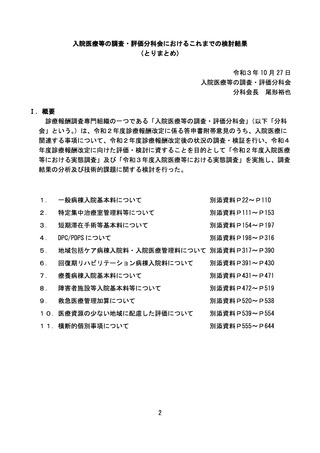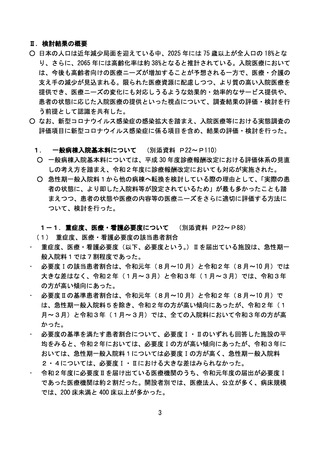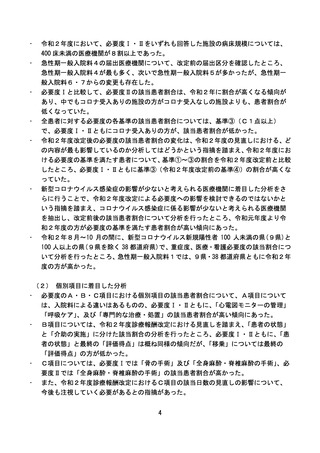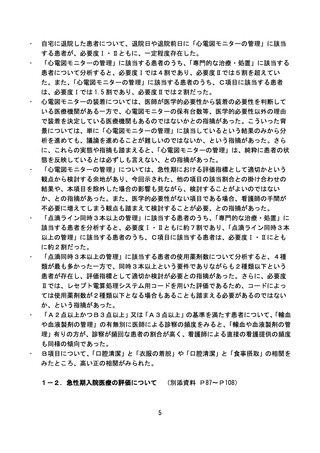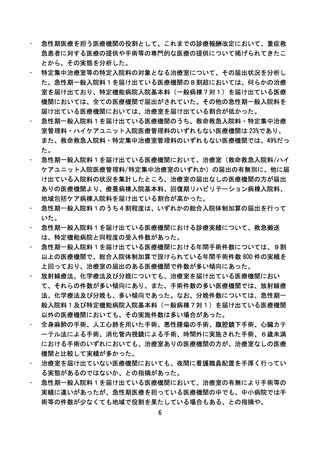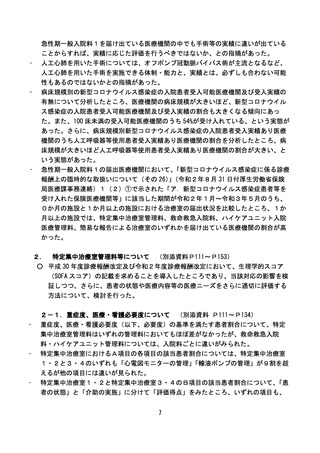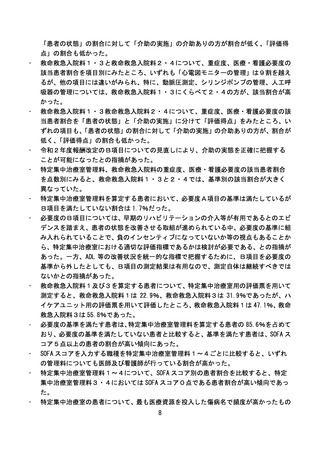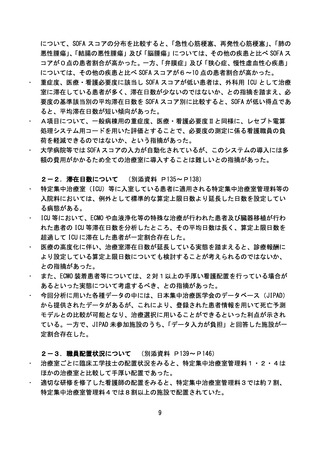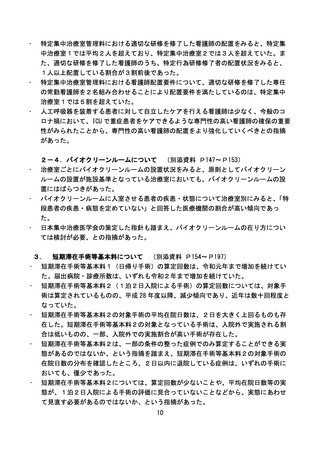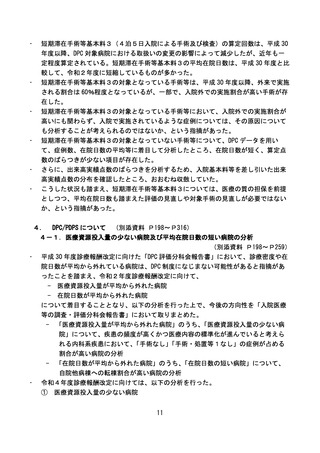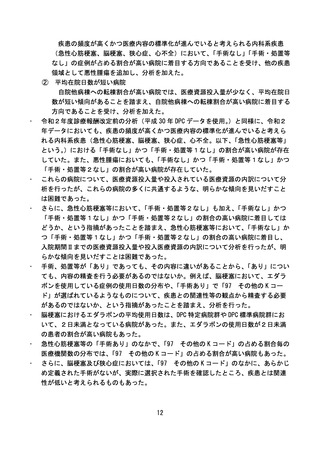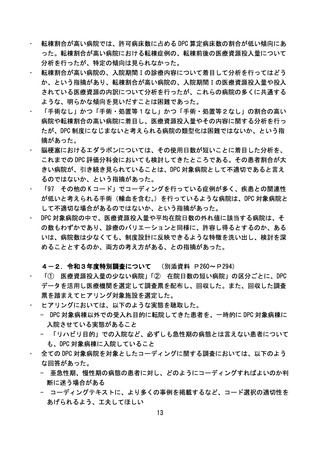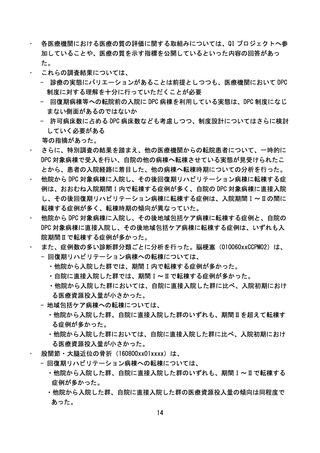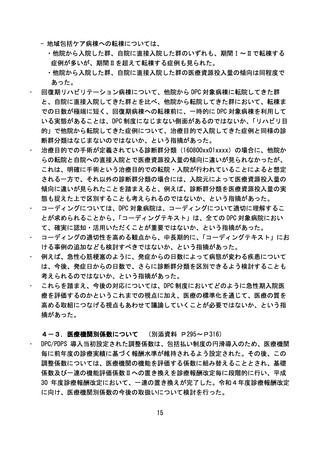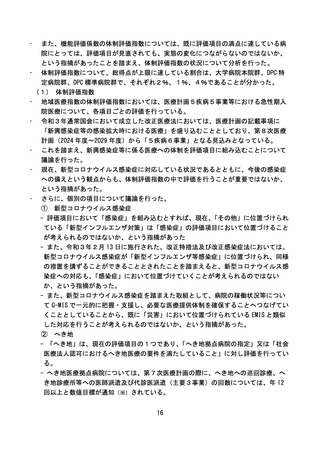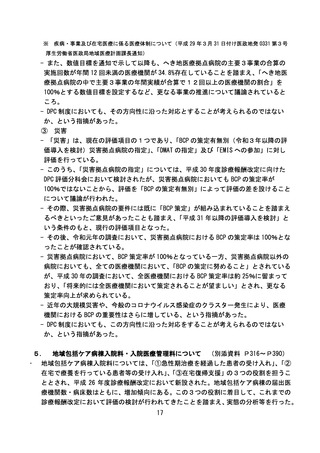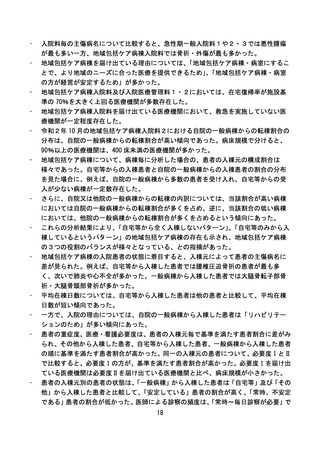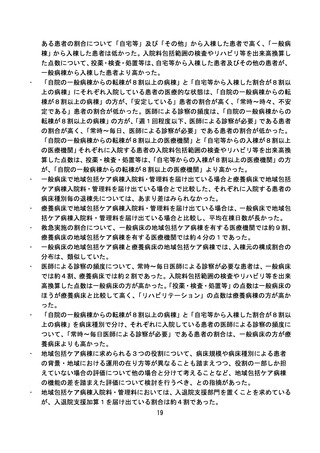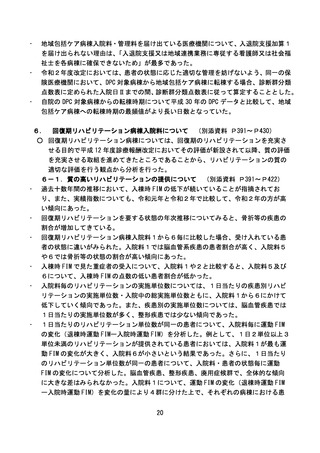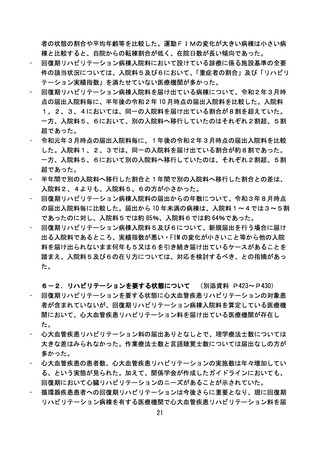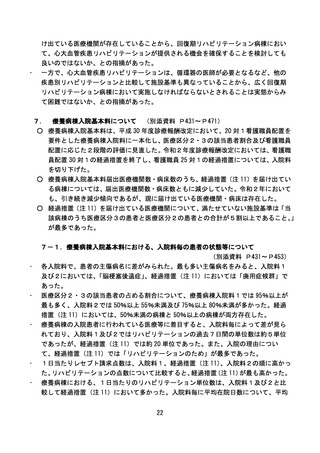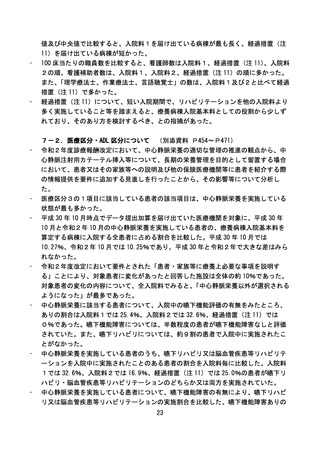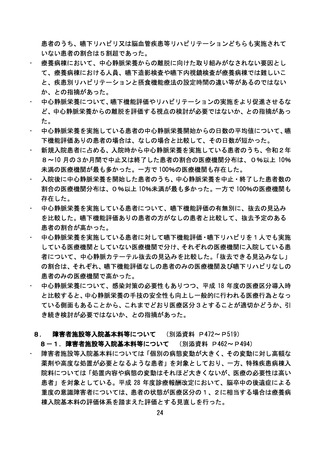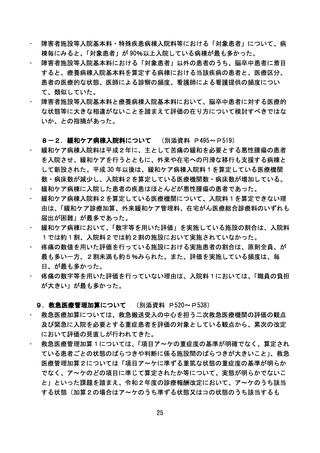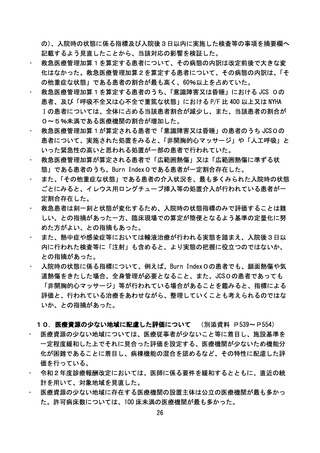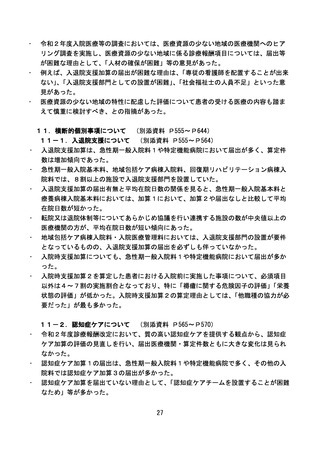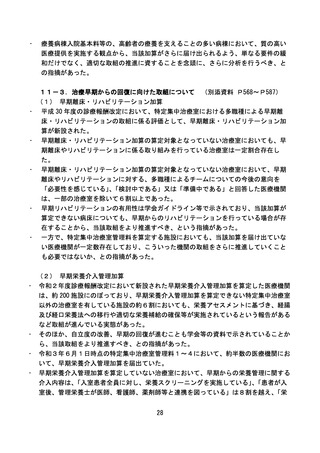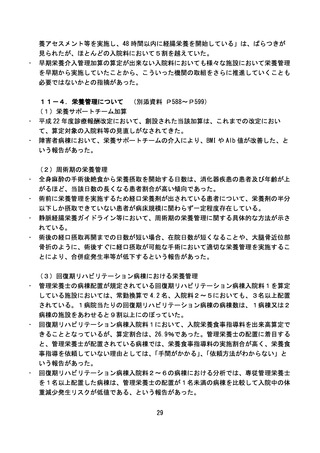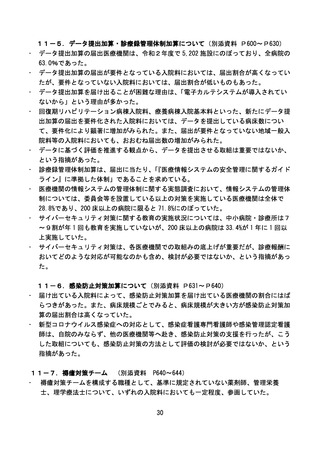よむ、つかう、まなぶ。
とりまとめ (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00032.html |
| 出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度とりまとめ 10/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
自宅に退院した患者について、退院日や退院前日に「心電図モニターの管理」に該当
する患者が、必要度Ⅰ・Ⅱともに、一定程度存在した。
「心電図モニターの管理」に該当する患者のうち、「専門的な治療・処置」に該当する
患者について分析すると、必要度Ⅰでは4割であり、必要度Ⅱでは5割を超えてい
た。また、「心電図モニターの管理」に該当する患者のうち、C項目に該当する患者
は、必要度Ⅰでは 1.5 割であり、必要度Ⅱでは2割だった。
心電図モニターの装着については、医師が医学的必要性から装着の必要性を判断して
いる医療機関がある一方で、心電図モニターの保有台数等、医学的必要性以外の理由
で装着を決定している医療機関もあるのではないかとの指摘があった。こういった背
景については、単に「心電図モニターの管理」に該当しているという結果のみから分
析を進めても、議論を進めることが難しいのではないか、という指摘があった。さら
に、これらの実態や指摘も踏まえると、「心電図モニターの管理」は、純粋に患者の状
態を反映しているとは必ずしも言えない、との指摘があった。
「心電図モニターの管理」については、急性期における評価指標として適切かという
観点から検討する余地があり、今回示された、他の項目の該当割合との掛け合わせの
結果や、本項目を除外した場合の影響も見ながら、検討することがよいのではない
か、との指摘があった。また、医学的必要性がない項目である場合、看護師の手間が
不必要に増えてしまう観点も踏まえて検討することが必要、との指摘があった。
「点滴ライン同時3本以上の管理」に該当する患者のうち、「専門的な治療・処置」に
該当する患者を分析すると、必要度Ⅰ・Ⅱともに約7割であり、「点滴ライン同時3本
以上の管理」に該当する患者のうち、C項目に該当する患者は、必要度Ⅰ・Ⅱにとも
に約2割だった。
「点滴同時3本以上の管理」に該当する患者の使用薬剤数について分析すると、4種
類が最も多かった一方で、同時3本以上という要件でありながらも2種類以下という
患者が存在し、評価指標として適切か検討が必要との指摘があった。さらに、必要度
Ⅱでは、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価であるため、コードによっ
ては使用薬剤数が2種類以下となる場合もあることも踏まえる必要があるのではない
か、という指摘があった。
「A2点以上かつB3点以上」又は「A3点以上」の基準を満たす患者について、
「輸血
や血液製剤の管理」の有無別に医師による診察の頻度をみると、「輸血や血液製剤の管
理」有りの方が、診察が頻回な患者の割合が高く、看護師による直接の看護提供の頻度
も同様の傾向であった。
B項目について、
「口腔清潔」と「衣服の着脱」や「口腔清潔」と「食事摂取」の相関を
みたところ、高い正の相関がみられた。
1-2.急性期入院医療の評価について
(別添資料 P87~P108)
5
自宅に退院した患者について、退院日や退院前日に「心電図モニターの管理」に該当
する患者が、必要度Ⅰ・Ⅱともに、一定程度存在した。
「心電図モニターの管理」に該当する患者のうち、「専門的な治療・処置」に該当する
患者について分析すると、必要度Ⅰでは4割であり、必要度Ⅱでは5割を超えてい
た。また、「心電図モニターの管理」に該当する患者のうち、C項目に該当する患者
は、必要度Ⅰでは 1.5 割であり、必要度Ⅱでは2割だった。
心電図モニターの装着については、医師が医学的必要性から装着の必要性を判断して
いる医療機関がある一方で、心電図モニターの保有台数等、医学的必要性以外の理由
で装着を決定している医療機関もあるのではないかとの指摘があった。こういった背
景については、単に「心電図モニターの管理」に該当しているという結果のみから分
析を進めても、議論を進めることが難しいのではないか、という指摘があった。さら
に、これらの実態や指摘も踏まえると、「心電図モニターの管理」は、純粋に患者の状
態を反映しているとは必ずしも言えない、との指摘があった。
「心電図モニターの管理」については、急性期における評価指標として適切かという
観点から検討する余地があり、今回示された、他の項目の該当割合との掛け合わせの
結果や、本項目を除外した場合の影響も見ながら、検討することがよいのではない
か、との指摘があった。また、医学的必要性がない項目である場合、看護師の手間が
不必要に増えてしまう観点も踏まえて検討することが必要、との指摘があった。
「点滴ライン同時3本以上の管理」に該当する患者のうち、「専門的な治療・処置」に
該当する患者を分析すると、必要度Ⅰ・Ⅱともに約7割であり、「点滴ライン同時3本
以上の管理」に該当する患者のうち、C項目に該当する患者は、必要度Ⅰ・Ⅱにとも
に約2割だった。
「点滴同時3本以上の管理」に該当する患者の使用薬剤数について分析すると、4種
類が最も多かった一方で、同時3本以上という要件でありながらも2種類以下という
患者が存在し、評価指標として適切か検討が必要との指摘があった。さらに、必要度
Ⅱでは、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価であるため、コードによっ
ては使用薬剤数が2種類以下となる場合もあることも踏まえる必要があるのではない
か、という指摘があった。
「A2点以上かつB3点以上」又は「A3点以上」の基準を満たす患者について、
「輸血
や血液製剤の管理」の有無別に医師による診察の頻度をみると、「輸血や血液製剤の管
理」有りの方が、診察が頻回な患者の割合が高く、看護師による直接の看護提供の頻度
も同様の傾向であった。
B項目について、
「口腔清潔」と「衣服の着脱」や「口腔清潔」と「食事摂取」の相関を
みたところ、高い正の相関がみられた。
1-2.急性期入院医療の評価について
(別添資料 P87~P108)
5