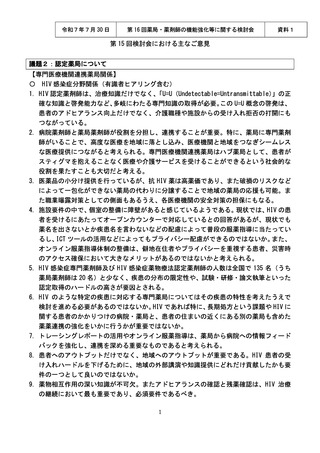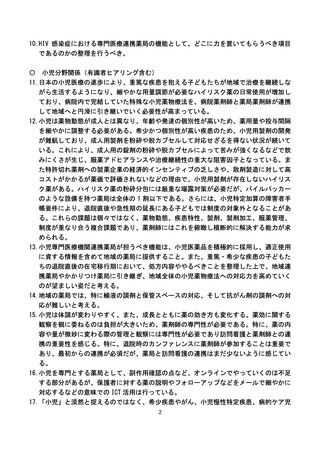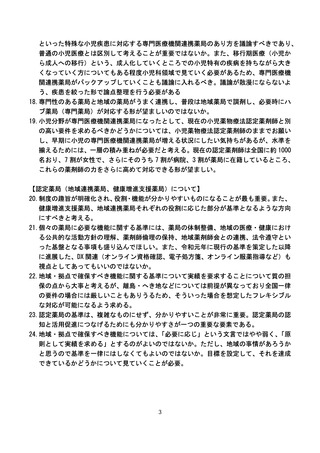よむ、つかう、まなぶ。
資料1_第15回検討会の主なご意見 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60318.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第16回 7/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
10.HIV 感染症における専門医療連携薬局の機能として、どこに力を置いてもらうべき項目
であるのかの整理を行うべき。
〇 小児分野関係(有識者ヒアリング含む)
11.日本の小児医療の進歩により、重篤な疾患を抱える子どもたちが地域で治療を継続しな
がら生活するようになり、細やかな用量調節が必要なハイリスク薬の日常使用が増加し
ており、病院内で完結していた特殊な小児薬物療法を、病院薬剤師と薬局薬剤師が連携
して地域へと円滑に引き継いでいく必要性が高まっている。
12.小児は薬物動態が成人とは異なり、年齢や発達の個別性が高いため、薬用量や投与間隔
を細やかに調整する必要がある。希少かつ個別性が高い疾患のため、小児用製剤の開発
が難航しており、成人用製剤を粉砕や脱カプセルして対応せざるを得ない状況が続いて
いる。これにより、成人用の錠剤の粉砕や脱カプセルによって苦みが強くなるなどで飲
みにくさが生じ、服薬アドヒアランスや治療継続性の重大な阻害因子となっている。ま
た特許切れ薬剤への製薬企業の経済的インセンティブの乏しさや、散剤製造に対して高
コストがかかるが薬価で評価されないなどの理由で、小児用製剤が存在しないハイリス
ク薬がある。ハイリスク薬の粉砕分包には厳重な曝露対策が必要だが、パイルパッカー
のような設備を持つ薬局は全体の 1 割以下である。さらには、小児特定加算の障害者手
帳要件により、退院直後や急性期の延長にある子どもでは制度の対象外となることがあ
る。これらの課題は個々ではなく、薬物動態、疾患特性、製剤、製剤加工、服薬管理、
制度が重なり合う複合課題であり、薬剤師にはこれを俯瞰し横断的に解決する能力が求
められる。
13.小児専門医療機関連携薬局が担うべき機能は、小児医薬品を積極的に採用し、適正使用
に資する情報を含めて地域の薬局に提供すること。また、重篤・希少な疾患の子どもた
ちの退院直後の在宅移行期において、処方内容ややるべきことを整理した上で、地域連
携薬局やかかりつけ薬局に引き継ぎ、地域全体の小児薬物療法への対応力を高めていく
のが望ましい姿だと考える。
14.地域の薬局では、特に輸液の調剤と保管スペースの対応、そして抗がん剤の調剤への対
応が難しいと考える。
15.小児は体調が変わりやすく、また、成長とともに薬の効き方も変化する。薬効に関する
観察を親に委ねるのは負担が大きいため、薬剤師の専門性が必要である。特に、薬の内
容や量が微妙に変わる際の管理と観察には専門性が必要であり訪問看護と薬剤師との連
携の重要性を感じる。特に、退院時のカンファレンスに薬剤師が参加することは重要で
あり、最初からの連携が必須だが、薬局と訪問看護の連携はまだ少ないように感じてい
る。
16.小児を専門とする薬局として、副作用確認の点など、オンラインでやっていくのは不足
する部分があるが、保護者に対する薬の説明やフォローアップなどをメールで細やかに
対応するなどの意味での ICT 活用は行っている。
17.「小児」と漠然と捉えるのではなく、希少疾患やがん、小児慢性特定疾患、病的ケア児
2
であるのかの整理を行うべき。
〇 小児分野関係(有識者ヒアリング含む)
11.日本の小児医療の進歩により、重篤な疾患を抱える子どもたちが地域で治療を継続しな
がら生活するようになり、細やかな用量調節が必要なハイリスク薬の日常使用が増加し
ており、病院内で完結していた特殊な小児薬物療法を、病院薬剤師と薬局薬剤師が連携
して地域へと円滑に引き継いでいく必要性が高まっている。
12.小児は薬物動態が成人とは異なり、年齢や発達の個別性が高いため、薬用量や投与間隔
を細やかに調整する必要がある。希少かつ個別性が高い疾患のため、小児用製剤の開発
が難航しており、成人用製剤を粉砕や脱カプセルして対応せざるを得ない状況が続いて
いる。これにより、成人用の錠剤の粉砕や脱カプセルによって苦みが強くなるなどで飲
みにくさが生じ、服薬アドヒアランスや治療継続性の重大な阻害因子となっている。ま
た特許切れ薬剤への製薬企業の経済的インセンティブの乏しさや、散剤製造に対して高
コストがかかるが薬価で評価されないなどの理由で、小児用製剤が存在しないハイリス
ク薬がある。ハイリスク薬の粉砕分包には厳重な曝露対策が必要だが、パイルパッカー
のような設備を持つ薬局は全体の 1 割以下である。さらには、小児特定加算の障害者手
帳要件により、退院直後や急性期の延長にある子どもでは制度の対象外となることがあ
る。これらの課題は個々ではなく、薬物動態、疾患特性、製剤、製剤加工、服薬管理、
制度が重なり合う複合課題であり、薬剤師にはこれを俯瞰し横断的に解決する能力が求
められる。
13.小児専門医療機関連携薬局が担うべき機能は、小児医薬品を積極的に採用し、適正使用
に資する情報を含めて地域の薬局に提供すること。また、重篤・希少な疾患の子どもた
ちの退院直後の在宅移行期において、処方内容ややるべきことを整理した上で、地域連
携薬局やかかりつけ薬局に引き継ぎ、地域全体の小児薬物療法への対応力を高めていく
のが望ましい姿だと考える。
14.地域の薬局では、特に輸液の調剤と保管スペースの対応、そして抗がん剤の調剤への対
応が難しいと考える。
15.小児は体調が変わりやすく、また、成長とともに薬の効き方も変化する。薬効に関する
観察を親に委ねるのは負担が大きいため、薬剤師の専門性が必要である。特に、薬の内
容や量が微妙に変わる際の管理と観察には専門性が必要であり訪問看護と薬剤師との連
携の重要性を感じる。特に、退院時のカンファレンスに薬剤師が参加することは重要で
あり、最初からの連携が必須だが、薬局と訪問看護の連携はまだ少ないように感じてい
る。
16.小児を専門とする薬局として、副作用確認の点など、オンラインでやっていくのは不足
する部分があるが、保護者に対する薬の説明やフォローアップなどをメールで細やかに
対応するなどの意味での ICT 活用は行っている。
17.「小児」と漠然と捉えるのではなく、希少疾患やがん、小児慢性特定疾患、病的ケア児
2