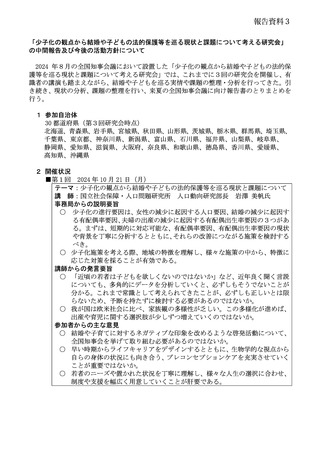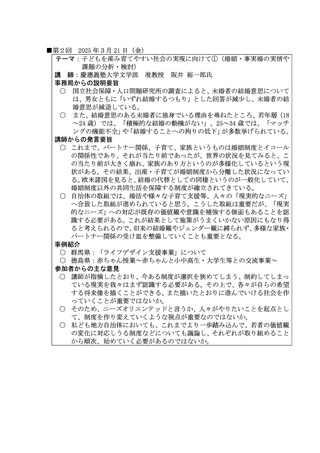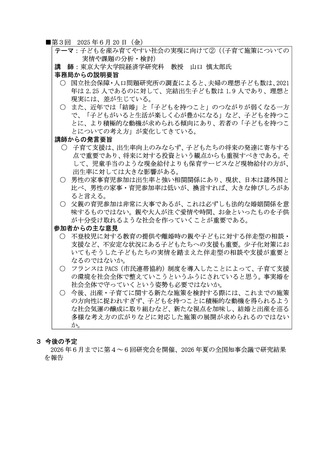よむ、つかう、まなぶ。
【報告(3)資料3】「少子化の観点から結婚や子どもの法的保護等を巡る現状と課題について考える研究会」の中間報告及び今後の活動方針について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
■第3回 2025 年6月 20 日(金)
テーマ:子どもを産み育てやすい社会の実現に向けて②((子育て施策についての
実情や課題の分析・検討)
講 師:東京大学大学院経済学研究科 教授 山口 慎太郎氏
事務局からの説明要旨
○ 国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、夫婦の理想子ども数は、2021
年は 2.25 人であるのに対して、完結出生子ども数は 1.9 人であり、理想と
現実には、差が生じている。
○ また、近年では「結婚」と「子どもを持つこと」のつながりが弱くなる一方
で、「子どもがいると生活が楽しく心が豊かになる」など、子どもを持つこ
とに、より積極的な動機が求められる傾向にあり、若者の「子どもを持つこ
とについての考え方」が変化してきている。
講師からの発言要旨
○ 子育て支援は、出生率向上のみならず、子どもたちの将来の発達に寄与する
点で重要であり、将来に対する投資という観点からも重視すべきである。そ
して、児童手当のような現金給付よりも保育サービスなど現物給付の方が、
出生率に対しては大きな影響がある。
○ 男性の家事育児参加は出生率と強い相関関係にあり、現状、日本は諸外国と
比べ、男性の家事・育児参加率は低いが、換言すれば、大きな伸びしろがあ
ると言える。
○ 父親の育児参加は非常に大事であるが、これは必ずしも法的な婚姻関係を意
味するものではない。親や大人が注ぐ愛情や時間、お金といったものを子供
が十分受け取れるような社会を作っていくことが重要である。
参加者からの主な意見
○ 不登校児に対する教育の提供や離婚時の親や子どもに対する伴走型の相談・
支援など、不安定な状況にある子どもたちへの支援も重要。少子化対策にお
いてもそうした子どもたちの実情を踏まえた伴走型の相談や支援が重要と
なるのではないか。
○ フランスは PACS(民連帯協約約)制度を導入したことによって、子育て支援
の環境を社会全体で整えていこうというふうにされていると思う。事実婚を
社会全体で守っていくという姿勢も必要ではないか。
○ 今後、出産・子育てに関する新たな施策を検討する際には、これまでの施策
の方向性に捉われすぎず、子どもを持つことに積極的な動機を得られるよう
な社会気運の醸成に取り組むなど、新たな視点を加味し、結婚と出産を巡る
多様な考え方の広がりなどに対応した施策の展開が求められるのではない
か。
3 今後の予定
2026 年6月までに第4~6回研究会を開催、2026 年夏の全国知事会議で研究結果
を報告
テーマ:子どもを産み育てやすい社会の実現に向けて②((子育て施策についての
実情や課題の分析・検討)
講 師:東京大学大学院経済学研究科 教授 山口 慎太郎氏
事務局からの説明要旨
○ 国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、夫婦の理想子ども数は、2021
年は 2.25 人であるのに対して、完結出生子ども数は 1.9 人であり、理想と
現実には、差が生じている。
○ また、近年では「結婚」と「子どもを持つこと」のつながりが弱くなる一方
で、「子どもがいると生活が楽しく心が豊かになる」など、子どもを持つこ
とに、より積極的な動機が求められる傾向にあり、若者の「子どもを持つこ
とについての考え方」が変化してきている。
講師からの発言要旨
○ 子育て支援は、出生率向上のみならず、子どもたちの将来の発達に寄与する
点で重要であり、将来に対する投資という観点からも重視すべきである。そ
して、児童手当のような現金給付よりも保育サービスなど現物給付の方が、
出生率に対しては大きな影響がある。
○ 男性の家事育児参加は出生率と強い相関関係にあり、現状、日本は諸外国と
比べ、男性の家事・育児参加率は低いが、換言すれば、大きな伸びしろがあ
ると言える。
○ 父親の育児参加は非常に大事であるが、これは必ずしも法的な婚姻関係を意
味するものではない。親や大人が注ぐ愛情や時間、お金といったものを子供
が十分受け取れるような社会を作っていくことが重要である。
参加者からの主な意見
○ 不登校児に対する教育の提供や離婚時の親や子どもに対する伴走型の相談・
支援など、不安定な状況にある子どもたちへの支援も重要。少子化対策にお
いてもそうした子どもたちの実情を踏まえた伴走型の相談や支援が重要と
なるのではないか。
○ フランスは PACS(民連帯協約約)制度を導入したことによって、子育て支援
の環境を社会全体で整えていこうというふうにされていると思う。事実婚を
社会全体で守っていくという姿勢も必要ではないか。
○ 今後、出産・子育てに関する新たな施策を検討する際には、これまでの施策
の方向性に捉われすぎず、子どもを持つことに積極的な動機を得られるよう
な社会気運の醸成に取り組むなど、新たな視点を加味し、結婚と出産を巡る
多様な考え方の広がりなどに対応した施策の展開が求められるのではない
か。
3 今後の予定
2026 年6月までに第4~6回研究会を開催、2026 年夏の全国知事会議で研究結果
を報告