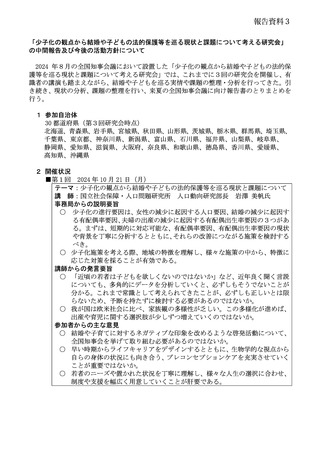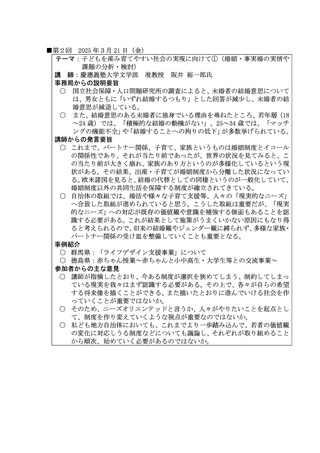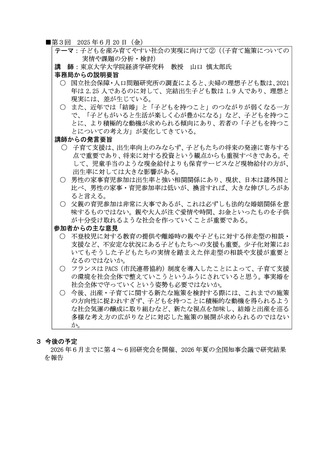よむ、つかう、まなぶ。
【報告(3)資料3】「少子化の観点から結婚や子どもの法的保護等を巡る現状と課題について考える研究会」の中間報告及び今後の活動方針について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
■第2回 2025 年3月 21 日(金)
テーマ:子どもを産み育てやすい社会の実現に向けて①(婚姻・事実婚の実情や
課題の分析・検討)
講 師:慶應義塾大学文学部 准教授 阪井 裕一郎氏
事務局からの説明要旨
○ 国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、未婚者の結婚意思について
は、男女ともに「いずれ結婚するつもり」とした回答が減少し、未婚者の結
婚意思が減退している。
○ また、結婚意思のある未婚者に独身でいる理由を尋ねたところ、若年層(18
~24 歳)では、「積極的な結婚の動機がない」、25~34 歳では、「マッチ
ングの機能不全」や「結婚することへの拘りの低下」が多数挙げられている。
講師からの発言要旨
○ これまで、パートナー関係、子育て、家族というものは婚姻制度とイコール
の関係性であり、それが当たり前であったが、世界の状況を見てみると、こ
の当たり前が大きく崩れ、家族のあり方というのが多様化しているという現
状がある。その結果、出産・子育てが婚姻制度から分離した状況になってい
る。欧米諸国を見ると、結婚の代替としての同棲というのが一般化していて、
婚姻制度以外の共同生活を保障する制度が確立されてきている。
○ 自治体の取組では、婚活や様々な子育て支援等、人々の「現実的なニーズ」
へ合致した取組が進められていると思う。こうした取組は重要だが、「現実
的なニーズ」への対応が既存の価値観や意識を補強する側面もあることを認
識する必要がある。これが結果として施策がうまくいかない原因にもなり得
ると考えられるので、旧来の結婚観やジェンダー観に縛られず、多様な家族・
パートナー関係の受け皿を整備していくことも重要となる。
事例紹介
○ 群馬県:「ライフデザイン支援事業」について
○ 徳島県:赤ちゃん授業~赤ちゃんと小中高生・大学生等との交流事業~
参加者からの主な意見
○ 講師が指摘したとおり、今ある制度が選択を狭めてしまう、制約してしまっ
ている現実を我々はまず認識する必要がある。その上で、各々が自らの希望
する将来像を描くことができる、また描いたとおりに進んでいける社会を作
っていくことが重要ではないか。
○ そのため、ニーズオリエンテッドと言うか、人々がやりたいことを起点とし
て、制度を作り変えていくような視点が重要なのではないか。
○ 私ども地方自治体においても、これまでより一歩踏み込んで、若者の価値観
の変化に対応しうる制度などについても議論し、それぞれが取り組めること
から順次、始めていく必要があるのではないか。
テーマ:子どもを産み育てやすい社会の実現に向けて①(婚姻・事実婚の実情や
課題の分析・検討)
講 師:慶應義塾大学文学部 准教授 阪井 裕一郎氏
事務局からの説明要旨
○ 国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、未婚者の結婚意思について
は、男女ともに「いずれ結婚するつもり」とした回答が減少し、未婚者の結
婚意思が減退している。
○ また、結婚意思のある未婚者に独身でいる理由を尋ねたところ、若年層(18
~24 歳)では、「積極的な結婚の動機がない」、25~34 歳では、「マッチ
ングの機能不全」や「結婚することへの拘りの低下」が多数挙げられている。
講師からの発言要旨
○ これまで、パートナー関係、子育て、家族というものは婚姻制度とイコール
の関係性であり、それが当たり前であったが、世界の状況を見てみると、こ
の当たり前が大きく崩れ、家族のあり方というのが多様化しているという現
状がある。その結果、出産・子育てが婚姻制度から分離した状況になってい
る。欧米諸国を見ると、結婚の代替としての同棲というのが一般化していて、
婚姻制度以外の共同生活を保障する制度が確立されてきている。
○ 自治体の取組では、婚活や様々な子育て支援等、人々の「現実的なニーズ」
へ合致した取組が進められていると思う。こうした取組は重要だが、「現実
的なニーズ」への対応が既存の価値観や意識を補強する側面もあることを認
識する必要がある。これが結果として施策がうまくいかない原因にもなり得
ると考えられるので、旧来の結婚観やジェンダー観に縛られず、多様な家族・
パートナー関係の受け皿を整備していくことも重要となる。
事例紹介
○ 群馬県:「ライフデザイン支援事業」について
○ 徳島県:赤ちゃん授業~赤ちゃんと小中高生・大学生等との交流事業~
参加者からの主な意見
○ 講師が指摘したとおり、今ある制度が選択を狭めてしまう、制約してしまっ
ている現実を我々はまず認識する必要がある。その上で、各々が自らの希望
する将来像を描くことができる、また描いたとおりに進んでいける社会を作
っていくことが重要ではないか。
○ そのため、ニーズオリエンテッドと言うか、人々がやりたいことを起点とし
て、制度を作り変えていくような視点が重要なのではないか。
○ 私ども地方自治体においても、これまでより一歩踏み込んで、若者の価値観
の変化に対応しうる制度などについても議論し、それぞれが取り組めること
から順次、始めていく必要があるのではないか。