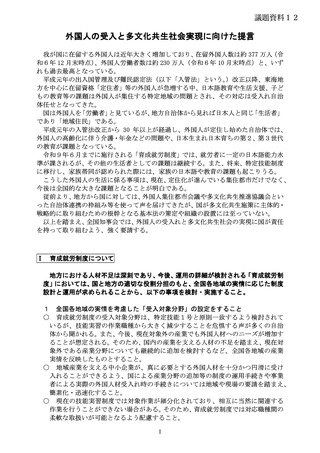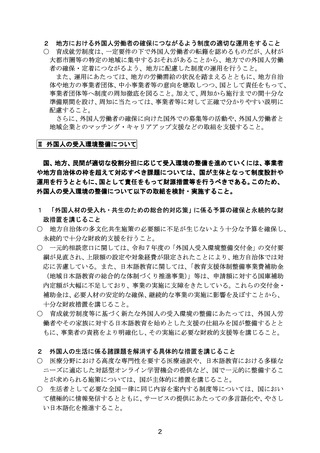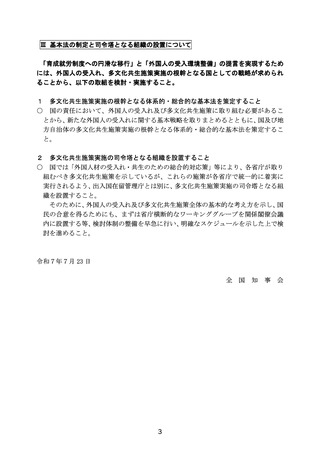よむ、つかう、まなぶ。
【議題(12)資料12】外国人の受入と多文化共生社会実現に向けた提言 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
議題資料12
外国人の受入と多文化共生社会実現に向けた提言
我が国に在留する外国人は近年大きく増加しており、在留外国人数は約 377 万人(令
和6年 12 月末時点)、外国人労働者数は約 230 万人(令和6年 10 月末時点)と、いず
れも過去最高となっている。
平成元年の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。
)改正以降、東海地
方を中心に在留資格「定住者」等の外国人が急増する中、日本語教育や生活支援、子ど
もの教育等の課題は外国人が集住する特定地域の問題とされ、その対応は受入れ自治
体任せとなってきた。
国は外国人を「労働者」と見ているが、地方自治体から見れば日本人と同じ「生活者」
であり「地域住民」である。
平成元年の入管法改正から 30 年以上が経過し、外国人が定住し始めた自治体では、
外国人の高齢化に伴う介護・年金などの問題や、日本生まれ日本育ちの第2、第3世代
の教育が課題となっている。
令和9年6月までに施行される「育成就労制度」では、就労者に一定の日本語能力水
準が課されるが、その他の生活者としての課題は継続する。また、将来、特定技能制度
に移行し、家族帯同が認められた際には、家族の日本語や教育の課題も起こりうる。
こうした外国人の生活に係る事項は、現在、定住化が進んでいる集住都市だけでなく、
今後は全国的な大きな課題となることが明白である。
従前より、地方から国に対しては、外国人集住都市会議や多文化共生推進協議会とい
った自治体連携の枠組み等を使って声を届けてきたが、国が多文化共生施策に主体的・
戦略的に取り組むための根幹となる基本法の策定や組織の設置には至っていない。
以上を踏まえ、全国知事会では、外国人の受入れと多文化共生社会の実現に国が責任
を持って取り組むよう、強く要請する。
Ⅰ
育成就労制度について
地方における人材不足は深刻であり、今後、運用の詳細が検討される「育成就労制
度」においては、国と地方の適切な役割分担のもと、全国各地域の実情に応じた制度
設計と運用が求められることから、以下の事項を検討・実施すること。
1 全国各地域の実情を考慮した「受入対象分野」の設定をすること
○ 育成就労制度の受入対象分野は、特定技能1号と原則一致するよう検討されて
いるが、技能実習の作業職種から大きく減少することを危惧する声が多くの自治
体から聞かれる。また、今後、現在対象外の産業でも外国人材へのニーズが増加す
ることが想定される。そのため、国内の産業を支える人材の不足を踏まえ、現在対
象外である産業分野についても継続的に追加を検討するなど、全国各地域の産業
実情を反映したものとすること。
〇 地域産業を支える中小企業が、真に必要とする外国人材を十分かつ円滑に受け
入れることができるよう、国による産業分野の追加等の制度の運用手続きや事業
者による実際の外国人材受入れ時の手続きについては地域や現場の要請を踏まえ、
簡素化・迅速化すること。
○ 現在の技能実習制度では対象作業が細分化されており、相互に当然に関連する
作業を行うことができない場合がある。そのため、育成就労制度では対応職種間の
柔軟な取扱いが可能となるよう配慮すること。
1
外国人の受入と多文化共生社会実現に向けた提言
我が国に在留する外国人は近年大きく増加しており、在留外国人数は約 377 万人(令
和6年 12 月末時点)、外国人労働者数は約 230 万人(令和6年 10 月末時点)と、いず
れも過去最高となっている。
平成元年の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。
)改正以降、東海地
方を中心に在留資格「定住者」等の外国人が急増する中、日本語教育や生活支援、子ど
もの教育等の課題は外国人が集住する特定地域の問題とされ、その対応は受入れ自治
体任せとなってきた。
国は外国人を「労働者」と見ているが、地方自治体から見れば日本人と同じ「生活者」
であり「地域住民」である。
平成元年の入管法改正から 30 年以上が経過し、外国人が定住し始めた自治体では、
外国人の高齢化に伴う介護・年金などの問題や、日本生まれ日本育ちの第2、第3世代
の教育が課題となっている。
令和9年6月までに施行される「育成就労制度」では、就労者に一定の日本語能力水
準が課されるが、その他の生活者としての課題は継続する。また、将来、特定技能制度
に移行し、家族帯同が認められた際には、家族の日本語や教育の課題も起こりうる。
こうした外国人の生活に係る事項は、現在、定住化が進んでいる集住都市だけでなく、
今後は全国的な大きな課題となることが明白である。
従前より、地方から国に対しては、外国人集住都市会議や多文化共生推進協議会とい
った自治体連携の枠組み等を使って声を届けてきたが、国が多文化共生施策に主体的・
戦略的に取り組むための根幹となる基本法の策定や組織の設置には至っていない。
以上を踏まえ、全国知事会では、外国人の受入れと多文化共生社会の実現に国が責任
を持って取り組むよう、強く要請する。
Ⅰ
育成就労制度について
地方における人材不足は深刻であり、今後、運用の詳細が検討される「育成就労制
度」においては、国と地方の適切な役割分担のもと、全国各地域の実情に応じた制度
設計と運用が求められることから、以下の事項を検討・実施すること。
1 全国各地域の実情を考慮した「受入対象分野」の設定をすること
○ 育成就労制度の受入対象分野は、特定技能1号と原則一致するよう検討されて
いるが、技能実習の作業職種から大きく減少することを危惧する声が多くの自治
体から聞かれる。また、今後、現在対象外の産業でも外国人材へのニーズが増加す
ることが想定される。そのため、国内の産業を支える人材の不足を踏まえ、現在対
象外である産業分野についても継続的に追加を検討するなど、全国各地域の産業
実情を反映したものとすること。
〇 地域産業を支える中小企業が、真に必要とする外国人材を十分かつ円滑に受け
入れることができるよう、国による産業分野の追加等の制度の運用手続きや事業
者による実際の外国人材受入れ時の手続きについては地域や現場の要請を踏まえ、
簡素化・迅速化すること。
○ 現在の技能実習制度では対象作業が細分化されており、相互に当然に関連する
作業を行うことができない場合がある。そのため、育成就労制度では対応職種間の
柔軟な取扱いが可能となるよう配慮すること。
1