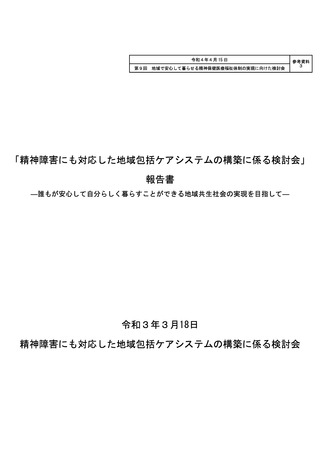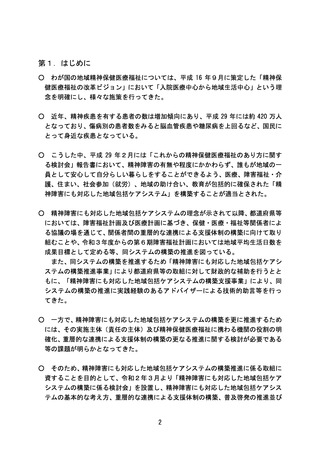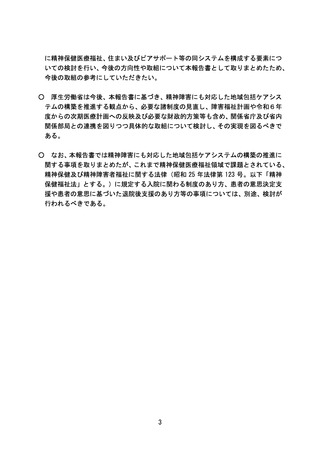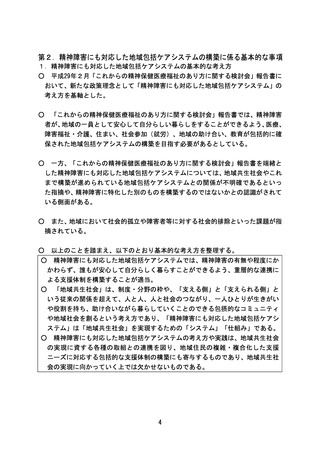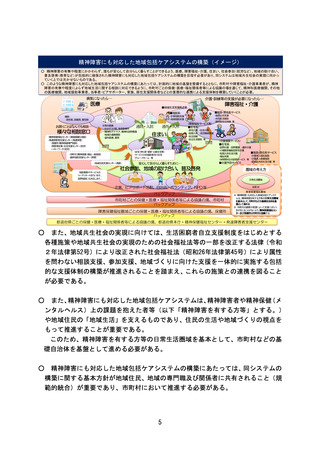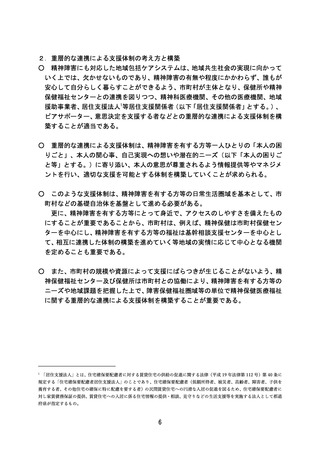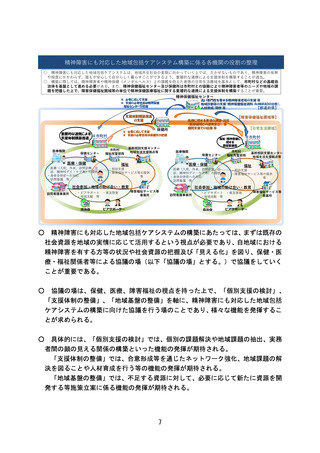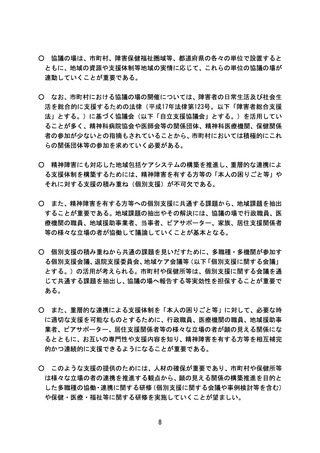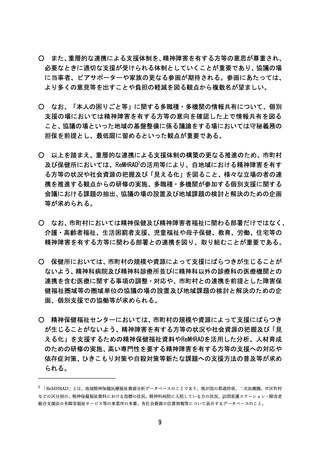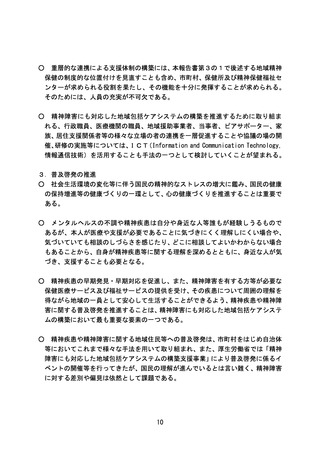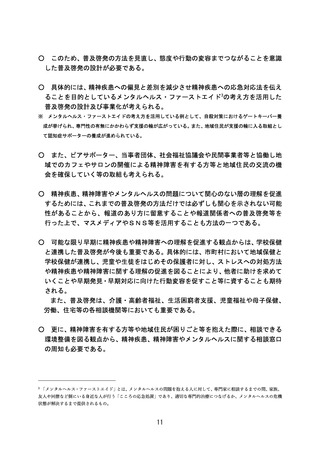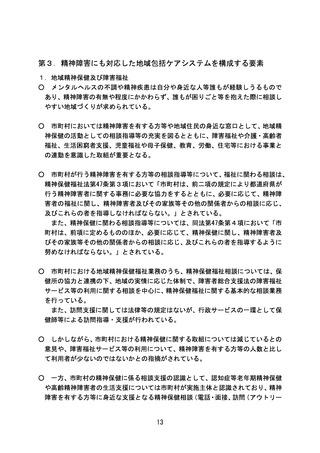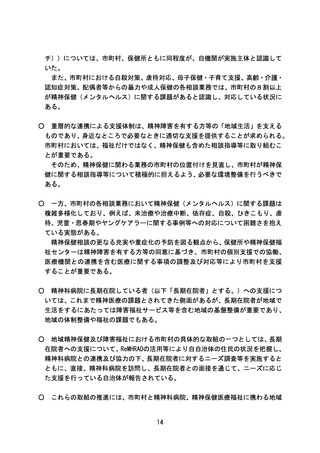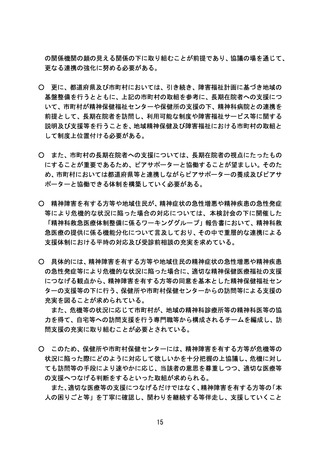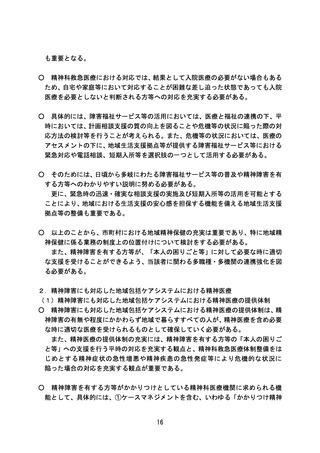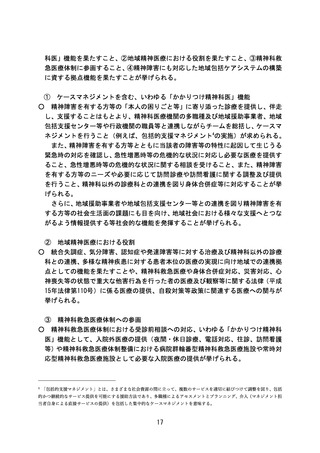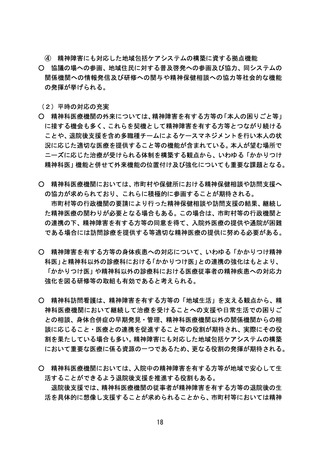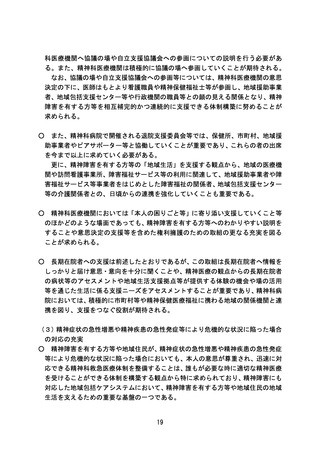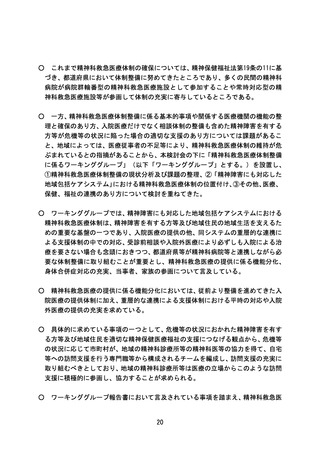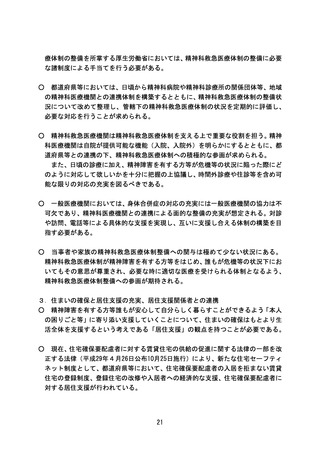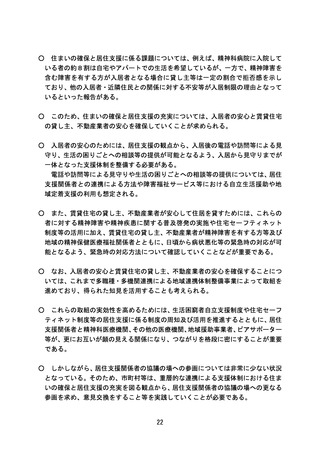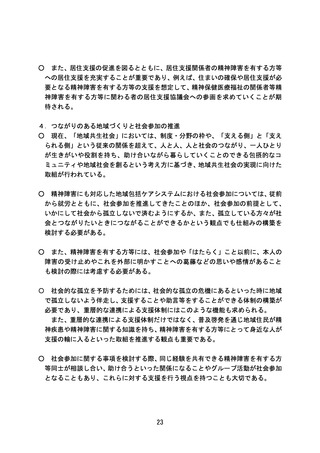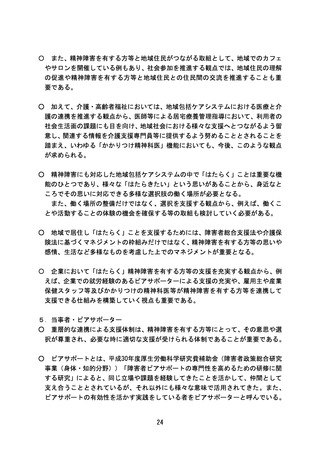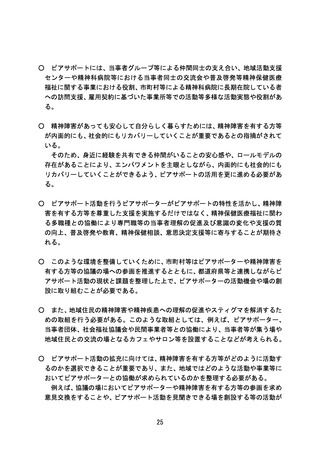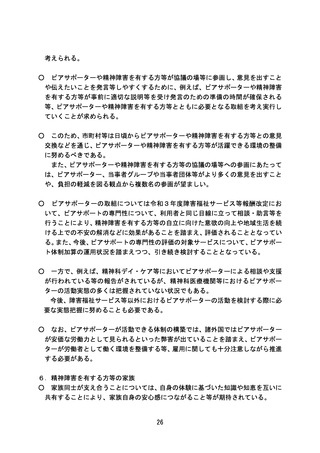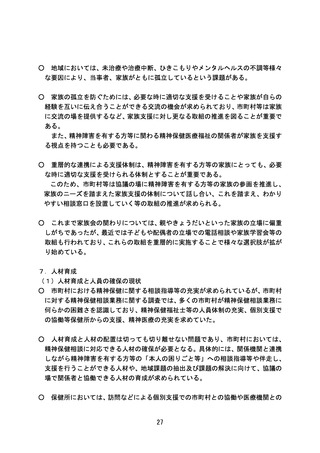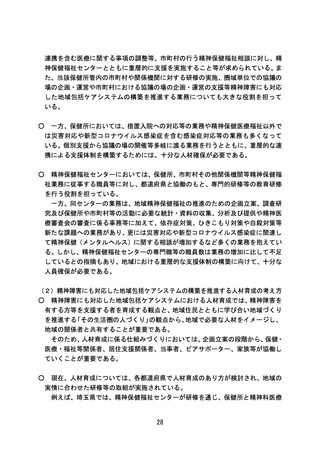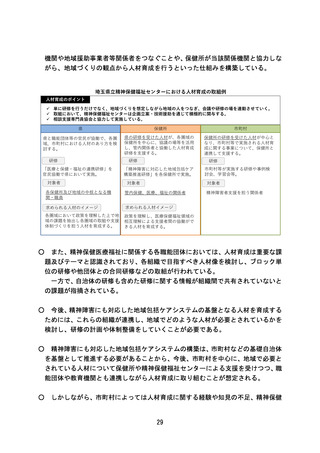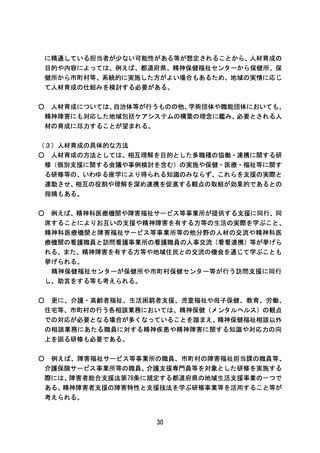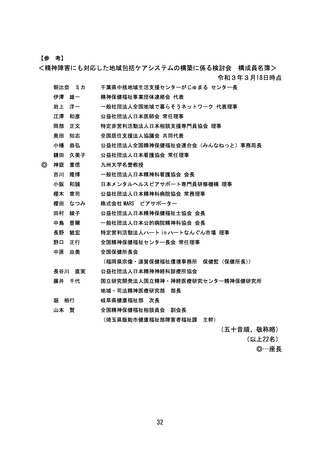よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料3)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
〇
また、精神障害を有する方等と地域住民がつながる取組として、地域でのカフェ
やサロンを開催している例もあり、社会参加を推進する観点では、地域住民の理解
の促進や精神障害を有する方等と地域住民との住民間の交流を推進することも重
要である。
○
加えて、介護・高齢者福祉においては、地域包括ケアシステムにおける医療と介
護の連携を推進する観点から、医師等による居宅療養管理指導において、利用者の
社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留
意し、関連する情報を介護支援専門員等に提供するよう努めることとされることを
踏まえ、いわゆる「かかりつけ精神科医」機能においても、今後、このような観点
が求められる。
○
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの中で「はたらく」ことは重要な機
能のひとつであり、様々な「はたらきたい」という思いがあることから、身近なと
ころでその思いに対応できる多様な選択肢の働く場所が必要となる。
また、働く場所の整備だけではなく、選択を支援する観点から、例えば、働くこ
とや活動することの体験の機会を確保する等の取組も検討していく必要がある。
○
地域で居住し「はたらく」ことを支援するためには、障害者総合支援法や介護保
険法に基づくマネジメントの枠組みだけではなく、精神障害を有する方等の思いや
感情、生活など多様なものを考慮した上でのマネジメントが重要となる。
〇
企業において「はたらく」精神障害を有する方等の支援を充実する観点から、例
えば、企業での就労経験のあるピアサポーターによる支援の充実や、雇用主や産業
保健スタッフ等及びかかりつけの精神科医等が精神障害を有する方等を連携して
支援できる仕組みを構築していく視点も重要である。
5.当事者・ピアサポーター
○ 重層的な連携による支援体制は、精神障害を有する方等にとって、その意思や選
択が尊重され、必要な時に適切な支援が受けられる体制であることが重要である。
○
ピアサポートとは、平成30年度厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究
事業(身体・知的分野))「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関
する研究」によると、同じ立場や課題を経験してきたことを活かして、仲間として
支え合うこととされているが、それ以外にも様々な意味で活用されてきた。また、
ピアサポートの有効性を活かす実践をしている者をピアサポーターと呼んでいる。
24
また、精神障害を有する方等と地域住民がつながる取組として、地域でのカフェ
やサロンを開催している例もあり、社会参加を推進する観点では、地域住民の理解
の促進や精神障害を有する方等と地域住民との住民間の交流を推進することも重
要である。
○
加えて、介護・高齢者福祉においては、地域包括ケアシステムにおける医療と介
護の連携を推進する観点から、医師等による居宅療養管理指導において、利用者の
社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留
意し、関連する情報を介護支援専門員等に提供するよう努めることとされることを
踏まえ、いわゆる「かかりつけ精神科医」機能においても、今後、このような観点
が求められる。
○
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの中で「はたらく」ことは重要な機
能のひとつであり、様々な「はたらきたい」という思いがあることから、身近なと
ころでその思いに対応できる多様な選択肢の働く場所が必要となる。
また、働く場所の整備だけではなく、選択を支援する観点から、例えば、働くこ
とや活動することの体験の機会を確保する等の取組も検討していく必要がある。
○
地域で居住し「はたらく」ことを支援するためには、障害者総合支援法や介護保
険法に基づくマネジメントの枠組みだけではなく、精神障害を有する方等の思いや
感情、生活など多様なものを考慮した上でのマネジメントが重要となる。
〇
企業において「はたらく」精神障害を有する方等の支援を充実する観点から、例
えば、企業での就労経験のあるピアサポーターによる支援の充実や、雇用主や産業
保健スタッフ等及びかかりつけの精神科医等が精神障害を有する方等を連携して
支援できる仕組みを構築していく視点も重要である。
5.当事者・ピアサポーター
○ 重層的な連携による支援体制は、精神障害を有する方等にとって、その意思や選
択が尊重され、必要な時に適切な支援が受けられる体制であることが重要である。
○
ピアサポートとは、平成30年度厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究
事業(身体・知的分野))「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関
する研究」によると、同じ立場や課題を経験してきたことを活かして、仲間として
支え合うこととされているが、それ以外にも様々な意味で活用されてきた。また、
ピアサポートの有効性を活かす実践をしている者をピアサポーターと呼んでいる。
24