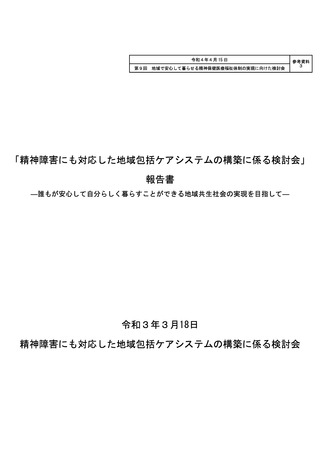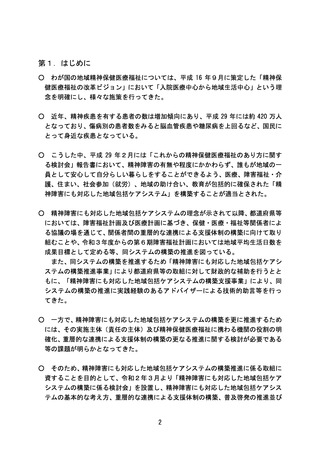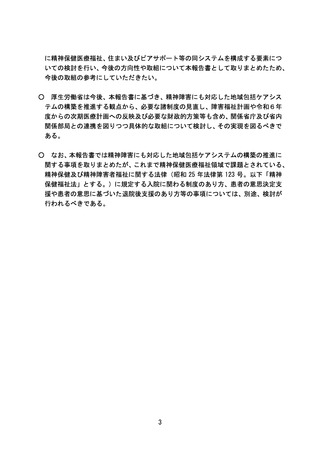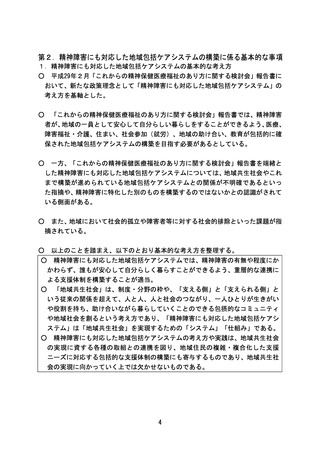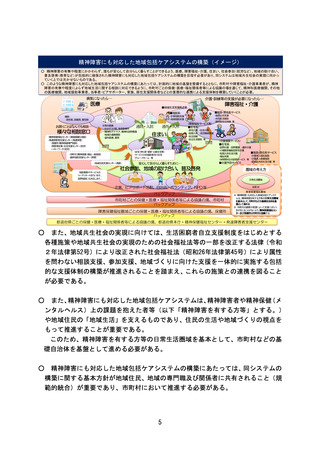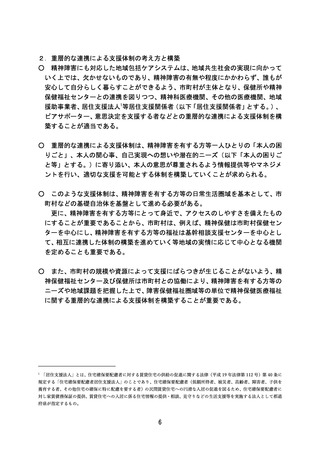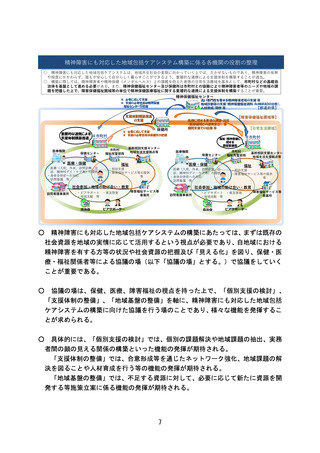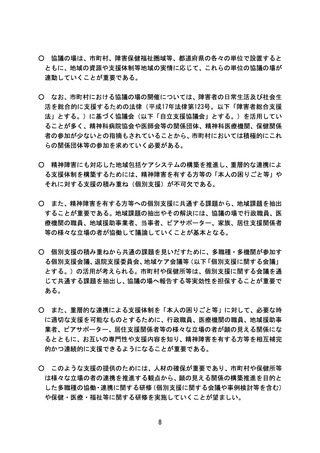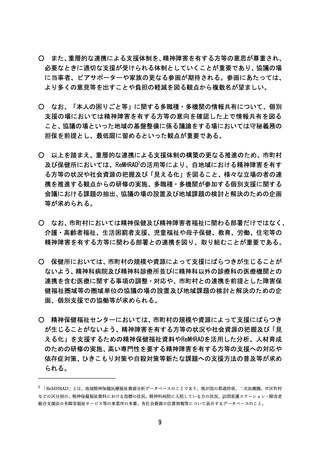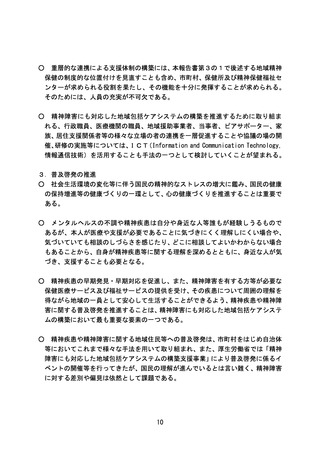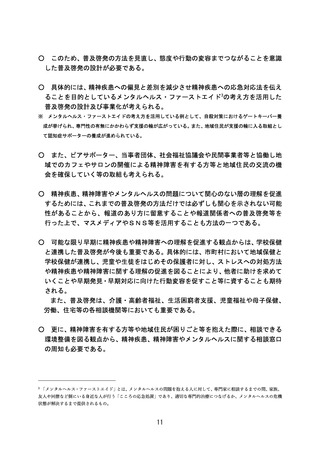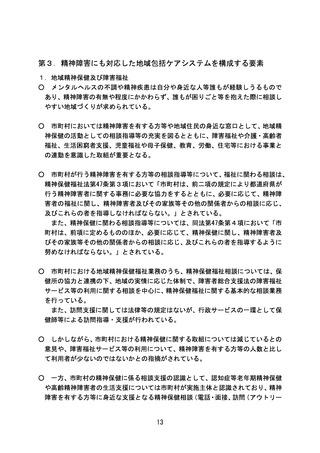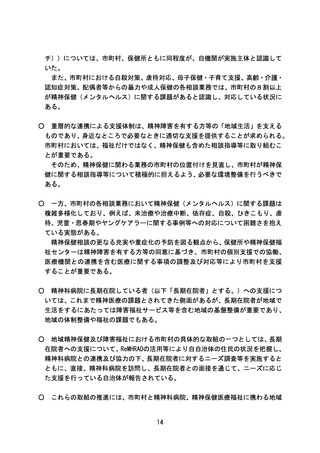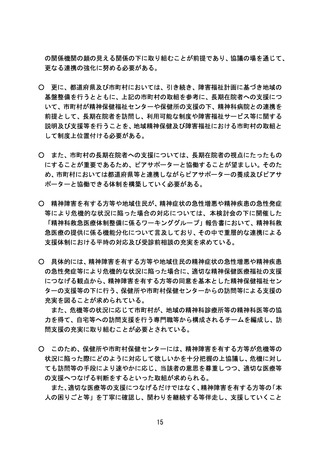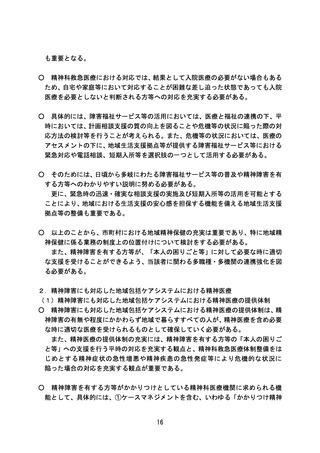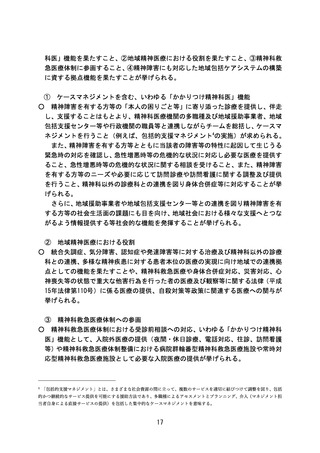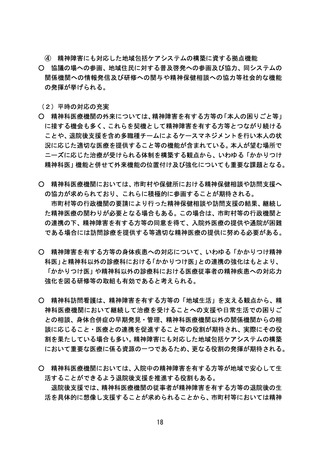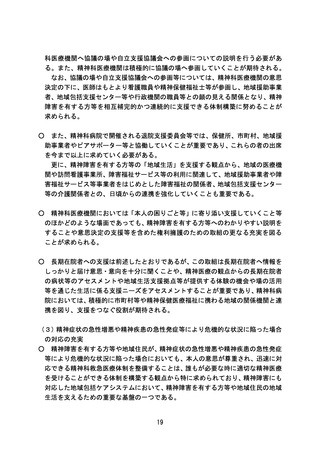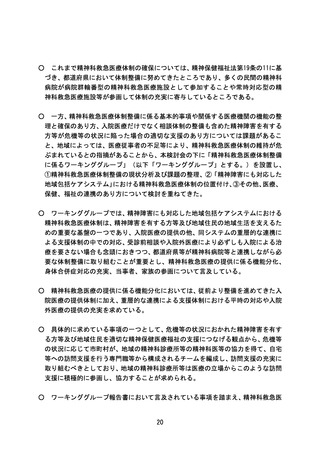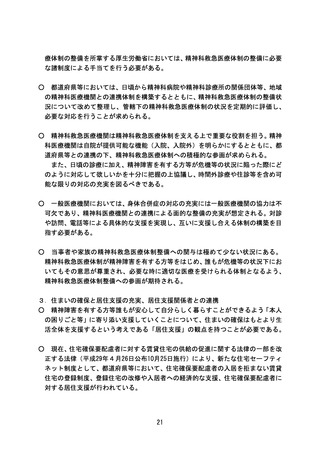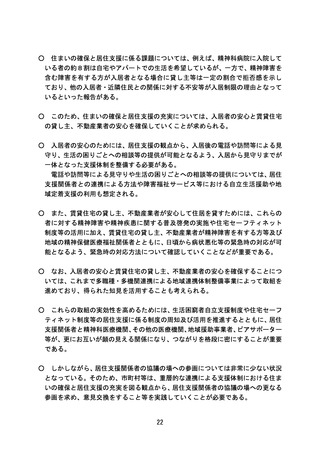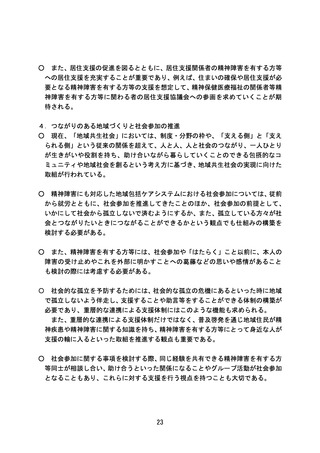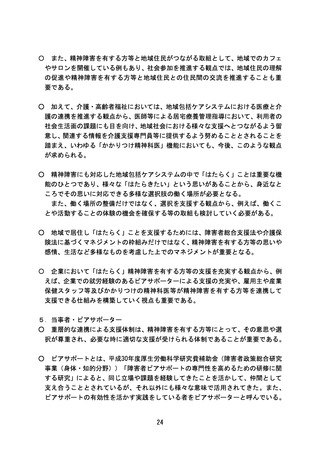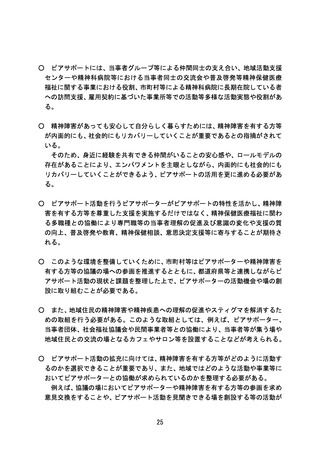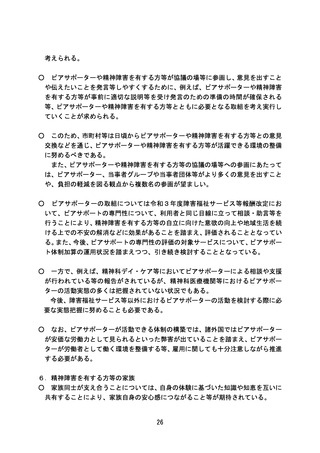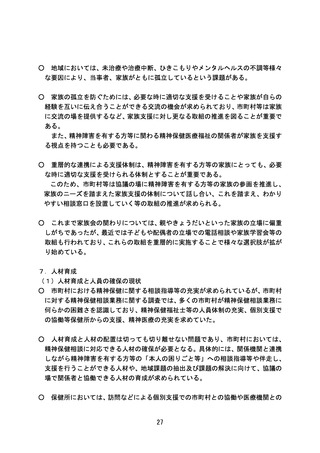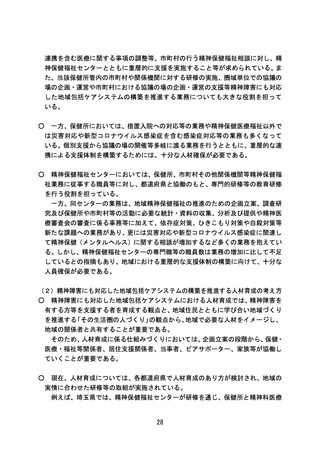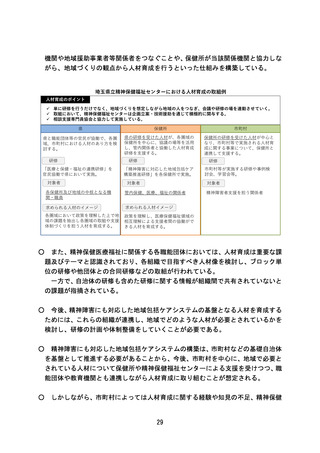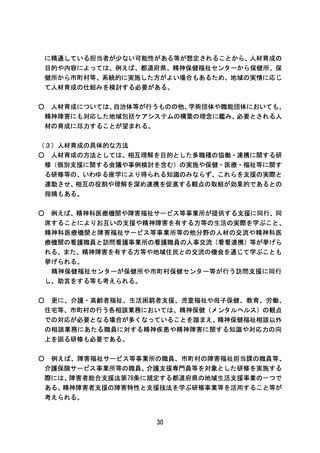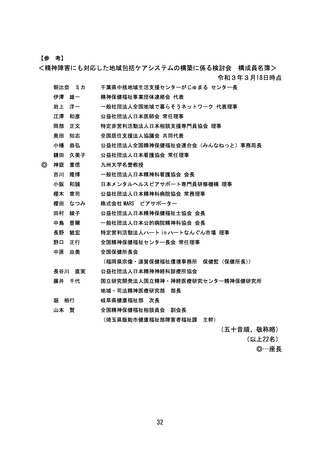よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料3)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の関係機関の顔の見える関係の下に取り組むことが前提であり、協議の場を通じて、
更なる連携の強化に努める必要がある。
○
更に、都道府県及び市町村においては、引き続き、障害福祉計画に基づき地域の
基盤整備を行うとともに、上記の市町村の取組を参考に、長期在院者への支援につ
いて、市町村が精神保健福祉センターや保健所の支援の下、精神科病院との連携を
前提として、長期在院者を訪問し、利用可能な制度や障害福祉サービス等に関する
説明及び支援等を行うことを、地域精神保健及び障害福祉における市町村の取組と
して制度上位置付ける必要がある。
○
また、市町村の長期在院者への支援については、長期在院者の視点にたったもの
にすることが重要であるため、ピアサポーターと協働することが望ましい。そのた
め、市町村においては都道府県等と連携しながらピアサポーターの養成及びピアサ
ポーターと協働できる体制を構築していく必要がある。
○
精神障害を有する方等や地域住民が、精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症
等により危機的な状況に陥った場合の対応については、本検討会の下に開催した
「精神科救急医療体制整備に係るワーキンググループ」報告書において、精神科救
急医療の提供に係る機能分化について言及しており、その中で重層的な連携による
支援体制における平時の対応及び受診前相談の充実を求めている。
○
具体的には、精神障害を有する方等や地域住民の精神症状の急性増悪や精神疾患
の急性発症等により危機的な状況に陥った場合に、適切な精神保健医療福祉の支援
につなげる観点から、精神障害を有する方等の同意を基本とした精神保健福祉セン
ターの支援等の下に行う、保健所や市町村保健センターからの訪問等による支援の
充実を図ることが求められている。
また、危機等の状況に応じて市町村が、地域の精神科診療所等の精神科医等の協
力を得て、自宅等への訪問支援を行う専門職等から構成されるチームを編成し、訪
問支援の充実に取り組むことが必要とされている。
○
このため、保健所や市町村保健センターには、精神障害を有する方等が危機等の
状況に陥った際にどのように対応して欲しいかを十分把握の上協議し、危機に対し
ても訪問等の手段により速やかに応じ、当該者の意思を尊重しつつ、適切な医療等
の支援へつなげる判断をするといった取組が求められる。
また、適切な医療等の支援につなげるだけではなく、精神障害を有する方等の「本
人の困りごと等」を丁寧に確認し、関わりを継続する等伴走し、支援していくこと
15
更なる連携の強化に努める必要がある。
○
更に、都道府県及び市町村においては、引き続き、障害福祉計画に基づき地域の
基盤整備を行うとともに、上記の市町村の取組を参考に、長期在院者への支援につ
いて、市町村が精神保健福祉センターや保健所の支援の下、精神科病院との連携を
前提として、長期在院者を訪問し、利用可能な制度や障害福祉サービス等に関する
説明及び支援等を行うことを、地域精神保健及び障害福祉における市町村の取組と
して制度上位置付ける必要がある。
○
また、市町村の長期在院者への支援については、長期在院者の視点にたったもの
にすることが重要であるため、ピアサポーターと協働することが望ましい。そのた
め、市町村においては都道府県等と連携しながらピアサポーターの養成及びピアサ
ポーターと協働できる体制を構築していく必要がある。
○
精神障害を有する方等や地域住民が、精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症
等により危機的な状況に陥った場合の対応については、本検討会の下に開催した
「精神科救急医療体制整備に係るワーキンググループ」報告書において、精神科救
急医療の提供に係る機能分化について言及しており、その中で重層的な連携による
支援体制における平時の対応及び受診前相談の充実を求めている。
○
具体的には、精神障害を有する方等や地域住民の精神症状の急性増悪や精神疾患
の急性発症等により危機的な状況に陥った場合に、適切な精神保健医療福祉の支援
につなげる観点から、精神障害を有する方等の同意を基本とした精神保健福祉セン
ターの支援等の下に行う、保健所や市町村保健センターからの訪問等による支援の
充実を図ることが求められている。
また、危機等の状況に応じて市町村が、地域の精神科診療所等の精神科医等の協
力を得て、自宅等への訪問支援を行う専門職等から構成されるチームを編成し、訪
問支援の充実に取り組むことが必要とされている。
○
このため、保健所や市町村保健センターには、精神障害を有する方等が危機等の
状況に陥った際にどのように対応して欲しいかを十分把握の上協議し、危機に対し
ても訪問等の手段により速やかに応じ、当該者の意思を尊重しつつ、適切な医療等
の支援へつなげる判断をするといった取組が求められる。
また、適切な医療等の支援につなげるだけではなく、精神障害を有する方等の「本
人の困りごと等」を丁寧に確認し、関わりを継続する等伴走し、支援していくこと
15