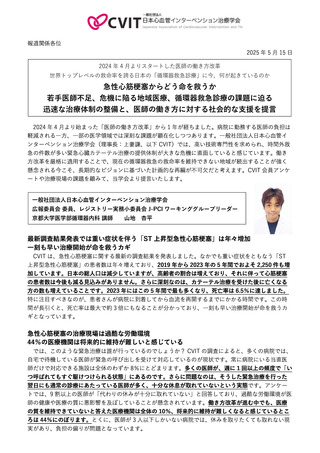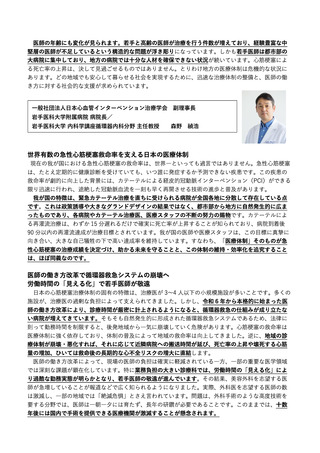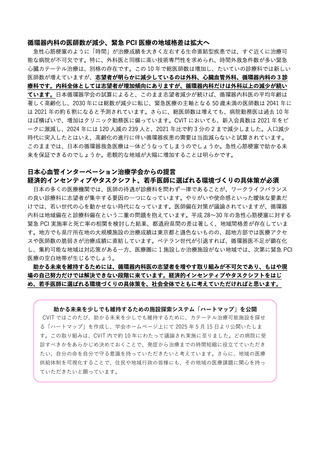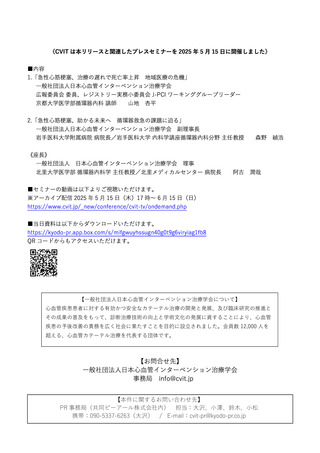よむ、つかう、まなぶ。
施設探索システム「ハートマップ」を公開 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | ハートマップ(全国インターベンション施設マップ)公開(5/15)《日本心血管インターベンション治療学会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
循環器内科の医師数が減少、緊急 PCI 医療の地域格差は拡大へ
急性心筋梗塞のように「時間」が治療成績を大きく左右する生命直結型疾患では、すぐ近くに治療可
能な病院が不可欠です。特に、外科医と同様に高い技術専門性を求められ、時間外救急件数が多い緊急
心臓カテーテル治療は、別格の存在です。この 10 年で総医師数は増加し、たいていの診療科では新しい
医師数が増えていますが、志望者が明らかに減少しているのは外科、心臓血管外科、循環器内科の 3 診
療科です。内科全体としては志望者が増加傾向にありますが、循環器内科だけは外科以上の減少が続い
ています。日本循環器学会の試算によると、このまま志望者減少が続けば、循環器内科医の平均年齢は
著しく高齢化し、2030 年には総数が減少に転じ、緊急医療の主軸となる 50 歳未満の医師数は 2041 年に
は 2021 年の約 6 割になると予測されています。さらに、総医師数は増えても、病院勤務医は過去 10 年
ほぼ横ばいで、増加はクリニック勤務医に偏っています。CVIT においても、新入会員数は 2021 年をピ
ークに激減し、2024 年には 120 人減の 239 人と、2021 年比で約 3 分の 2 まで減少しました。人口減少
時代に突入したとはいえ、高齢化の進行に伴い循環器疾患の需要は当面減らないと試算されています。
このままでは、日本の循環器救急医療は一体どうなってしまうのでしょうか。急性心筋梗塞で助かる未
来を保証できるのでしょうか。悲観的な地域が大幅に増加することは明らかです。
日本心血管インターベーション治療学会からの提言
経済的インセンティブやタスクシフト、若手医師に選ばれる環境づくりの具体策が必須
日本の多くの医療機関では、医師の待遇が診療科を問わず一律であることが、ワークライフバランス
の良い診療科に志望者が集中する要因の一つになっています。やりがいや使命感といった曖昧な要素だ
けでは、若い世代の心を動かせない時代になっています。医師偏在対策が議論されていますが、循環器
内科は地域偏在と診療科偏在という二重の問題を抱えています。平成 28~30 年の急性心筋梗塞に対する
緊急 PCI 実施率と死亡率の相関を検討した結果、都道府県間の差は著しく、地域間格差が存在していま
す。地方でも県庁所在地の大規模施設の治療成績は東京都と遜色ないものの、超地方部では医療アクセ
スや医師数の脆弱さが治療成績に直結しています。ベテラン世代が引退すれば、循環器医不足が顕在化
し、集約可能な地域は対応策がある一方、医療圏に 1 施設しか治療施設がない地域では、次第に緊急 PCI
医療の空白地帯が生じるでしょう。
助かる未来を維持するためには、循環器内科医の志望者を増やす取り組みが不可欠であり、もはや現
場の自己努力だけでは解決できない段階に来ています。経済的インセンティブやタスクシフトをはじ
め、若手医師に選ばれる環境づくりの具体策を、社会全体でともに考えていただければと思います。
助かる未来を少しでも維持するための施設探索システム「ハートマップ」を公開
CVIT ではこのたび、助かる未来を少しでも維持するために、カテーテル治療可能施設を探せ
る「ハートマップ」を作成し、学会ホームページ上にて 2025 年 5 月 15 日より公開いたしま
す。この取り組みは、CVIT 内で約 10 年にわたって議論され実施に至りました。どの病院に受
診すべきかをあらかじめ決めておくことで、発症から治療までの時間短縮に役立てていただき
たい、自分の命を自分で守る意識を持っていただきたいと考えています。さらに、地域の医療
供給体制を可視化することで、住民や地域行政の皆様にも、その地域の医療課題に関心を持っ
ていただきたいと願っています。
急性心筋梗塞のように「時間」が治療成績を大きく左右する生命直結型疾患では、すぐ近くに治療可
能な病院が不可欠です。特に、外科医と同様に高い技術専門性を求められ、時間外救急件数が多い緊急
心臓カテーテル治療は、別格の存在です。この 10 年で総医師数は増加し、たいていの診療科では新しい
医師数が増えていますが、志望者が明らかに減少しているのは外科、心臓血管外科、循環器内科の 3 診
療科です。内科全体としては志望者が増加傾向にありますが、循環器内科だけは外科以上の減少が続い
ています。日本循環器学会の試算によると、このまま志望者減少が続けば、循環器内科医の平均年齢は
著しく高齢化し、2030 年には総数が減少に転じ、緊急医療の主軸となる 50 歳未満の医師数は 2041 年に
は 2021 年の約 6 割になると予測されています。さらに、総医師数は増えても、病院勤務医は過去 10 年
ほぼ横ばいで、増加はクリニック勤務医に偏っています。CVIT においても、新入会員数は 2021 年をピ
ークに激減し、2024 年には 120 人減の 239 人と、2021 年比で約 3 分の 2 まで減少しました。人口減少
時代に突入したとはいえ、高齢化の進行に伴い循環器疾患の需要は当面減らないと試算されています。
このままでは、日本の循環器救急医療は一体どうなってしまうのでしょうか。急性心筋梗塞で助かる未
来を保証できるのでしょうか。悲観的な地域が大幅に増加することは明らかです。
日本心血管インターベーション治療学会からの提言
経済的インセンティブやタスクシフト、若手医師に選ばれる環境づくりの具体策が必須
日本の多くの医療機関では、医師の待遇が診療科を問わず一律であることが、ワークライフバランス
の良い診療科に志望者が集中する要因の一つになっています。やりがいや使命感といった曖昧な要素だ
けでは、若い世代の心を動かせない時代になっています。医師偏在対策が議論されていますが、循環器
内科は地域偏在と診療科偏在という二重の問題を抱えています。平成 28~30 年の急性心筋梗塞に対する
緊急 PCI 実施率と死亡率の相関を検討した結果、都道府県間の差は著しく、地域間格差が存在していま
す。地方でも県庁所在地の大規模施設の治療成績は東京都と遜色ないものの、超地方部では医療アクセ
スや医師数の脆弱さが治療成績に直結しています。ベテラン世代が引退すれば、循環器医不足が顕在化
し、集約可能な地域は対応策がある一方、医療圏に 1 施設しか治療施設がない地域では、次第に緊急 PCI
医療の空白地帯が生じるでしょう。
助かる未来を維持するためには、循環器内科医の志望者を増やす取り組みが不可欠であり、もはや現
場の自己努力だけでは解決できない段階に来ています。経済的インセンティブやタスクシフトをはじ
め、若手医師に選ばれる環境づくりの具体策を、社会全体でともに考えていただければと思います。
助かる未来を少しでも維持するための施設探索システム「ハートマップ」を公開
CVIT ではこのたび、助かる未来を少しでも維持するために、カテーテル治療可能施設を探せ
る「ハートマップ」を作成し、学会ホームページ上にて 2025 年 5 月 15 日より公開いたしま
す。この取り組みは、CVIT 内で約 10 年にわたって議論され実施に至りました。どの病院に受
診すべきかをあらかじめ決めておくことで、発症から治療までの時間短縮に役立てていただき
たい、自分の命を自分で守る意識を持っていただきたいと考えています。さらに、地域の医療
供給体制を可視化することで、住民や地域行政の皆様にも、その地域の医療課題に関心を持っ
ていただきたいと願っています。