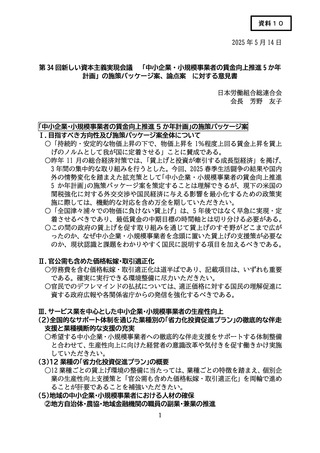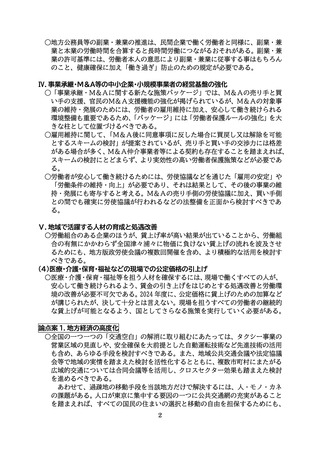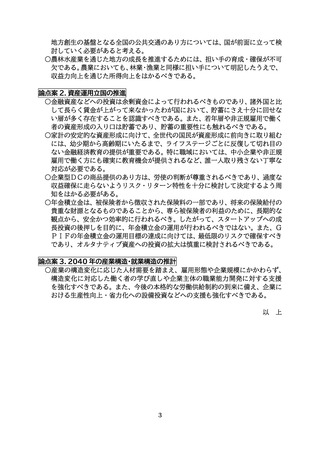よむ、つかう、まなぶ。
資料10芳野委員提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
| 出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○地方公務員等の副業・兼業の推進は、民間企業で働く労働者と同様に、副業・兼
業と本業の労働時間を合算すると長時間労働につながるおそれがある。副業・兼
業の許可基準には、労働者本人の意思により副業・兼業に従事する事はもちろん
のこと、健康確保に加え「働き過ぎ」防止のための規定が必要である。
Ⅳ.事業承継・M&A等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化
○「事業承継・M&Aに関する新たな施策パッケージ」では、M&Aの売り手と買
い手の支援、官民のM&A支援機能の強化が掲げられているが、M&Aの対象事
業の維持・発展のためには、労働者の雇用維持に加え、安心して働き続けられる
環境整備も重要であるため、
「パッケージ」には「労働者保護ルールの強化」を大
きな柱として位置づけるべきである。
○雇用維持に関して、「M&A後に同意事項に反した場合に買戻し又は解除を可能
とするスキームの検討」が提案されているが、売り手と買い手の交渉力には格差
がある場合が多く、M&A仲介事業者等による契約も存在することを踏まえれば、
スキームの検討にとどまらず、より実効性の高い労働者保護施策などが必要であ
る。
○労働者が安心して働き続けるためには、労使協議などを通じた「雇用の安定」や
「労働条件の維持・向上」が必要であり、それは結果として、その後の事業の維
持・発展にも寄与すると考える。M&Aの売り手側の労使協議に加え、買い手側
との間でも確実に労使協議が行われるなどの法整備を正面から検討すべきであ
る。
Ⅴ.地域で活躍する人材の育成と処遇改善
〇労働組合のある企業のほうが、賃上げ率が高い結果が出ていることから、労働組
合の有無にかかわらず全国津々浦々に物価に負けない賃上げの流れを波及させ
るためにも、地方版政労使会議の複数回開催を含め、より積極的な活用を検討す
べきである。
(4)医療・介護・保育・福祉などの現場での公定価格の引上げ
〇医療・介護・保育・福祉等を担う人材を確保するには、現場で働くすべての人が、
安心して働き続けられるよう、賃金の引き上げをはじめとする処遇改善と労働環
境の改善が必要不可欠である。2024 年度に、公定価格に賃上げのための加算など
が講じられたが、決して十分とは言えない。現場を担うすべての労働者の継続的
な賃上げが可能となるよう、国としてさらなる施策を実行していく必要がある。
論点案 1.地方経済の高度化
〇全国の一つ一つの「交通空白」の解消に取り組むにあたっては、タクシー事業の
営業区域の見直しや、安全確保を大前提とした自動運転技術など先進技術の活用
も含め、あらゆる手段を検討すべきである。また、地域公共交通会議や法定協議
会等で地域の実情を踏まえた検討を活性化するとともに、複数市町村にまたがる
広域的交通については合同会議等を活用し、クロスセクター効果も踏まえた検討
を進めるべきである。
あわせて、過疎地の移動手段を当該地方だけで解決するには、人・モノ・カネ
の課題がある。人口が東京に集中する要因の一つに公共交通網の充実があること
を踏まえれば、すべての国民の住まいの選択と移動の自由を担保するためにも、
2
業と本業の労働時間を合算すると長時間労働につながるおそれがある。副業・兼
業の許可基準には、労働者本人の意思により副業・兼業に従事する事はもちろん
のこと、健康確保に加え「働き過ぎ」防止のための規定が必要である。
Ⅳ.事業承継・M&A等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化
○「事業承継・M&Aに関する新たな施策パッケージ」では、M&Aの売り手と買
い手の支援、官民のM&A支援機能の強化が掲げられているが、M&Aの対象事
業の維持・発展のためには、労働者の雇用維持に加え、安心して働き続けられる
環境整備も重要であるため、
「パッケージ」には「労働者保護ルールの強化」を大
きな柱として位置づけるべきである。
○雇用維持に関して、「M&A後に同意事項に反した場合に買戻し又は解除を可能
とするスキームの検討」が提案されているが、売り手と買い手の交渉力には格差
がある場合が多く、M&A仲介事業者等による契約も存在することを踏まえれば、
スキームの検討にとどまらず、より実効性の高い労働者保護施策などが必要であ
る。
○労働者が安心して働き続けるためには、労使協議などを通じた「雇用の安定」や
「労働条件の維持・向上」が必要であり、それは結果として、その後の事業の維
持・発展にも寄与すると考える。M&Aの売り手側の労使協議に加え、買い手側
との間でも確実に労使協議が行われるなどの法整備を正面から検討すべきであ
る。
Ⅴ.地域で活躍する人材の育成と処遇改善
〇労働組合のある企業のほうが、賃上げ率が高い結果が出ていることから、労働組
合の有無にかかわらず全国津々浦々に物価に負けない賃上げの流れを波及させ
るためにも、地方版政労使会議の複数回開催を含め、より積極的な活用を検討す
べきである。
(4)医療・介護・保育・福祉などの現場での公定価格の引上げ
〇医療・介護・保育・福祉等を担う人材を確保するには、現場で働くすべての人が、
安心して働き続けられるよう、賃金の引き上げをはじめとする処遇改善と労働環
境の改善が必要不可欠である。2024 年度に、公定価格に賃上げのための加算など
が講じられたが、決して十分とは言えない。現場を担うすべての労働者の継続的
な賃上げが可能となるよう、国としてさらなる施策を実行していく必要がある。
論点案 1.地方経済の高度化
〇全国の一つ一つの「交通空白」の解消に取り組むにあたっては、タクシー事業の
営業区域の見直しや、安全確保を大前提とした自動運転技術など先進技術の活用
も含め、あらゆる手段を検討すべきである。また、地域公共交通会議や法定協議
会等で地域の実情を踏まえた検討を活性化するとともに、複数市町村にまたがる
広域的交通については合同会議等を活用し、クロスセクター効果も踏まえた検討
を進めるべきである。
あわせて、過疎地の移動手段を当該地方だけで解決するには、人・モノ・カネ
の課題がある。人口が東京に集中する要因の一つに公共交通網の充実があること
を踏まえれば、すべての国民の住まいの選択と移動の自由を担保するためにも、
2