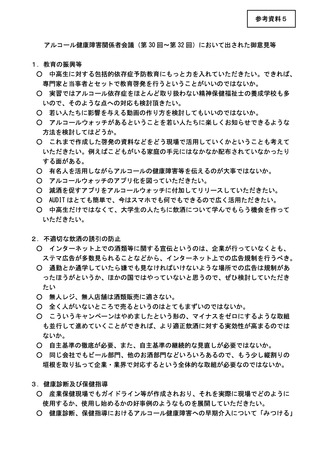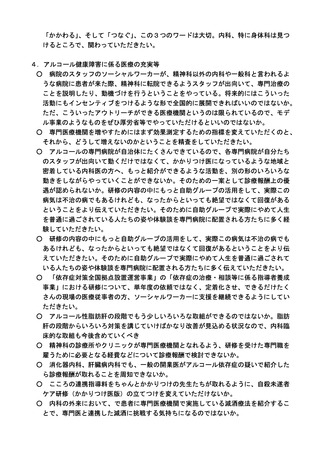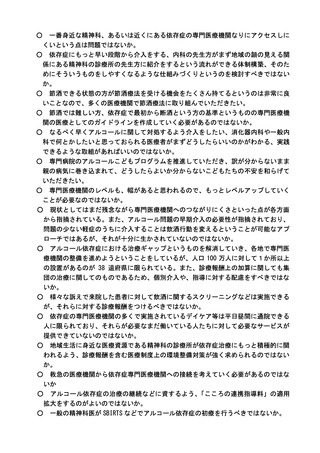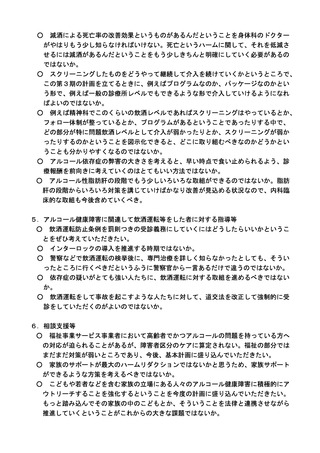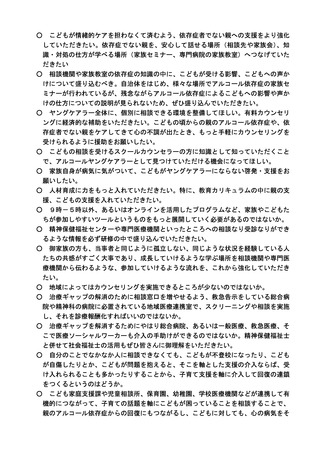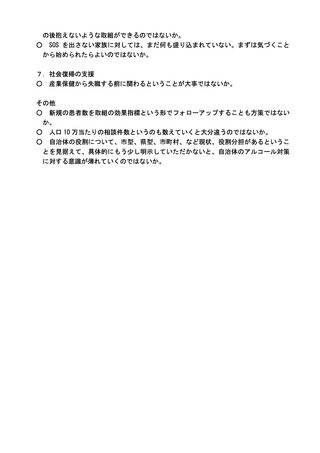よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 アルコール健康障害関係者会議(第30回~第32回)において出された御意見等 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57432.html |
| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第33回 4/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
一番身近な精神科、あるいは近くにある依存症の専門医療機関なりにアクセスしに
くいという点は問題ではないか。
○ 依存症にもっと早い段階から介入をする、内科の先生方がまず地域の顔の見える関
係にある精神科の診療所の先生方に紹介をするという流れができる体制構築、そのた
めにそういうものをしやすくなるような仕組みづくりというのを検討すべきではない
か。
○ 節酒できる状態の方が節酒療法を受ける機会をたくさん持てるというのは非常に良
いことなので、多くの医療機関で節酒療法に取り組んでいただきたい。
○ 節酒では難しい方、依存症で最初から断酒という方の基準というものの専門医療機
関の医療としてのガイドラインを作成していく必要があるのではないか。
○ なるべく早くアルコールに関して対処するよう介入をしたい、消化器内科や一般内
科で何とかしたいと思っておられる医療者がまずどうしたらいいのかがわかる、実践
できるような取組があればいいのではないか。
○ 専門病院のアルコールこどもプログラムを推進していただき、訳が分からないまま
親の病気に巻き込まれて、どうしたらよいか分からないこどもたちの不安を和らげて
いただきたい。
○ 専門医療機関のレベルも、幅があると思われるので、もっとレベルアップしていく
ことが必要なのではないか。
○ 現状としてはまだ残念ながら専門医療機関へのつながりにくさといった点が各方面
から指摘されている。また、アルコール問題の早期介入の必要性が指摘されており、
問題の少ない軽症のうちに介入することは飲酒行動を変えるということが可能なアプ
ローチではあるが、それが十分に生かされていないのではないか。
○
アルコール依存症における治療ギャップというものを解消していき、各地で専門医
療機関の整備を進めようということをしているが、人口 100 万人に対して1か所以上
の設置があるのが 38 道府県に限られている。また、診療報酬上の加算に関しても集
団の治療に関してのものであるため、個別介入や、指導に対する配慮をすべきではな
いか。
○ 様々な訴えで来院した患者に対して飲酒に関するスクリーニングなどは実施できる
が、それらに対する診療報酬をつけるべきではないか。
○ 依存症の専門医療機関の多くで実施されているデイケア等は平日昼間に通院できる
人に限られており、それらが必要なまだ働いている人たちに対して必要なサービスが
提供できていないのではないか。
○
地域生活に身近な医療資源である精神科の診療所が依存症治療にもっと積極的に関
われるよう、診療報酬を含む医療制度上の環境整備対策が強く求められるのではない
か。
○ 救急の医療機関から依存症専門医療機関への接続を考えていく必要があるのではな
いか
○ アルコール依存症の治療の継続などに資するよう、「こころの連携指導料」の適用
拡大をするのがよいのではないか。
○ 一般の精神科医が SBIRTS などでアルコール依存症の初療を行うべきではないか。
一番身近な精神科、あるいは近くにある依存症の専門医療機関なりにアクセスしに
くいという点は問題ではないか。
○ 依存症にもっと早い段階から介入をする、内科の先生方がまず地域の顔の見える関
係にある精神科の診療所の先生方に紹介をするという流れができる体制構築、そのた
めにそういうものをしやすくなるような仕組みづくりというのを検討すべきではない
か。
○ 節酒できる状態の方が節酒療法を受ける機会をたくさん持てるというのは非常に良
いことなので、多くの医療機関で節酒療法に取り組んでいただきたい。
○ 節酒では難しい方、依存症で最初から断酒という方の基準というものの専門医療機
関の医療としてのガイドラインを作成していく必要があるのではないか。
○ なるべく早くアルコールに関して対処するよう介入をしたい、消化器内科や一般内
科で何とかしたいと思っておられる医療者がまずどうしたらいいのかがわかる、実践
できるような取組があればいいのではないか。
○ 専門病院のアルコールこどもプログラムを推進していただき、訳が分からないまま
親の病気に巻き込まれて、どうしたらよいか分からないこどもたちの不安を和らげて
いただきたい。
○ 専門医療機関のレベルも、幅があると思われるので、もっとレベルアップしていく
ことが必要なのではないか。
○ 現状としてはまだ残念ながら専門医療機関へのつながりにくさといった点が各方面
から指摘されている。また、アルコール問題の早期介入の必要性が指摘されており、
問題の少ない軽症のうちに介入することは飲酒行動を変えるということが可能なアプ
ローチではあるが、それが十分に生かされていないのではないか。
○
アルコール依存症における治療ギャップというものを解消していき、各地で専門医
療機関の整備を進めようということをしているが、人口 100 万人に対して1か所以上
の設置があるのが 38 道府県に限られている。また、診療報酬上の加算に関しても集
団の治療に関してのものであるため、個別介入や、指導に対する配慮をすべきではな
いか。
○ 様々な訴えで来院した患者に対して飲酒に関するスクリーニングなどは実施できる
が、それらに対する診療報酬をつけるべきではないか。
○ 依存症の専門医療機関の多くで実施されているデイケア等は平日昼間に通院できる
人に限られており、それらが必要なまだ働いている人たちに対して必要なサービスが
提供できていないのではないか。
○
地域生活に身近な医療資源である精神科の診療所が依存症治療にもっと積極的に関
われるよう、診療報酬を含む医療制度上の環境整備対策が強く求められるのではない
か。
○ 救急の医療機関から依存症専門医療機関への接続を考えていく必要があるのではな
いか
○ アルコール依存症の治療の継続などに資するよう、「こころの連携指導料」の適用
拡大をするのがよいのではないか。
○ 一般の精神科医が SBIRTS などでアルコール依存症の初療を行うべきではないか。