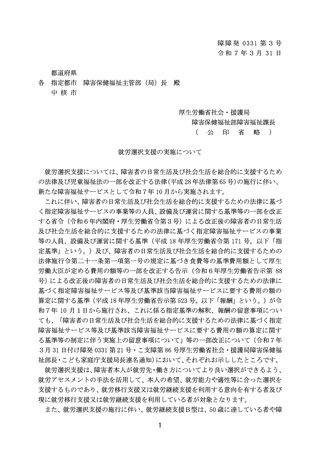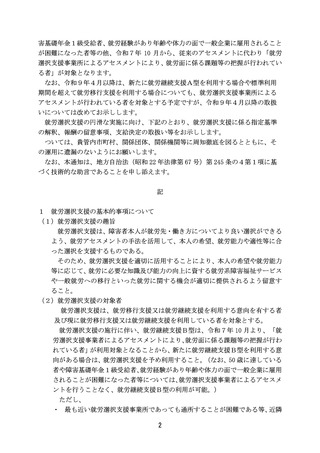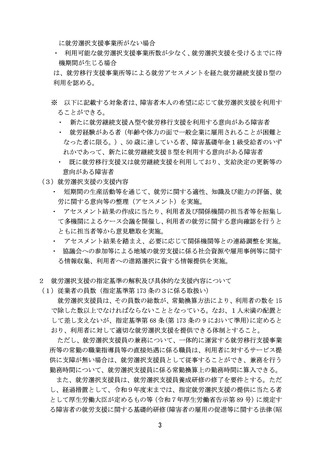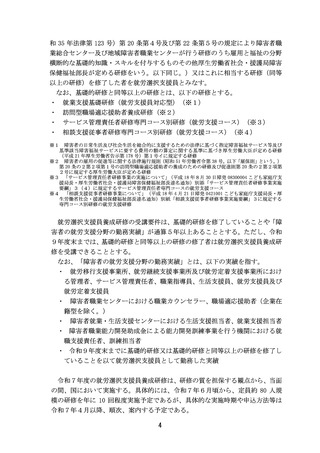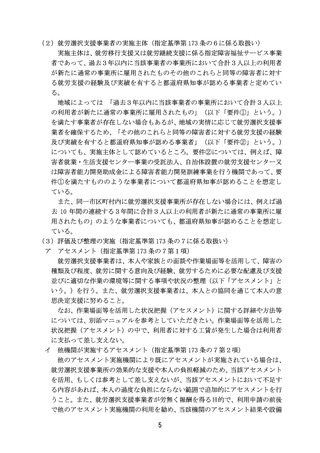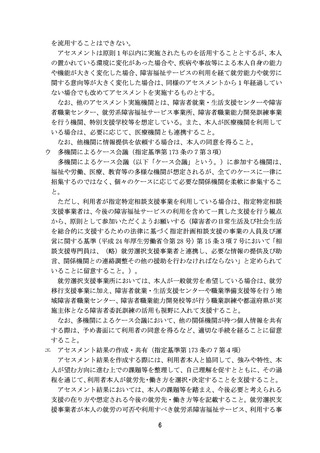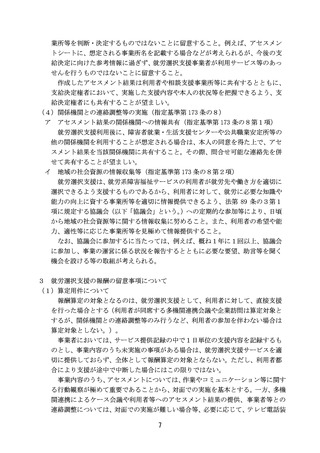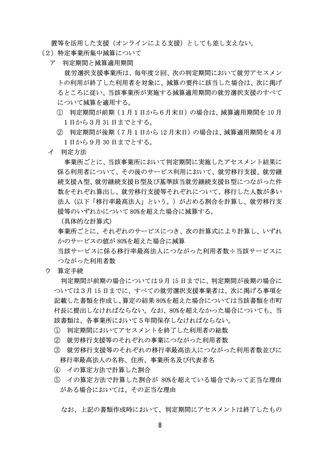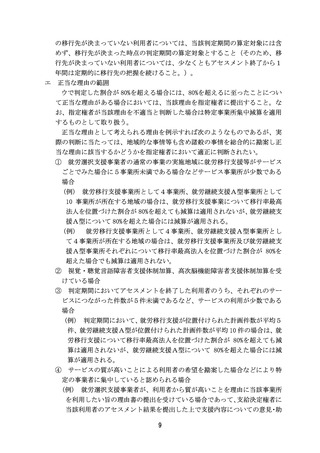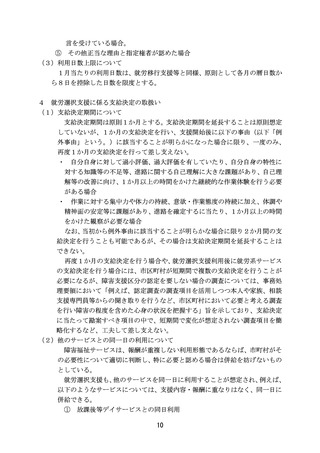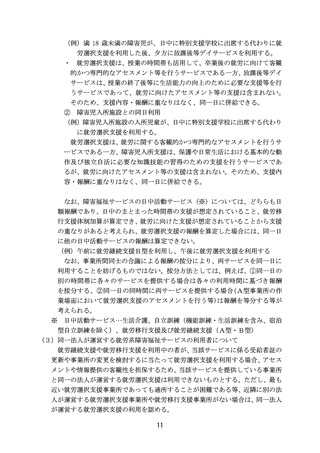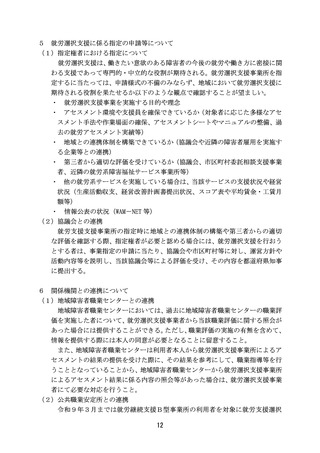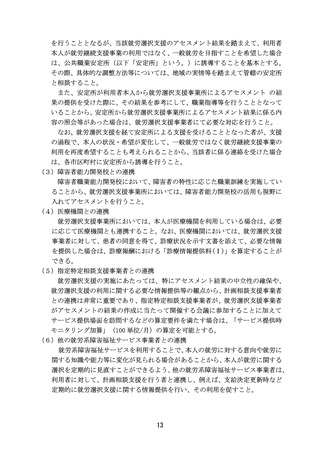よむ、つかう、まなぶ。
就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
| 出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を流用することはできない。
アセスメントは原則1年以内に実施されたものを活用することとするが、本人
の置かれている環境に変化があった場合や、疾病や事故等による本人自身の能力
や機能が大きく変化した場合、障害福祉サービスの利用を経て就労能力や就労に
関する意向等が大きく変化した場合は、同様のアセスメントから1年経過してい
ない場合でも改めてアセスメントを実施するものとする。
なお、他のアセスメント実施機関とは、障害者就業・生活支援センターや障害
者職業センター、就労系障害福祉サービス事業所、障害者職業能力開発訓練事業
を行う機関、特別支援学校等を想定している。また、本人が医療機関を利用して
いる場合は、必要に応じて、医療機関とも連携すること。
なお、他機関に情報提供を依頼する場合は、本人の同意を得ること。
ウ 多機関によるケース会議(指定基準第 173 条の7第3項)
多機関によるケース会議(以下「ケース会議」という。)に参加する機関は、
福祉や労働、医療、教育等の多様な機関が想定されるが、全てのケースに一律に
招集するのではなく、個々のケースに応じて必要な関係機関を柔軟に参集するこ
と。
ただし、利用者が指定特定相談支援事業を利用している場合は、指定特定相談
支援事業者は、今後の障害福祉サービスの利用を含めて一貫した支援を行う観点
から、原則として参加いただくようお願いする(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運
営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第 15 条3項7号において「相
談支援専門員は、(略)就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び助
言、関係機関との連絡調整その他の援助を行わなければならない」と定められて
いることに留意すること。)。
就労選択支援事業所においては、本人が一般就労を希望している場合は、就労
移行支援事業に加え、障害者就業・生活支援センターや職業準備支援等を行う地
域障害者職業センター、障害者職業能力開発校等が行う職業訓練や都道府県が実
施主体となる障害者委託訓練の活用も視野に入れて支援すること。
なお、多機関によるケース会議において、他の関係機関が持つ個人情報を共有
する際は、予め書面にて利用者の同意を得るなど、適切な手続を経ることに留意
すること。
エ アセスメント結果の作成・共有(指定基準第 173 条の7第4項)
アセスメント結果を作成する際には、利用者本人と協同して、強みや特性、本
人が望む方向に進む上での課題等を整理して、自己理解を促すとともに、その過
程を通じて、利用者本人が就労先・働き方を選択・決定することを支援すること。
アセスメント結果においては、本人の課題等を踏まえ、今後必要と考えられる
支援の在り方や想定される今後の就労先・働き方等を記載すること。就労選択支
援事業者が本人の就労の可否や利用すべき就労系障害福祉サービス、利用する事
6
アセスメントは原則1年以内に実施されたものを活用することとするが、本人
の置かれている環境に変化があった場合や、疾病や事故等による本人自身の能力
や機能が大きく変化した場合、障害福祉サービスの利用を経て就労能力や就労に
関する意向等が大きく変化した場合は、同様のアセスメントから1年経過してい
ない場合でも改めてアセスメントを実施するものとする。
なお、他のアセスメント実施機関とは、障害者就業・生活支援センターや障害
者職業センター、就労系障害福祉サービス事業所、障害者職業能力開発訓練事業
を行う機関、特別支援学校等を想定している。また、本人が医療機関を利用して
いる場合は、必要に応じて、医療機関とも連携すること。
なお、他機関に情報提供を依頼する場合は、本人の同意を得ること。
ウ 多機関によるケース会議(指定基準第 173 条の7第3項)
多機関によるケース会議(以下「ケース会議」という。)に参加する機関は、
福祉や労働、医療、教育等の多様な機関が想定されるが、全てのケースに一律に
招集するのではなく、個々のケースに応じて必要な関係機関を柔軟に参集するこ
と。
ただし、利用者が指定特定相談支援事業を利用している場合は、指定特定相談
支援事業者は、今後の障害福祉サービスの利用を含めて一貫した支援を行う観点
から、原則として参加いただくようお願いする(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運
営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第 15 条3項7号において「相
談支援専門員は、(略)就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び助
言、関係機関との連絡調整その他の援助を行わなければならない」と定められて
いることに留意すること。)。
就労選択支援事業所においては、本人が一般就労を希望している場合は、就労
移行支援事業に加え、障害者就業・生活支援センターや職業準備支援等を行う地
域障害者職業センター、障害者職業能力開発校等が行う職業訓練や都道府県が実
施主体となる障害者委託訓練の活用も視野に入れて支援すること。
なお、多機関によるケース会議において、他の関係機関が持つ個人情報を共有
する際は、予め書面にて利用者の同意を得るなど、適切な手続を経ることに留意
すること。
エ アセスメント結果の作成・共有(指定基準第 173 条の7第4項)
アセスメント結果を作成する際には、利用者本人と協同して、強みや特性、本
人が望む方向に進む上での課題等を整理して、自己理解を促すとともに、その過
程を通じて、利用者本人が就労先・働き方を選択・決定することを支援すること。
アセスメント結果においては、本人の課題等を踏まえ、今後必要と考えられる
支援の在り方や想定される今後の就労先・働き方等を記載すること。就労選択支
援事業者が本人の就労の可否や利用すべき就労系障害福祉サービス、利用する事
6