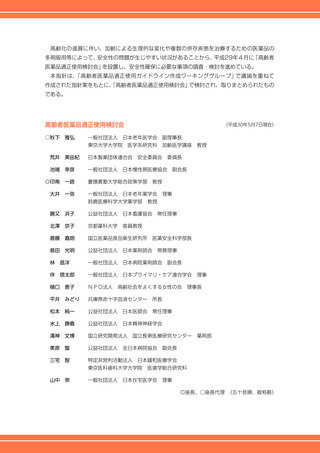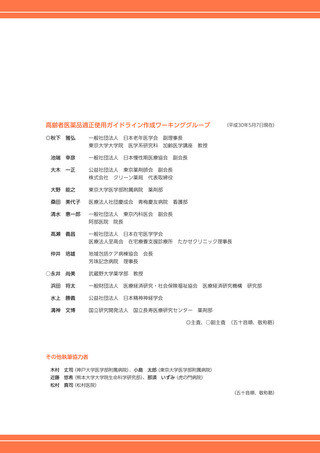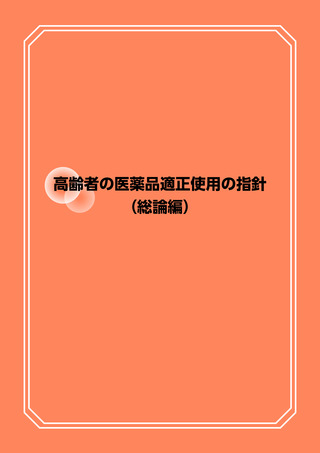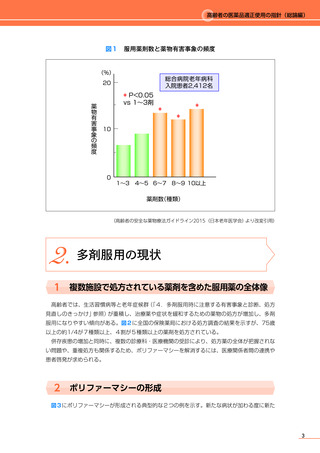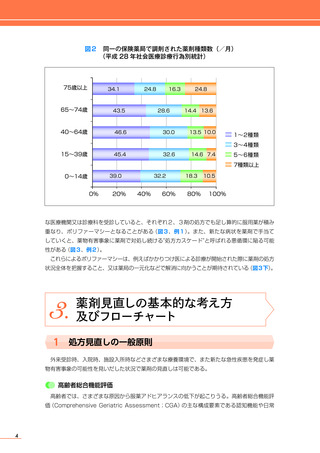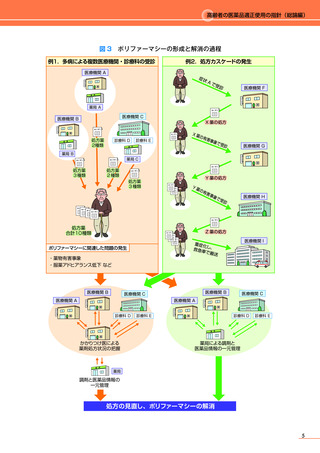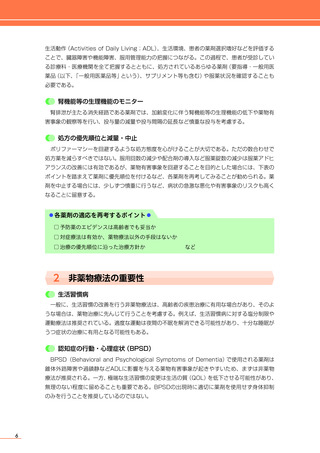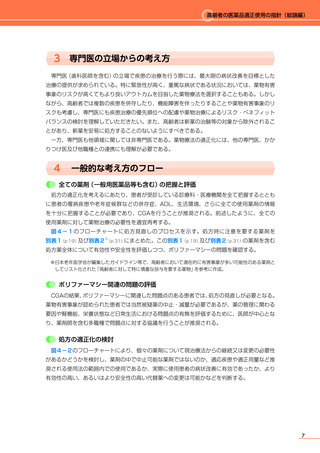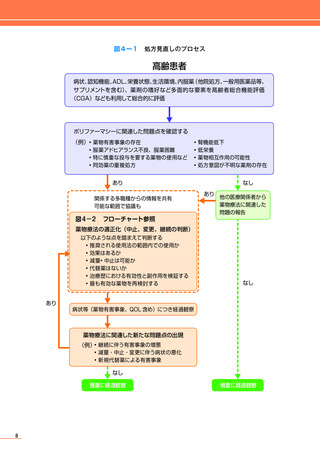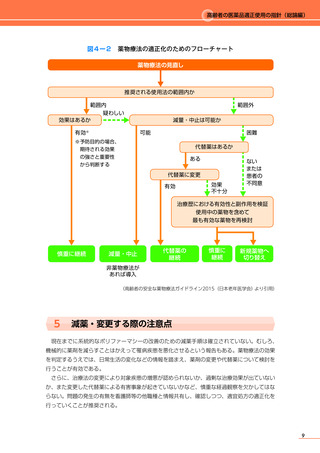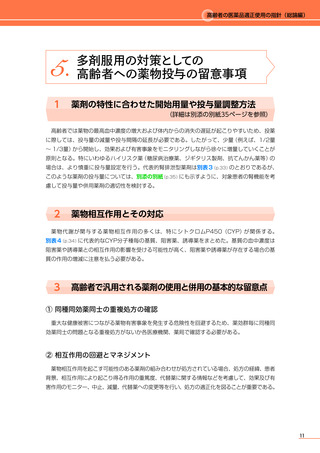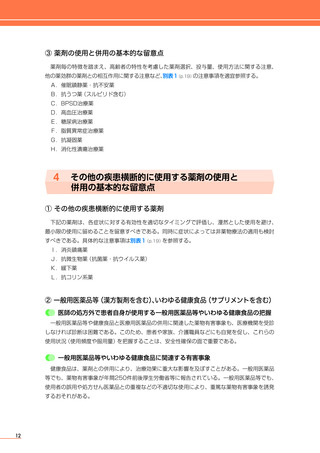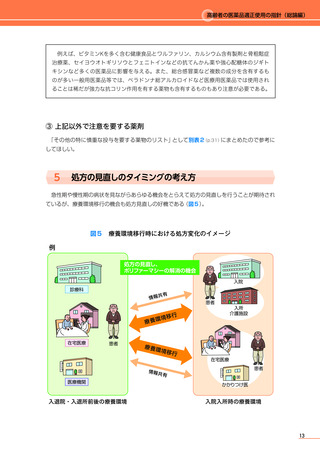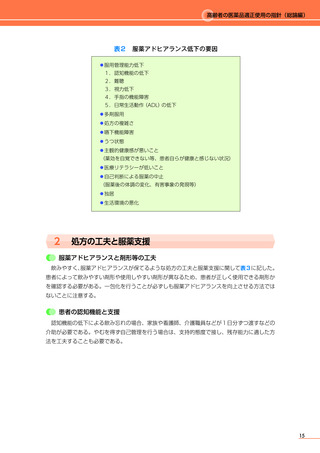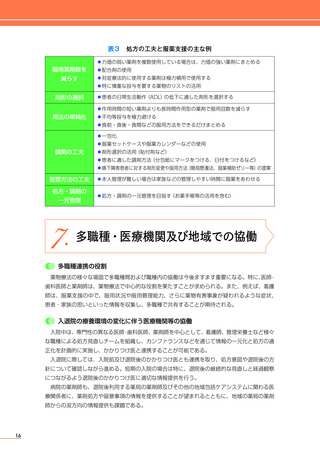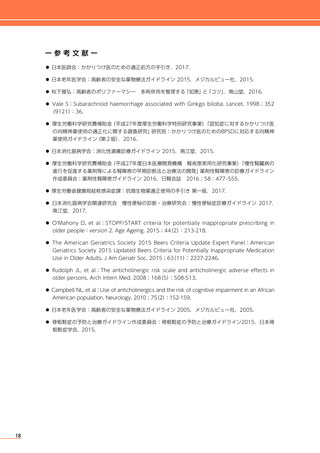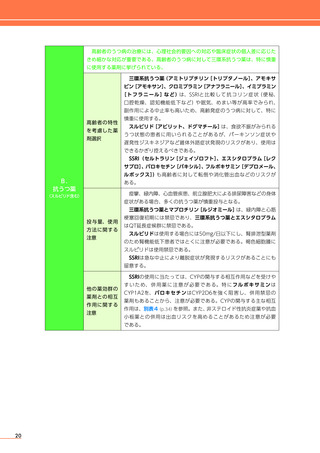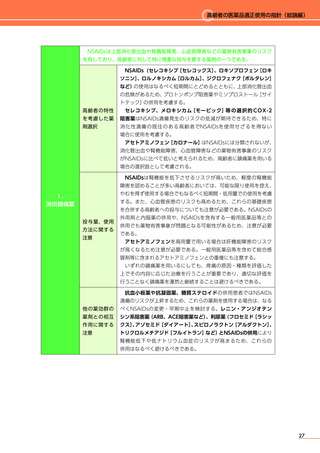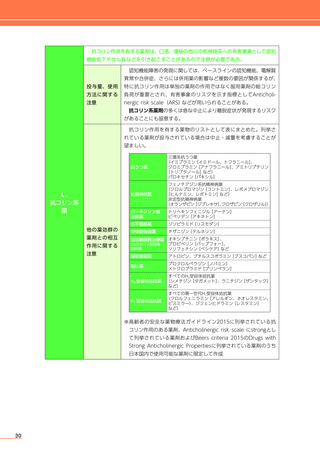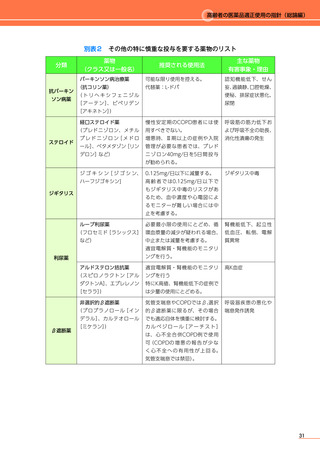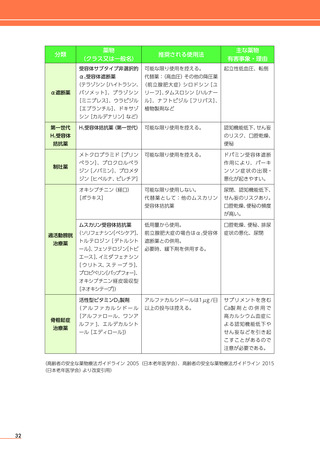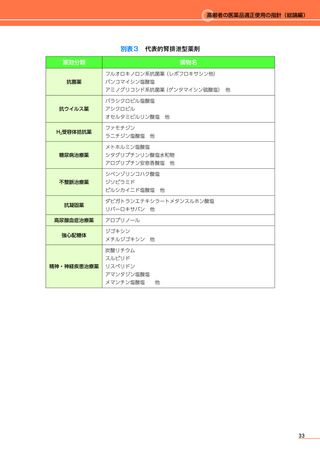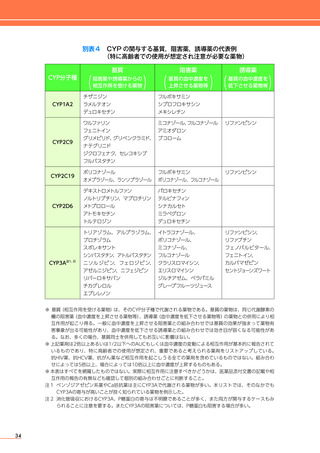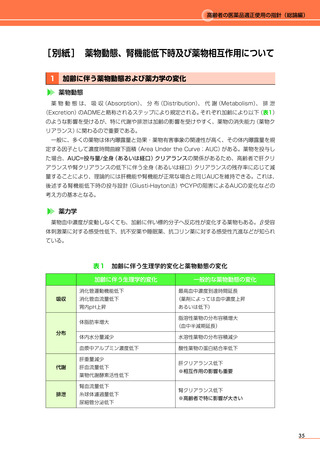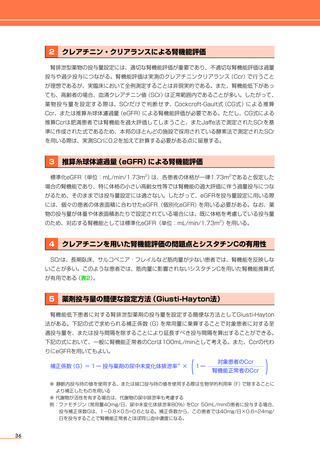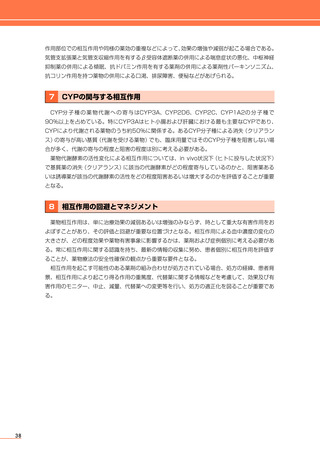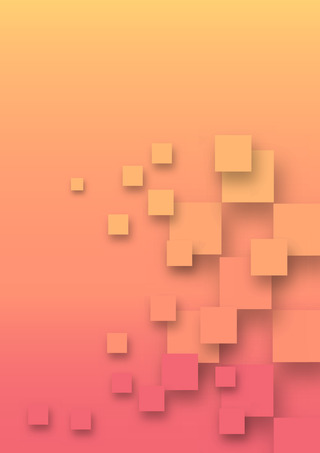よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |
| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)
●
● 医療機関を超えた地域での協働
介護施設や在宅医療、外来等の現場でも、それぞれの人的資源に応じて施設内又は地域内で多
職種のチームを形成することが可能である。また、一堂に会さなくても、お薬手帳等を活用すれ
ば連携・協働機能を発揮できる。
入・退院後のいずれの状況でも、地域内や外来の現場でも、地域包括ケアシステムでの多職種
の協力の下に、医師が処方を見直すことができるための情報の提供が必要である。例えば、訪問
看護師と在宅訪問に対応する薬剤師の連携により、服薬状況、残薬の確認や整理、服薬支援を行
うことなども、期待されている。
8. 国民的理解の醸成
本指針が医療現場で広く活用されるには、医療を受ける立場にある患者と家族を含む一般の方
の理解が必須である。ポリファーマシーに対する問題意識や高齢者にリスクの高い薬剤、薬物相
互作用、服薬薬剤の見直し、適切な服薬支援の必要性などは患者・家族や介護職員では理解が難
しい場合がある。一方、薬剤の減量や中止により病状が改善する場合があることを患者等にも理
解していただく必要があり、広く国民に薬剤の適正な使用法の知識を普及させることが望まれる。
本指針の精神である「患者中心」の医療を実践するためにも、医療関係者による一般の方への啓
発にも本指針を役立てていただきたい。また、一般向けの教育資材も望まれている。例えば、日
本老年医学会と日本老年薬学会等が共同で作成した一般向け啓発パンフレット「高齢者が気を付
けたい多すぎる薬と副作用」なども活用し、高齢者における薬剤使用の原則、服薬アドヒアラン
スの遵守、定期的な使用妥当性の見直し等のプロセスについて国民の理解が浸透することも期待
される。また、ポリファーマシーの未然防止のために、ポリファーマシーのリスクや非薬物療法
に関する啓発も必要である。
17
●
● 医療機関を超えた地域での協働
介護施設や在宅医療、外来等の現場でも、それぞれの人的資源に応じて施設内又は地域内で多
職種のチームを形成することが可能である。また、一堂に会さなくても、お薬手帳等を活用すれ
ば連携・協働機能を発揮できる。
入・退院後のいずれの状況でも、地域内や外来の現場でも、地域包括ケアシステムでの多職種
の協力の下に、医師が処方を見直すことができるための情報の提供が必要である。例えば、訪問
看護師と在宅訪問に対応する薬剤師の連携により、服薬状況、残薬の確認や整理、服薬支援を行
うことなども、期待されている。
8. 国民的理解の醸成
本指針が医療現場で広く活用されるには、医療を受ける立場にある患者と家族を含む一般の方
の理解が必須である。ポリファーマシーに対する問題意識や高齢者にリスクの高い薬剤、薬物相
互作用、服薬薬剤の見直し、適切な服薬支援の必要性などは患者・家族や介護職員では理解が難
しい場合がある。一方、薬剤の減量や中止により病状が改善する場合があることを患者等にも理
解していただく必要があり、広く国民に薬剤の適正な使用法の知識を普及させることが望まれる。
本指針の精神である「患者中心」の医療を実践するためにも、医療関係者による一般の方への啓
発にも本指針を役立てていただきたい。また、一般向けの教育資材も望まれている。例えば、日
本老年医学会と日本老年薬学会等が共同で作成した一般向け啓発パンフレット「高齢者が気を付
けたい多すぎる薬と副作用」なども活用し、高齢者における薬剤使用の原則、服薬アドヒアラン
スの遵守、定期的な使用妥当性の見直し等のプロセスについて国民の理解が浸透することも期待
される。また、ポリファーマシーの未然防止のために、ポリファーマシーのリスクや非薬物療法
に関する啓発も必要である。
17