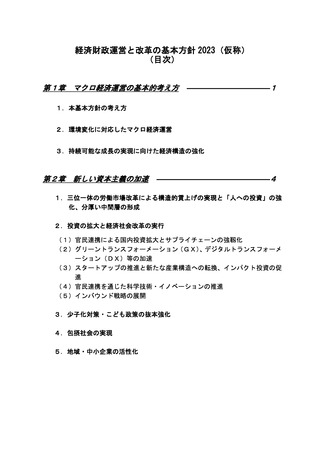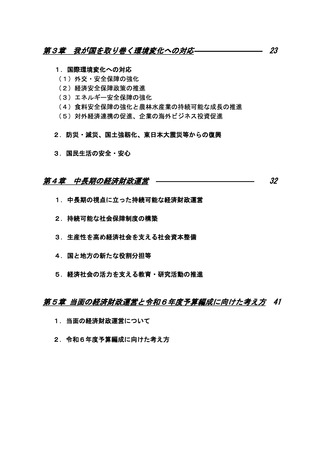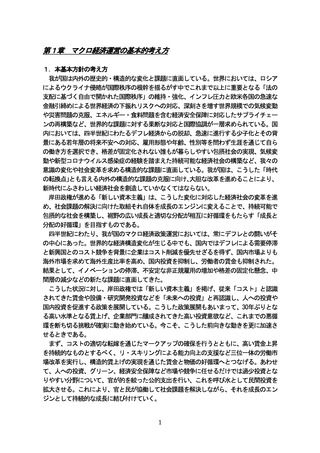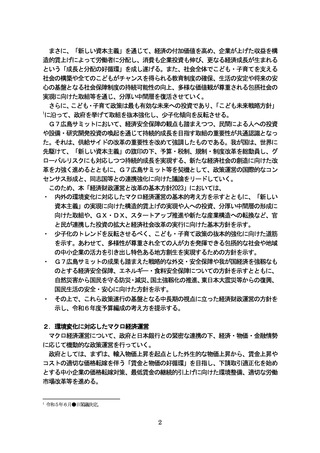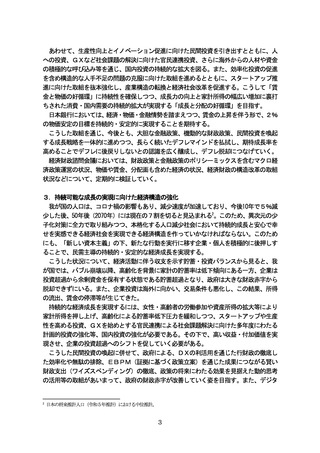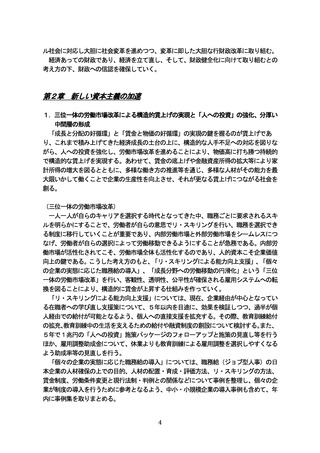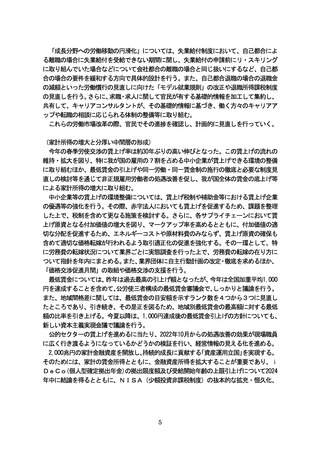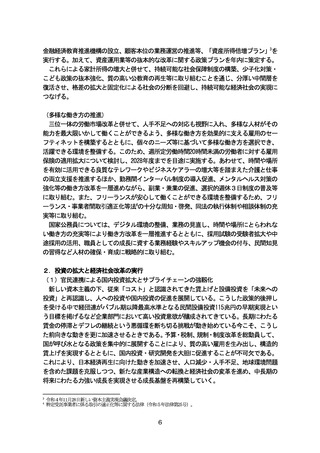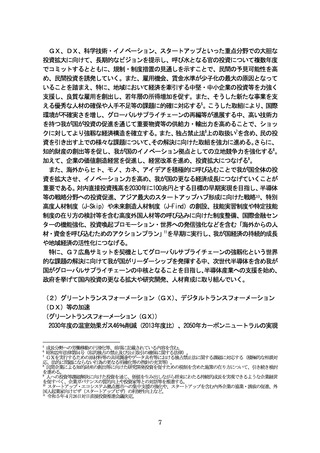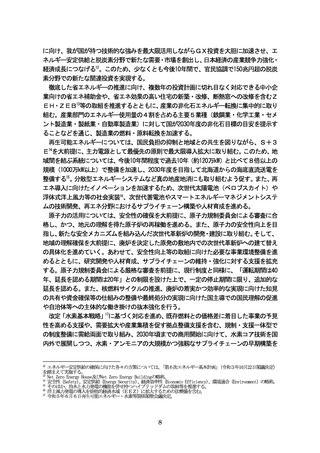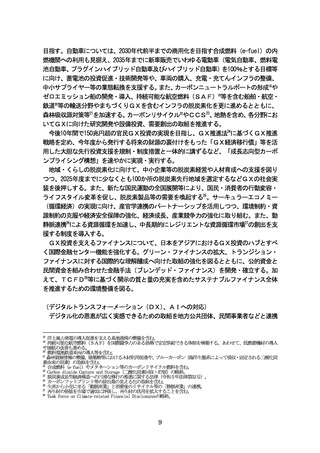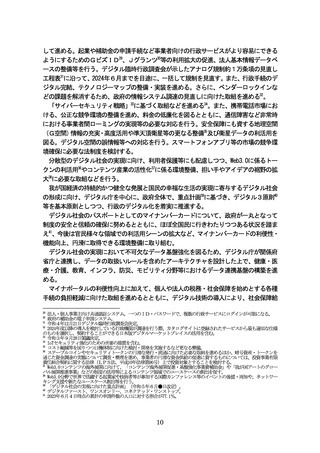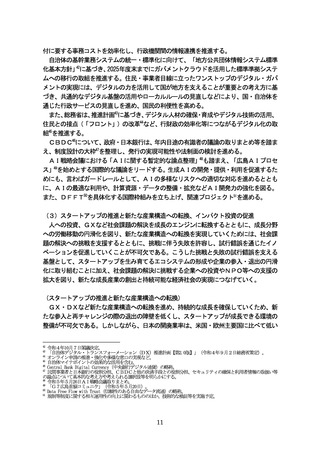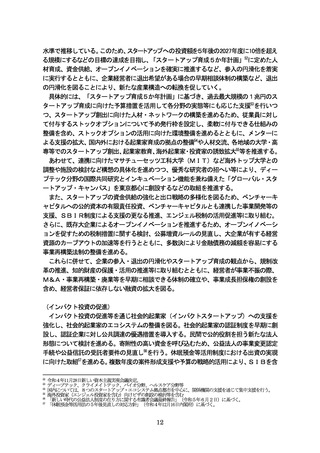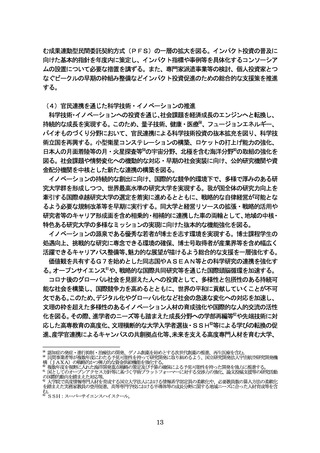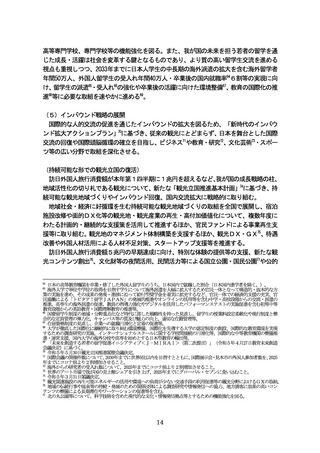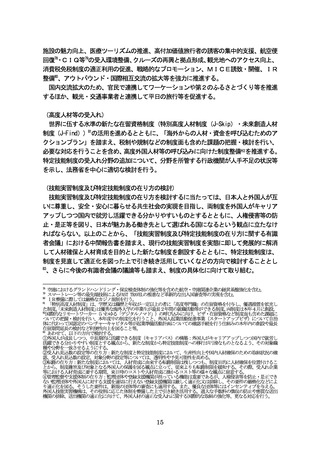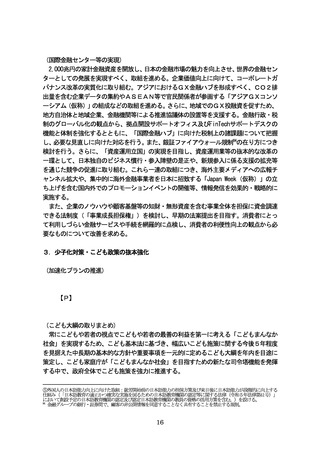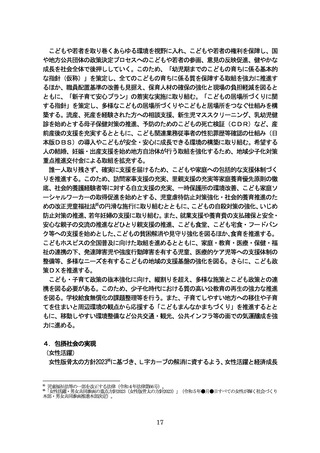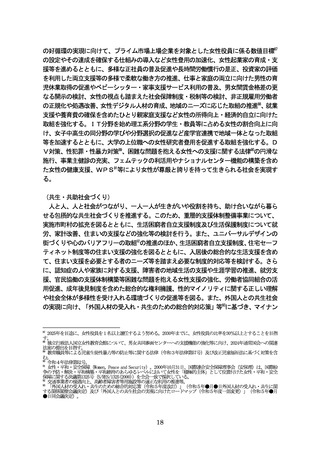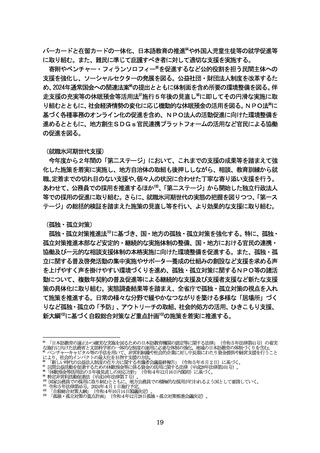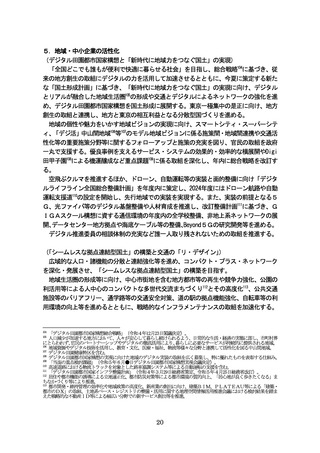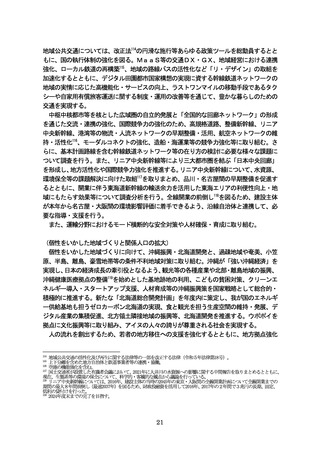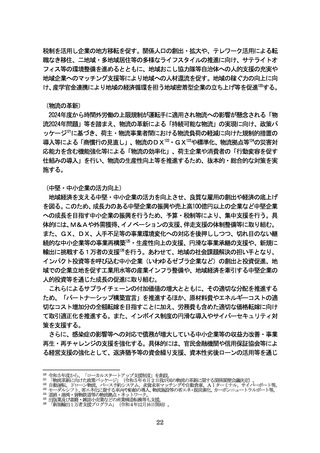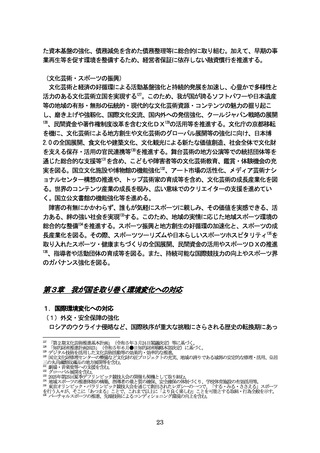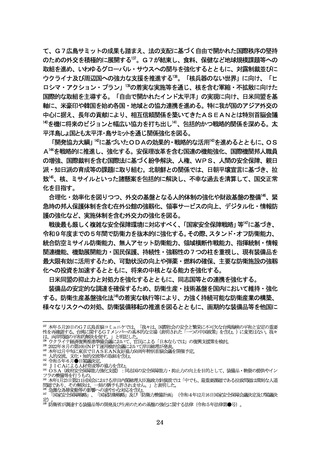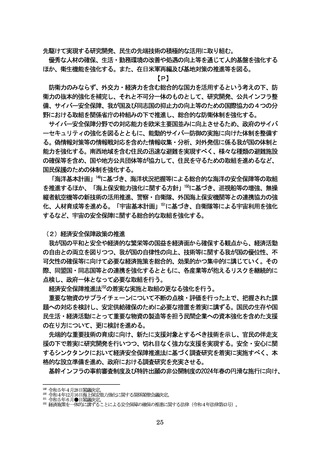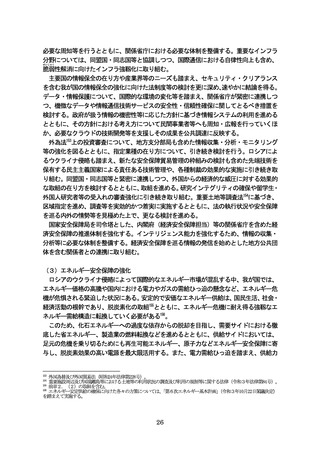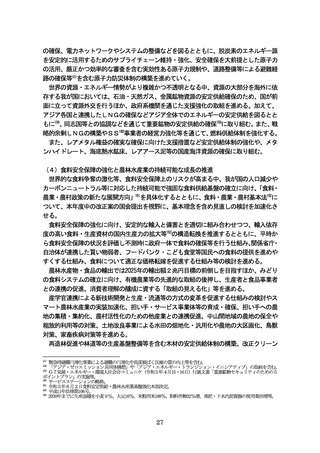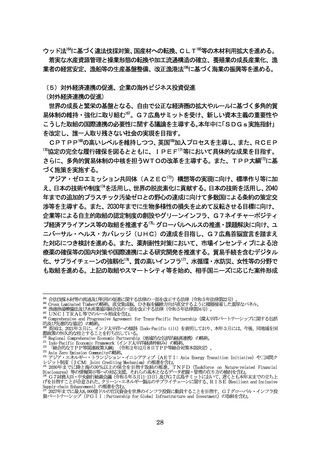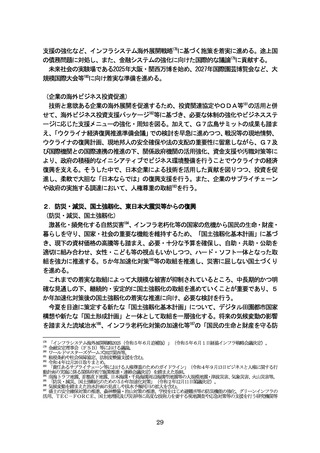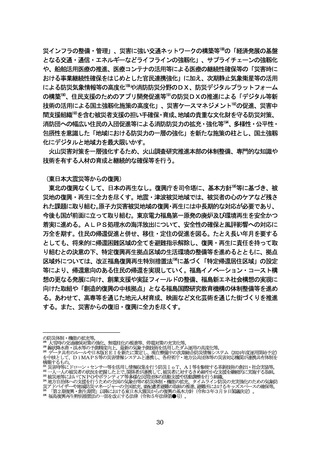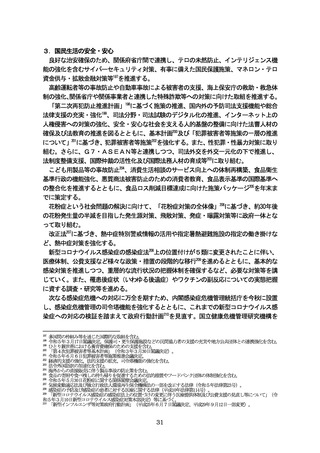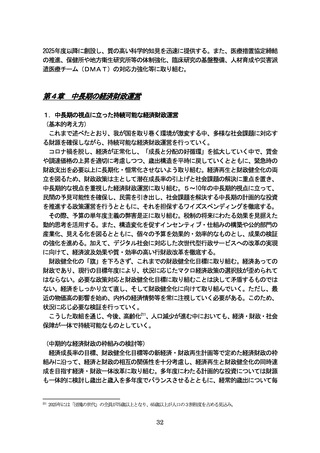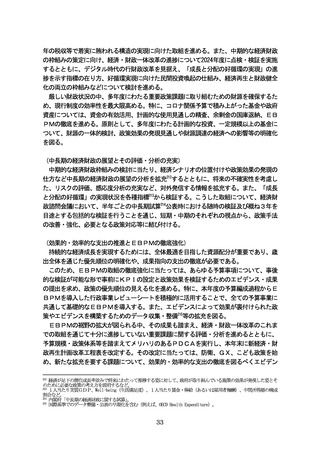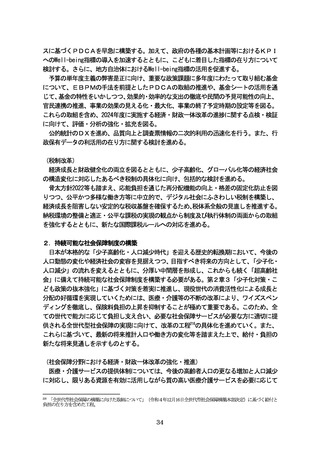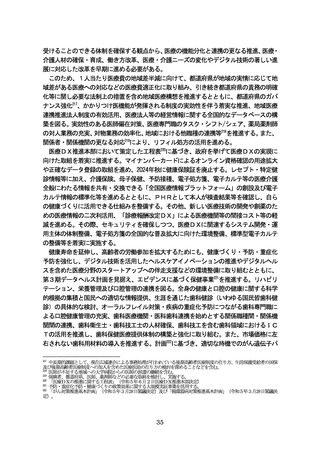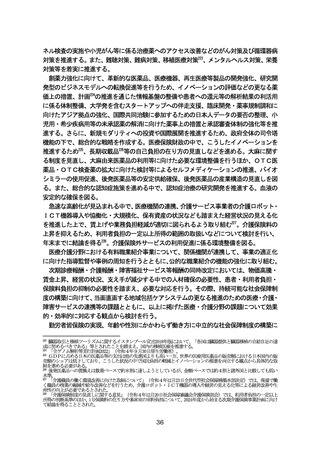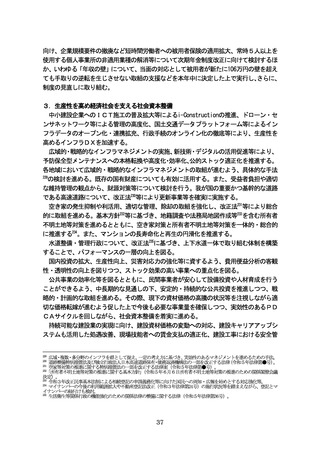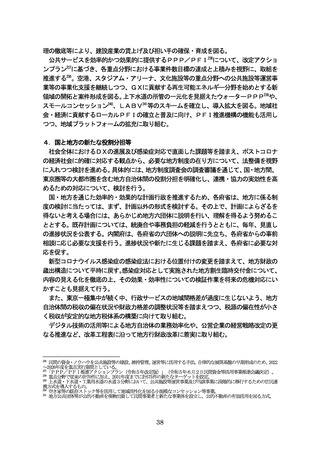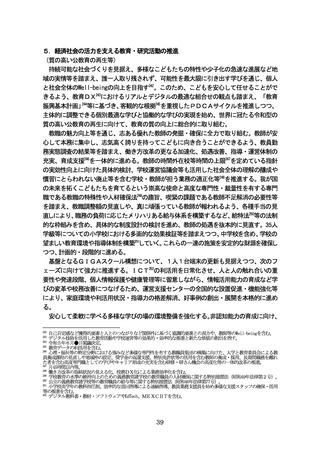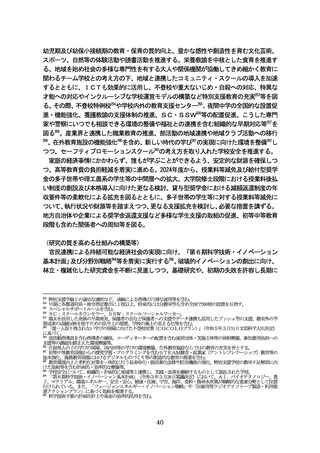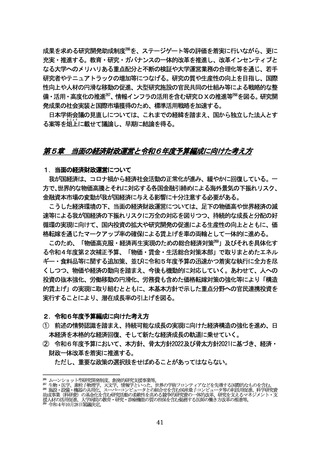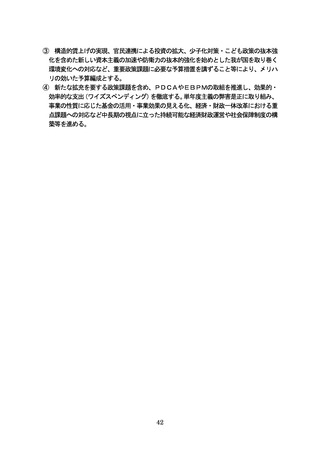よむ、つかう、まなぶ。
資料1 経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称)原案 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2023/0607/agenda.html |
| 出典情報 | 経済財政諮問会議(令和5年第8回 6/7)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第1章 マクロ経済運営の基本的考え方
1.本基本方針の考え方
我が国は内外の歴史的・構造的な変化と課題に直面している。世界においては、ロシア
によるウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがす中でこれまで以上に重要となる「法の
支配に基づく自由で開かれた国際秩序」の維持・強化、インフレ圧力と欧米各国の急速な
金融引締めによる世界経済の下振れリスクへの対応、深刻さを増す世界規模での気候変動
や災害問題の克服、エネルギー・食料問題を含む経済安全保障に対応したサプライチェー
ンの再構築など、世界的な課題に対する果断な対応と国際協調が一層求められている。国
内においては、四半世紀にわたるデフレ経済からの脱却、急速に進行する少子化とその背
景にある若年層の将来不安への対応、雇用形態や年齢、性別等を問わず生涯を通じて自ら
の働き方を選択でき、格差が固定化されない誰もが暮らしやすい包摂社会の実現、気候変
動や新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた持続可能な経済社会の構築など、我々の
意識の変化や社会変革を求める構造的な課題に直面している。我が国は、こうした「時代
の転換点」
とも言える内外の構造的な課題の克服に向け、
大胆な改革を進めることにより、
新時代にふさわしい経済社会を創造していかなくてはならない。
岸田政権が進める「新しい資本主義」は、こうした変化に対応した経済社会の変革を進
め、社会課題の解決に向けた取組それ自体を成長のエンジンに変えることで、持続可能で
包摂的な社会を構築し、裾野の広い成長と適切な分配が相互に好循環をもたらす「成長と
分配の好循環」を目指すものである。
四半世紀にわたり、我が国のマクロ経済政策運営においては、常にデフレとの闘いがそ
の中心にあった。世界的な経済構造変化が生じる中でも、国内ではデフレによる需要停滞
と新興国とのコスト競争を背景に企業はコスト削減を優先せざるを得ず、国内市場よりも
海外市場を求めて海外生産比率を高め、国内投資を抑制し、労働者の賃金も抑制された。
結果として、イノベーションの停滞、不安定な非正規雇用の増加や格差の固定化懸念、中
間層の減少などの新たな課題に直面してきた。
こうした状況に対し、岸田政権では「新しい資本主義」を掲げ、従来「コスト」と認識
されてきた賃金や設備・研究開発投資などを「未来への投資」と再認識し、人への投資や
国内投資を促進する政策を展開している。こうした政策展開もあいまって、30年ぶりとな
る高い水準となる賃上げ、企業部門に醸成されてきた高い投資意欲など、これまでの悪循
環を断ち切る挑戦が確実に動き始めている。今こそ、こうした前向きな動きを更に加速さ
せるときである。
まず、コストの適切な転嫁を通じたマークアップの確保を行うとともに、高い賃金上昇
を持続的なものとするべく、リ・スキリングによる能力向上の支援など三位一体の労働市
場改革を実行し、構造的賃上げの実現を通じた賃金と物価の好循環へとつなげる。あわせ
て、人への投資、グリーン、経済安全保障など市場や競争に任せるだけでは過少投資とな
りやすい分野について、官が的を絞った公的支出を行い、これを呼び水として民間投資を
拡大させる。これにより、官と民が協働して社会課題を解決しながら、それを成長のエン
ジンとして持続的な成長に結び付けていく。
1
1.本基本方針の考え方
我が国は内外の歴史的・構造的な変化と課題に直面している。世界においては、ロシア
によるウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがす中でこれまで以上に重要となる「法の
支配に基づく自由で開かれた国際秩序」の維持・強化、インフレ圧力と欧米各国の急速な
金融引締めによる世界経済の下振れリスクへの対応、深刻さを増す世界規模での気候変動
や災害問題の克服、エネルギー・食料問題を含む経済安全保障に対応したサプライチェー
ンの再構築など、世界的な課題に対する果断な対応と国際協調が一層求められている。国
内においては、四半世紀にわたるデフレ経済からの脱却、急速に進行する少子化とその背
景にある若年層の将来不安への対応、雇用形態や年齢、性別等を問わず生涯を通じて自ら
の働き方を選択でき、格差が固定化されない誰もが暮らしやすい包摂社会の実現、気候変
動や新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた持続可能な経済社会の構築など、我々の
意識の変化や社会変革を求める構造的な課題に直面している。我が国は、こうした「時代
の転換点」
とも言える内外の構造的な課題の克服に向け、
大胆な改革を進めることにより、
新時代にふさわしい経済社会を創造していかなくてはならない。
岸田政権が進める「新しい資本主義」は、こうした変化に対応した経済社会の変革を進
め、社会課題の解決に向けた取組それ自体を成長のエンジンに変えることで、持続可能で
包摂的な社会を構築し、裾野の広い成長と適切な分配が相互に好循環をもたらす「成長と
分配の好循環」を目指すものである。
四半世紀にわたり、我が国のマクロ経済政策運営においては、常にデフレとの闘いがそ
の中心にあった。世界的な経済構造変化が生じる中でも、国内ではデフレによる需要停滞
と新興国とのコスト競争を背景に企業はコスト削減を優先せざるを得ず、国内市場よりも
海外市場を求めて海外生産比率を高め、国内投資を抑制し、労働者の賃金も抑制された。
結果として、イノベーションの停滞、不安定な非正規雇用の増加や格差の固定化懸念、中
間層の減少などの新たな課題に直面してきた。
こうした状況に対し、岸田政権では「新しい資本主義」を掲げ、従来「コスト」と認識
されてきた賃金や設備・研究開発投資などを「未来への投資」と再認識し、人への投資や
国内投資を促進する政策を展開している。こうした政策展開もあいまって、30年ぶりとな
る高い水準となる賃上げ、企業部門に醸成されてきた高い投資意欲など、これまでの悪循
環を断ち切る挑戦が確実に動き始めている。今こそ、こうした前向きな動きを更に加速さ
せるときである。
まず、コストの適切な転嫁を通じたマークアップの確保を行うとともに、高い賃金上昇
を持続的なものとするべく、リ・スキリングによる能力向上の支援など三位一体の労働市
場改革を実行し、構造的賃上げの実現を通じた賃金と物価の好循環へとつなげる。あわせ
て、人への投資、グリーン、経済安全保障など市場や競争に任せるだけでは過少投資とな
りやすい分野について、官が的を絞った公的支出を行い、これを呼び水として民間投資を
拡大させる。これにより、官と民が協働して社会課題を解決しながら、それを成長のエン
ジンとして持続的な成長に結び付けていく。
1