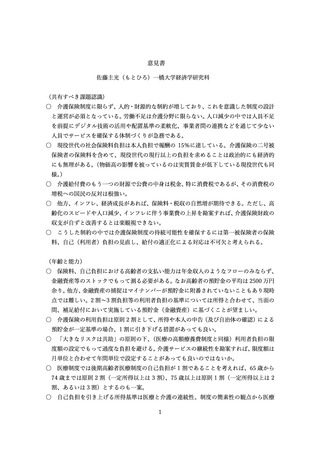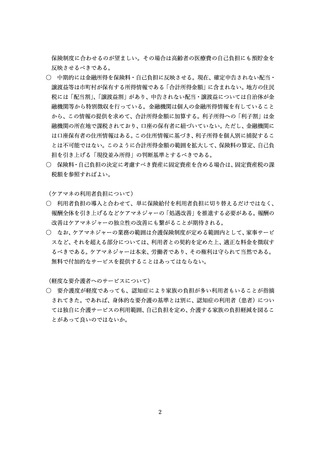よむ、つかう、まなぶ。
佐藤委員 提出資料 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
意見書
佐藤主光(もとひろ)一橋大学経済学研究科
(共有すべき課題認識)
〇 介護保険制度に限らず、人的・財源的な制約が増しており、これを意識した制度の設計
と運営が必須となっている。労働不足は介護分野に限らない。人口減少の中では人員不足
を前提にデジタル技術の活用や配置基準の柔軟化、事業者間の連携などを通じて少ない
人員でサービスを確保する体制づくりが急務である。
〇 現役世代の社会保険料負担は本人負担で報酬の 15%に達している。介護保険の二号被
保険者の保険料を含めて、現役世代の現行以上の負担を求めることは政治的にも経済的
にも無理がある。
(物価高の影響を被っているのは実質賃金が低下している現役世代も同
様。)
〇 介護給付費のもう一つの財源で公費の中身は税金、特に消費税であるが、その消費税の
増税への国民の反対は根強い。
〇 他方、インフレ、経済成⾧があれば、保険料・税収の自然増が期待できる。ただし、高
齢化のスピードや人口減少、インフレに伴う事業費の上昇を勘案すれば、介護保険財政の
収支が自ずと改善するとは楽観視できない。
〇
こうした制約の中では介護保険制度の持続可能性を確保するには第一被保険者の保険
料、自己(利用者)負担の見直し、給付の適正化による対応は不可欠と考えられる。
(年齢と能力)
〇 保険料、自己負担における高齢者の支払い能力は年金収入のようなフローのみならず、
金融資産等のストックでもって測る必要がある。なお高齢者の預貯金の平均は 2500 万円
余り。他方、金融資産の捕捉はマイナンバーが預貯金に附番されていないこともあり現時
点では難しい。2 割~3 割負担等の利用者負担の基準については所得と合わせて、当面の
間、補足給付において実施している預貯金(金融資産)に基づくことが望ましい。
〇 介護保険の利用負担は原則 2 割として、所得や本人の申告(及び自治体の確認)による
預貯金が一定基準の場合、1 割に引き下げる措置があっても良い。
〇 「大きなリスクは共助」の原則の下、
(医療の高額療養費制度と同様)利用者負担の限
度額の設定でもって過度な負担を避ける。介護サービスの継続性を勘案すれば、限度額は
月単位と合わせて年間単位で設定することがあっても良いのではないか。
〇 医療制度では後期高齢者医療制度の自己負担が 1 割であることを考えれば、65 歳から
74 歳までは原則 2 割(一定所得以上は 3 割)
、75 歳以上は原則 1 割(一定所得以上は 2
割、あるいは 3 割)とするのも一案。
〇
自己負担を引き上げる所得基準は医療と介護の連続性、制度の簡素性の観点から医療
1
佐藤主光(もとひろ)一橋大学経済学研究科
(共有すべき課題認識)
〇 介護保険制度に限らず、人的・財源的な制約が増しており、これを意識した制度の設計
と運営が必須となっている。労働不足は介護分野に限らない。人口減少の中では人員不足
を前提にデジタル技術の活用や配置基準の柔軟化、事業者間の連携などを通じて少ない
人員でサービスを確保する体制づくりが急務である。
〇 現役世代の社会保険料負担は本人負担で報酬の 15%に達している。介護保険の二号被
保険者の保険料を含めて、現役世代の現行以上の負担を求めることは政治的にも経済的
にも無理がある。
(物価高の影響を被っているのは実質賃金が低下している現役世代も同
様。)
〇 介護給付費のもう一つの財源で公費の中身は税金、特に消費税であるが、その消費税の
増税への国民の反対は根強い。
〇 他方、インフレ、経済成⾧があれば、保険料・税収の自然増が期待できる。ただし、高
齢化のスピードや人口減少、インフレに伴う事業費の上昇を勘案すれば、介護保険財政の
収支が自ずと改善するとは楽観視できない。
〇
こうした制約の中では介護保険制度の持続可能性を確保するには第一被保険者の保険
料、自己(利用者)負担の見直し、給付の適正化による対応は不可欠と考えられる。
(年齢と能力)
〇 保険料、自己負担における高齢者の支払い能力は年金収入のようなフローのみならず、
金融資産等のストックでもって測る必要がある。なお高齢者の預貯金の平均は 2500 万円
余り。他方、金融資産の捕捉はマイナンバーが預貯金に附番されていないこともあり現時
点では難しい。2 割~3 割負担等の利用者負担の基準については所得と合わせて、当面の
間、補足給付において実施している預貯金(金融資産)に基づくことが望ましい。
〇 介護保険の利用負担は原則 2 割として、所得や本人の申告(及び自治体の確認)による
預貯金が一定基準の場合、1 割に引き下げる措置があっても良い。
〇 「大きなリスクは共助」の原則の下、
(医療の高額療養費制度と同様)利用者負担の限
度額の設定でもって過度な負担を避ける。介護サービスの継続性を勘案すれば、限度額は
月単位と合わせて年間単位で設定することがあっても良いのではないか。
〇 医療制度では後期高齢者医療制度の自己負担が 1 割であることを考えれば、65 歳から
74 歳までは原則 2 割(一定所得以上は 3 割)
、75 歳以上は原則 1 割(一定所得以上は 2
割、あるいは 3 割)とするのも一案。
〇
自己負担を引き上げる所得基準は医療と介護の連続性、制度の簡素性の観点から医療
1